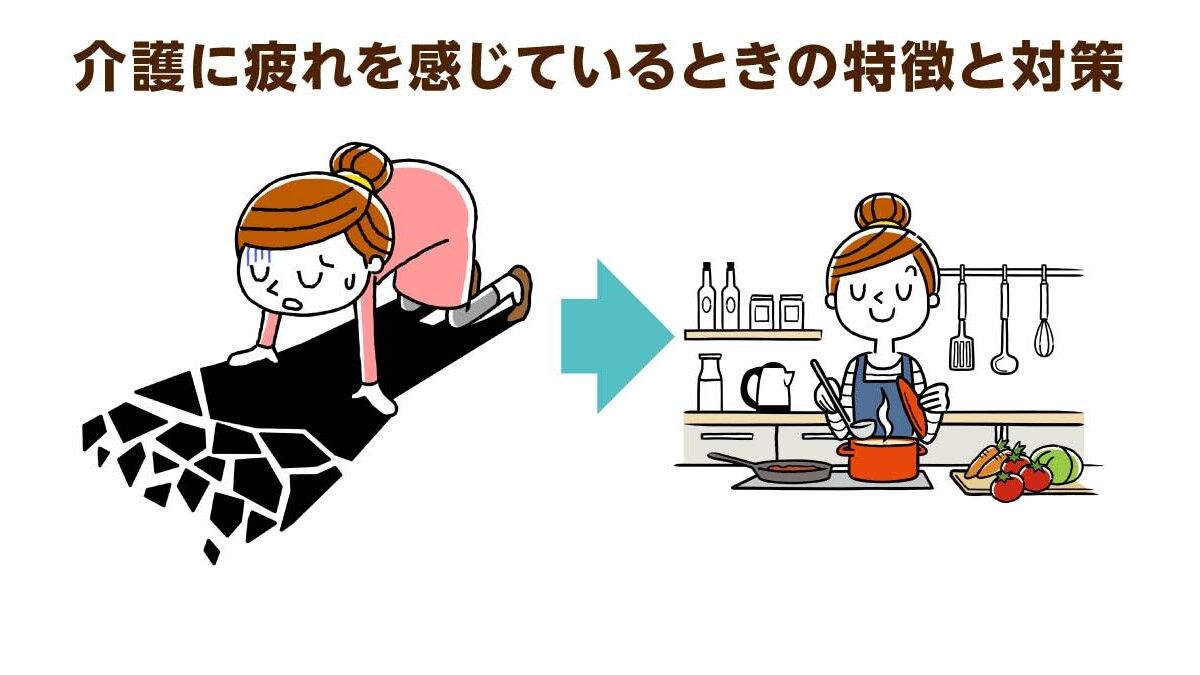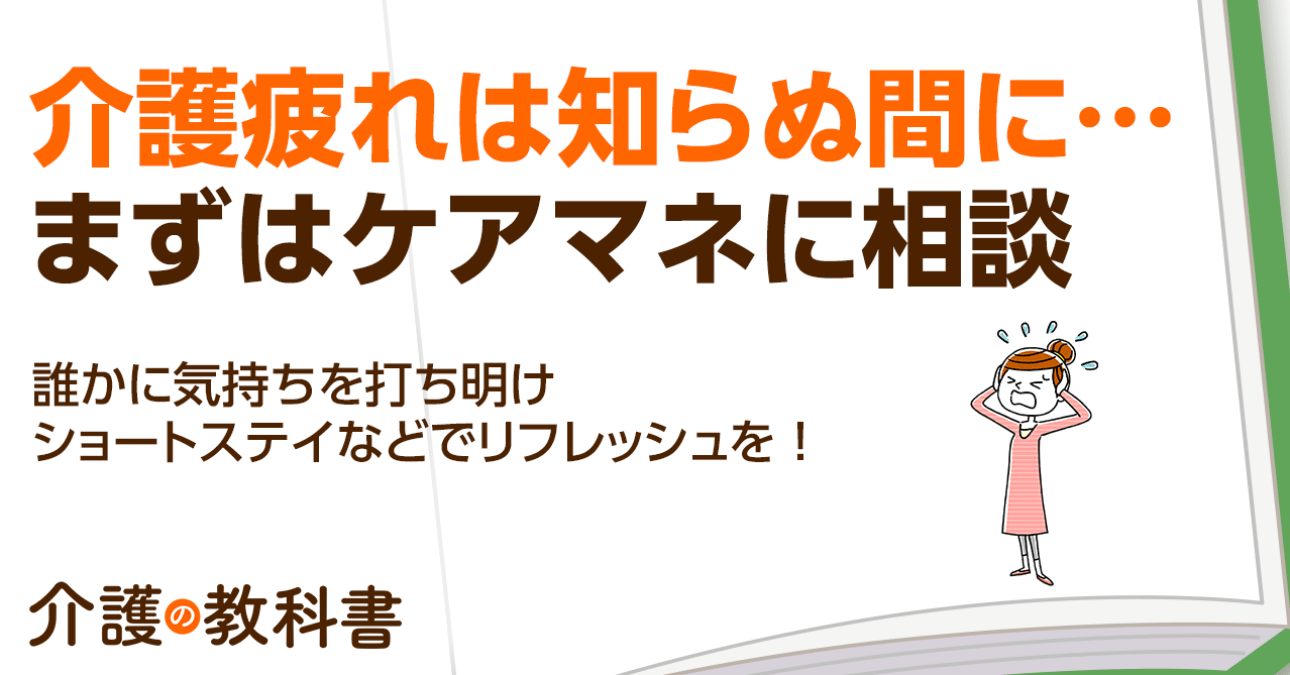こんにちは。介護の教科書「メンタル」を担当している、介護者メンタルケア協会代表で、心理カウンセラーの橋中今日子です。今回は「介護に疲れを感じているときの特徴と対策」についてお話します。
疲労を自覚したときはすでに危険信号
皆様が疲労を自覚するのは、どのようなときでしょうか?
- 体がだるい
- 些細なことで泣いてしまう
- 週末ずっと寝ても、疲れが取れない
- やる気が出ない など
上記のような変化を感じて、はじめて「疲れているな」と自覚する方がほとんどではないでしょうか? 実は、この状態は熱中症で例えば病院での処置が必要なレベルの疲労です。熱中症は「のどが渇いた」と感じてから水を飲むのは対応としては遅く、既に脱水症状が進んでいる状態だと言われます。疲労もそれとまったく同じです。「疲れているな」と自覚したときには、かなりダメージが深くなっています。
しかし、多くの方が疲労に気がつくのは重症になってからです。動けなくなってはじめて、自分が限界にきていたことを知るのです。
初期段階は注意力が落ちる
以下は、20年以上家族を介護してきた私自身の経験と、1,000人以上の家族介護者のご相談を受ける中で見つけた「疲労の初期段階」によくある症状例です。
- 忘れものが増えて、頻繁に物を探している
- 朝起きられなくなり、寝坊が増える
- 予定を間違えたり忘れたりする
- よく物を落とす
- お釣りの計算が面倒になり、すべてお札で支払う
- 集中力がすぐ途切れ、新聞や本を読み進められない
- ミスが増え、自分を責めることが多くなる
注意力が落ちるのが特徴で、車庫入れや時間の計算など、今まで簡単にできていたことの失敗が多くなります。私が母と祖母、弟の3人を1人で在宅介護していたときは、さまざまな失敗をしてきました。しかし、その原因が疲労であることにまったく気づかず、「私はなんてダメな人間なんだ」と自分を責めては落ち込んでいました。

感情の変化は疲れから生じる
イライラしたり、怒鳴ってしまったりするのも「疲労」のサインです。要介護者にやさしい態度を取れないとき、介護者の多くが「私はひどい人間だ」と自身のことを責め、「もっと頑張らなければいけない」と、さらに無理を重ねます。
優しくできない自分を責めたくなったら「限界になるくらい頑張ってきたんだよね」「つらいよね」と、誰かをねぎらうときと同じように自分をいたわってあげてください。

また食事やトイレ介助など、これまでなんとも思わなかった作業がつらくなったり、嫌だと感じたりするときも、疲労が影響していることがあります。特に、汚れや汚物に対する嫌悪感が減ったときは注意が必要。疲労がより進んで、感情や感覚が麻痺している可能性があるからです。
疲労は介護者のセルフネグレクトを招く
セルフネグレクトとは、自分の身だしなみや衛生面へのケア、適切な医療を受けたり食事、入浴など、自分の生活全般の配慮が滞る状態を指します。認知症の方が入浴や着替えを嫌がるのも、セルフネグレクトの一種です。
これは、疲労で心身の余裕がなくなった介護者にも起きます。そして、いったんこの状態に陥ると、状況が改善しても元に戻れなくなることがあるのです。実際に、私自身もセルフネグレクトを経験しました。食事をつくるのも食べるのも面倒になり、何日も髪を洗わなくても平気になりました。
整理整頓する気になれず、家はゴミ屋敷一歩手前までの状態に。その後、祖母や母が施設に入居しても片づける意欲が出ず、何年も家は荒れ放題になったのです。
小さな取り組みで疲労の蓄積を防ぐ
以前の記事でもご紹介しましたが軽い運動や日光浴、五感を刺激したり、心地良いと思う体験を増やすことが疲労の軽減に役立ちます。
私が意識しているのは、「1人になる時間をつくること」。今、コロナ禍で在宅時間が増えています。私だけでなく、同居している知的障がいの弟もストレスを感じやすくなっているためです。弟の訪問介護サービスがあるときは、散歩に行ったり、自分の部屋で仮眠を取ったりするように心がけています。
たとえ20〜30分の時間であったとしても、自分のために使える時間があることでリフレッシュできますし、弟も家族以外の人との交流をとても楽しんでいます。日々の中でできる、小さな対策をぜひ取り入れてみてくださいね。
「同じことを何度も言われて辛い」「介護サービスを嫌がって使ってくれない」といった日々の介護の悩みについては、拙書『がんばらない介護』(ダイヤモンド社)で解説をしています。ぜひ、手にとって参考にしていただければと思います。
また、コロナ禍の介護で経験されていること、対策をとられていることがあれば介護メンタル協会の問い合わせフォームでお声を聞かせてください。お困りのことやご相談には、こちらの「介護の教科書」の記事でお答えできればと考えています。