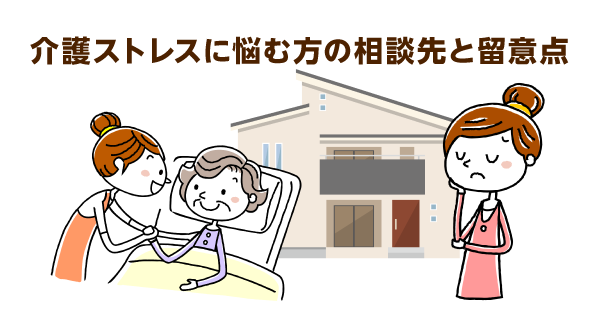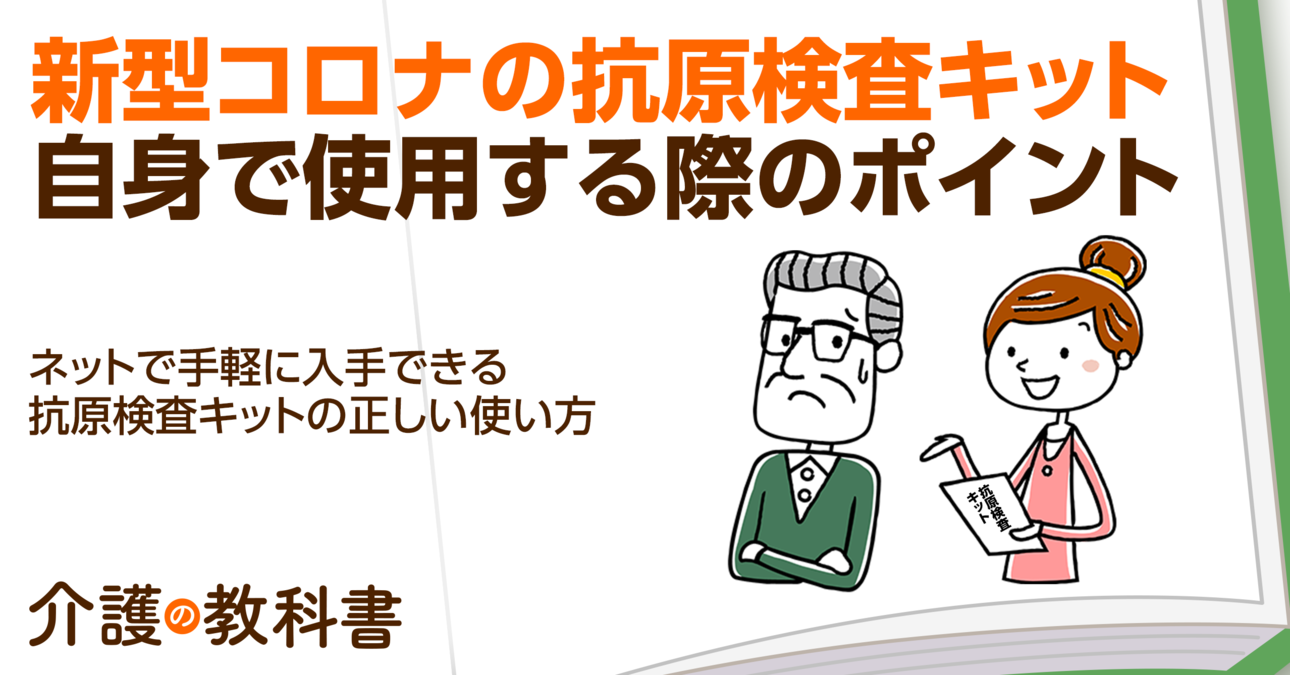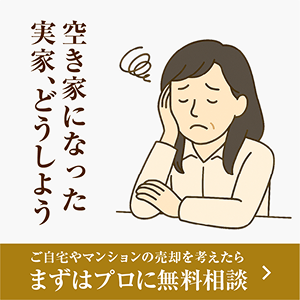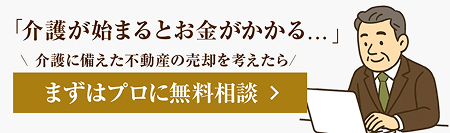こんにちは。介護の教科書「メンタル」を担当している、介護者メンタルケア協会代表で、心理カウンセラーの橋中今日子です。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が全面的に解除されてから、1ヵ月以上が経ちました。
しかし、第2波や第3波の発生に備えて、引き続き注意喚起が続いています。
私が代表を務める介護者メンタルケア協会では、感染への不安を相談される方が減ってきました。対して、「自粛期間中の疲労やストレスを引きずっている」との声が届き始めています。
今回は、「コロナ疲労を解消する3つのポイント」をお話しします。
コロナ禍で蓄積した介護者の疲労
コロナ禍での介護に、ストレスを感じている方々の声が集まっています。
「認知症の母と過ごした3週間がトラウマ」Aさん 50代 会社員 男性
「認知症の母が通うデイサービスが、4月中旬から自主休業しました。同じ時期に私も在宅勤務になったので、時間的な余裕があると思っていましたが、母と過ごす時間が長くなったことで、イライラすることが増えました。母は一日中『あれがない、これがない』と大騒ぎしながら物を探し続けます。私はその対応に追われています。深夜に母が廊下を歩きまわる足音を聞くだけで、心臓がバクバクして眠れません」
Aさんの場合、母親が通うデイサービスの自主休業と在宅勤務が開始したタイミングが重なりました。
最初は「何とかなる」と思っていたそうです。
しかし、母親には認知症特有の症状があり、起きている間は何かを探し続けます。
「ようやく寝てくれた!」と思ったら夜中に起きて、再び家の中を歩き回りながら物を探し始めます。
Aさんは、在宅勤務が始まって1週間で、母親の気配を感じただけで胸がしめつけられるような苦しさを感じるようになりました。
「このままでは自分がダメになる」と絶望的な気分になったと言います。
幸い、GW明けからデイサービスの営業が再開し、日中は一息つけるようになったそうですが、「母と過ごした3週間の間の体験がトラウマになり、心身ともに不調です。来週から通勤が再開される予定ですが、体力が持つか心配です。このまま介護を続けられるかどうか、不安を感じています」と話してくれました。
Aさんのように、介護サービスが利用できなかった数週間を乗り切ったものの、「眠れない」「朝起き上がれない」「憂鬱な気分が晴れない」といった症状を感じている人は少なくありません。

非常事態を乗り切った後の体の不調は自然なこと
新型コロナウイルスに関する報道が過熱し始めた2月頃から、私たちは知らず知らずのうちに緊張感を抱えながら生活しています。
「仕事や家事、介護を行いながら自分自身と要介護者を新型コロナウイルスから守らなければならない」という強い責任感と緊張感が重なったわけです。
これは、介護者だけではなく、医療や福祉に従事し、利用者と家族を守るために働いていた方々も同じ状態だったでしょう。
このように、私たちの脳は緊急事態に直面すると、「闘争逃走反応」というモードに切り替わります。
危機から逃れるために、やる気や集中力を高めるホルモンである「アドレナリン」が放出され、素早く行動するために心拍数が上がります。
スポーツ選手が試合前に気分を上げるために音楽を聴いたりするのは、計画的にこのモードに切り替えてアドレナリンを分泌し、集中力を高めるためです。
「火事場の馬鹿力」とは、アドレナリンが放出されたときのパワーを指します。
闘争逃走反応は、太古の昔に人間が野生動物から命を守るために獲得したもので、私たちが生き抜くうえで必要なモードなのです。
しかし、エネルギーを多く費やし、心身を消耗します。
危機を脱出した後は、1人になれる時間を確保し、栄養バランスの良いものを食べたり良質な睡眠をとるなどして心身を回復させることが必要です。
これは、新たな危機に対応できるように備えるためでもあります。
緊張感を伴う状況が長引き、自分の休息時間が取れずにいる人が少なくありません。
当然、疲労が溜まっています。心身に負担がかかった極限の状態が続けば、何かしらの不調が出ます。
それは「よく頑張りました。今後ために今はゆっくり休みましょう」という、体からのメッセージでもあるのです。

心身の不調を解消する3つの方法
とは言っても、「すぐには休めない」という方もいらっしゃるかもしれません。
「心身の不調を解消するためにできること」を3つご紹介します。
「3つ全部やらなければ」と義務感を持って取り組むと緊張してしまうので、「やってみたい!」と思ったものを試してみてくださいね。
意識して日光を浴びる
通勤の際に会社まで歩いたり、昼休みにコンビニに買い物に行くなどして短時間で複数回、日に当たることを意識してみましょう。
朝日を浴びると、体内時計が整って睡眠の質が上がります。
また、オーストラリアの研究によると、日光を1日15~20分浴びると「セロトニン」というホルモンが分泌されることがわかっています。
セロトニンが分泌されると精神が安定し、安心感が増すと言います。
1回あたりの日光浴を5分とし、4回に細かく分けて行っても効果があります。
外出を控えていたり在宅勤務をしている方は、日光を浴びる時間が減っていると思います。
可能な範囲で、日光浴を行なうようにしましょう。
在宅勤務から会社勤務に戻った方もいらっしゃると思います。「日光を浴びると、精神的に安定する」と意識してみると、より効果が高まるのでぜひ試してみてくださいね。
五感を刺激する
外出する機会が減って、人と会ったり話すことがほとんどない状況では、気分が落ち込んだり、後ろ向きな気持ちになったりします。
そんなときには、五感で心地良いと感じるものを取り入れてみましょう。
ふわっとして肌触りが良いタオルを使ったり、好きな香りのシャンプーを使ってみたり、日常的によく触れるスマートフォンのカバーを新調するなど小さなことでも効果があります。
音楽や動画鑑賞も効果的です。自粛生活で不安を抱えた人を勇気付けるために、SNSで音楽動画を公開しているアーティストが話題になりました。
これまで興味がなかった歌手やミュージカル俳優たちが合唱する動画を見て、感動した方もおられるでしょう。
新しい発見があるかもしれません。「今の自分を励まし、癒すような刺激は何だろう」と、楽しみながら探してみてください。
体を動かしてみる
外出自粛中は、健康な人でも活動量が落ちています。
私自身も、以前は1日1万歩歩以上歩いていたのですが、自宅での仕事が増えたため、1日2,000歩程度しか歩かなくなりました。
そこで、足のむくみや体が重くだるい感じを解消するために10~20分散歩するようにしています。
運動不足は、身体機能の低下だけでなく気分が落ち込むことにもつながります。
「鬱々していたけれど少し歩いたら気分が変わった」「体を軽く動かしたら気分が変わった」などという経験をした方も多いでしょう。
体を動かすと、セロトニンやノルアドレナリンといった心を落ち着かせたり、自律神経を調整してくれる脳内物質が出ることが、畿央大学やほか複数の研究で報告されています。
外出に抵抗をお持ちの方は、立ち上がってその場で軽く体を動かしてみましょう。
ラジオ体操やテレビ体操、その場で足踏みを30秒するだけでも良いのです。
日光浴と同様に、短時間の運動を複数回行っていただいても構いません。
やる気や気力が出てから行動するのではなく、先に体を動かして気分を変える方が、心身に良い影響があるのでぜひ試してみてください。

つらいときほど助けを求める必要がある
つらいときほど、誰かに相談をし、助けを求める必要があります。
けれども、本当に苦しいときには助けを求める意欲が奪われます。
「相談できない」と感じていらっしゃる方は、今回紹介した「心身の不調を軽減するためにできること」をぜひ取り入れてみましょう。
もし、周りの人に相談できなくて苦しい気持ちを抱えておられたら、ぜひ、介護者メンタルケア協会の介護相談お問い合わせフォーム からご相談ください。
介護者メンタルケア協会が発信している、介護の心を軽くする無料メールマガジン「介護に疲れた時、心が軽くなるヒント」でも、心の葛藤の解消法やストレス対策の具体的な方法をお伝えしています。ぜひ登録してくださいね。