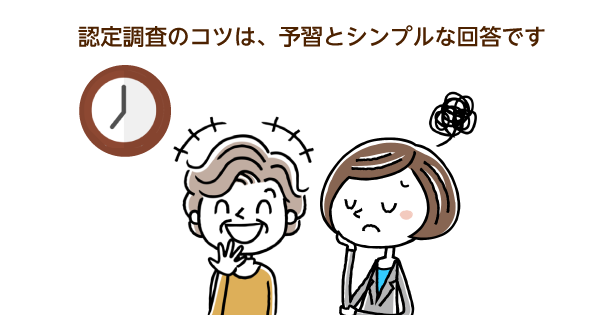こんにちは。介護者メンタルケア協会代表で、心理カウンセラーの橋中今日子です。
今回、家族や親族が介護に参加してくれないときの対処法についてお話します。
介護にかかわろうとしない人の気持ちを知ることが大切
介護者メンタルケア協会には、配偶者や兄弟、親族との間で「意見が合わない」「協力してくれない」「負担に差がある」といった思いを抱えている方からの相談が多数寄せられます。
内容は、「父が施設に入ってから5年間、兄が一度も面会に来ない」「両親と同じ敷地に住んでいる弟が何もしてくれない」など、さまざまです。
頼れるはずの人がいるのに頼れないと、絶望的な気持ちになってしまうことは私にもよくわかります。
私自身、20年以上にわたって家族3人の介護をしてきましたが、一番辛かったのは、近くに住む姉の協力が得られなかったことでした。
ですが、心理学やコミュニケーションについて学んだことで、介護を遠ざける人の心理状態を理解できました。
そのうえで根気強く対策を取り、姉との協力関係は大きく変わりました。

介護にかかわろうとしない人の心理状態
介護に協力したがらない人の心理状態では、以下の3つのケースが考えられます。
- 1)情報や体験が足りず、単に気づいていない
- 2)介護の実態を知るのが不安で、かかわることを拒否している
- 3)状況を多少は理解しているけれど、楽観的に構えて見て見ぬふりをしている
情報や体験が足りず、単に気づいていない
主介護者(主に介護する人)の負担は、周りの人には伝わりにくいものです。
たとえ同居している人であっても、実際に要介護者(介護を必要とする人)と四六時中と過ごすわけではないので、主介護者が具体的に何をしていて何が負担なのか理解することはできません。
別居している人はなおさら、主介護者が追いつめられている状況に気づくことが難しいです。
実際、介護殺人・心中事件の内、ほかに兄弟がいるのにもかかわらず1人で介護によるストレスを抱え込んでいたケースは少なくありません。
事件が起きてから「こんなにも追い詰められていたなんて!」「どうして相談してくれなかったのか!」と家族はショックを受けることになります。
このように、情報が不足しているために協力が得にくい場合は、介護の様子を撮った写真や動画を使って状況を伝えましょう。
その際、「昼間は穏やかに過ごしているけど、夕方や深夜は暴言を吐くことが多い」「トイレの失敗が増えて、汚物の片付けや洗濯で一日が終わる」など、状況を記した箇条書きのメモを添えると効果的です。
ただし、介護費用のレシートなど金額を示すものは、現段階では使わない方がいいでしょう。
相手は「責められた」「自分が何もしてこなかった証拠を突き付けられた」と感じて防衛的に怒ることがあるからです。
距離が離れた家族で、直接的な手助けを得にくい場合には、「何かあった時に病院(あるいは施設)から連絡が取れるように、緊急連絡網の連絡先として記載させてもらっていい?」と聞いて、連絡や情報を共有できる関係性をつくるところから始めましょう。
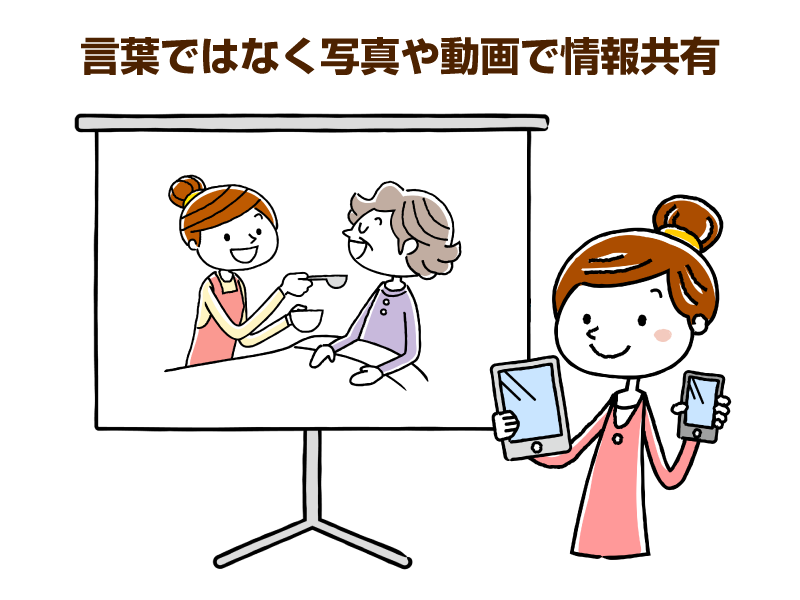
介護の実態を知るのが不安、または見て見ぬふりをしている
人の脳はネガティブな情報を察知すると、「かかわりたくない!」と問題から遠ざかろうとしたり、根拠はないのに「大丈夫だろう」と、問題をなかったことにしようとすることが研究によって明らかになっています。
ちなみに、私の姉は前者のケースでした。
これは脳による生存本能が影響しているので、理性や知性ではコントロールできません。
メールを読んでいるのに返事がなかったり、攻撃的な言葉を投げつけたりするのは、不安から逃れるための防衛的行動です。
「親が認知症になって変わってしまった姿を見たくない」という気持ちや「施設で暮らすなんてかわいそう」という気持ちが生じて、面会に抵抗を示す人もいます。
かかわりを避けようとする態度を取る人は、不安で脳がパニックになっていると考えてください。
パニックは脳の本能的な反応なので、どれだけ理論的に説得しても、対抗できないのです。
家族・親族の協力が得られないときの3つの対処法
①説得しようとせず、まずは不安を取り除く
先述した2)、3)のケースの人に、1)のケース同様に具体的な証拠を提示したり、「大変なの!」「助けて!」と伝えても効果はありません。
かえって不安を煽ることになり、さらに介護の現実を直視せずに逃げようとしてしまいます。
この場合はまず、彼らが介護に対して感じている漠然とした不安を和らげることから始めましょう。
要介護者が楽しんでいる写真とともに、メールやLINEで「元気だよ」と一言添えたり、「〇〇(かかわろうとしない方の名前)の話をしたら喜んでいたよ」など、要介護者が人生を楽しんでいる様子を伝えてみるのです。
これが、始めの一歩です。
しかし、残念なことですが、すぐに協力を得られるようにはならないでしょう。
私の姉の場合も、ボジティブな連絡を始めてから、実際にかかわってくれるようになるまで3年かかりました。

②介護保険・介護保険外サービスを利用する
配偶者や兄弟、親族の協力を得るには時間と工夫が必要です。
しかし、どれだけ工夫しても欲しい反応が得られず、心が折れそうになることもあるでしょう。
介護保険・介護保険外サービスを使っていない場合には積極的に利用して、現実的な自分の負担を減らしましょう。
その際に、家族が非協力的で困っていること、このままの状態が続くとどんなことが起きそうか、といった未来の不安要素を書き出して、ケアマネジャーや施設の相談員さんに伝えておきます。
相談する際に、文章ではなく箇条書きのメモにして渡すと、伝わりやすいです。
③自分がかかわっている項目を記録する
また、自分が介護で携わっていることを箇条書きで記録に残しておくことも効果的です。
面会の回数、衣類やおむつなど日常品にかかる出費、交通費(ガソリン代)などをレシートとともに記録しつづけておきます。
家族の態度が和らぎ、情報の共有ができるようになってから清算しましょう。
これらは、「介護費用を使い込んだのではないか」といった誤解を防ぐための証拠になりますし、相続時の資料にもなります。
プロと一緒に状況改善に努めよう
配偶者や兄弟、親族の協力を得たい、苦労や負担をわかってほしいという期待をあきらめる必要はありません。
まずはケアマネジャーや施設スタッフなどのプロの力を借りて負担を減らしましょう。
それと並行して、介護の事実を直視したがらない人の不安を少しづつ取り除いてみてください。
介護者メンタルケア協会では、介護の心を軽くする無料メールマガジン「介護に疲れた時、心が軽くなるヒント」を配信しています。
ご興味がある方は登録してくださいね。