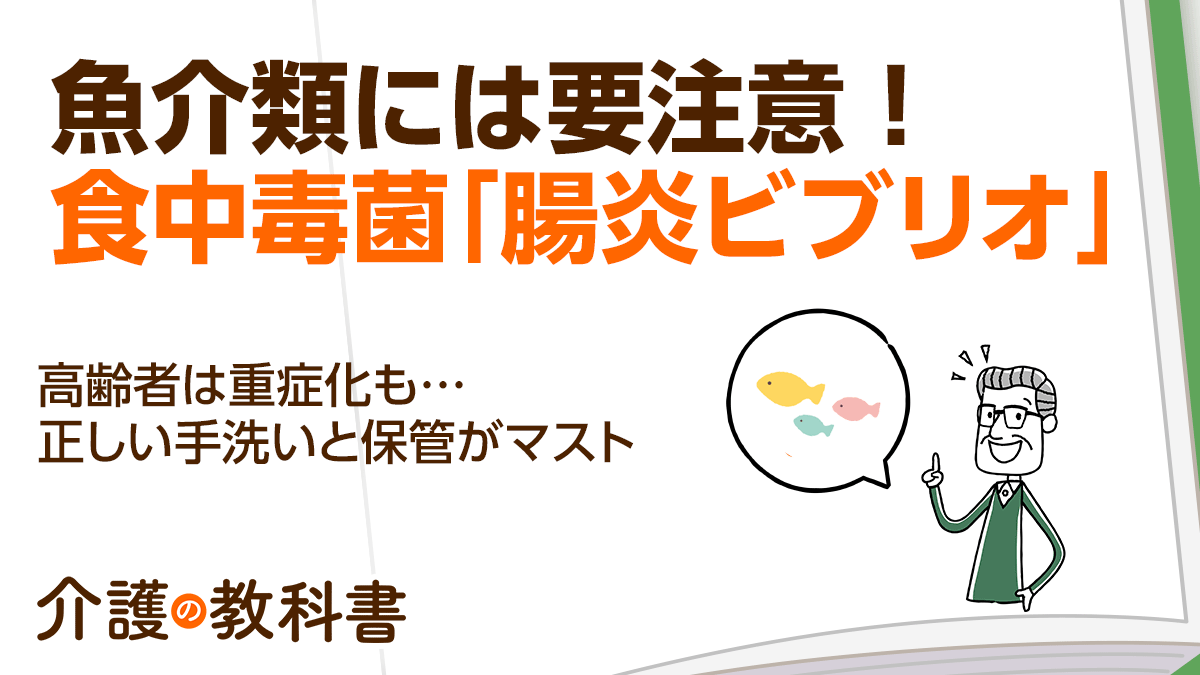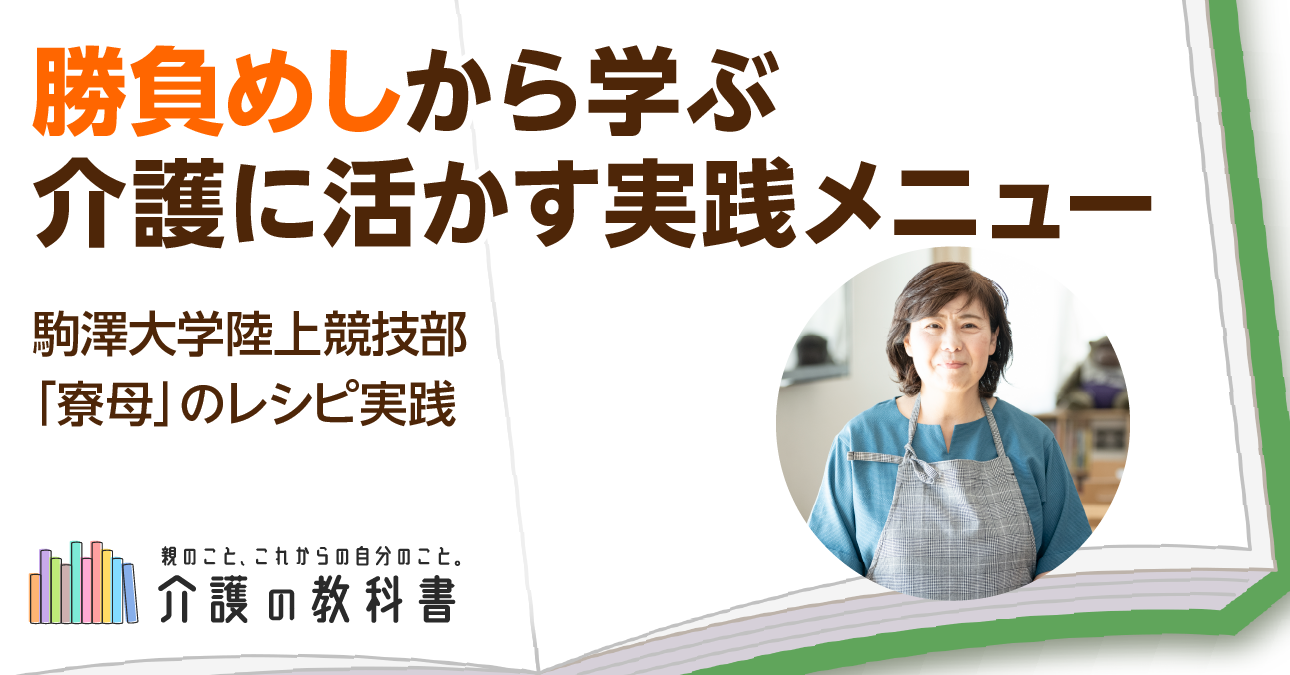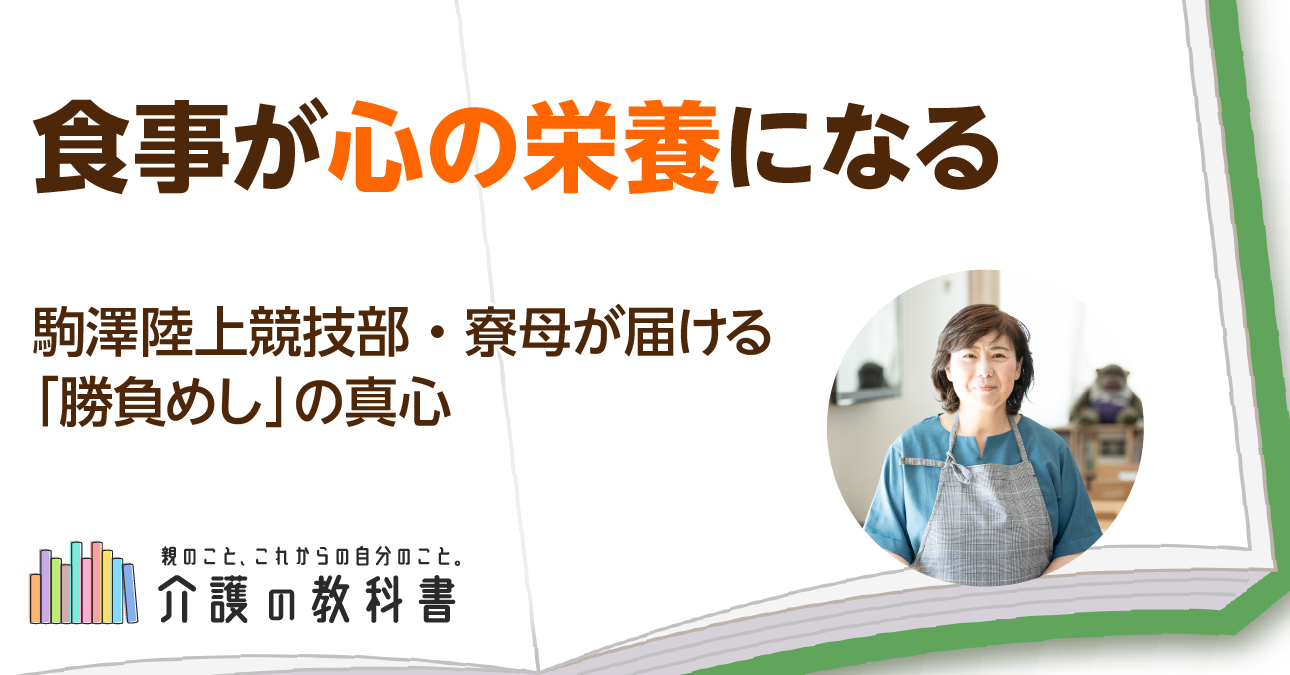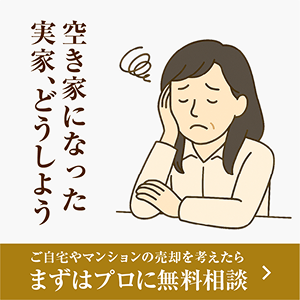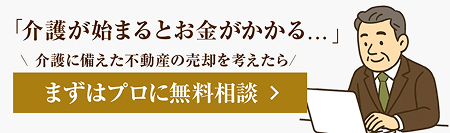食中毒注意報が出される季節になりました。食中毒は1年を通して注意が必要ですが、特に6~8月は注意が必要です。高齢者ですと脱水にもつながる危険性もあります。
今回は夏場に増える「腸炎ビブリオ」について書きたいと思います。
腸炎ビブリオってどんな菌?
腸炎ビブリオは海底の泥のなかに生息する細菌で、塩分(2~5%)でよく発育し、海水温度の高くなる夏場に活発に活動します。
そのため、海水温度が高く、海水中に腸炎ビブリオが多い時期に獲れた魚介類には、腸炎ビブリオが付着していることが多く、感染症も夏場に多く発生しています。
腸炎ビブリオは低温では増殖できません。また、低温で腸炎ビブリオの増殖は抑えられるものの、凍結しても短期間では死滅しないという特徴があります。
腸炎の原因となる食中毒は、腸炎ビブリオ以外では腸管出血性大腸菌(O157、O111など)やカンピロバクター、サルモネラ菌などです。
食中毒を引き起こす細菌の多くは、室温(約20℃)で活発に増え始め、人間や動物の体温ぐらいの温度で増殖のスピードが最も速くなります。また、細菌の多くは湿気を好むため、気温が高くなり始め、湿度も高くなる梅雨時には、細菌による食中毒が増えます。
どんな食品に危険がある?
生で食べる魚介類(すし・刺身・貝類など)が多いですが、食中毒の原因となる細菌やウイルスは目に見えないため、私たちの周りの至るところに存在している可能性があります。
生の肉や魚などの食材には、細菌やウイルスが付着していると考えたほうがいいでしょう。また、いろいろな物に触った自分の手にも、細菌やウイルスが付着していることがあります。細菌やウイルスの付着した手を洗わずに食材や食器などを触ると、手を介して、それらにも細菌やウイルスがついてしまいますので、特に注意が必要です。
食中毒の症状
原因となる食品を食べてから、8~24時間(短い場合で2、3時間)で発症します。症状としては、激しい腹痛、下痢などがあり、発熱、はき気、おう吐を起こす人もいます。
高齢者では体力が低下している方も多く、このような症状がでた場合は症状の進行が早い可能性があるため、早期に病院受診を行うようにすすめてください。
食中毒を防ぐ方法
きれいにしているキッチンでも、食中毒の原因となる細菌やウイルスがまったくいないとは限りません。
食器用スポンジやふきん、シンク、まな板などは、細菌が付着・増殖したり、ウイルスが付着しやすい場所と言われています。
腸炎ビブリオは他の食中毒菌よりも速く増殖できる特徴があります。しかし、この菌は真水(水道水)の中では増殖しません。
腸炎ビブリオの食中毒は以下の方法で予防しましょう。
- 魚介類は、調理前に流水(水道水)で良く洗って菌を洗い流す
- 魚介類に使った調理器具類は良く洗浄・消毒して二次汚染を防ぐ
- 魚介類を調理したままのまな板で、野菜などを切らない(まな板を使い分ける)
- 夏季の魚介類の生食は十分注意し、わずかな時間でも冷蔵庫でできれば4℃以下に保存する
- 冷凍食品を解凍する際は専用の解凍庫や冷蔵庫内で行なう
- 加熱調理する場合は中心部まで充分に加熱する(60℃、10分以上)
食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。
食中毒を防ぐためには、細菌を食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」という3つが原則です。
このほか、食品に触れる前には必ずしっかりとした手洗いを行うことも食中毒の予防になります。正しい手洗いを心がけましょう。