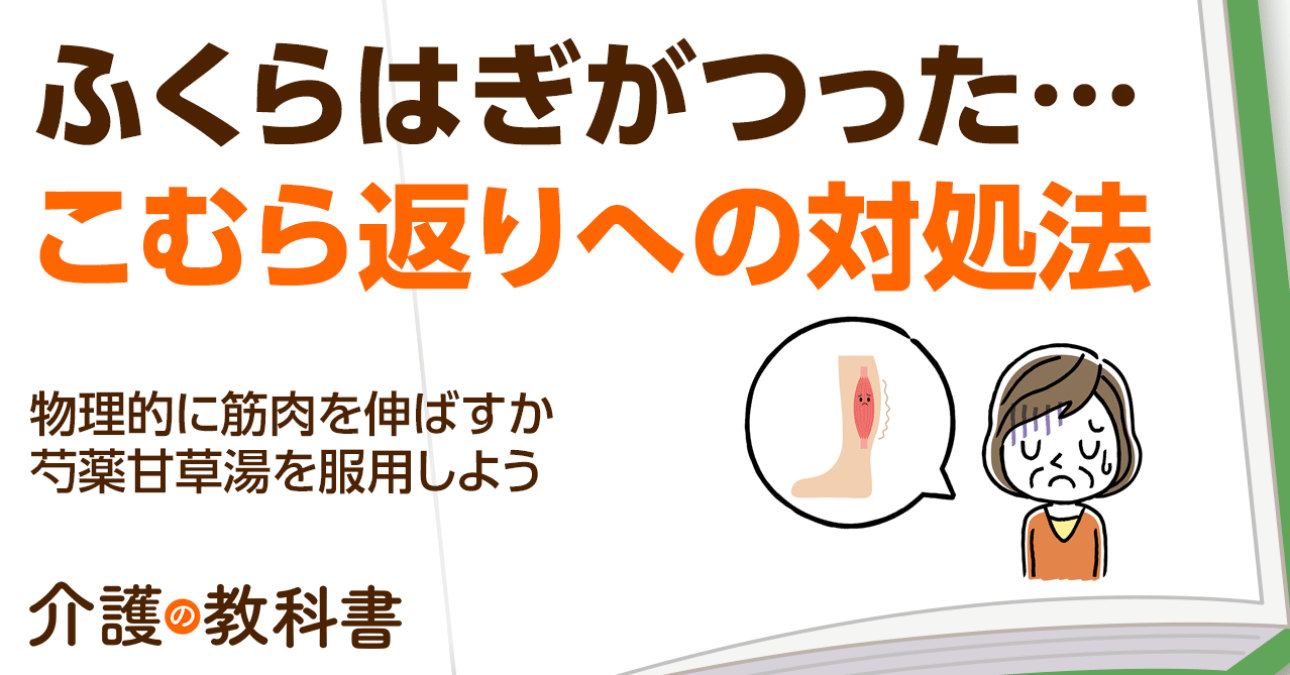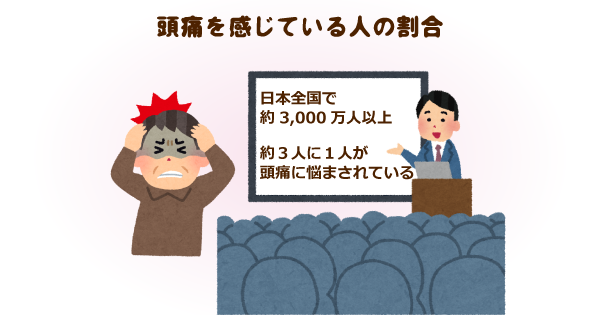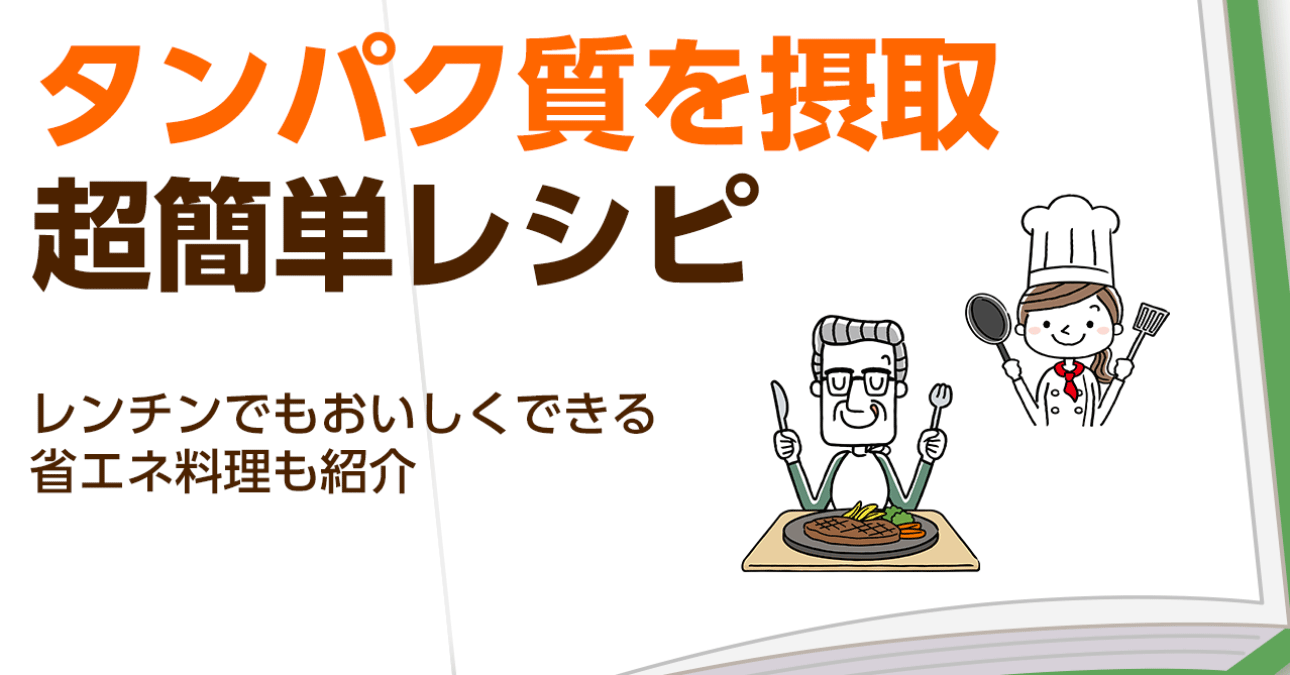高齢になると外出する時間が減ったり、家で座って過ごす時間が増える方も多いのではないでしょうか?
それに加えて体重も減ってきているという方は、必要な栄養を十分に摂れていない可能性があります。活動量や食欲が低下してくると、健康維持のために必要なタンパク質も十分に摂取できていない可能性があります。
タンパク質は筋力の向上に関連があるため、高齢者では若い頃と同じかそれ以上に摂取する必要があります。
日本人の食事摂取基準(2015 年版)では、70歳以上の高齢者について、タンパク質の推定平均必要量は1日0.85g/kgと成人の0.72g/kgよりも高い値を基に計算されています。
そこで、どのようにして必要なタンパク質を摂って体の中で筋肉になるのかを解説します。
タンパク質の働き
タンパク質は私たち人間が生きていくために必要な栄養素で下の表1のようにさまざまな働き(成分)があります。
| 体構成成分 | 筋肉、臓器、皮膚、毛髪 |
|---|---|
| 体調節機能成分 | ホルモン、酵素、抗体 |
| 食品成分 | 豆類、卵類、肉類、魚類 |
タンパク質はアミノ酸が50以上結合した化合物ですが、食品タンパク質は、アミノ酸の構成により体内での働きが違います。
アミノ酸の中で、特に筋肉の合成に重要な役目を果たすBCAA(分岐鎖アミノ酸)と呼ばれているものがあります。BCAAとはアミノ酸のバリン・ロイシン・イソロイシンの3つの総称です。
その中でもロイシンは筋たんぱくの合成に関係しているという研究も出ています。日本人の食事摂取基準2020年度版では18歳以上・体重60kgの人であれば、ロイシンは1日に最低2,34g必要としています。
ロイシンを多く含む食べ物は、マグロ・サンマなどの魚類、牛肉・鶏肉・豚肉などの肉類、豆腐などの大豆製品、牛乳・チーズなどの乳製品などが主に挙げられます。
中でもマグロの赤身は刺身8切れほどで2.1gと大変多く含まれています。ほかにも次のような食品に多く含まれています。
- 鶏胸肉100g:1.9g
- サンマ1匹:1.6g
- 鶏もも肉100g:1.5g
- 牛肉(サーロイン)100g:1.1g
- 卵1個:1.1g

高齢者が摂取しにくい理由
自分の嗜好に合わせて毎日の食事に取り入れてほしいところですが、高齢者にとっては摂取しにくいものもあります。
高齢になりタンパク質を摂りにくくなる理由はさまざまありますが、私が実際にケアを担当した高齢者の方には、以下のような理由がありました。
- 夫婦で暮らしていたが急に一人暮らしになり、近所に知人が少なかったので精神面で食欲が落ちてしまった
- 口腔の状態(義歯があわない・噛む力が弱くなった・飲み込むときにむせがひどくて食べることがおっくう)の低下
- 認知症状の低下により食欲が落ちてしまう
近くにこうした方がいる場合は、まずこの原因を解決する方法を見つけることが大切です。
しかし、自分で食べる量や食事の質を確認するのは大変です。地域包括支援センターや市役所の福祉課などの窓口で相談すると、栄養について支援してくれる管理栄養士を紹介してくれると思います。ささいなお悩みでもぜひ相談してみてください。
おやつを準備して手軽にタンパク質を摂取
原因がみつかったら、次は食べる物をどのように選べば元気に動ける体をつくることができるのかを考えましょう。工夫の仕方についてご提案します。
高齢になると若い頃のように3食で必要な栄養量を摂ることが難しくなることがあるため、そのような方は朝・昼・夕食の間に間食として足りない栄養を摂ると良いでしょう。
間食と言っても「おやつ」ではなく、タンパク質が摂れるものを選びます。例えば、次のような食べ物です。
- 具入りおにぎり(鮭・サバ・卵など)
- 卵やハムのサンドイッチ
- たまごかけごはん
- お好み焼き
- たこ焼き
- チーズ など
これらを手軽に食べられるように準備しておくと良いでしょう。最近は日持ちする冷凍食品も増えているので、買い物の際におやつの購入も検討してみてください。
そのほか、食事に次のような工夫を加えてもタンパク質の摂取量が安定します。
- ごはん+ツナやサバやサンマの缶詰+卵
- カップラーメンや雑炊等+卵+冷凍野菜(ほうれんそう・ブロッコリーなど)
個人の嗜好に合わせて、これらの食材を積極的に選んだり、普段の食事に追加してみてください。

食べた物を消化して筋肉にするためには、食事だけでなく、運動をすることも必要です。BCAAは筋肉をつくり出す一方で運動中に使われることも多いので、自らの筋肉のBCAAが不足しないよう運動前に摂取すると良いでしょう。