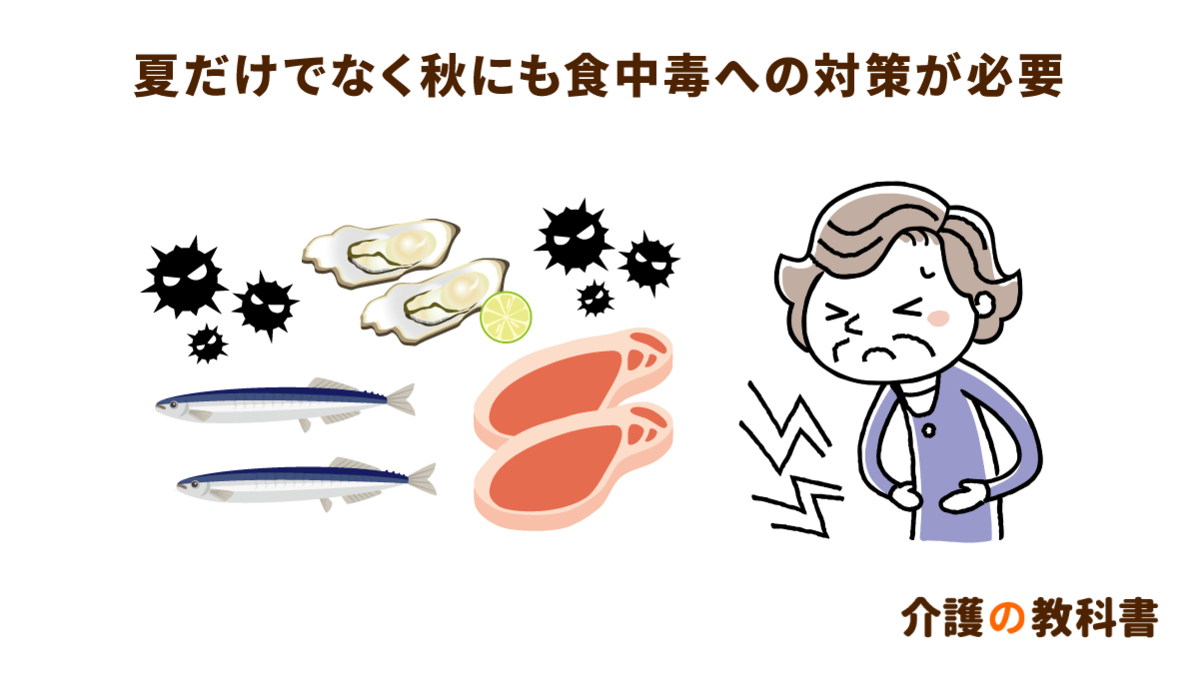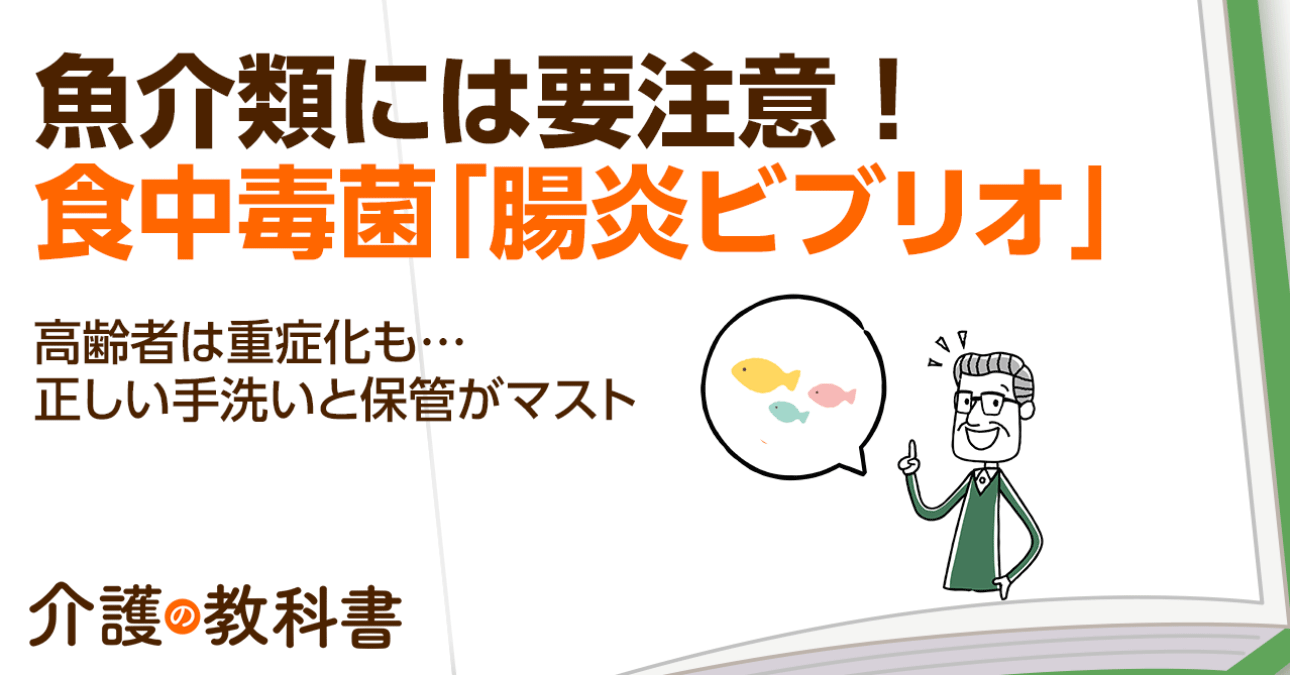皆さん、こんにちは。管理栄養士の濱田美紀です。
食中毒というと、梅雨や夏の時期に気をつければいいと思っている方が多いのではないかと思います。しかし、実際には年間を通して食中毒は発生しています。
今回は、涼しくなってきた秋でも気をつけたい食中毒についてお話いたします。
食中毒を引き起こす「原因物質」の基礎知識
昨年発生した食中毒で多かったのは、カンピロバクター、ノロウイルス、サルモネラ菌によるものでした。それぞれの主な原因食品や潜伏期間、症状と対策について説明します。
カンピロバクター
牛や豚、鶏の腸内に生息し、100個程度の少ない菌数で発症するのが特徴です。細菌性食中毒の中では最も発生件数が多く、事故のほとんどが鶏肉の加熱不足によって発生しています。まれに合併症として、ギラン・バレー症候群(四肢や顔、呼吸器官などに麻痺などが起こる疾患)などを引き起こすことがあります。
主な原因食品:鶏肉の生食、鶏肉などから二次汚染された食材、井戸水
潜伏期間:2~5日
症状:下痢、嘔吐、発熱、腹痛、筋肉痛、悪寒など
対策:加熱殺菌(中心温度75℃で1分以上)、生野菜はよく洗浄する。食肉にふれた手指や調理器具は、その都度洗浄・消毒し、食肉とほかの食品が触れないようにする
ノロウイルス
一度で多くの患者が出ることがあるのが特徴です。もともとは、牡蠣などの二枚貝を食べることで事故が発生していましたが、現在では人の糞便や嘔吐物を介して、人から人へ感染するケースもあります。また、数個程度のウイルスで発症する場合もあり、乾燥、低温、加熱、アルコール消毒にも強いウイルスです。
主な原因食品:二枚貝(牡蠣)、ノロウイルスに感染した調理従事者が汚染した食品
潜伏期間:24~48時間
症状:腹痛、下痢、発熱、嘔吐、吐き気
対策:加熱殺菌(中心温度90℃で90秒以上)。調理する人の健康管理を徹底して、特に下痢などの症状がある人は調理をしないようにする。手洗いの徹底、調理器具の洗浄・消毒。嘔吐物の適切な処理(次亜塩素酸ナトリウム1,000ppm)。トイレの定期的な洗浄・消毒
サルモネラ菌
動物の腸管内や自然界に広く生息し、これまでに2,500種以上の血清型が発見されています。食肉や卵以外にも、ネズミやハエ、ゴキブリ、は虫類などのペット、そのほか汚染された水から感染する場合もあります。1998年には、サルモネラ菌対策として「食品衛生法」が改正され、鶏卵の表示基準、液卵の規格基準が定められました。
主な原因食品:鶏卵(加工品含む)、食肉(加工品含む)
潜伏期間:5~72時間
症状:下痢、嘔吐、発熱、腹痛、悪心など
対策:加熱殺菌(中心温度75℃で1分以上)。食肉などは低温管理する。卵の割り置きはしない。食肉にふれた手指や調理器具はその都度洗浄・消毒し、食肉と他の食品が触れないようにする
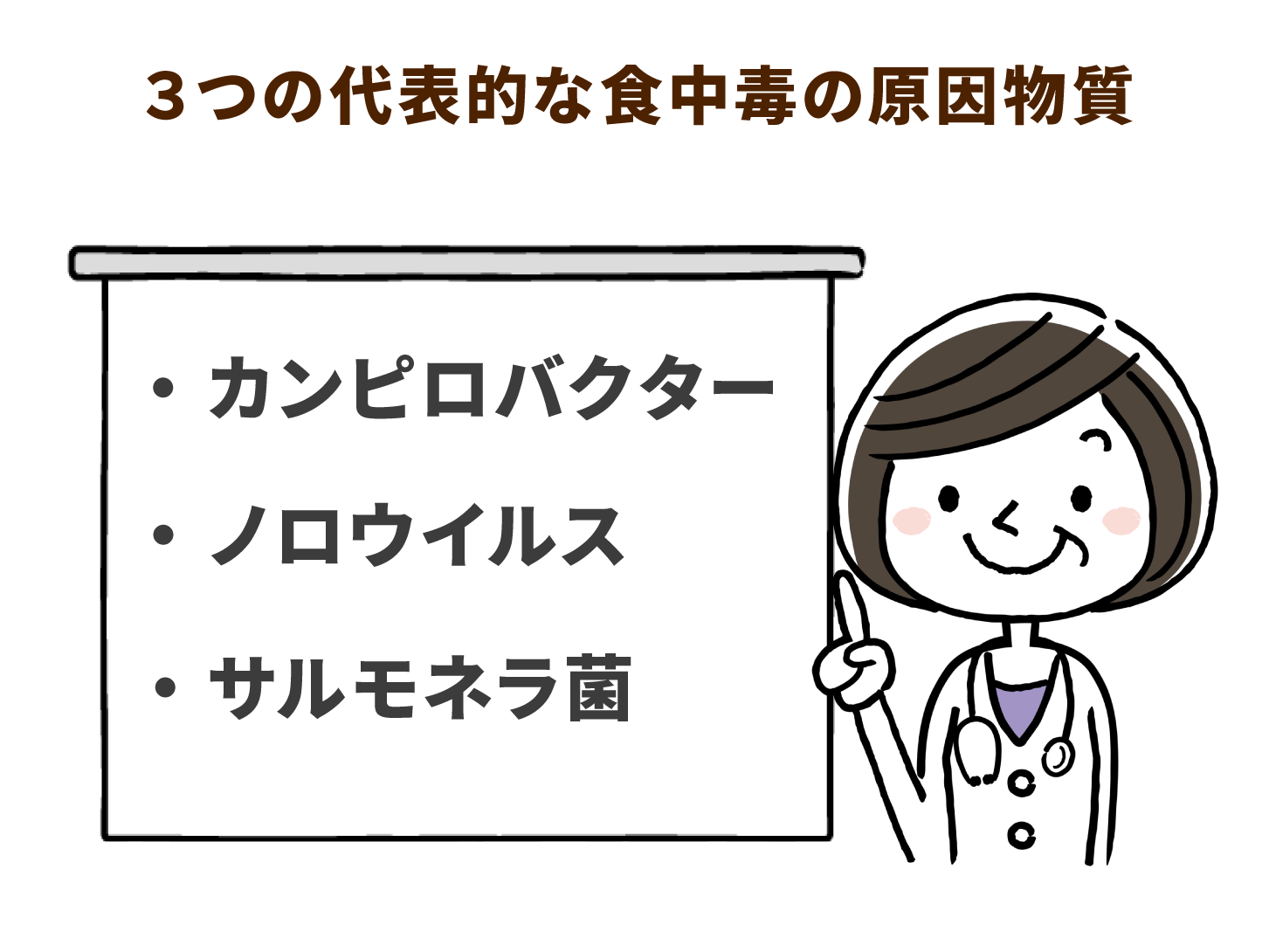
そのほか、加熱処理しても死滅しないウエルシュ菌は、カレーやシチューなどを大量につくった際、保存状態や再加熱の方法が悪い場合に食中毒を引き起こします。腸管出血性大腸菌や黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌などさまざまな食中毒菌があります。
食中毒予防の「3つの基本」
食中毒になると、多くは腹痛や下痢、嘔吐という消化管症状や発熱が出ます。食中毒にならないために家庭でできる基本的な予防策を説明しましょう。
- つけない
- 食中毒の原因物質である細菌やウイルスは小さくて目で見ることはできないため、食品についているかどうかを確かめることはできません。食中毒菌をつけないようにするためには、手で食材で洗うことができるものは「しっかり洗う」「調理をするまな板や包丁、食器をきれいに洗い乾燥する」「食中毒菌が多く付着していると考えられる肉や魚はほかの食品と分けて冷蔵・冷凍保存をする」といったことに気をつけて、食中毒菌をつけないようにすることが大切です。
- ふやさない
- 細菌やウイルスは、時間とともに増えていきます。また、菌が大好きな温度、栄養、水分がある環境になると育ちやすくなります。生ものやつくった料理をあたたかい部屋に置いたままにしておくと、細菌やウイルスが増えてしまいます。準備した料理はなるべく早く食べてしまうか、冷蔵庫や冷凍庫で保存し、食べる際にしっかりあたためるようにしましょう。
- やっつける
- 多くの細菌やウイルスは、高い温度に弱いので、充分に加熱することでやっつけることができます。料理をするときは食材の中心まで熱が通るように充分加熱しましょう。
「3つの基本」を守るために家庭でできる対策
これまで食中毒を起こす、細菌やウイルスの種類や予防策について説明しましたが、このほかでご家庭でできる予防策を紹介します。
- 調理の前には必ずしっかり手を洗う
-
厚生労働省が推奨している正しい手洗いは以下の通りです。
- 流水でよく手を濡らした後、石けんをつけ、手のひらをよくこする
- 手の甲をのばすようにこする
- 指先・爪の間を念入りにこする
- 指の間を洗う
- 親指と手のひらをねじり洗いをする
- 手首も忘れずに洗う
- まな板を熱湯で消毒する
- 調理するときに使うまな板に細菌などが付着していると、食品にもついてしまいます。そのため、消毒することが大切です。食品安全員会の資料によると、腸管出血性大腸菌O157を付着させたまな板を70℃のお湯で洗浄した後には、菌数がゼロになったという報告もあります。
- 布巾やスポンジを煮沸消毒する
- 毎日使う布巾やスポンジも、細菌が付着しやすいので気をつけないといけません。1日の最後に鍋などにお湯を沸かして5分煮沸消毒すると、大腸菌群はほとんどなくなります。

これからの季節は特にノロウイルスの発生が心配な時期になります。皆さんもきちんと食中毒予防をして、おいしく楽しく食事をしてくださいね。