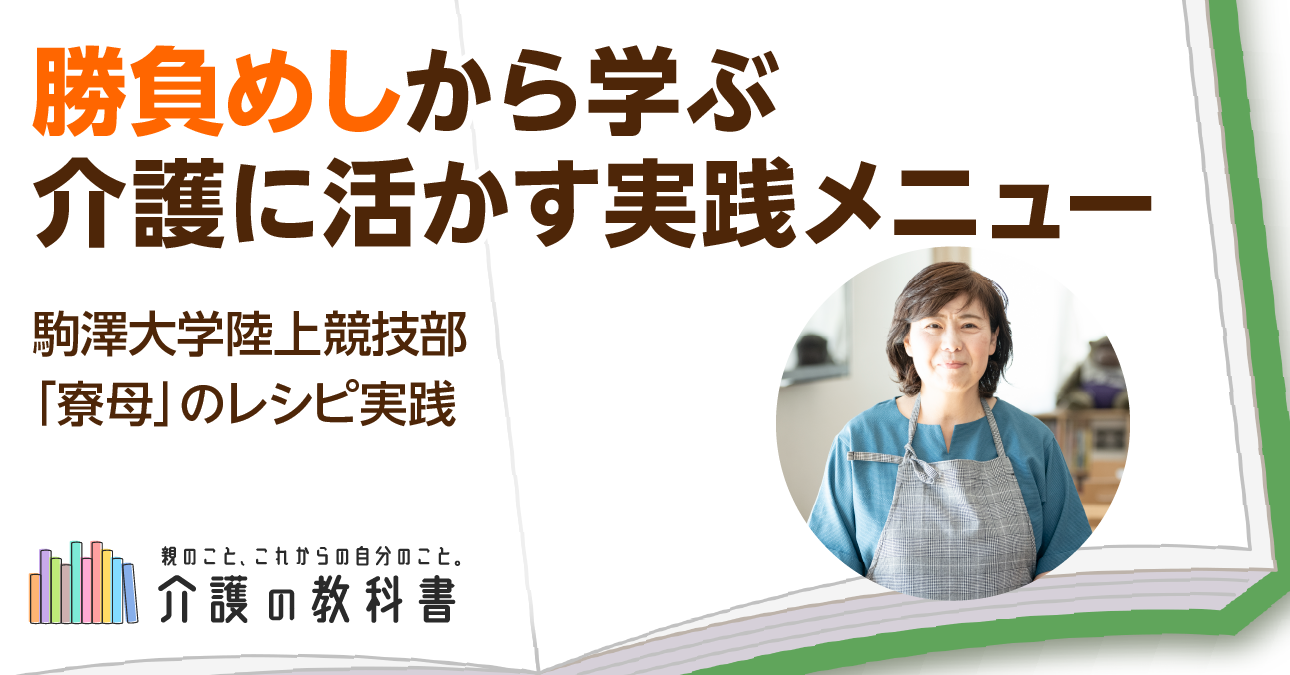ヘルパーに頼める食事作りの範囲と料金の仕組み
訪問介護のヘルパーに食事作りを依頼する場合、介護保険を使うか自費で依頼するかで、頼める内容や料金は大きく変わります。まずは、それぞれのサービス内容と料金体系を理解しておきましょう。
ヘルパーができる食事作りの範囲
訪問介護のヘルパーに食事作りを依頼する際、「介護保険を使うサービス」と「全額自己負担の自費サービス」では、頼める範囲が大きく異なります。
介護保険の訪問介護(生活援助)で認められる調理は、要介護認定を受けた本人のための食事準備に限定されるのが原則です。同居している家族がいる場合、家族分の調理をヘルパーに依頼することは基本的にできません。
これは、介護保険が利用者本人の生活を援助するために設計されており、家族の家事代行サービスとして機能することを想定していないためです。
また、調理できる分量にも制限があります。数日分をまとめてつくる「作り置き」や「常備菜の大量調理」は、原則として認められていません。
認められるのは、利用者の健康管理上、当日分や翌日分など、直ちに必要な最小限の食事の準備のみとなります。
一方、自費サービス(保険外サービス)では、介護保険法の制約を受けないため、サービス内容の自由度が高くなります。事業所と利用者との間の契約に基づいてサービスが決定されるため、家族全員分の食事作りや、数日分の常備菜、冷凍保存食の大量調理も可能です。
介護保険の範囲を超えた広範な支援を求める場合は、介護保険と自費サービスを組み合わせて利用することを検討するとよいでしょう。
ヘルパーに食事作りを依頼する際の材料費
ヘルパーに食事作りを依頼する際、ヘルパーの労働に対する費用は介護保険の介護報酬として支払われますが、調理に使用する食材費、調味料費、消耗品費などは、介護報酬には含まれない実費負担となります。
食材費は、介護保険サービスの自己負担割合の対象外であり、別途、全額が利用者の実費負担となります。
食材の購入(買い物代行)は、利用者の生活を援助する行為として、訪問介護のサービス提供時間内に組み込まれることがあります。
買い物にかかるヘルパーの支援時間は、ケアプランに位置づけられている場合、介護保険の訪問介護サービス(生活援助)の対象となります。生活援助のサービス時間は、報酬算定上「20分以上45分未満」や「45分以上」などの区分に分けられていますが、これはあくまで算定の目安であり、実際のサービス提供時間は利用者の状況や必要性に応じて柔軟に設定されます。
買い物時間が介護保険の適用時間を超えた場合、超過分は事業所が定める自費(時間単価制)での支払いとなる可能性があります。
ヘルパーが利用者に代わって食材費を立て替えた場合、事業所は領収書を添付し、速やかに利用者へ請求・精算する義務を負います。金銭トラブルを避けるため、多くの事業所は事前に必要な金額をお預かりし対応しています。
生活援助の自己負担額を抑えるには、利用者が事前に具体的な買い物リストを作成したり、家族が材料を揃えておいたりと、ヘルパーが効率的に買い物を行えるよう準備しておくことが重要です。

介護保険と自費サービスの料金体系の違い
ヘルパーによる食事作りサービスの費用は、「介護保険」と「自費サービス」というまったく異なる料金体系で計算されます。
介護保険の料金
介護保険サービスでは、サービス内容と提供時間に応じて定められた「単位」を用いて費用が計算されます。この単位は全国一律ですが、実際の1単位あたりの円換算額は、物価や人件費を考慮した「地域区分」によって変動します。
例えば、東京23区や政令指定都市の一部など、物価の高い地域は「1級地」に分類され、1単位あたり11.40円(2024年度概算)が適用されます。
利用者が実際に支払う金額は、この総費用に、所得に応じた自己負担割合(1割~3割)を乗じた金額です。
訪問介護の生活援助(20分以上45分未満)が179単位の場合、1級地での総費用は2,041円(179単位×11.40円)となります。自己負担1割であれば、約204円の支払いです。
自費サービスの料金
自費サービス(保険外サービス)は、介護保険法の制限を受けず、事業所が自由に設定する「時間単価」に基づいて費用が発生します。この費用は全額利用者の負担です。
一般的な家事代行や料理代行サービスの時間単価は、地域や事業所のブランド、ヘルパーのスキルレベルによって変動しますが、通常3,000円から5,000円程度が市場相場となります。
自費サービスでは、契約時間外のサービス、早朝・夜間の割増料金、交通費、家族分調理の追加料金など、さまざまな形で加算が発生し得ます。
ヘルパーの食事作り料金シミュレーション
ここでは、具体的な利用パターンに基づき費用をシミュレーションし、介護保険の費用対効果と区分支給限度額への影響を確認していきます。
前提として、1級地(1単位11.4円)、自己負担1割、生活援助(20分以上45分未満:179単位)として計算しています。
週2回利用した場合
週2回の利用は、費用を抑えつつ、安定した食事支援を受けるのに適したケースです。
介護保険(生活援助)を週2回(月8回)利用した場合の概算費用は以下の通りとなります。
- 1回あたりの自己負担額:179単位×11.4円/単位×0.1(1割負担)で約204円
- 月額自己負担額:204円×8回で1,632円
この利用頻度であれば、介護保険の限度額を、訪問リハビリテーションやデイサービスなど、ほかのサービスに充てられます。
毎日利用+作り置きの場合
毎日の食事支援と、保険外の作り置きサービスを自費で利用する場合は、費用体系が複雑になるため注意が必要です。
まず、毎日訪問(月30回)を介護保険で利用した場合の概算費用を計算します。
- 1回あたりの自己負担額:約204円
- 月額自己負担額:204円×30回で約6,120円
次に、作り置きの自費サービスを利用する場合の料金を合わせます。
例えば、週1回、2時間(月4回)の作り置きサービスを依頼し、市場相場を4,000円/時間と仮定した場合、自費部分の月額費用は以下の通りとなります。
- 4,000円/時間×2時間×4回で32,000円
この場合の合計月額費用は、以下の通りです。
- 6,120円(保険)+32,000円(自費)=40,700円
また、費用面だけでなく、制度的な注意点も考慮する必要があります。毎日訪問介護を利用し、生活援助の利用回数が大幅に増加すると、区分支給限度額の利用割合が高まります。
厚生労働省の通知では、介護保険の利用限度額の7割以上を使い、そのうち訪問介護が6割以上を占める場合、ケアプランが市町村による検証(チェック)の対象となることが示されています。
毎日訪問介護で食事作りを依頼するケースは、制度が想定していない「過度な依存」と見なされる傾向があり、検証の結果、訪問介護の利用抑制や、他のサービスへの切り替え指導が入る可能性があります。
保険利用を週数回に減らし、残りのニーズを自費の作り置きに切り替える選択肢もあります。これにより全体的な費用は増加しますが、過度な利用と見なされるリスクを回避し、生活の質を高めるためには有効な手段といえるでしょう。

家族分の料理作りや買い物代行依頼など特殊な場合
介護保険では対応できない特殊なニーズ、特に「家族分の調理」や「大量の買い物代行」は、自費サービスの利用が必須となります。
家族分の調理は、全額自費サービスとなるため、費用は事業所が定める時間単価(例:4,000円/時間)に基づいて計算されます。事業所によっては、調理量や人数に応じて追加料金を設定するケースもあるでしょう。
買い物代行についても、自費サービスを利用するメリットは大きいでしょう。介護保険では「最低限の買い物」という制約がありますが、自費サービスでは、移動時間、購入時間、帰宅時間すべてがヘルパーの労働時間として時間単価で計算されるため、大量の食材や日用品をまとめて購入できます。
これらの特殊なニーズを自費で賄うことは、直接的には利用者の介護費用とは関係しませんが、間接的に高齢者本人や家族の生活の質を安定させ、長期的な介護の継続を可能にする効果も期待できます。
家族の食事負担が重いと介護疲れが生じやすいため、自費サービスで家族分の食事作りを代行することで、家族は休息や高齢者本人との交流に時間を割けるようになります。
ヘルパーに食事作りを依頼する際のポイント
介護サービスは、高齢者本人の状態や制度の変更に伴い、常に適切な管理と見直しが行われます。ここでは、ヘルパーに食事作りを依頼する際に押さえておきたいポイントを解説します。
介護保険を最大限活用するポイント
介護保険を上手に活用するには、まず自分の要介護度に応じた月間の利用限度額を把握しておくことが大切です。この限度額内で必要なサービスを組み立てることになります。
介護保険を使う際は、入浴や排泄などの身体介護やリハビリテーションなど、身体機能の維持・向上に直結する必要なサービスを優先的に確保することをおすすめします。
食事作りを含む生活援助は比較的費用が安く利用しやすいサービスですが、利用しすぎると、より重要なサービスに回せる予算が少なくなってしまう可能性があります。
また、生活援助を過度に利用すると、市町村からケアプランの見直しを求められることがあります。厚生労働省の通知では、限度額の利用割合が7割以上で、かつその中で訪問介護が6割以上を占める場合、ケアプランが検証の対象となることが示されています。
こうした状況を避けるには、訪問介護だけに頼らず、デイサービスや訪問看護など、ほかの必要なサービスも組み合わせて利用するのが良いでしょう。
限度額の利用率が50%〜60%を超えてきたら、ケアマネジャーに相談しながら、訪問介護を減らして自費サービスに切り替えるなど、早めに見直しを検討することが大切です。
ヘルパーサービスを選ぶポイント
食事作りは利用者の健康に直結するため、料金の安さだけでなく、サービスの質と事業所の信頼性に着目して選ぶことが大切です。
- 調理に対応できるか
- 事業所が、介護職員初任者研修などの資格に加え、調理研修や衛生管理に関する独自の研修を実施しているかを確認すると良いでしょう。
特に、糖尿病食や腎臓病食などの制限食が必要な場合は、栄養士や調理師の指導を受けているヘルパーがいるかを確認することが重要です。 - 料金体系がはっきりしているか
- 時間単価、最低利用時間、家族分調理の追加料金、キャンセル料、交通費など、すべての料金が契約前に明確に示されているかをチェックし、後々のトラブルを避けましょう。
事業所が取得している加算(例:サービス提供体制強化加算)は、サービスの質の目安になります。

サービスの利用見直しタイミング
介護サービスは、一度決めたら終わりではなく、利用者の状態や生活環境の変化に合わせて、定期的に見直すことが大切です。
- 利用者の身体状況や要介護度が変わったとき
- 飲み込みや噛む力が変化した場合は、調理方法や食事の形態(ペースト食、きざみ食など)を変更する必要があり、ヘルパーのサービス時間にも影響が出ます。
また、要介護度が更新されれば、利用できる限度額が変わるため、ケアプラン全体を見直す必要があるでしょう。 - 調理した食事が頻繁に残るようになったとき
- 量が多すぎる、好みに合わない、あるいは食欲が低下している可能性があるため、ヘルパー事務所やケアマネジャーに相談してサービス内容を調整しましょう。
- 限度額が不足し始めた場合・市町村からケアプランの検証依頼があった場合
- 直ちにサービス内容を見直すか、自費サービスへの切り替えを検討するタイミングです。
- 介護報酬が改訂された場合
- 介護報酬は、原則として3年ごとに改定され、単位数や加算のルールが変わります。これにより自己負担額が変わるため、改定のタイミングでサービスの利用頻度を再検討すると良いでしょう。
- 家族に生活環境の変化があったとき
- 家族が介護に専念できるようになった場合や、逆に家族が介護疲れで支援が難しくなった場合など、必要性が変化した場合は、訪問介護の必要性を見直すタイミングです。
利用者の状態やニーズは常に変化するため、問題が起きてから対応するのではなく、定期的にケアマネジャーと相談しながら、無理なく続けられる介護の形を整えていくことが大切です。
まとめ
ヘルパーによる食事作りサービスは、介護保険を利用すれば1回あたり数百円程度の負担で利用できます。
ただし、利用者本人分の調理に限定され、家族分や作り置きは原則として認められないため、家族分の調理や大量調理を希望する場合は、自費サービスを利用する必要があります。
介護保険は身体介護やリハビリなど優先度の高いサービスに集中させ、生活援助は必要最低限にとどめることで、長期的に安定した介護生活を送ることができるでしょう。
サービスを選ぶ際は、料金だけでなく調理技術や事業所の体制も確認し、定期的に利用者の状態に合わせて見直すことが大切です。
介護保険と自費サービスを上手に組み合わせることで、利用者も家族も安心できる食生活を実現できます。まずは包括支援センターやケアマネジャーに相談し、自分たちに合ったサービスの形を見つけていきましょう。