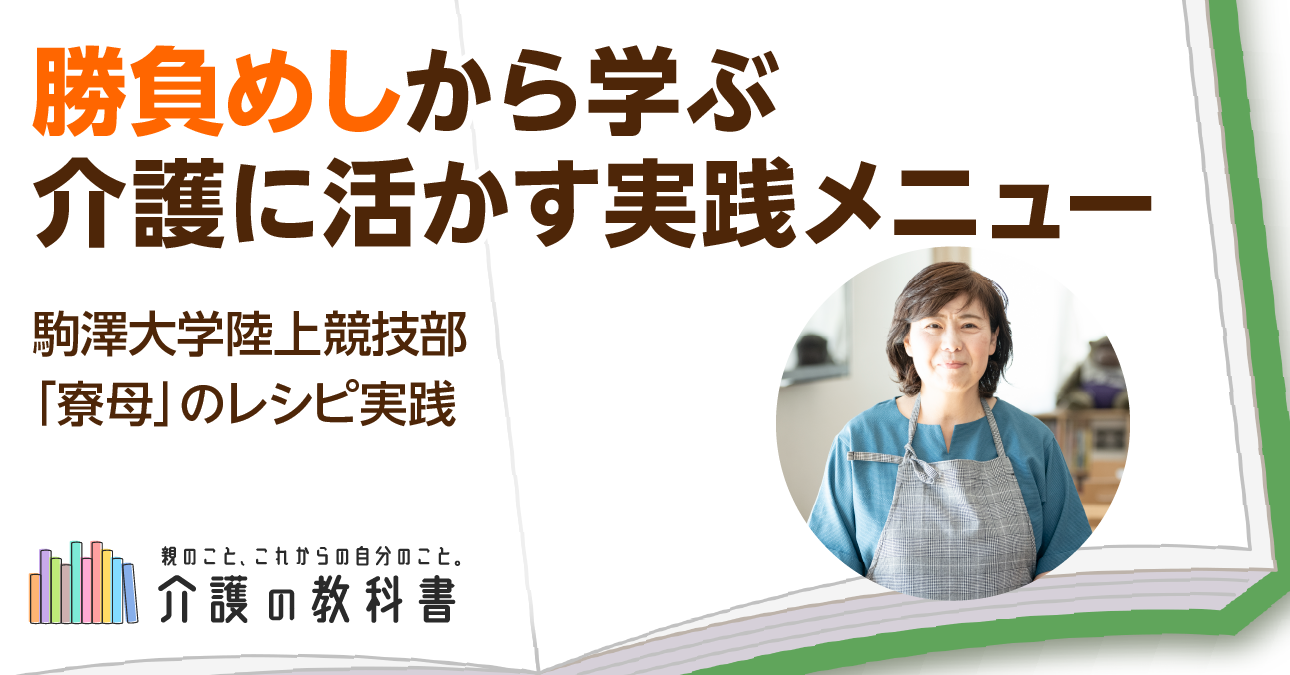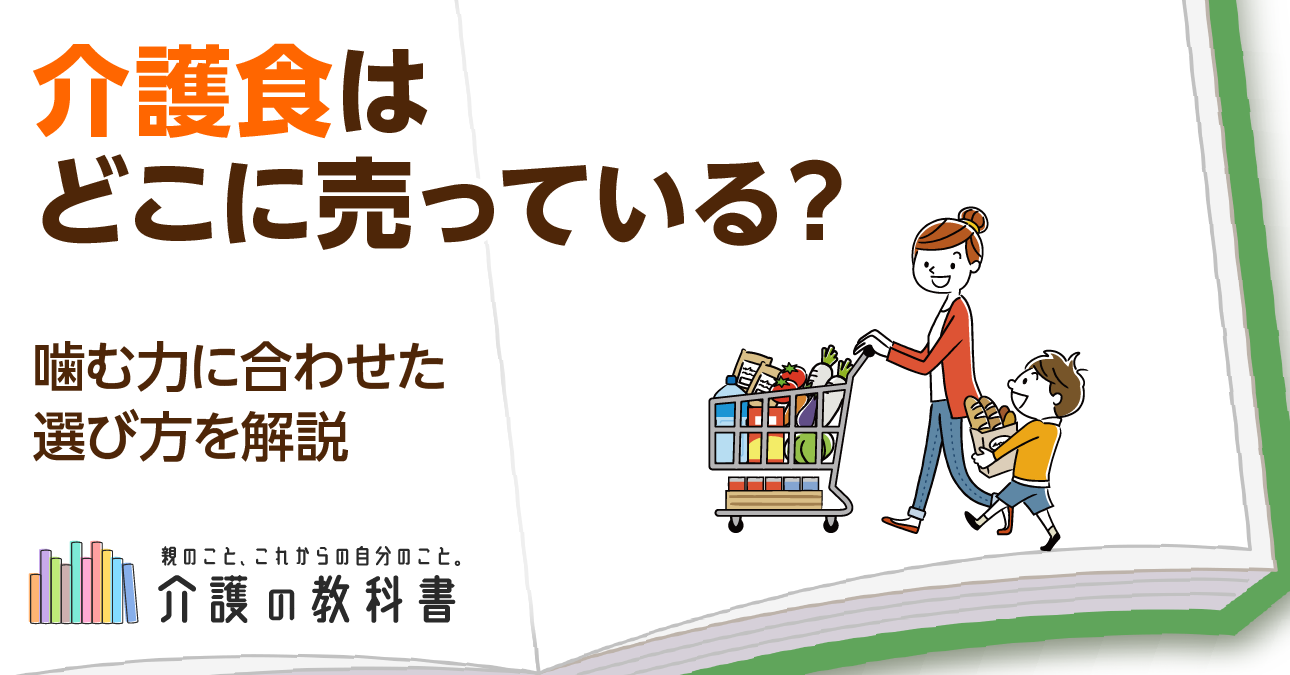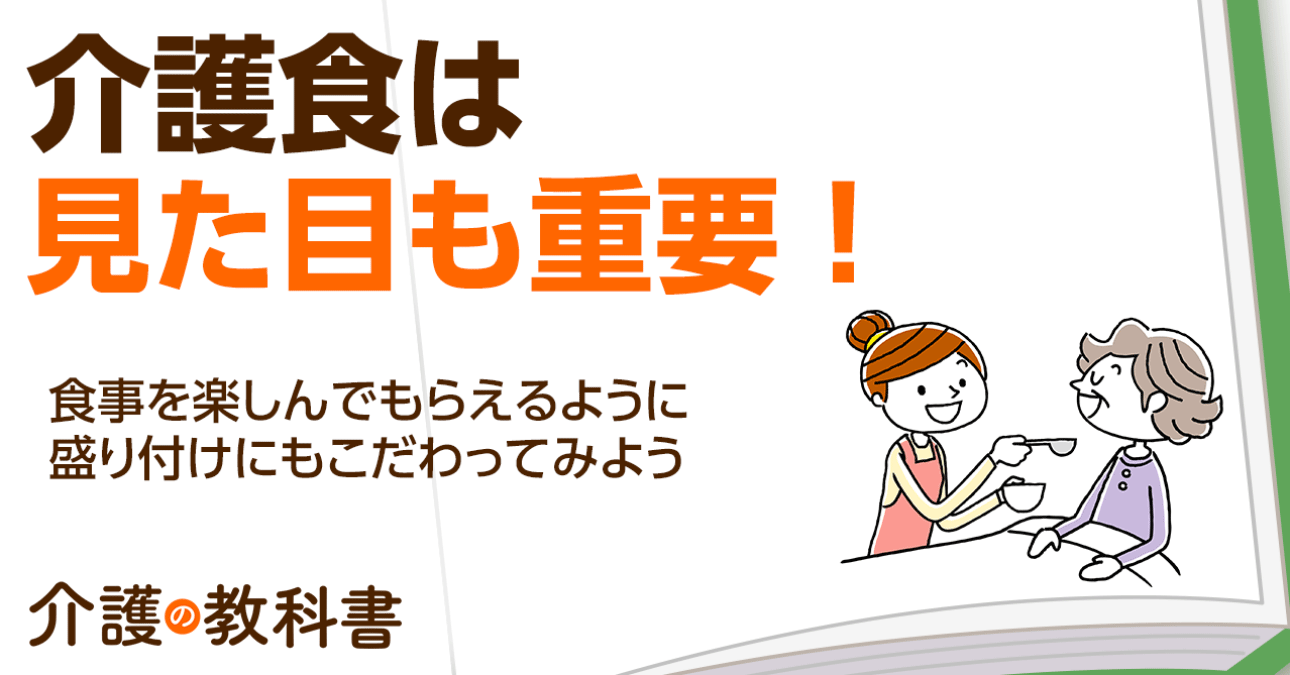はじめまして、大八木京子です。私は夫の大八木弘明が総監督を務める駒澤大学陸上競技部の寮母として、30年にわたり選手たちの食事をつくり続けてきました。いつしかその料理は「勝負めし」と呼ばれるようになりましたが、特別なことをしているつもりはありません。大切にしてきたのは、日々の食卓を通じて選手の体と心を支えることです。
また、栄養士として、以前は介護施設向けに献立を考えていた時期もあります。アスリートの食事と高齢者の食事――立場も年齢も異なるように見えて、実は「食べる力」を支えるという点で、共通する工夫がたくさんあると感じます。
本記事では、アスリートを支えてきた経験の中で育まれた“料理に込める思い”をご紹介します。全2回構成の前編として、「食べること」の本当の意味を、いま改めて一緒に考えてみませんか。
アスリートも高齢者も、“食べる”ことが力になる
食事は、単なる栄養補給にとどまらず、筋力・免疫・気力といった人間の生命活動を支える「体の土台」です。アスリートにとっては、トレーニングの成果を最大限に引き出すために欠かせないコンディショニング手段であり、高齢者にとっては、年齢による身体機能の衰えや病気への抵抗力を補うための「防御力」とも言えます。つまり、「食べること」は人の人生のあらゆるフェーズにおいて、健康を守るための原点であり続けています。
駒澤大学陸上競技部の「寮母」として30年、選手たちの日々の食事を一手に担い、チームの心と体の両面を気にかけてきました。箱根駅伝などの大きな大会の裏側で、私ができることは限られています。ただ、選手たちが日々の練習を乗り越え、力を出し切れるようにと願って、毎日のごはんに心を込めてきました。「勝負めし」と呼んでいただくこともありますが、特別なことをしてきたという意識はありません。
料理は、栄養だけでなく気持ちも届けるものです。食材の組み合わせや味つけの工夫はもちろんですが、「美味しい」と思ってもらえるように、そして「また食べたい」と感じてもらえるように。そんな思いをいつも大切にしてきました。

実は、この「勝負めし」に込められた考え方は、介護の現場でも十分に応用が利くと感じます。加齢に伴い食欲が落ち、栄養が偏りがちな高齢者にとってこそ、「食べる力を引き出す工夫」が大きなヒントになります。相手の状態を観察し、無理のない範囲で必要な栄養を取り入れ、何より「美味しい」と思ってもらえる食事を作る――その姿勢は、介護に携わる人々にも深い共感を呼ぶと思います。
本記事では、駒澤大学陸上競技部というトップアスリートの現場を支えた「勝負めし」を作るうえでのベースをもとに、介護の現場で活かせる食事の知恵を探っていきます。箱根駅伝の舞台裏で培われた、食と人を結ぶ哲学。「元気に生きる」ための食のヒントを、大学陸上界で考えていた思いをベースに記載していきます。
共通する栄養ニーズ:「動ける体」を支えるたんぱく質と鉄分
アスリートと高齢者──年齢やライフステージこそ異なりますが、実はその「体のつくり方」に共通するニーズは少なくありません。どちらも、自らの身体機能を維持・向上させるという課題に直面しています。アスリートは過酷なトレーニングに打ち勝ち、最大限のパフォーマンスを発揮するために、そして高齢者は日々の生活の質(QOL)を保ち、転倒や病気のリスクを抑えるために、食事で担える基盤を必要としています。
特に注目すべきなのが、たんぱく質や鉄分などの基礎的な栄養素です。たんぱく質は、アスリートにとっては筋肉の損傷を修復し、トレーニング効果を最大化するための「再構築の材料として不可欠。一方で高齢者にとっては、加齢とともに自然に減少する筋肉量を維持し、転倒やフレイル(虚弱)を防ぐための心身を支えるような存在です。
鉄分も同様に、アスリートと高齢者の双方にとって重要です。陸上競技にとっては持久力や回復力の維持に直結し、酸素の運搬効率を左右します。高齢者にとっても、慢性疲労や免疫低下、認知機能の低下を防ぐために必要な栄養素。特に高齢になるほど吸収効率が下がり、食事量も減りがちになるため、意識的に鉄分を取り入れる工夫が求められます。
こうした栄養素の摂取を、薬やサプリメントに頼るのではなく、日常の食事で無理なく取り入れるというのが、「勝負めし」流の真骨頂。肉類だけでなく、豆腐や納豆といった植物性たんぱく質を組み合わせたり、鉄分豊富なレバーや小松菜を副菜に取り入れるなど、食卓には栄養を美味しく届けるための知恵が詰まっています。これはまさに、噛む力や消化力が落ちた高齢者にも応用できる、優しく実用的な食の工夫です。
以下の表では、アスリートと高齢者それぞれの視点から、主要な栄養素の役割と、日常の食事での工夫例をまとめました。
| 栄養素 | アスリートでの役割 | 高齢者での役割 | 摂取の工夫例 |
|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 筋肉の修復と合成 | フレイル・サルコペニア予防 | 鶏そぼろ・豆腐・卵などやわらかく調理する |
| 鉄分 | 持久力・貧血予防 | 疲れやすさ・免疫力低下予防 | レバー・赤身肉・ほうれん草などを副菜で少しずつ |
| カルシウム | 骨の強度維持 | 骨折予防 | 牛乳・しらす・ひじきの和え物で摂取 |
| 糖質 | エネルギー源 | 活動量を支える燃料 | 冷やご飯のおにぎり・炊き込みご飯で食べやすく |
食べやすく、続けやすい「勝負めし」流の介護食へのヒント
五感を刺激して「食べたい」を引き出す
食欲を呼び起こすには、視覚・嗅覚・触覚といった五感の刺激が不可欠です。特に高齢者にとっては、加齢により感覚が鈍化しやすく、「食べたい」と感じるきっかけそのものが少なくなりがちです。
そこで重要になるのが、見た目の彩りや香り、温度感といった、視覚・嗅覚・温覚への働きかけです。例えば、彩り豊かな副菜、香ばしい焼き魚、湯気の立つ味噌汁など、五感をやさしく刺激する工夫が「おいしそう」「食べてみようかな」という気持ちを引き出します。
また、食材のかたさや大きさ、調理法も工夫する必要があります。噛みやすく、飲み込みやすい形に整えることで、食事が苦痛ではなく楽しみに変わります。私の料理には、あんかけやとろみを活用したり、小鉢に分けて少量ずつ盛るといった工夫をしています。これらはまさに、介護食に求められる視点と一致するものです。
“目分量”と“対話”で作る、やさしい食卓
栄養管理と聞くと、つい「何キロカロリー」「何グラムのたんぱく質」と数値管理に目が向きがちですが、そうした管理栄養の常識にとらわれず、あくまで人に寄り添う食事づくりを実践してきました。栄養士の資格を取得したあとも、「目分量」と「対話」を何よりも大切にしていたのは、食べる人一人ひとりの状態に応じた柔軟な対応を優先していたからです。
「今日は疲れていそうだから、味を少し薄めにしよう」「あの子は最近食欲がないから、見た目を明るくしよう」——そうした観察と対話の積み重ねが、選手たちにとっても安心できる食事時間になっていました。
介護の現場でも同じです。数字で厳密に管理された献立よりも、目の前の高齢者が「食べたい」と思えるかどうかを優先する視点こそが、食事ケアの本質ではないでしょうか。口数が少なくなった高齢者でも、目の動きや箸の進み具合を見れば、その日の体調や好みが垣間見えます。食べる人の変化に気づき、料理を微調整していく——それは、食事を単なる“提供”ではなく対話の時間に変える鍵になります。
家庭料理の延長にある栄養ケア
「アスリートの食事」と聞くと、特別なプロテインやサプリメント、高価な食材を想像する方もいるかもしれません。しかし“勝負めし”は、驚くほど「ふつうのごはん」です。肉じゃがや焼き魚、味噌汁、煮物など、日本の食卓に昔から並んできた家庭料理の数々。そのなかに、必要な栄養をしっかりと詰め込む工夫こそが、ポイントです。
たとえば、煮物の具材に鶏肉や豆腐を入れることでたんぱく質を強化し、ひじきや切り干し大根で鉄分やミネラルを補います。味付けも濃くしすぎず、素材の味を活かすことで、飽きのこない優しい味に仕上げる。さらに、見た目に変化をつけるために季節の野菜や薬味を取り入れたり、お椀を工夫することで、料理全体の印象がガラリと変わります。
これはそのまま、高齢者の食卓にも応用できます。大切なのは、「無理をしないで、日常の延長でできること」。介護食を“病人食”としてではなく、日常の食事の中にあるケアと捉えることで、食べる人の心にも寄り添えるようになります。
アスリートを支えた料理が、家庭の温かさとともに栄養を届けてきたように、介護の現場でも同じように心をほぐすごはんは、大きな力を持つのです。

次回予告
次回は、「アスリートと高齢者に共通する栄養ニーズ」や「介護の現場で応用できる勝負めしレシピ」について、私が日々実践してきた具体例をご紹介します。
“美味しく、やさしく、そして続けやすい”食の工夫を、ぜひご覧ください。