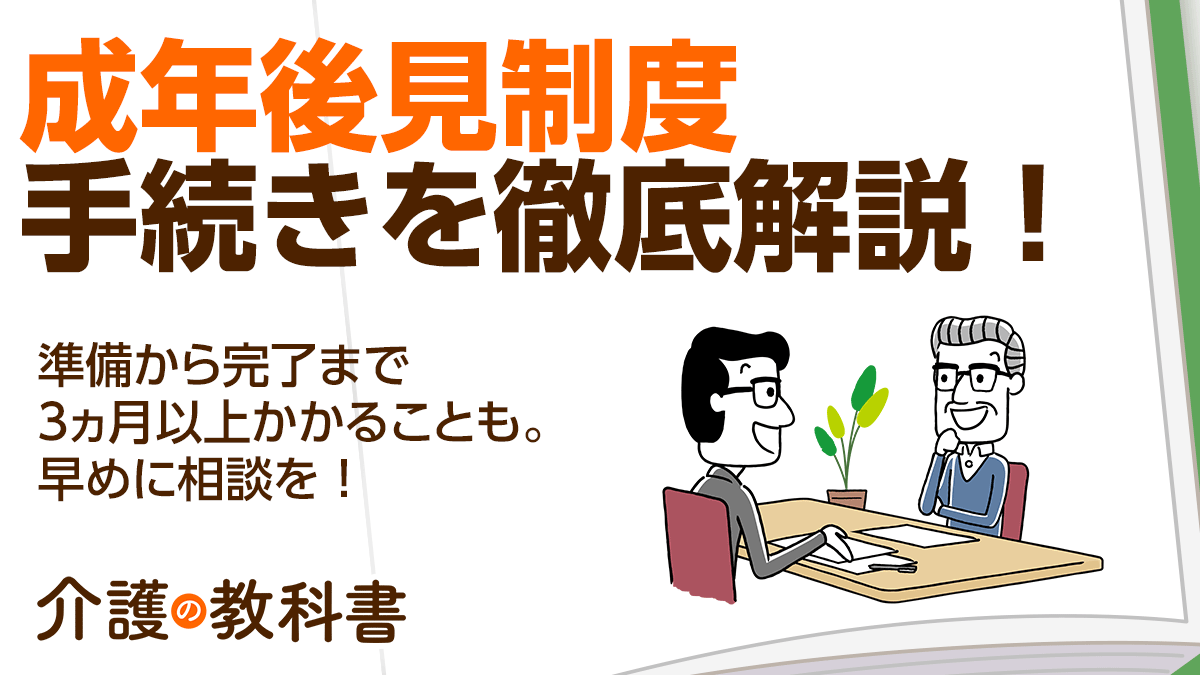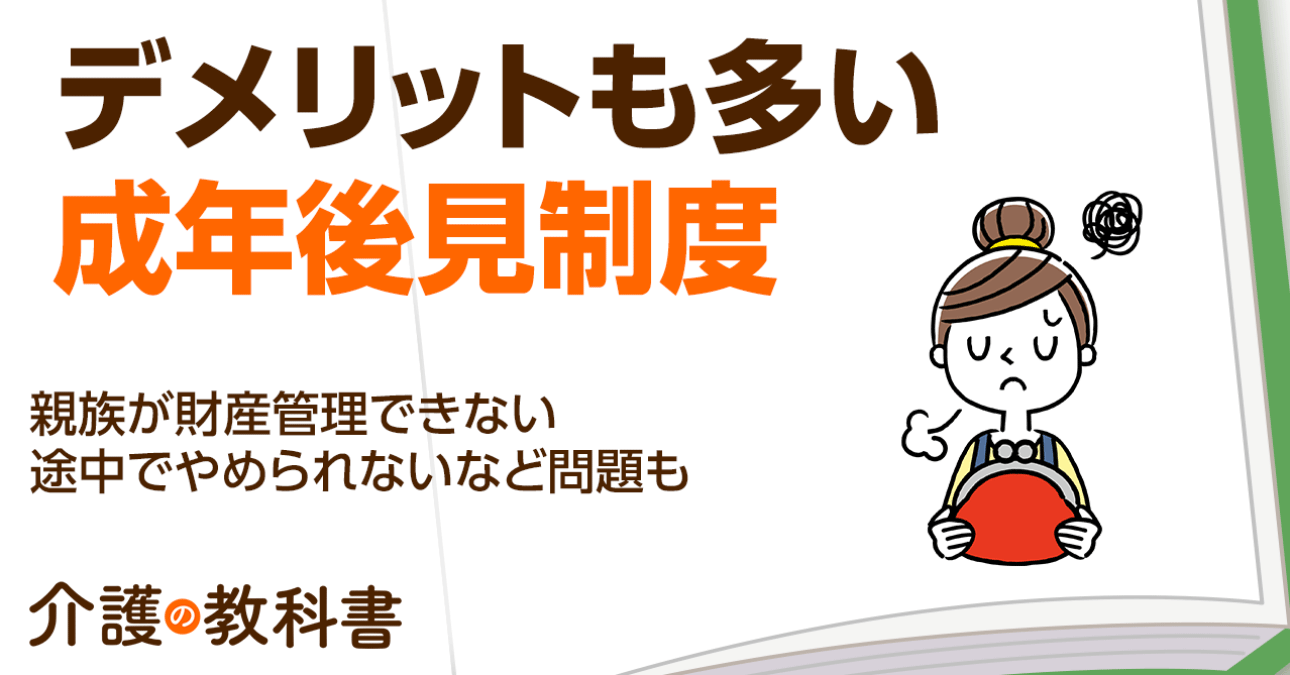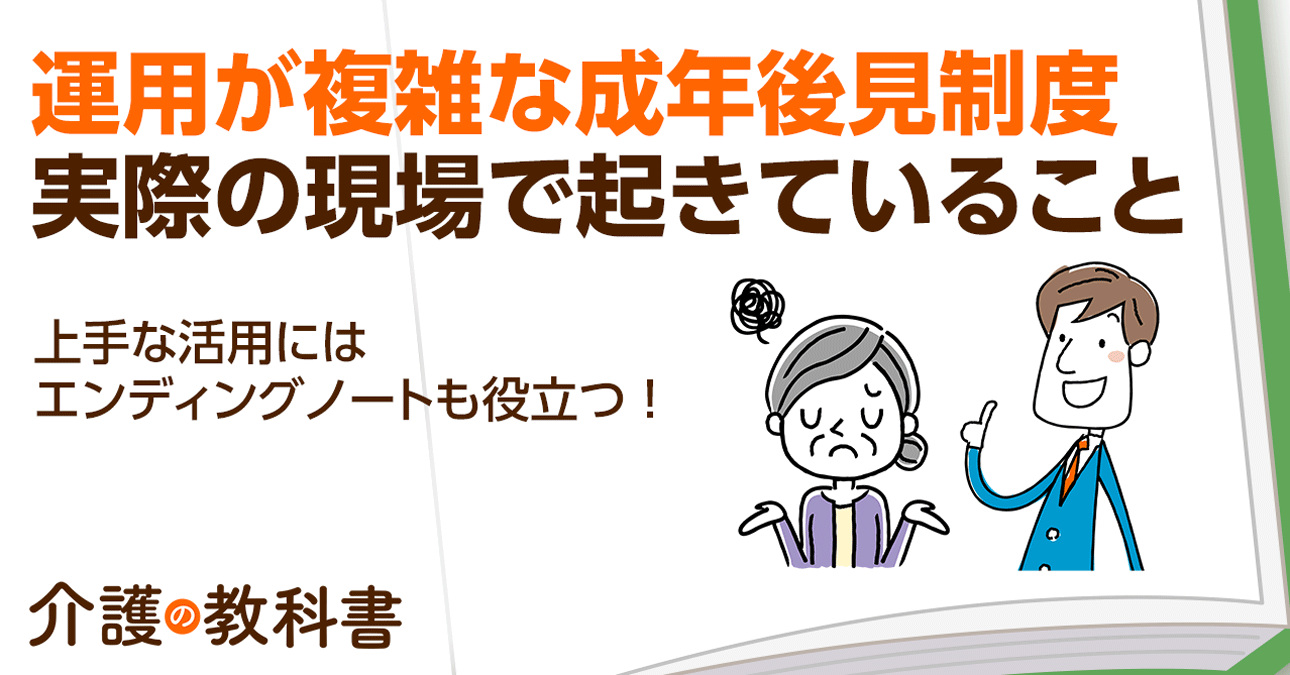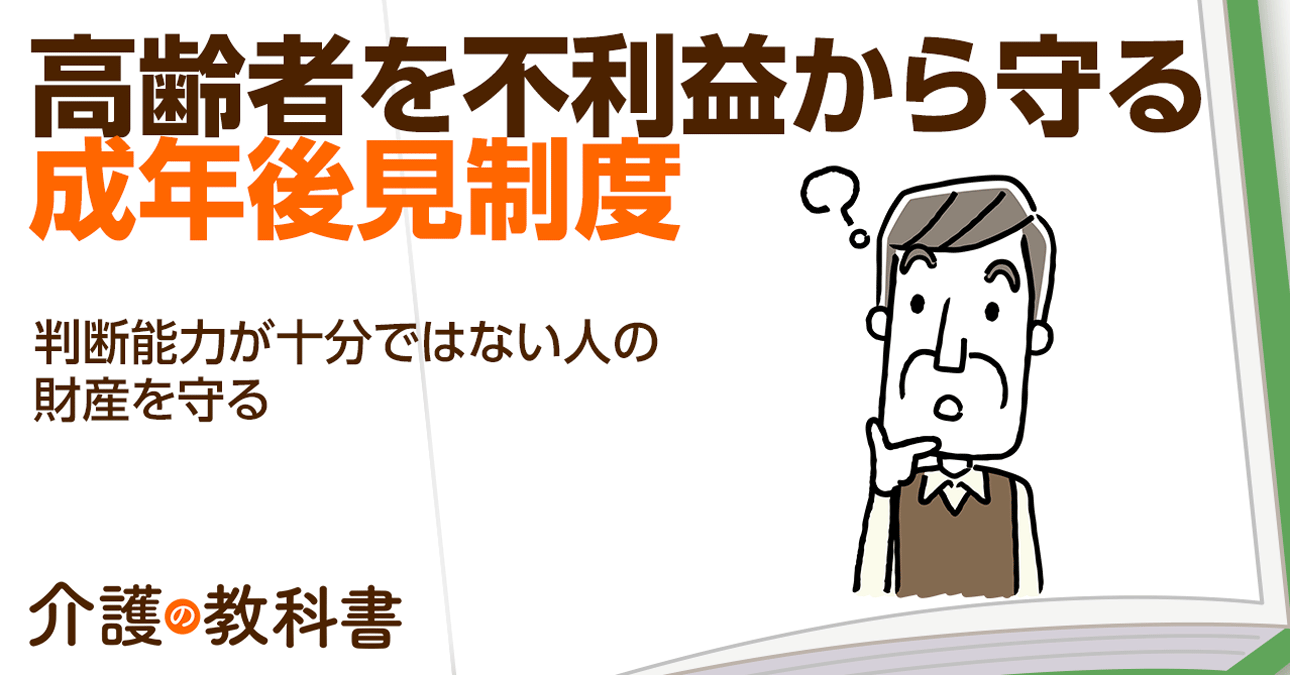認知症などによって、日常生活における判断能力などが低下した際に役立つのが成年後見制度です。
しかし、手続きが複雑なため、利用するには敷居が高いと感じる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は成年後見制度の手続きについてわかりやすく解説いたします。
成年後見制度について
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した(※)人(本人)の生活を支援するためにできた国の制度です。成年後見人が本人に代わって契約を結んだり、財産の管理をしたりすることで、本人が安心して生活できるように支援することを目的としています。
(※「判断能力が低下した」とは、現状を正しく認識したり、適切な判断ができない状態のこと。
成年後見制度は3種類
法定後見制度は本人の認知症などの程度によって判断能力の低い方から「後見」「保佐」「補助」と3つの種類に分かれています。
| 種類 | 後見 | 保佐 | 補助 |
|---|---|---|---|
| 本人の状況 | 判断能力がない状態 ・家族の名前がわからない ・日常の買い物を一人でできない |
判断能力が著しく不十分な状態 ・財産管理は一人では難しい ・日常の買い物は一人でできる |
判断能力が不十分な状態 ・一人でもできそうだが、不安がある |
判断能力がほとんどなくなってしまった人に適用される「後見人」の場合、権限も大きく、財産管理、および財産に関する法律行為についての広範囲な代理権と取消権が付与されます。
中間に位置する「保佐人」は、包括的な同意権(本人が単独で行った法律行為を完全に有効にする権利)と取消権を付与されます。ただし、代理権は付与されません。もしも代理権が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
「補助人」は、日常生活を送るにあたっては、特に問題がない人に適用されます。よって、必要な代理権や同意権を選び、補助人に個別に付与することになります。包括的に付与することはできません。
成年後見制度が必要な理由
認知症の進行などにより判断能力がない方の場合、高額商品の詐欺被害に遭ったり、不動産売却時に誤った判断をしてしまったりするおそれがあります。そこで、成年後見人が本人に代わって契約をすることにより、本人の財産を守ることができます。
なお、委任状を持った親族が金融機関の窓口で手続きをしようとすると、金融機関側から「成年後見人を立ててください」と断られてしまうことがあります。資産の多寡や相続人となる家族の状況にもよりますが、金融機関側が相続問題に巻き込まれることを懸念してのことです。
成年後見制度の手続の流れ
成年後見人の申立てができる人(申立権者)
申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長、成年後見人など。法律で申立てをすることができる人が決められています。
成年後見人が決まるまでの流れと所要期間
本人の住民票住所を管轄する家庭裁判所へ申立てをして、本人の診断書や必要な書類、手数料や郵便切手などを提出します。場合によっては、面接をし、本人や親族、後見人候補者の状況を確認されます。申立てから1~2ヵ月、遅くても4ヵ月以内に家庭裁判所が成年後見人を決定する流れとなります。
まずは家庭裁判所へ電話しよう
家庭裁判所へ成年後見人の申立てをしたいと連絡をしましょう。家庭裁判所によっては専用電話番号があります。そのとき電話でいくつか質問される内容によって、次のように対応が分かれます。
- 面接は不要/書類を郵送するように
- ●●日に面接/書類は郵送(面接日の3日前(土日祝除く)までに必着
- ●●日面談、書類は当日持参
このように、本人や申立人、後見候補者の状況によって、指示が違うので、電話の指示に従って対応することになります。②③で指定される面接日は電話した日から1週間以上先の日に設定されます。
申立て時に提出する書式
まずは裁判所の「後見サイト」で、「後見・保佐・補助開始申立セット(書式)」をダウンロードします。
【後見・保佐・補助開始申立セット(書式)】
- 提出書類確認シート
- 後見、保佐、補助開始申立書
- 代理行為目録【保佐、補助用】
- 同意行為目録【補助用】
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録
- 相続財産目録
- 収支予定表
- 後見人候補者事情説明書
- 親族の意見書について
- 親族の意見書・記載例
- 「本人情報シート」の作成を依頼された福祉関係者の方へ
- 本人情報シート(成年後見制度用)
- 診断書を作成していただく医師の方へ
- 診断書(成年後見制度用)
- 診断書付票
【その他必要書類】
先述の裁判所のサイトでダウンロードした書式以外にも、以下のものが必要です。念のため、必要な書類については申立てをする家庭裁判所で事前に確認すると良いでしょう。
- 本人、後見人候補者の戸籍謄本(発行後3ヵ月以内、本籍地の市区町村役所)
- 本人、後見人候補者の住民票の写し(世帯全員、発行後3ヵ月以内、住民票住所のある市区町村役所)
- 本人の「登記されていないことの証明書」(発行後3ヵ月以内、法務局)
申立て時に提出する書類は以上の通りたくさんありますが、書類によっては、後日提出でよいものがあります。また、作成が難しいものについては家庭裁判所へ相談ができます。早めに書類を作成して申立てを行いましょう。
申立てに必要な費用
【絶対必要な費用】
- 家庭裁判所への申立手数料:800円「収入印紙(400円×2枚)」
- 登記手数料:2,600円「収入印紙(1,000円×2枚+300円×2枚)」
- 連絡料:「後見」→3,270円分の郵便切手、「保佐・補助」→4,210円の郵便切手
収入印紙と郵便切手は郵便局で購入できます。家庭裁判所によっては収入印紙や郵便切手を販売しているところがありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
【もしかしたら必要になるかもしれない費用】
本人の判断能力がどの程度なのかを診断書や面接で判断ができず、医学的に判定するための鑑定をすることになった場合、鑑定費用(およそ5万円程度)がかかります。
申立て後1~2ヵ月で審判、2週間の不服申し立て期間を経て後見登記完了
申立書提出や面接後に家庭裁判所の調査を経て、家庭裁判所から「審判書」が本人自宅に郵送されます。審判書が届いてから本人が不服申し立てをできる期間が2週間と決まっているため、その期間を経て審判が確定。成年後見登記が完了します。
手続きが不安な場合は相談窓口へ
書類をつくったり、申立てが不安という場合は、地域の相談窓口(社会福祉協議会や市区町村の相談窓口など)へ相談をすることができます。また、申立てを弁護士や司法書士などの専門家へ有償で依頼することも可能です。
まとめ
今回は成年後見人制度の実際の手続きに必要な書類や、その流れをご紹介しました。
書類をそろえることも含めると手続き完了まで3ヵ月以上かかることもあります。ご両親の体調に不安があるなどで、申請を考えている方は、まず市町村の窓口などで相談することをおすすめします。