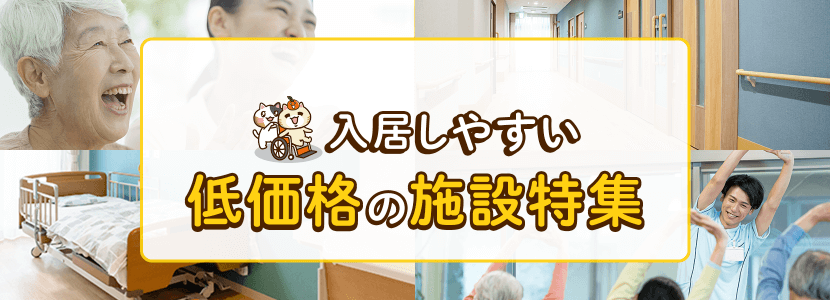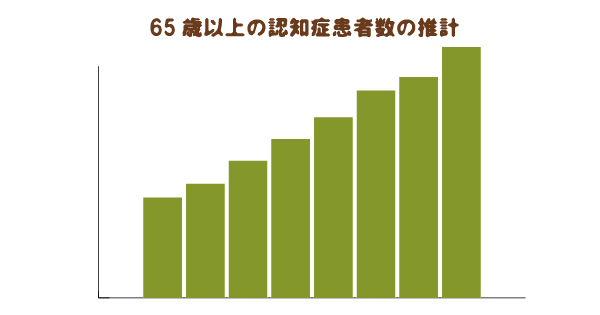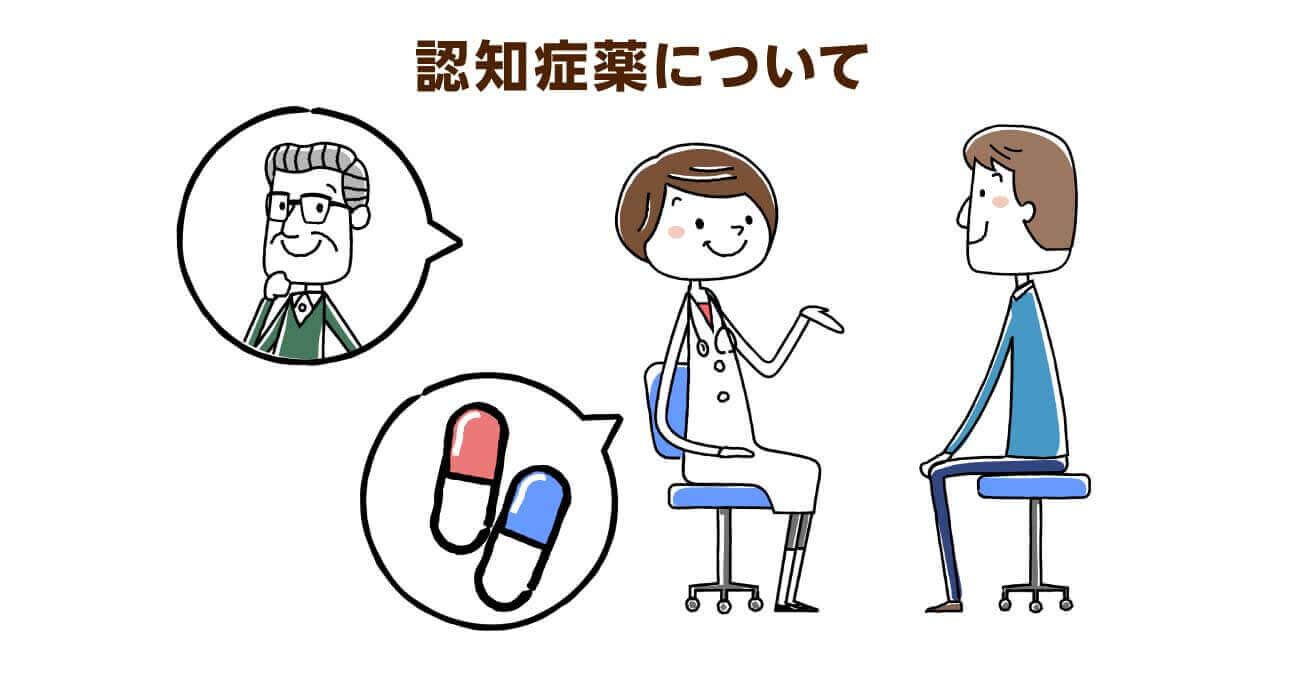こんにちは。安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所の安部静男です。
皆さんは、「親の扶養義務」について考えたことがありますか?最近は「そろそろ親の介護が始まりそうなんですが、自分たちの生活で精一杯、どうしたらいいですか」とか、「兄弟がいるのですが、親の介護をどのように分担したら良いですか」といった、親の介護に関する相談を受けることがあります。このような場合に備えて知っておくべき「親の扶養義務」についてお話していきます。
扶養義務は曽祖父・曾孫など三親等内でも発生する
まず、法律では扶養義務についてどのように記載されているかを見ていきましょう。民法では以下のように規定されています。
第877条1項 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
第877条2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
「直系血族」とは下の図にあるように、祖父母→父母→本人→子→孫のように、自分を中心として父母や祖父母などに直接さかのぼっていく場合と、子や孫のように直接下がっていく場合の親族を言います。ですから、親や子、孫、兄弟姉妹は相互に扶養する義務があるのです。
また、扶養義務を負担させることが相当とされるような、「経済的対価」を得ているなどの特別な事情がある場合は、家庭裁判所は三親等内の親族間においても扶養義務を負わせることができます。夫婦の扶養義務については、民法第752条に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という規定があります。

原則、親や兄弟姉妹間の扶養義務は「金銭による扶養」
扶養義務の程度や内容は次の2つです。
- 自分と同じ程度の生活を保障する義務
- 自分の社会的地位、収入などに相応した生活をしたうえで、余力のある範囲で扶養する義務
夫婦間や未成年の子に対しては①が、親や兄弟姉妹に対しては②が当てはまると考えられています。②については、前述した通り、あくまでも「自身の生活に余裕がある場合」です。余裕があるかないかの判断は、家庭裁判所に判断してもらうことができます。
扶養義務の内容については「金銭による扶養」と「同居や引き取りによる扶養」の2種類がありますが、親や兄弟姉妹間の扶養義務については「金銭による扶養」が原則です。
ここまで見てきた通り、子には親の扶養義務があり、その経済状況に応じて余力のある範囲で金銭的な援助を行う義務が発生すると考えられます。
親の介護に必要なお金は基本的に親のお金から
実際に親の介護などが必要になった場合の基本的な考え方としては、「親の介護に必要となるお金は、親のお金(貯蓄、年金、収入)でまかなう」ことが原則です。そのうえで、足りない場合の諸費用を配偶者や兄弟などで「誰がどのような割合で負担するか」を話しあいで決めることになります。
扶養の方法などは当事者が話し合って決めますが、その場合にも親の気持ちを十分聞いて、できるだけその意に沿うよう努めることが望ましいです。もし話しあいがまとまらない場合は、家庭裁判所に判断してもらうことができます。 民法では以下のように規定されています。
第878条
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
第879条
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力そのほか一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

介護費用に関する話し合いが決着しなければ扶養請求調停へ
親の介護が必要になり、費用について兄弟間で話しあいがうまくまとまらず、争いとなってしまうことがあります。前述した通り、親との同居や費用の支払いなどについて話しあいがまとまらない(できない)場合には、家庭裁判所に扶養請求の調停か、審判を申し立てることが可能です。
家庭裁判所に「扶養請求調停」の申し立てをすると、裁判所が選任する「調停委員」が兄弟姉妹の間に入り、お互いの合意を目指した提案、助言を行います。調停委員がまず行うことは、「介護に必要な人的な負担はどのくらいなのか」などの生活状況と、「親および兄弟姉妹それぞれの収入」などの経済状況を確認し、兄弟姉妹間における感情の行き違いや、親への想い、さらに介護に対する考え方の相違点などを聞き取ります。
その後、「〇〇さんは、毎月〇円の介護費用を金銭的に援助する」などの解決策を示し、その内容に兄弟姉妹が合意すれば調停成立です。調停成立後は、裁判所が合意内容をまとめた書面(調停調書)を作成するので、当事者である兄弟姉妹はその内容を履行しなければなりません。仮に、取りまとめたそれぞれの義務のうち、介護費⽤などの⽀払い義務が履⾏されていないなど、義務が果たされない場合は強制執行が可能で、財産の差し押さえなども行われます。
※義務が果たされない例:介護費用などの支払い義務が履行されていない
もし調停でも合意できなければ、裁判所にて「審判」の手続きに移行します。審判とは、調停で合意が得られなかった内容について、提出書類および調査結果を根拠に裁判所が当事者に成り代わって取り決めを行うことです。
将来的なトラブル防止には事前の話しあいが重要
親の扶養義務が問題となるようなケースでは、裁判などの争いやトラブルにならないように親子や兄弟で事前に話しあいをしておくことが必要です。話しあいの際には、下記の内容について確認をしておくと良いと思います。
- 介護が始まる前に親の貯金・資産を確認する
- それぞれの「できそうなこと」「できなさそうなこと」を把握する
- それぞれの状況を考慮して主介護者を決める
- 主介護者以外の兄弟姉妹の役割も決める
- 介護が始まる前から兄弟姉妹で「介護貯金」する
- 金銭面をどのように分担するか決める
- お金が足りない場合は、生活保護など制度の活用を検討する
現在は高齢者の一人世帯や、夫婦のみ世帯が増えています。親と同居していない場合など、将来親の介護をどうしたらいいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。この機会に将来トラブルとならないよう、事前の準備を検討してみましょう。