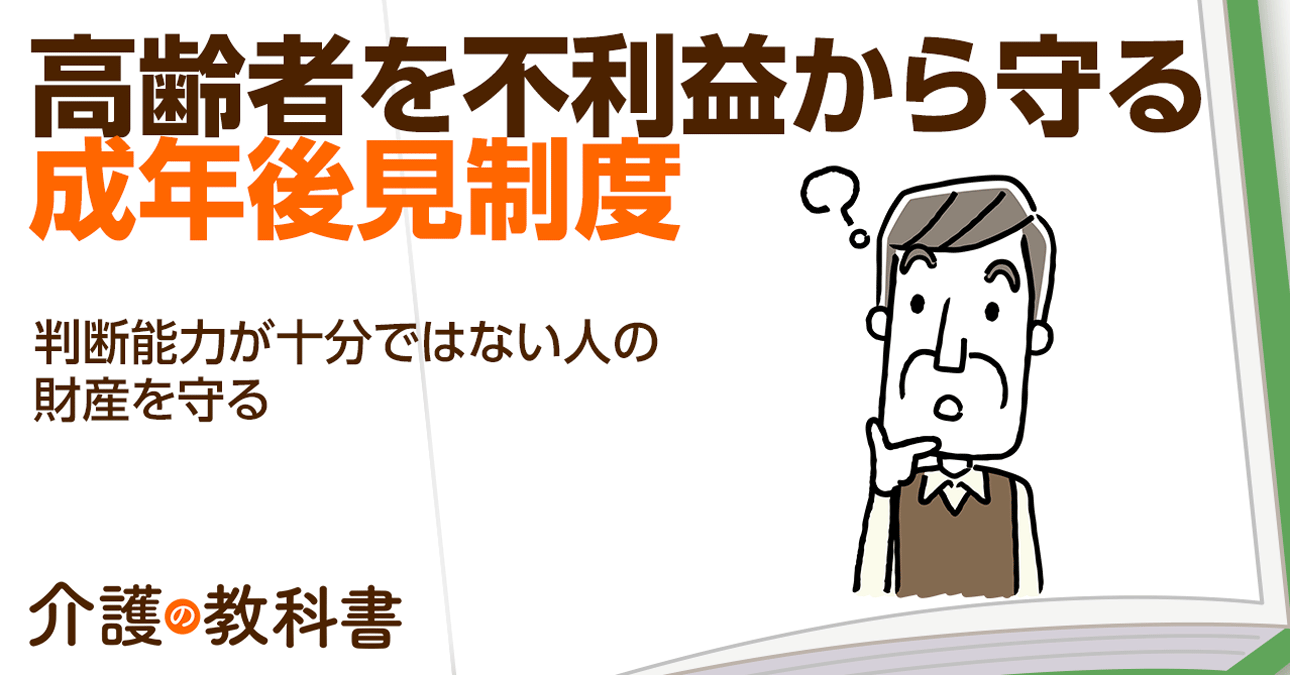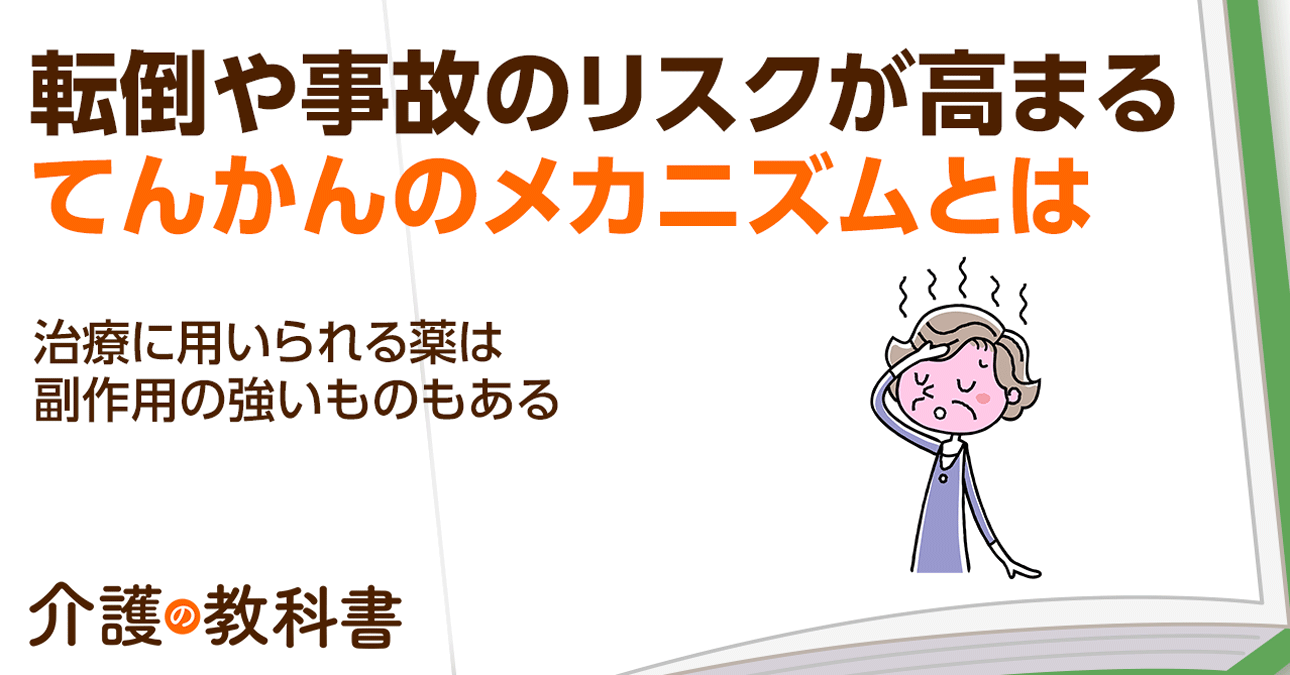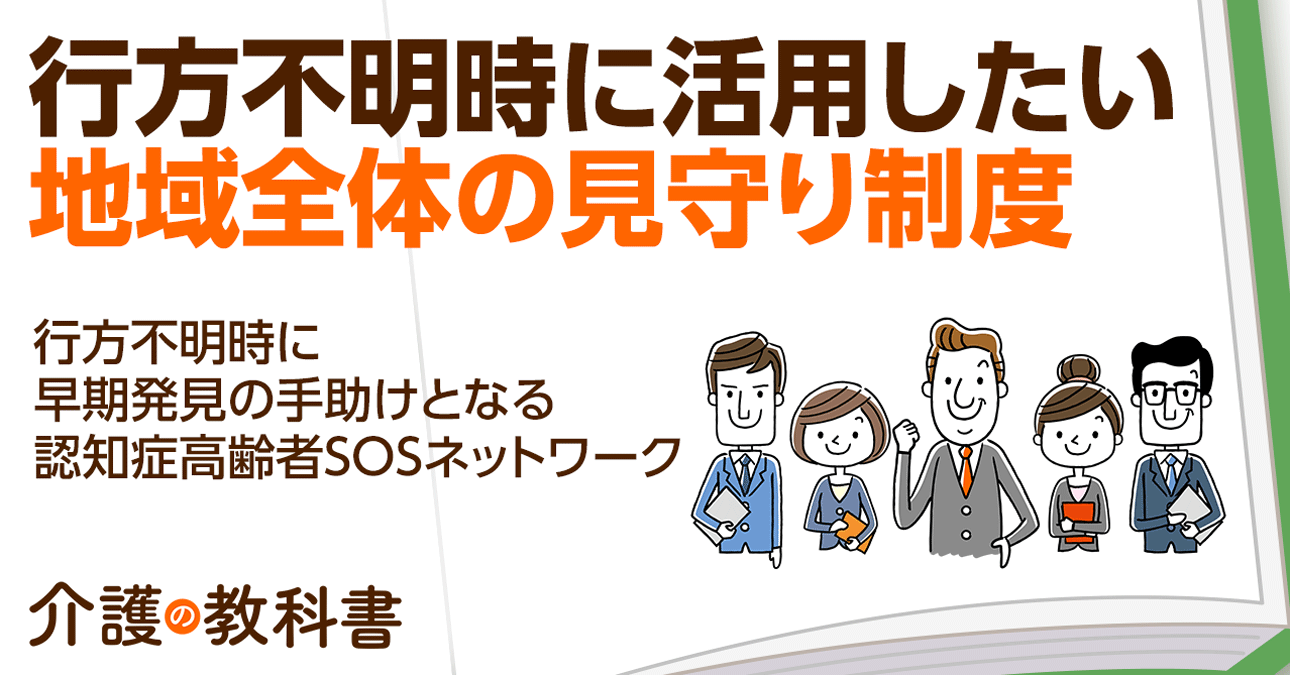こんにちは。安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所の安部静男です。
皆さんは、「成年後見制度」をご存じですか。
「成年後見制度」とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が不十分な方々を支援する制度です。
認知症の方などは自分で財産を管理したり、治療や介護を受ける際に必要な契約を結んだりすることが難しくなります。
また、悪徳商法などの被害にあう可能性もあります。
「成年後見制度」は、身内がいない方や身近に相談相手がいない方にとって頼りになる制度です。
「成年後見制度」には、「任意後⾒制度」と「法定後⾒制度」の2つがありますが、今回は「任意後⾒制度」にスポットを当てて解説します。
事前に自分で後見人を選んでおける「任意後見制度」
「任意後見制度」とは、判断能力があるうちに、自分で任意後見人を選んだり、代理で行ってもらう項目を決められる制度です。
正常な判断能⼒があるうちに、「任意後⾒契約」を公証⼈が作成する公正証書で結んでおくことで将来に備えます。「任意後⾒契約」とは、あらかじめ⾃分で選んだ任意後⾒⼈に⾃分の⽣活や療養看護、財産管理について代理権を与える契約のことです。
「任意後見制度」は、判断能力が衰える前に自分で援助者や援助内容を決める制度です。
一方、「法定後見制度」は判断能力が低下した後で、家庭裁判所が適切な援助者を選択するところが特徴と言えます。なお、後見人や保佐人、補助人を引き受けてくれる方を、候補者として推薦することは可能です。
「任意後見契約」の内容としては、主に以下の6つがあります。
【「任意後見契約」の主な内容】
- 不動産、動産、預貯金、有価証券などの財産の管理、保存、処分に関する手続き
- 金融機関、保険会社などとの取引に関する手続き
- 定期的な収入の受領、支出の支払いなどに関する手続き
- 医療契約、介護契約、そのほかの福祉サービスの利用契約に関する手続き
- 印鑑、各種キャッシュカード、預貯金通帳、保険証券、年金関係書類などの保管や手続きに必要な範囲内での使用
- 遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限定承認など相続に関する手続き
自分の将来の生活をイメージしながら、どのような内容を任意後見人に依頼するか決めることができます。
ただし、介護や葬儀、埋葬など死後の処理、結婚、離婚、養子縁組などの一身専属的な権利に関することなど、任意後見契約に盛り込むことができない内容もあるので注意しましょう。

判断力が低下してから効力が発生する
「任意後見契約」は、判断能力のあるうちに結びますが、判断能力がある間には効力が生じません。
判断能力が低下し、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて、「任意後見契約」の効力が発生します。
【「任意後見契約」の効力発生までの流れ】
- 任意後見契約の締結
- 判断能力が低下
- 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て
- 任意後見監督人の選任
- 効力発生
任意後⾒監督⼈には、任意後⾒⼈が「任意後⾒契約」の内容通りに適正に仕事をしているのかを、任意後⾒⼈から財産⽬録など受け取って監督する役割があります。
任意後見監督人によって、不正行為が抑制されるというわけです。

任意後⾒制度の利用をお勧めする方
どのような人が、「任意後見制度」を利用すると良いのでしょうか。
以下のような方は、利用を検討してみてください。
【「任意後見制度」の利用を検討するケース】
- 身寄りのない独居高齢者
- 子供がいない高齢者夫婦
- 知的障がいの子を持つ親
- 身内がいない方
- 子供がいない高齢者夫婦
- 将来に不安がある方
- 子供の将来に不安がある方
将来の不安に備えたい場合などに、活用を検討してみてください。
「任意後見制度」のメリット・デメリット
「任意後見制度」には、どのようなメリットやデメリットがあるでしょうか。
メリット
メリットには、判断能力がある間に自分で任意後見人や依頼内容を決められることや、任意後見人の報酬を契約で決められることが挙げられます。
デメリット
続いてデメリットには、本人がした契約を任意後見人は取り消すことができない(取消権)ことや、任意後見監督人の報酬が必要になることが挙げられます。
「任意後見制度」のメリットやデメリットを理解したうえで、制度の活用を検討する必要があります。
制度を正しく理解して将来に備える
今回は「任意後見制度」について説明しました。
「成年後見制度」という言葉を耳にすることが増えてきていますが、「任意後見制度」の認知度は高くないと思います。
制度の内容を知っておくことで、将来の不安に備えたり、自らが望む生活を実現させることにつながるのではないかと思います。
後見制度は、手続きや内容などを難しいと感じる方が多いと思います。
活用を検討する場合には、お近くの専門家や各市町村の地域包括支援センター、社会福祉協議会、家庭裁判所などに問い合わせしてみてください。