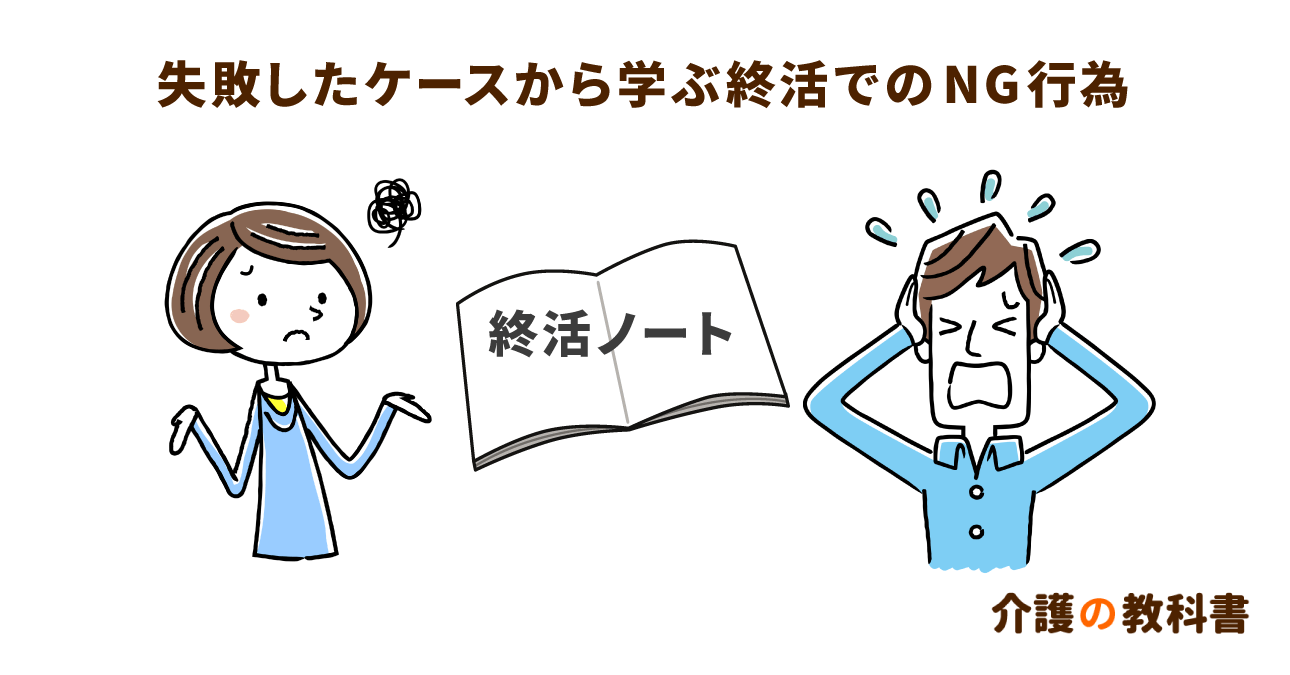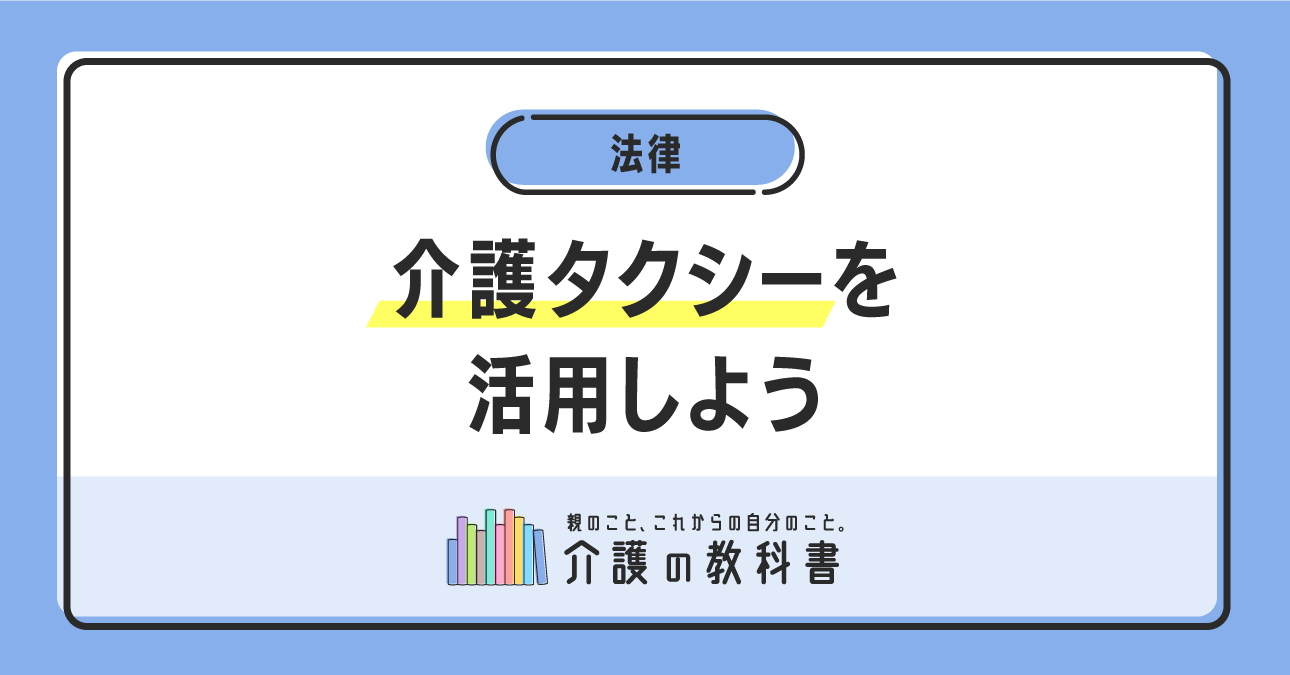こんにちは。安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所の安部静男です。
みなさんは、尊厳死という言葉を聞いたことがありますか?
日本尊厳死協会によると、『尊厳死とは、不治で末期に至った患者が、本人の意思に基づいて、死期を単に引き延ばすためだけの延命措置を断わり、自然の経過のまま受け入れる死のこと』としています。
治療をしても治る見込みがなく、ただ延命措置のために人工呼吸器をつけたり、胃ろうをした場合、それを後から外すことは難しくなります。
そのため、延命措置を希望しない方は、元気なときに“延命措置を行わない”と意思表示をしておくことが大切です。
今回は行政書士として作成のお手伝いをさせていただくことがある『尊厳死宣言公正証書』について紹介をさせていただきます。
"延命治療は行わず"を望む声が9割
最近は『人生100年時代』という言葉を聞くことが増えてきましたね。
日本では医療技術の進歩により、高齢者の平均寿命が長くなってきていますが、健康寿命との間にはまだ大きな開きがあります。

こうした背景を考えると、突然の疾病や認知症などにより、ご自身やご家族に「介護が必要になるかもしれない…」と心配される方も多いと思います。
それに伴い、元気なうちから、どのように最期を迎えるかについて考えている方も増えてきているのではないでしょうか?
平成27年版高齢社会白書によると、延命治療は行わず「自然にまかせてほしい」と回答した人の割合は91.1%と9割を超えているようです。
延命措置をしない意思表示"リビングウィル"
ご自身やご家族が終末期を迎えたとき、延命治療を行うかどうかについて、悩まれる方は多いと思います。
「少しでも長生きしていたい(長生きしてほしい)」「家族に迷惑はかけたくない」「医療費の負担が心配」など、いろいろな事を考えられるのではないでしょうか?
延命治療
回復する見込みがない死期の迫った患者に、人工呼吸器や心肺蘇生装置を着けたり点滴で栄養補給をしたりなどして生命を維持するだけの治療【デジタル大辞泉より】
このような延命治療に対して、『自分の身体はもう治ることのない、末期の状態であるなら延命治療をしないで欲しい』と思っている方が、元気なうちにその意思表示として記しておくことを“リビングウィル”(living will=生前の意志)と言います。

尊厳死宣言公正証書は法律のプロである公証人が作成している
リビングウィルを行う方法としては、尊厳死宣言公正証書や日本尊厳死協会が発行するリビング・ウイル(終末期医療における事前指示書)があります。
今回は尊厳死宣言公正証書についてご紹介しますね。
簡単に説明すると、法律のプロである公証人が記載内容について法令違反がないかや、作成者の身元・意思などを確認して作成する文書のため、証明力があり、信頼性や安全性の高い尊厳死宣言文書と言えます。
記載する内容としては、以下のような内容が考えられます。
- 1.病状が不治かつ死期が迫っている状態になった場合には、延命治療を拒否すること
- 2.家族も尊厳死について同意をしていること
- 3.尊厳死を容認した家族や医師に対して、刑事上、民事上の責任を求めないこと
- 4.苦痛の緩和に関する処置は行ってほしいこと
- 5.精神が健全な状態にあるときに本人が撤回しない限り、その効力は有効であること
この内容については、公証役場で公証人と相談して決めることもできます。
ただし、尊厳死宣言公正証書を作成したとしても、尊厳死が必ず実現できるとは限りません。
現在、尊厳死に関する法的な整備はなされておらず、法的に有効なものとは言えないからです。
もっとも、医療の現場では尊厳死宣言公正証書などを提示することで、9割程度の医師は尊厳死を許容しているようです。
尊厳死宣言公正証書を作成するには
尊厳死宣言公正証書は公証役場で作成することができます。
- 必要書類
-
作成に必要な書類は以下の書類が必要になります。
上記1~5までのうちいずれか1つ ※詳細はお近くの公証役場で事前にご確認ください。
- 1.印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3ヵ月以内に発行されたもの)及び実印
- 2.運転免許証及び認印
- 3.パスポート及び認印
- 4.住民基本台帳カード(写真付き)及び認印
- 5.その他顔写真入りの公的機関発行の証明書及び認印
- 公証人手数料
-
公証人に依頼するためには、手数料が必要です。
基本手数料:11,000円
正本代:約750円(正本1枚につき250円かかります。署名用紙1枚含めて正本3枚なら750円になります。)
尊厳死宣言公正証書を作成した後は、信頼できる人や家族に自分の意思を伝えて、尊厳死宣言公正証書を渡しておくことも大切です。
尊厳死を迎える状況になる前に、事前に担当の医師や主治医に尊厳死宣言公正証書を示す必要があるためです。
そのような状況になったときに、家族間で争いがおこらないように、きちんとご家族にも自分の意思を伝えておくことも必要です。
作成時点から意思は変化する可能性がある
尊厳死宣言公正証書は、作成時点の本人の意思・意向です。
しかし、本人の意思は時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等、状況に応じて変化する可能性があります。
そのため、医療や介護に携わるケアチームは、症状が安定している時期に、ケア全体の目標や、具体的な治療や療養の方針などについて本人やご家族と話し合うことが求められています。
そのプロセスを『アドバンス・ケア・プランニング』と言います。
また、実際に終末期を迎えたときにも、ケアチームはその時々の状況に合わせてよく話し合いを行いながら、本人の支援を行うことが重要です。

最後に一言
いつかは迎える終末期に、自分がどのような状態にあるかはわかりません。
自分の意思を伝えることができない状況も考えられます。
そのような場合でも、事前に尊厳死宣言公正証書などを作成しておくことによって、自分の意思をご家族や医師等に知ってもらうことが可能になります。
延命治療に関しては、本人の意向の確認ができない場合にはご家族はどうしたら良いか悩むことなるでしょう。
もし終末期には延命治療をしないで欲しいと思っているなら、早めの備えとして、尊厳死宣言公正証書を検討してみても良いかもしれませんね。