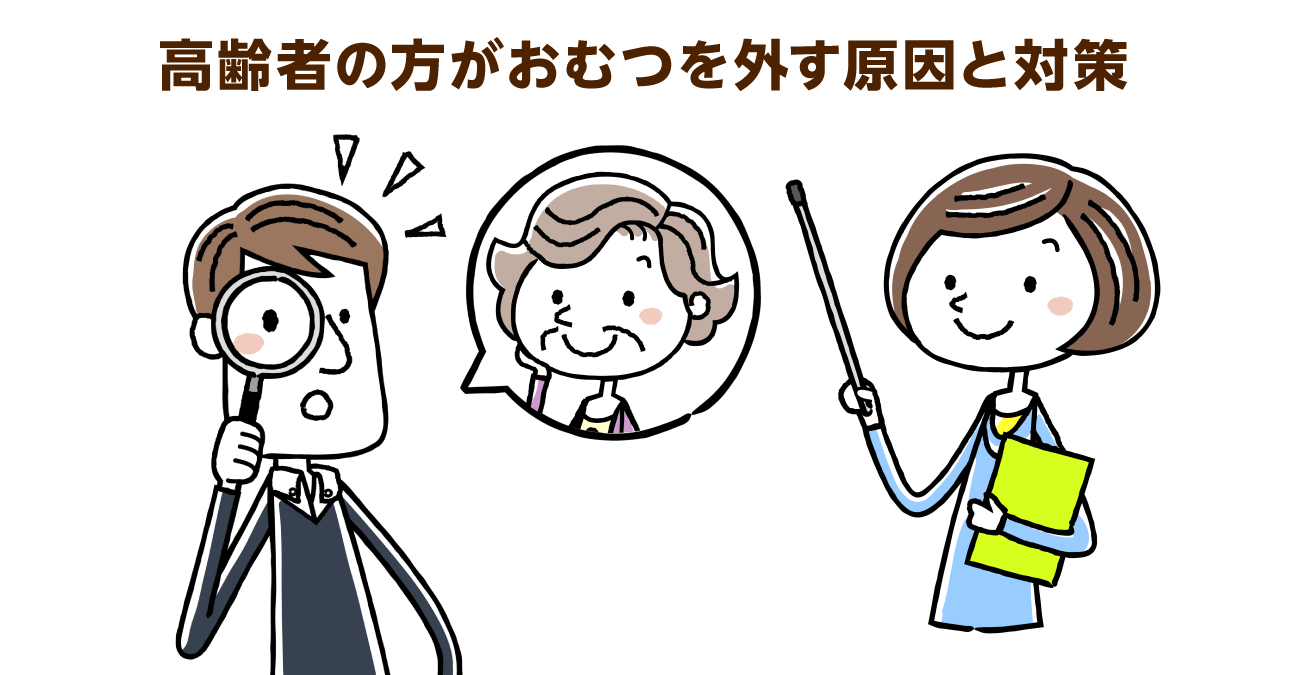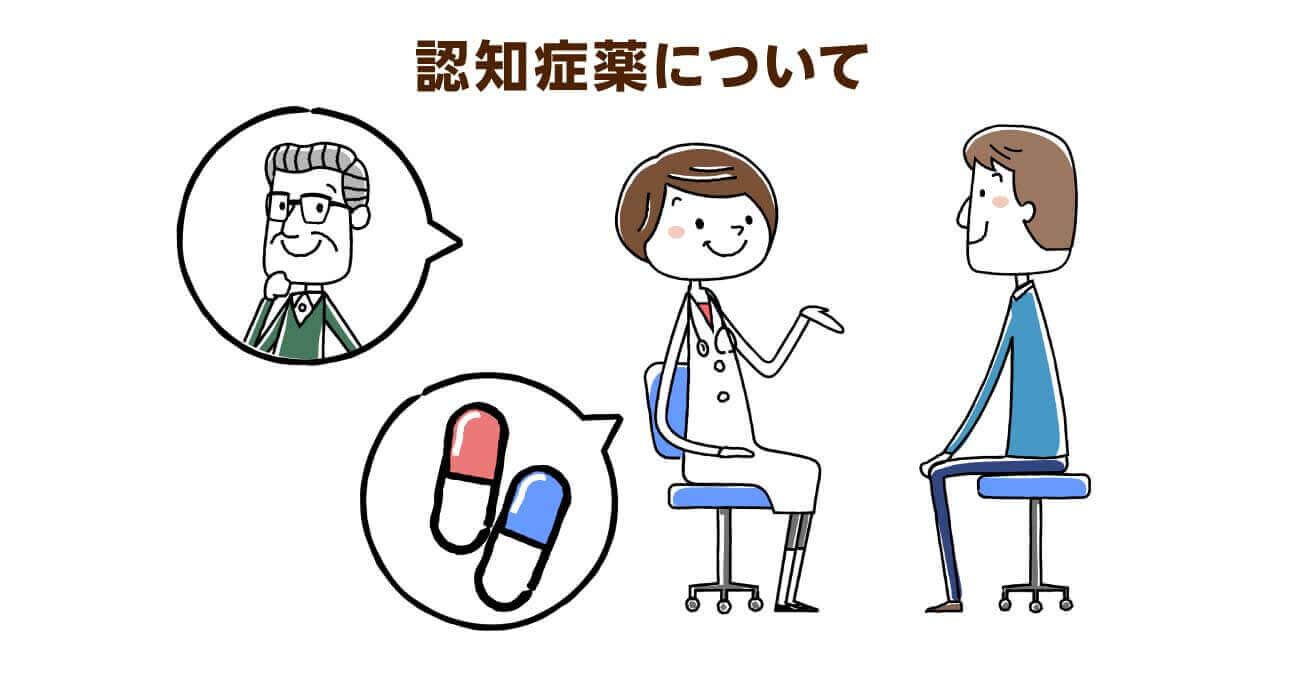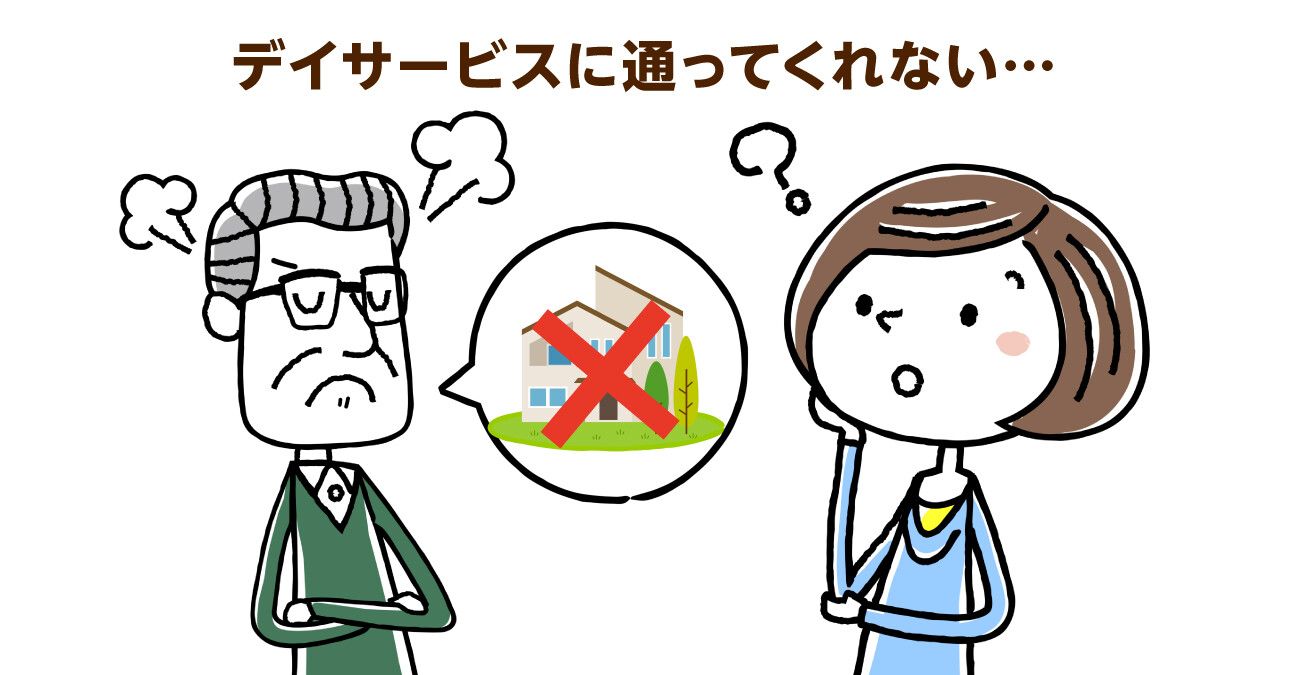読者のみなさん、はじめまして。介護業界で30年ほど勤務しており、在宅介護は10年になる貝塚です。
現在は母親の介護をしながら、貝塚ケアサービス研究所代表の代表として「介護施設のコンサルティング」「職員研修や講演」「執筆活動」など行っています。
出版(介護技術などの本)、連載、単発執筆などの執筆活動も多く、家族向けの連載としては「けあサポ(中方法規出版)」というWebマガジンで長く書いていました。
介護の教科書では「在宅介護」をテーマに、「家族の思いや視点」「介護サービスの利用の仕方や心得」「入居施設の選び方」「介護職など専門職の思い」「ケアマネージャーや介護職など専門職との付き合い方」などをわかりやすい言葉でお伝えしていきます。よろしくお願いします。
今回は、在宅介護の成り立ちについてお話ししていきます。
親の世話は家族で行ってきた歴史がある
日本の在宅介護には長い歴史があります。
社会全体で高齢者を支えるといった国の施策として「在宅介護(高齢者介護)」の取り組みは日が浅いと言えます。
高齢者よりは、「戦争孤児」「経済的社会的等により育児が困難」や「生まれながらの重度障がい」などを対象とした、児童や障がいを持つ人を対象とした福祉が先行していました。
高齢者である「親の世話は家族で」と言う考え方を前提としていたからです。

在宅介護は女性を中心に成り立ってきた
日本社会は江戸時代から、そして特に明治時代以降は、男系優先の考えを主とする家族制度を基本としていました。
長男と結婚する女性は、長男の親と同居することが普通と言った時代が長く続いたのです。
さらに、妻よりも長男の地位が高いと考えられていたため、俗にいう下級労働は女性が行うべきと考えられていました。
その下級労働には、長男の親の世話(在宅介護)が含まれていたのです。
ですから家庭においては、主に女性が親の介護をして来た歴史が長くあります。
その当時、女性(妻)が日常的に行っていたことは、親の介護・子育て・家事全般・近所付き合い・親族付き合いから仕事(農業や商売など)まで多岐に渡っていました。

昭和時代に入り、男性は外で働き、女性は家庭を守る人と言った社会的価値観が浸透するなか、昭和38年に特別養護老人ホームは誕生しました。
しかし介護業務は女性が担うべきものだという考えのもと、入浴や排泄介助など、直接介助を行う業務はすべて女性職員が担っていたのです。
まだ介護という言葉がなかった時代、介護職員は「寮母」と呼ばれていたことからも、女性が担うことで施設介護が成り立っていました。
介護は家族の人生を変えてしまう
“身内のことは身内で担う”意識が染みついている人は多くいます。
「親との同居生活が長かったから」「長男や長男の妻だから」「祖父や祖母のお世話をしていた親の姿を思い出すから」「結婚をして義理の親と暮らした時間が長いから」…など、親(家族)を大切に思う気持ち。
それに加えて「本来は自分達身内で介護しなければならないのでは」「老人ホームに入居させて良いのだろうか」…など、子としての責任感がその要因だと考えられます。
私はこれまで、大勢の在宅介護を担う家族と出会い、その姿を支援・応援してきました。
義理の親の介護では、“義務感”により苦痛を感じていた人もいれば、介護を“当たり前”と思い最後まで看取れて幸せを感じていた人など、介護に対する思いはさまざまでした。
介護をする体制、悩みもそれぞれです。
認知症の母親を1週間ごとに、交代で各家庭に招いて介護をしている3姉妹。
主人に親の介護で実家に日帰りで帰りたいと相談すると「お前はうちの人間で、もう○○(長女の実家)の人間ではない。帰る必要はない」と言われ、途方に暮れて相談に来た女性。
ある50歳代の男性は、「親が倒れ、要介護状態となったことで好きな仕事を辞めることを選んだ…。今は実家に戻り非常勤社員として働き、親の介護をしている」と言う人も。

介護は要介護となった人の人生だけではなく、家族の人生も変えてしまうのです。
最後に一言
まだまだ在宅介護の現場は、女性が担っていることが多いのが現状です。
しかし、施設介護の現場では職員の半数近くの男性が活躍している所も数多く存在するようになりました。
女性、男性に関係なく親や身内の介護を担うことは大変です。
介護保険制度を活用したとしても、在宅介護の担い手として「家族」の存在が大きいことは昔も今も同じなのです。