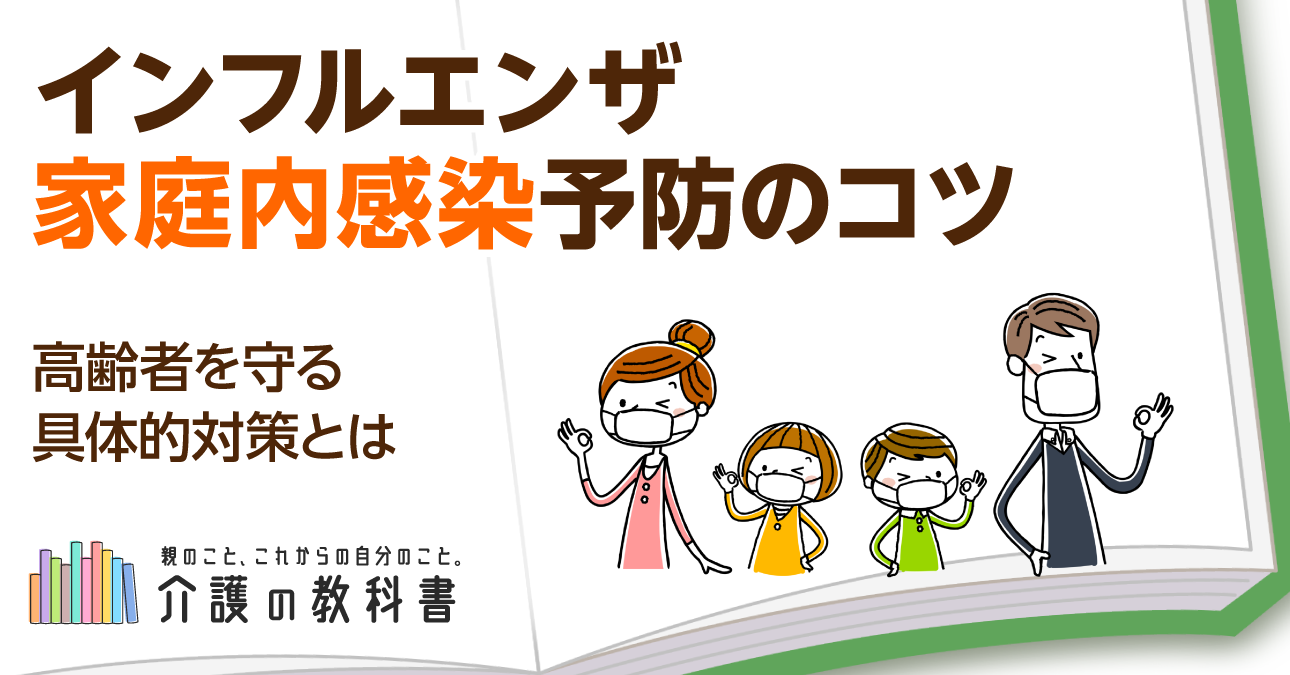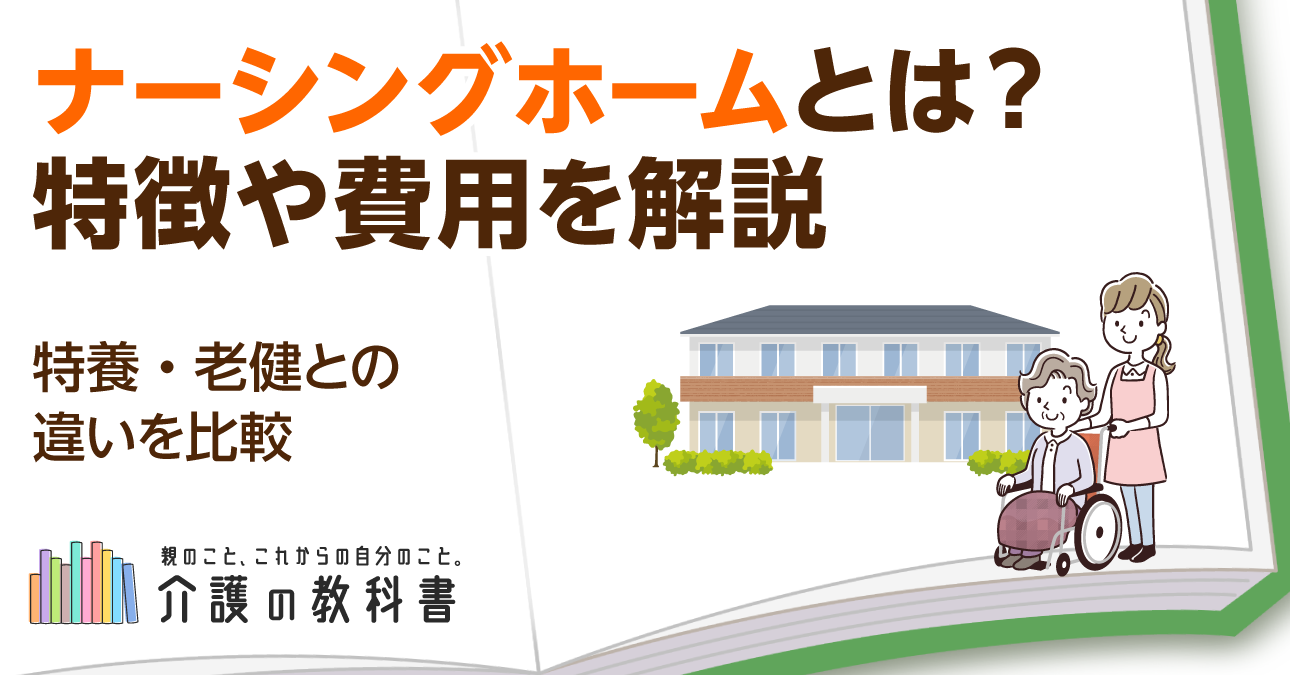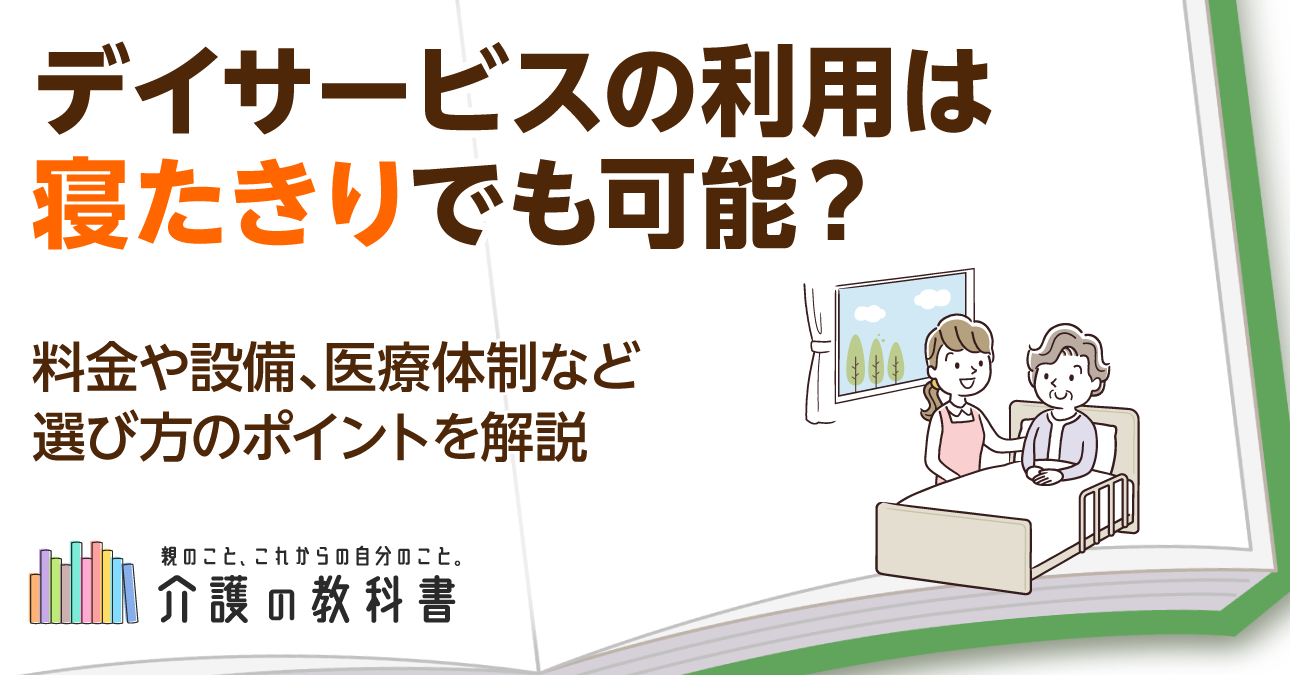介護保険について調べられているみなさん、こんにちは。介護コンサルタントの星 多絵子です。
私は仕事柄、いつも地元のスーパーで人間観察をしているのですが、高齢者の方々にあたっては年金だけで生活していくことに苦労している様子がうかがえます。
介護の教科書では、介護を制度やお金の面から解説しています。
25回目になる今回は、生活保護受給者が受けられる介護サービスについて書きます。
生活保護を受けている人はどのようなサービスを受けることができるのか、問題点も含めて解説していきますね。
生活保護を受けると貰える介護扶助とは
65歳以上で介護保険サービスを受けている方の場合、介護サービスの自己負担は原則1割となっています。
しかし、生活保護者はこの1割を自己負担する必要がありません。
この1割は生活保護法により負担される仕組みになっており、これを介護扶助と呼びます。
また、40歳以上65歳未満の方が生活保護になった場合も、介護サービスを利用するときは介護扶助を受けることができます。
つまり、介護が必要な40歳以上65歳未満の生活保護受給者も、自己負担はありません。
介護保険料について
介護保険料は、生活保護を受けている65歳以上の方の場合、生活扶助に上乗せして介護保険料を受け取ることができます。
40~64歳の場合では、生活保護費のなかで「介護扶助」として賄われているのです。
介護保険の被保険者ではありませんが、第2号被保険者とみなして認定審査が行われます。
介護保険を使えない「みなし2号」の介護サービス費用は、10割すべてが介護扶助から支払われます。
そして65歳以上になれば、介護保険が適用されることになります。
介護扶助のサービス内容
介護扶助は、通常の介護保険サービスと同じように現金支給ではなく、現物支給になります。
受けられる現物支給の介護サービスとして、具体的に以下のものがあります。
介護扶助で受けられるサービス
- 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
- 福祉用具
- 住宅改修
- 施設介護
- 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
- 介護予防福祉用具
- 介護予防住宅改修
- 移送
介護扶助の問題点
生活保護受給者は無料で介護サービスを受けられます。
デイサービスも介護保険の上限までであれば、ほぼ希望通り通うことができ、介護用品も無料で手に入るのです。
要介護1で介護保険サービスをフル活用すると、年間200万円分を無料で使えることになります。
これに対し、生活保護を受給しない人は、限られた年金のなかでやりくりしなければなりませんよね。
介護保険を使えば1割の自己負担で済むとはいっても、例えば要介護1で介護保険サービスをフル活用することになると、年間の自己負担額は20万円にもなります。
これは収入が限られている高齢者にとって、大きな痛手です。
これでは、税金を納めている方が介護保険サービスの恩恵を受けられず、税金で生活保護を受けている方が恩恵を受けている、といった矛盾が生じています。
生活保護受給者のモラルの問題も生じており、生活保護の適正利用が求められています。

国の財政
介護扶助は、介護保険制度が開始された2000年度から、扶助人員、扶助費ともに増加しています。
この現状は医療扶助ほどではないものの、財政を圧迫している原因のひとつです。
今後、生活保護の申請について、厳格化されることが予想されます。
| 年度 | 介護扶助人員 (万人) |
介護扶助費 (億円) |
|---|---|---|
| 2000 | 6.7 | 14.3 |
| 2001 | 6.4 | 22.2 |
| 2002 | 10.6 | 29.1 |
| 2003 | 12.7 | 35.8 |
| 2004 | 14.7 | 41.9 |
| 2005 | 16.4 | 47.0 |
| 2006 | 17.2 | 50.2 |
| 2007 | 18.4 | 53.9 |
| 2008 | 19.6 | 56.2 |
| 2009 | 21.0 | 61.0 |
| 2010 | 22.8 | 65.9 |
| 2011 | 24.8 | 70.7 |
「福祉行政報告例」(大臣官房統計情報部)更新
生活保護を受けるデメリット
生活保護には、介護保険の負担がないというメリットがありまが、その反面で人としての経済的自由が制限され、監視下に置かれるというデメリットもあります。
また、生活保護申請の際、資産の保有について綿密な調査が行われます。
例えば、不動産。ローンが残っている家・土地を所有している場合は生活保護を受給することはできません。
これらを所有したまま生活保護を受給することを認めてしまうと、国のお金で個人の資産を増やすことになってしまうからです。

また、生活保護受給中は原則、自動車を使用することも、所有することも認められていません。
現金化がしやすい宝飾品、売った場合に高額になるハイビジョン薄型テレビやパソコンなどの所有も認められません(売った場合に高額にならないものは所持できます)。
要するに、人としての自由が大幅に制限されることになります。
このような資産を持っている方は、生活保護の申請時にこれらすべてを手放すという、相当な覚悟を求められます。
最後に一言
生活保護を受けるような状態にならないのが一番良いのですが、万一に備えて、仕組みを大まかにでも理解しておきましょう。
生活保護はお金の心配をしなくて良い反面、人としての経済的自由を制限されます。
もし生活に困窮し、生活保護を検討しなくてはならなくなった場合は、これら両面からよく考えることが大切です。
本当に生活保護が必要なのか悩んだときは、市区町村の窓口の方や、ケアマネージャーなどとよく話し合いましょう。