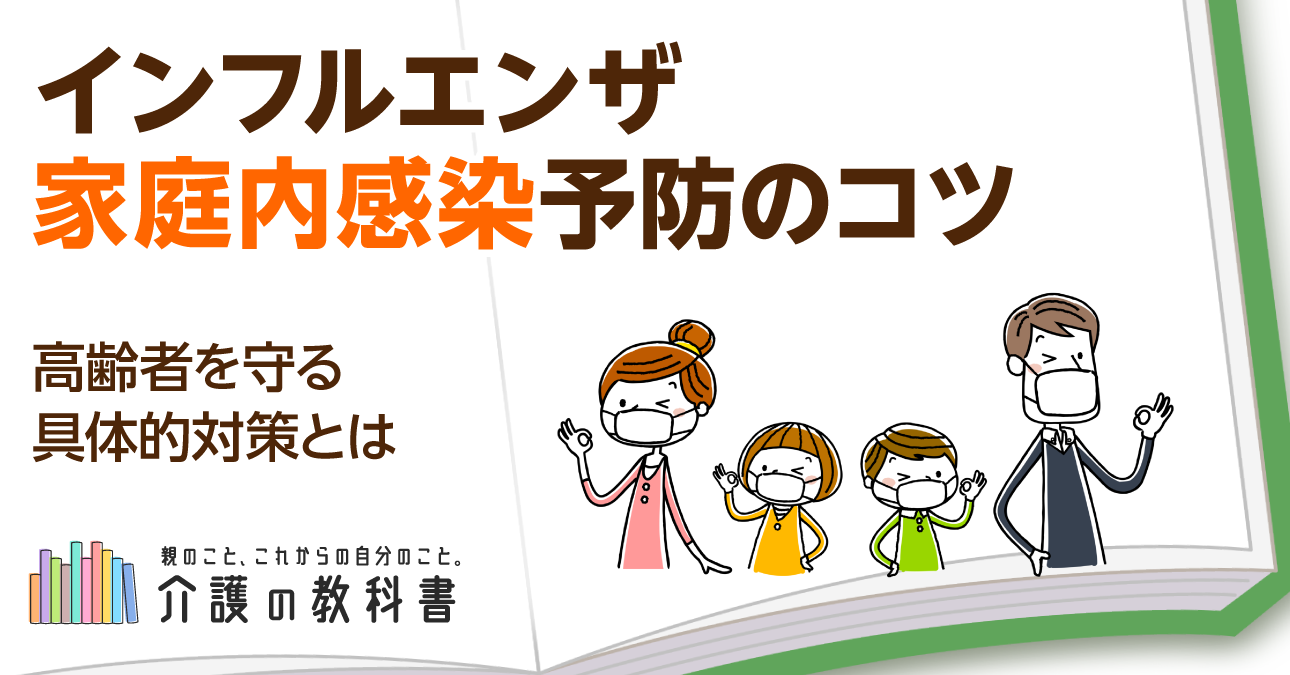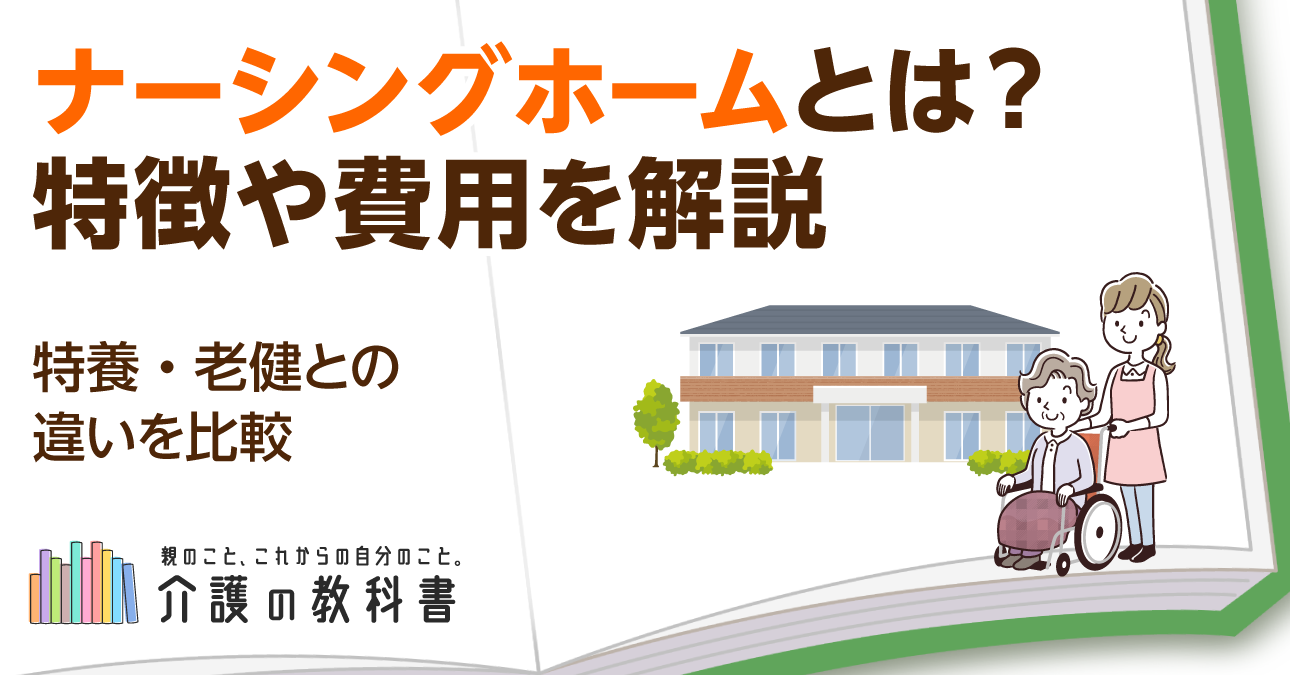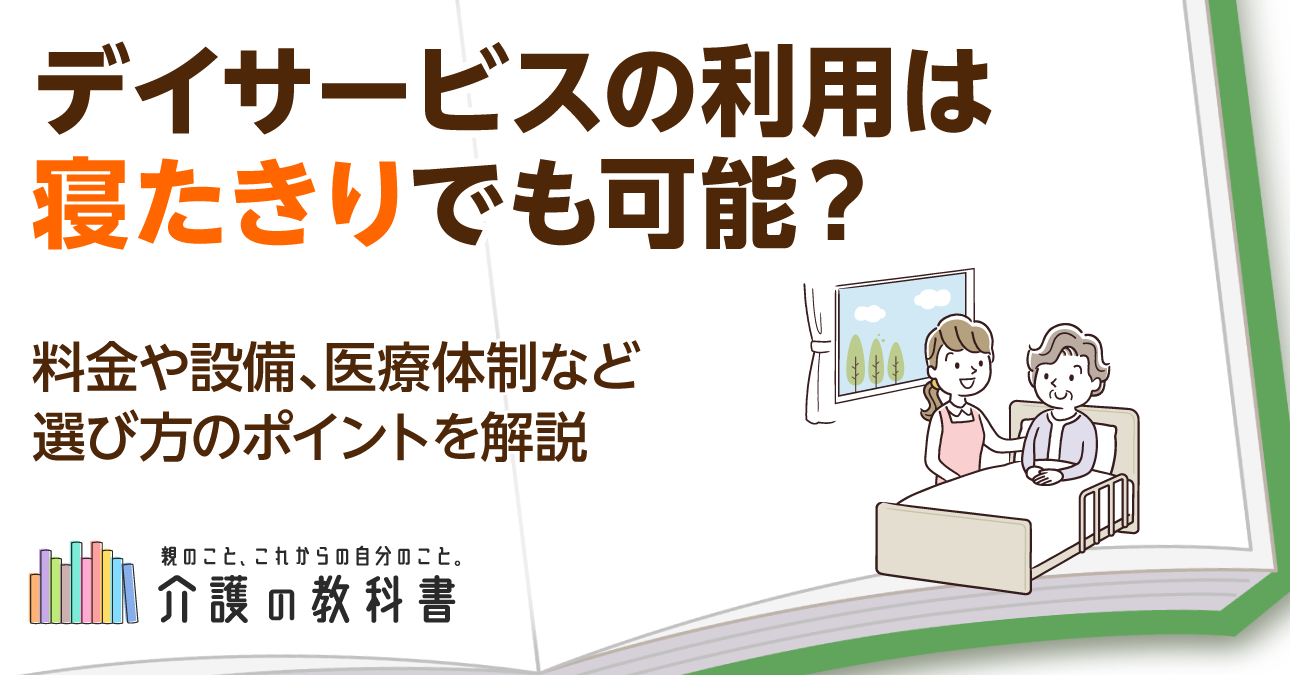こんにちは、「有限会社リハビリの風」でデイサービスの管理者をしている阿部洋輔です。
今回は「自立支援」について書いていきます。
突然ですが、「引き算の介護」という言葉を聞いたことがありますか?
これまでの介護サービスは、被介護者が自分でできることでも、介護士がありとあらゆることをお手伝いしてくれるというイメージを持たれていました。
しかし、過剰介助は被介護者の自立を妨げ、身体機能を衰えさせてしまう可能性があります。
介護者としても、介助することが足し算のようにどんどん増えていってしまうため、これは「足し算の介護」と呼ばれています。
「引き算の介護」とはその逆で、本来の介護の在り方である被介護者の主体性を尊重し、できないことだけを介助するというものです。
介護者が助けるべきこと=被介護者がやりたいこと-被介護者ができること
この「引き算の介護」は、介護保険制度の目的である「自立支援」の考え方に基づいています。
「自立支援」の考え方とは

最初にも述べたように、何から何まですべてを手伝ってあげることが介護ではありません。
日常的な介護を思い浮かべてください。
- 車に乗り込む
- ベッドから車椅子に移乗する
- 上着を脱ぐ
- 靴を履き替える
これらの動作を介助するとき、ただ漫然と手伝っていませんか?
被介護者が自分で行える動作に関しては、手伝わずに見守ることが本来の介護の在り方です。
これまでの介護では、被介護者は「何でも手伝ってもらう」、介護士は「何でも手伝う」といった依存的な関係を築いていました。
親切に介護をしている介護者ほど、つい過剰なサービスを提供してしまう、なんてことはよくあるのではないでしょうか。
もちろん、介護保険事業はサービス業でもあります。
しかし、介護保険の本来の目的は「自立支援」です。
介護者が過剰に手伝い過ぎることで、被介護者の残存機能を低下させたり、主体性を損なわせたりと、マイナスになってしまうことも考えなければいけません。
被介護者が一人ではできないのか、ゆっくりでも時間をかければできるのか。
介護スタッフは被介護者のできることをよく見極め、できることであれば本人に任せることも大事な仕事のひとつなのです。
自立支援を率先して行っている「夢のみずうみ村」

自立支援を考えるときに、良い題材となるデイサービスがあります。
それが社会福祉法人「夢のみずうみ村」です。
この施設は作業療法士(リハビリを行う国家資格者)の藤原茂さんが開設しているため、リハビリに効果的な工夫がたくさんあります。
さまざまなTV番組でも取り上げられているので、介護業界だけに限らず認知度が高いかもしれませんね。
それでは、自立支援の工夫として何をしているのかをご紹介します。
- 身体の機能訓練のために、段差や坂を多く設置している「バリアアリー」の設置
- 自分で食事を盛り付ける動きにより、主体性とリハビリ効果を引き出す「バイキングスタイル」の食事
- カラオケや料理教室など、多種多様なアクティビティーから積極的にやりたいことを決めることができる「自己選択・自己決定方式」の採用
こうした工夫からも、「夢のみずうみ村」の自立支援に対する徹底が伺えますね。
ちなみに、私が「夢のみずうみ村」を見学に行ったときには、施設の利用者さんに見学対応をしていただきました。
びっくりですよね。
そのとき、利用者の方々がイキイキしながら、その施設で積極的に楽しく生活していることがよくわかりました。
被介護者の主体性を尊重しよう

利用者が自分でやりたいことを決め、自ら積極的に行う。
そこには、介護施設が陥りがちな「利用者を管理してあげなければ」という概念がありません。
もちろん、介護度は人それぞれですから、一概にどの施設が良いと言うことはできません。
しかし、利用者の一人ひとりができること・やりたいことに取り組める環境づくりは大切です。
「引き算の介護」は、被介護者が主体になることから始まります。
親切心から何でも手助けしてしまうことは、被介護者のためにはなりません。
うまくいかないときは、被介護者がうまく動作を行える方法を一緒になって考えてみましょう。
今日から少しでも「引き算の介護」実践してみてください。
きっと被介護者の方ができることが、少しずつ増えていくはずです。
介護サービスへのイメージが、「介護者がやってあげる」ではなく「被介護者が自分でやる、それを介助者が手伝う」といったような、被介護者が主体のものに変化していくと良いですね。
今回のテーマまとめ
- 被介護者ができることは介助をせず、見守ってみましょう
- 残存機能を動かしてもらえる介助を心がけましょう
- 被介護者が上手に動作ができなかったときは、一緒にできる方法を考えてみましょう