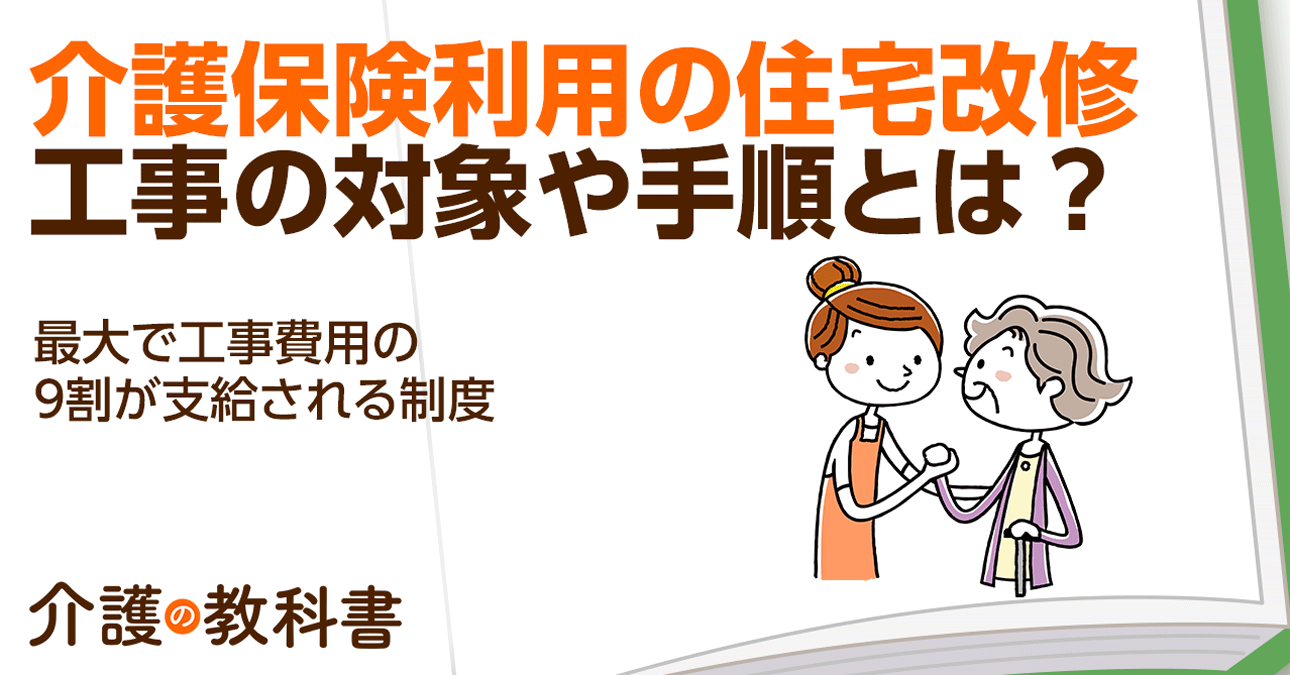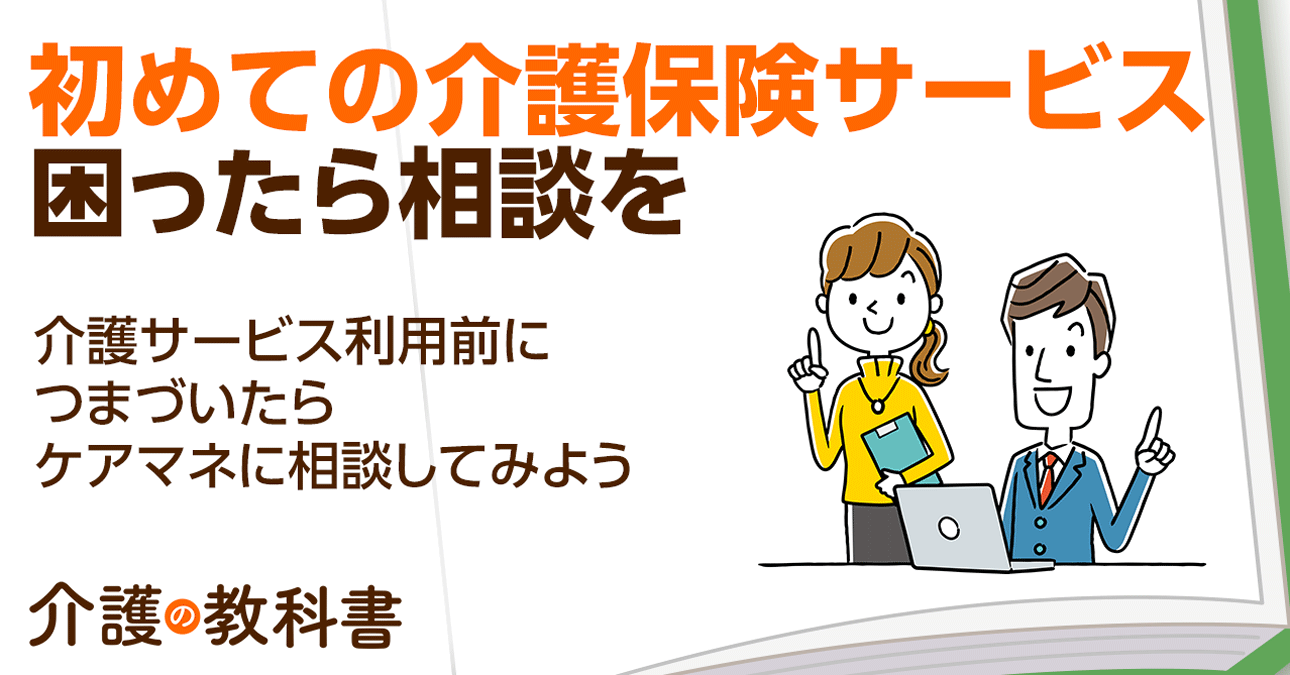介護保険について調べられている皆さん、こんにちは。介護コンサルタントの星多絵子です。
このコーナーでは、介護を制度やお金の面から解説します。できるだけわかりやすい説明を心がけます。わからない部分がございましたら、巻末までご連絡ください。個別相談もいたします。
今回は、生活保護と介護保険について解説していきます。
そこで、読者の皆さんに質問です。生活保護を受けている人は介護保険の給付を受けられるでしょうか。
正解は、「受けられます」。その理由を、かみ砕いて詳しく説明していきたいと思います。
生活保護受給者の現状と生活保護の内容
高齢者の生活保護受給の現状
厚生労働省の調査によれば、生活保護受給者のうち65歳以上の高齢者が45.5%を占めています。
この数字から高齢者世帯における貧困問題が見過ごすことができないものであることがわかります。
現在、政府の政策では「一億総活躍社会」がさけばれていますが、定年退職後に高齢者が就業できないことも、こうした状況の要因のひとつなのはないでしょうか。
生活保護の内容

生活保護には8つの扶助があり、保護受給者は必要な扶助を必要な分だけ支給され生活しています。
8つの扶助とは、介護扶助、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助です。それぞれの生活に合わせて、どの扶助が必要であるか行政が判断し、生活保護受給者に支給されています。
今回の内容で重要なのは、介護扶助と生活扶助です。理由は後述します。
介護保険の年齢による区分とは

介護保険は年齢により、区分されています。
①第1号被保険者…65歳以上
介護保険料は年金から天引き。
原因を問わず、要介護、あるいは、要支援状態と認定されれば介護サービスを受けられます。
②第2号被保険者…40歳以上64歳以下であり、かつ医療保険加入者
介護保険料は医療保険料に上乗せで徴収。
介護サービスの利用は、末期がんや関節リウマチ等、加齢を原因とする16の疾患が原因で要介護状態になったときに限られます。
この区分により、介護保険に生活保護が絡んできます。
生活保護受給者と介護保険

①65歳以上の場合
65歳以上であれば医療保険を支払っていない人であっても、全員が介護保険の第1号被保険者となります。したがって、介護保険料を支払う義務が生じます。
ただ、生活保護受給者であるため、支払いが困難です。このため、介護保険料の分を生活扶助に上乗せしてこちらから支払うようにしています。
介護サービスを受けることになったら、利用者負担分が生じます。社会保障にはさまざまな仕組みがありますが、介護保険が優先して使われるようになっているからです。
介護サービスは、所得が低い場合、介護保険9割、利用者負担1割となっています。生活保護受給者は、利用者負担1割を介護扶助から支払われます。
②40~64歳の場合
先述したとおり、介護保険の第2号被保険者は医療保険から介護保険料が上乗せで徴収されます。このため、医療保険加入者が第2号被保険者になります。
理屈のうえでは、保険料を納められない生活保護受給者は、第2号被保険者になりえないことになります。
こうした人が要支援または介護状態になった場合、生活保護費のなかの「介護扶助」で賄われることになっています。介護保険被保険者ではないけれど、第2号被保険者とみなして認定審査が行われます。
介護保険を使えないみなし2号の介護サービス費用は、10割すべてが介護扶助から支払われます。
まとめ
生活保護と介護保険の仕組みは複雑です。まず、年齢により区分されること。「65歳以上」か「40~64歳」かで大きく変わります。万一に備えて、仕組みを大まかに理解しておきましょう。
介護保険を使わないで済むのが理想ですが、現実にはそうはいきません。介護保険料や利用者の一部負担金が重くなったら、1人で抱え込まず、市区町村の窓口に相談に行きましょう。
平成30年度改定は大きな節目の年です。さて、どう変わるでしょうか?今後も注目ポイントをピックアップ!
次回も、平成30年度介護報酬改定の具体的な内容について書きます。大切なことなので、わかりやすく説明いたします。次回もご覧ください。