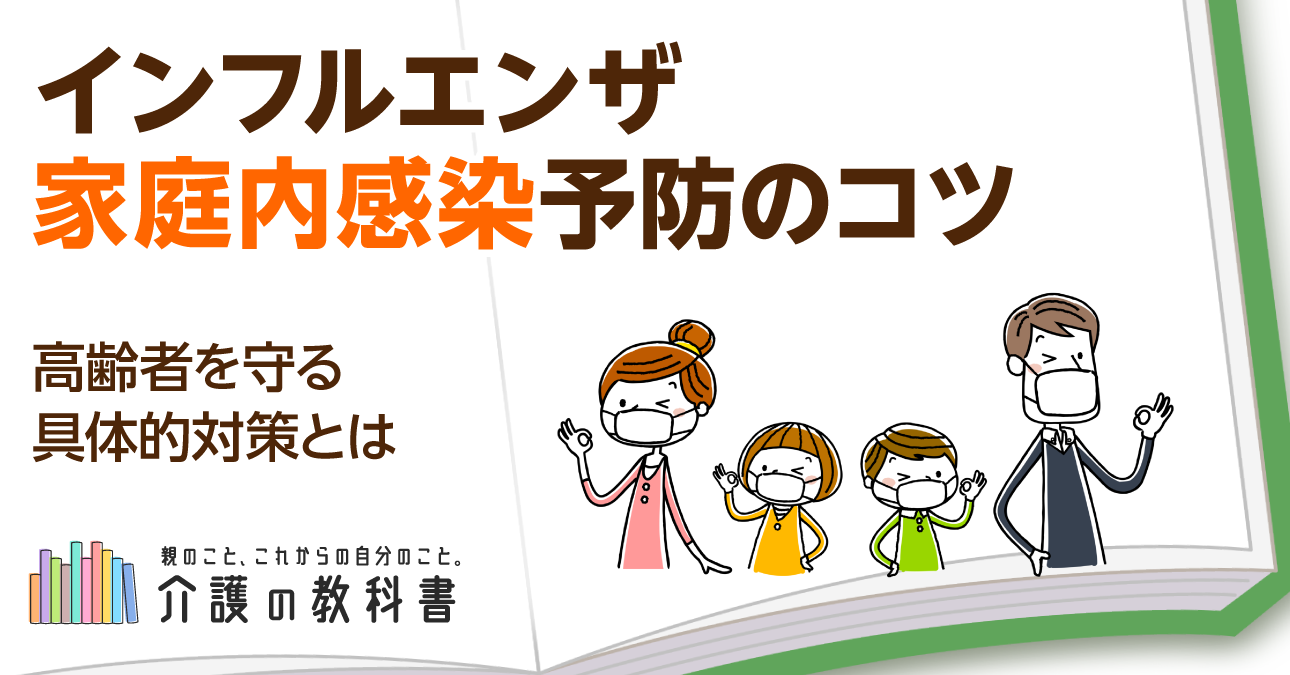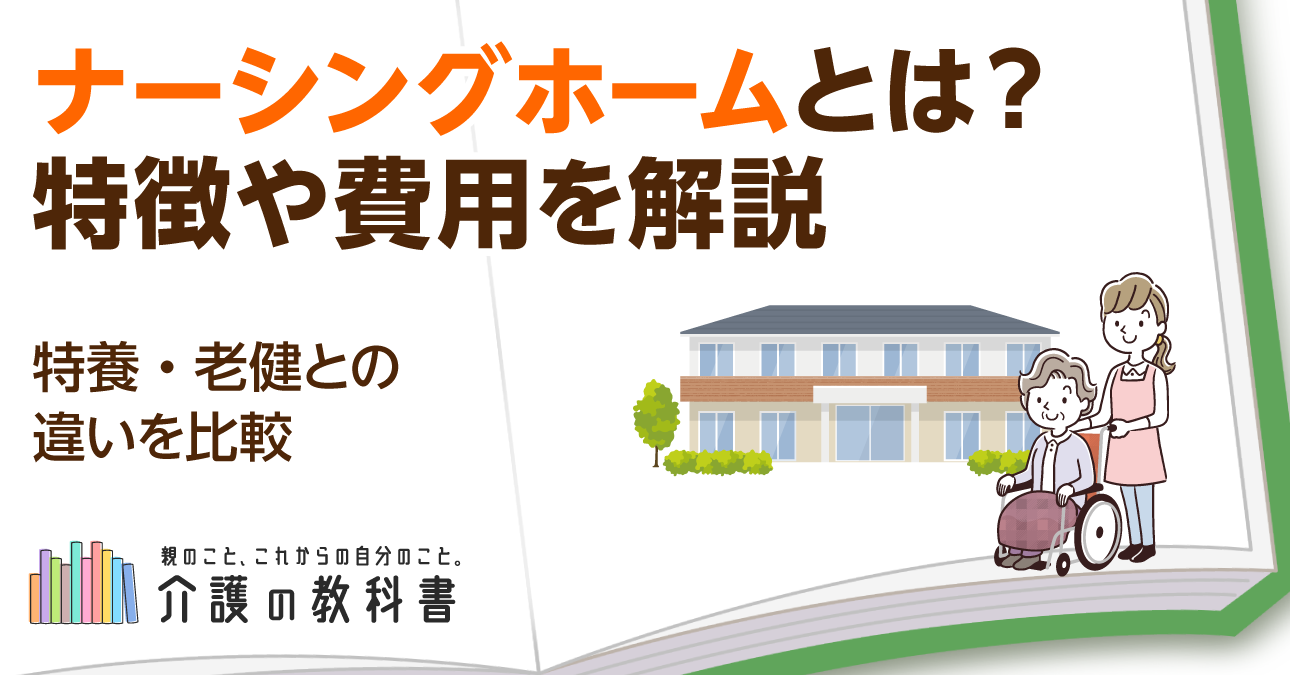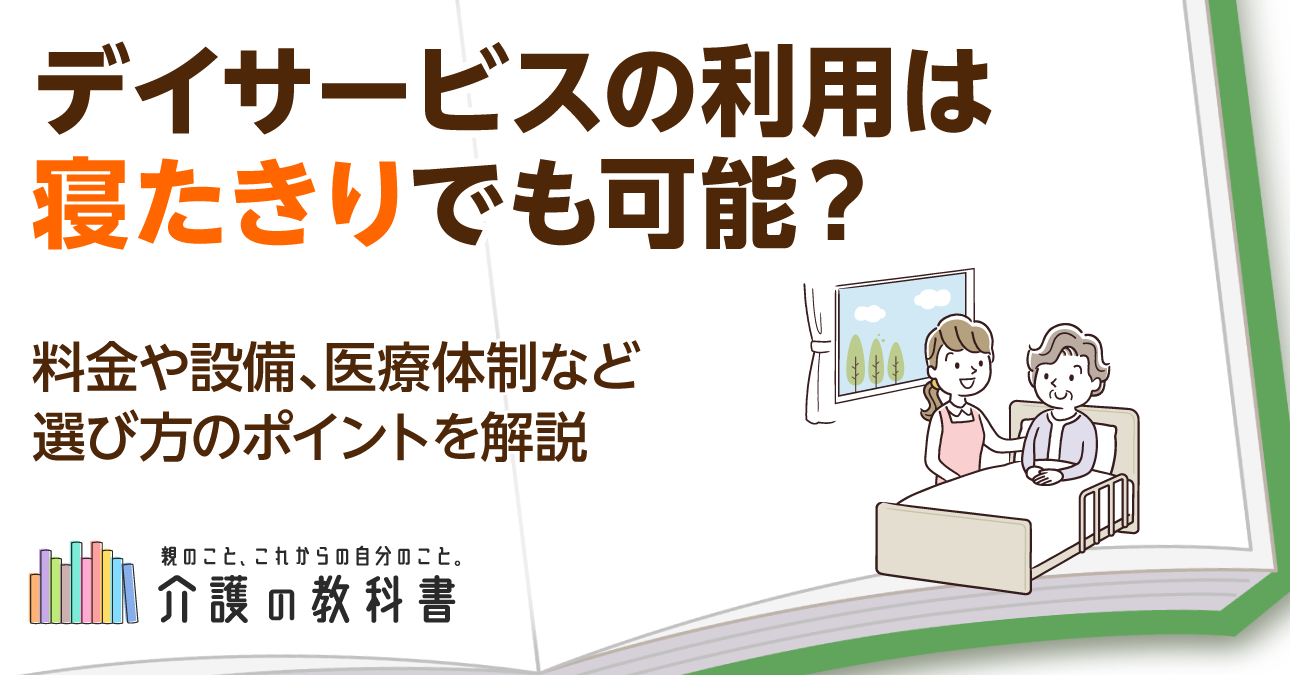高齢者向けの防災グッズ選びは、一般的な防災用品とは異なる視点が必要です。持病の薬や介護用品、身体機能の低下に配慮したアイテムなど、高齢者の状況に合わせたグッズを準備することが重要になります。
この記事では、高齢者やそのご家族、介護従事者の皆様に向けて、実際に役立つ防災グッズと対策方法を詳しく解説します。
高齢者向け防災グッズの基本セット
高齢者の防災準備において、まず押さえておきたいのが基本的な防災グッズです。一般的な防災用品に加えて、高齢者特有のニーズに配慮したアイテムを選びましょう。内閣府の防災基本計画では、最低3日分、できれば1週間分の備蓄を推奨しています。
水・食料品
災害時の水と食料は生命に直結する最重要アイテムです。高齢者の場合、一般的な成人よりもさらに注意深い準備が必要になります。
水については、1人1日3リットルを基準に、最低3日分の9リットル、できれば7日分の21リットルを備蓄しましょう。高齢者は脱水症状を起こしやすく、特に夏場の災害では熱中症のリスクが高まります。
水は飲用だけでなく、薬の服用や簡単な清拭にも使用するため、余裕を持った量を備蓄しておくと安心です。
食料品選びでは、高齢者の咀嚼機能や嚥下機能を考慮することが重要です。固い食べ物や大きな塊の食品は避け、やわらかく食べやすいものを選びましょう。
- おかゆやうどん
- ゼリー状の栄養補助食品
- レトルトの介護食
これらのようなものが適しています。また、普段から食べ慣れている味付けのものを選ぶことで、災害時のストレスを軽減できます。
アルファ米は水やお湯を注ぐだけで食べられるため、災害時の主食として優秀です。缶詰では、魚の水煮やフルーツ缶など、そのまま食べられるものが便利です。
栄養面では、災害時は野菜不足になりがちで、便秘や体調不良の原因となることがあるためビタミン・ミネラル補給ができるものを準備しましょう。野菜ジュースや経口補水液・ビタミン補給ゼリーなどカフェインや糖分が過剰でない製品がおすすめです。

衛生用品・生活必需品
災害時の衛生管理と生活必需品の準備は、高齢者の健康維持に直結する重要な要素です。普段の生活で使用している身近なアイテムこそ、災害時に不足すると大きな支障をきたします。
- 携帯トイレ
- 断水時や避難所での使用を想定して、携帯トイレは1人1日5個目安に、まずは3日分(15個)、可能なら7日分(35回)を準備しましょう。高齢者の場合、夜間の排尿回数が多くなることも考慮して、やや多めに用意することをお勧めします。また、携帯トイレには凝固剤が含まれているタイプを選び、臭いの発生を抑える機能があるものが理想的です。
- 大人用おむつやパッド
- 最低1週間分を備蓄しましょう。これらの用品はかさばるため、圧縮袋を使用して保管スペースを節約する工夫も有効です。おしりふきやボディタオルなど、身体を清潔に保つためのアイテムも忘れずに準備してください。
- 歯ブラシと入れ歯洗浄シート
- 災害時でも歯磨きを継続することで、誤嚥性肺炎や歯周病の悪化を防ぐことができます。入れ歯を使用している方は、水がなくても清拭できる入れ歯洗浄シートを用意しておきましょう。
- メガネや老眼鏡の予備
- 災害時にメガネを紛失したり破損したりすると、避難行動や情報収集に大きな支障をきたします。古いメガネでも度数が合っていれば十分に使用できるため、買い替え時に古いメガネを防災用として保管しておくことをお勧めします。
- 手指消毒用のアルコールジェルや除菌シート
- 手指消毒用のアルコールジェルや除菌シートも、感染症予防の観点から重要なアイテムです。避難所では多くの人が集まるため、衛生管理により一層の注意が必要になります。
情報・連絡カード
災害時の情報収集と連絡手段の確保は、高齢者の安全を守るために不可欠です。停電や通信網の混雑により、通常の連絡手段が使えなくなることを想定した準備が必要です。
まず、情報収集のためにラジオを準備しましょう。スマートフォンのバッテリーを温存するためにも、災害情報の収集には専用のラジオが有効です。手回し充電機能付きのものを選べば、電池切れの心配がありません。
緊急連絡先をまとめた連絡カードも必要です。家族の連絡先、かかりつけ医の情報、服用中の薬の名前、既往症やアレルギーなどの医療情報を記載しておきましょう。このカードは防水ケースに入れて、常に携帯できるようにしておきましょう。
介護負担を減らす+αの便利グッズ
基本的な防災グッズに加えて、高齢者特有の困りごとに対応した便利グッズを準備することで、災害時の介護負担を大幅に軽減できます。これらのアイテムは、高齢者本人の自立性を保ちながら、介護者の精神的・身体的負担も和らげる効果があります。
災害時は通常の介護サービスが受けられなくなることが多く、家族による介護負担が急激に増加します。そのような状況に備えて、日頃から介護を楽にする便利グッズを準備しておくことが重要です。
体温管理グッズ
災害時の体温管理は、高齢者の健康維持において極めて重要です。加齢により体温調節機能が低下するため、気温の変化に対応できずに体調を崩しやすくなります。
- 使い捨てカイロ
- 寒冷期の災害時に欠かせないアイテム。足裏用や首元巻きタイプなど、用途別に準備が必要。末梢循環の悪化しやすい高齢者には、手足の冷えを防ぐことで体温維持に役立つ。
- 備蓄目安:1日3〜4個 × 3日分(9〜12個)。寒冷地や在宅避難の長期化に備え、多めに用意することが推奨される。
- アルミシートやアルミブランケット
- 体温保持に便利で、軽量かつコンパクトなため避難時の持ち出しに適している。通常の毛布と組み合わせることで、保温効果が向上する。
- 冷却シートや濡れタオル用の水
- 夏場の災害対策として準備が必要。高齢者は熱中症になりやすく、体温上昇は命に関わる危険がある。首元や脇の下を冷やすことで、効率的に体温を下げられる。

服薬サポートグッズ
災害時でも継続的な服薬は高齢者の健康維持に不可欠です。しかし、環境の変化やストレスにより、普段通りの服薬管理が困難になることがあります。
- お薬カレンダーや薬の仕分けケース
- 災害時の服薬管理を大幅に簡素化します。1週間分の薬を曜日別・時間別に整理しておくことで、混乱した状況でも正確な服薬が可能です。透明なケースを使用することで、薬の残量も一目で確認できます。
- 水なしで服用できる薬
- 災害時の選択肢として検討できます。かかりつけの医師や薬剤師に相談のうえ、可能であれば一部の薬を水なしタイプに変更しておくと有効です。
- 薬用ゼリーや服薬補助用品
- 避難所では十分な水が確保できない場合があり、薬の服用が困難になることもあります。これらの補助用品があると、確実な服薬を継続できます。
- 薬剤名、用法・用量、副作用などの情報
- ノートやメモにまとめて防水ケースに入れて保管しておくと安心です。災害時に医療機関を受診する際、正確な情報を医療スタッフに伝えることができます。
移動サポートグッズ
災害時の避難や移動において、高齢者の身体機能の低下をサポートするグッズは安全確保に直結します。普段は杖や車椅子を使用していない方でも、災害時の混乱した状況では移動支援が必要になることがあります。
- 折りたたみ式の杖
- コンパクトで持ち運びやすく、災害時の移動支援に適しています。普段杖を使用していない方でも、瓦礫や段差のある道を歩く際の安全確保に役立ちます。滑り止め機能付きの先端ゴムがあるものを選ぶことで、より安全に使用できます。
- 簡易車椅子や折りたたみ式キャリーカート
- 移動が困難な高齢者にとって重要なアイテムです。本格的な車椅子は重くて持ち運びが困難ですが、軽量の簡易タイプなら避難時にも対応できます。
- 滑り止めマットや滑り止めシール
- 避難所での転倒防止に効果的です。慣れない環境での生活では、普段以上に転倒のリスクが高まります。簡単に設置できるタイプを選び、寝床やトイレ周辺に使用しましょう。
- ヘッドライトや首掛け式のライト
- 両手を自由に使いながら明かりを確保できるため、移動時の安全性を高めます。懐中電灯と違って手で持つ必要がないため、杖や手すりを使いながらの移動も安全に行えます。
- 履きやすい靴や滑りにくいスリッパ
- 災害時は靴を履く時間がない場合も多く、避難後に適切な履物がないと足の怪我や転倒の原因となります。マジックテープ式の靴なら、素早く確実に着用できます。
防災対策をラクに続けるコツ
防災グッズを準備するだけでなく、継続的に管理し続けることが真の防災対策です。高齢者の場合、複雑な管理方法では長続きしないため、シンプルで実行しやすい仕組みづくりが重要になってきます。
内閣府が実施した防災に関する世論調査では、防災対策を継続できない理由として「面倒だから」「何をすればよいか分からない」といった回答が多く見られました。特に高齢者の場合、身体的な負担や記憶力の問題もあり、より簡単で分かりやすい方法が求められます。
防災対策を習慣化するためには、日常生活の中に自然に組み込める工夫が必要です。特別なことをするのではなく、普段の生活の延長線上で続けられる方法を見つけることが、長期的な防災対策の成功につながります。
玄関横に持ち出し袋を置く
防災グッズの保管場所は、緊急時の持ち出しやすさを最優先に考えて決めましょう。玄関は家の中で最も避難経路に近い場所であり、災害時に必ず通る場所でもあります。ここに持ち出し袋を置くことで、避難の際に忘れる心配がありません。また、日常的に目に触れる場所にあることで、中身の確認や入れ替えを思い出しやすくなります。
持ち出し袋は、高齢者でも持ち運びやすい重さに調整することが大切です。一般的には男性で15キログラム、女性で10キログラム程度が目安とされていますが、高齢者の場合はさらに軽くして、5から8キログラム程度に抑えることをお勧めします。重すぎると避難時に持ち出すことができなくなってしまいます。
袋の種類は、両手が自由に使えるリュックサック型が理想的です。手提げ袋では片手がふさがってしまい、杖を使用する方や手すりを必要とする方の避難を妨げてしまう可能性があります。リュックサックの肩ひもはクッション性のあるものを選び、肩への負担を軽減しましょう。
袋の外側には氏名と連絡先を明記したタグを付けておきましょう。避難所で他の人の荷物と混同することを防ぎ、万が一紛失した場合の発見にも役立ちます。また、中身のリストも外側に貼り付けておくことで、定期的な点検が簡単になります。
家族と一緒に暮らしている場合は、持ち出し袋の場所と中身について必ず共有しておきましょう。高齢者本人が持ち出せない状況でも、家族が代わりに持ち出すことができます。
半年ごとにローリングストック
食料品や消耗品の管理には、ローリングストック法が効果的です。この方法は、普段から少し多めに食品を買い置きし、古いものから消費して新しいものを補充するサイクルを作る手法です。
ローリングストックの利点は、特別な備蓄食品を用意する必要がないことです。普段食べ慣れているレトルト食品や缶詰、冷凍食品などを多めに購入し、日常の食事で消費していきます。これにより、災害時でも普段と同じ味の食事を取ることができ、ストレスの軽減につながります。
管理のタイミングは、半年ごとに設定することをお勧めします。春と秋の年2回、具体的には3月と9月など、覚えやすい月を決めて定期的に点検しましょう。この時期に、賞味期限の確認、消費期限の近いものの入れ替え、不足しているアイテムの補充を行います。
点検の際は、チェックリストを作成して漏れを防ぎましょう。水、主食、おかず、薬、電池など、カテゴリー別に分けて記載することで、効率的に確認できます。家族がいる場合は、一緒に作業することで負担を分散し、防災意識の共有にもつながります。
薬については、かかりつけの医師に相談して、可能な範囲で多めに処方してもらうことも検討しましょう。ただし、法律の規定により、一度に処方できる日数には制限があるため、医師との相談が必要です。
安否確認サービスの活用
現代の防災対策では、デジタル技術を活用した安否確認システムの利用が重要になっています。高齢者の場合、スマートフォンの操作に不慣れな方もいますが、簡単に使えるサービスを選ぶことで、災害時の連絡手段として大いに役立ちます。
災害用伝言ダイヤル171は、NTTが提供する音声による安否確認サービスです。携帯電話からでも固定電話からでも利用でき、操作も比較的簡単です。
体験利用ができる期間もあるため、事前に家族間で使用方法を確認し、定期的に練習することをお勧めします。
携帯電話各社が提供する災害用伝言板サービスも有効です。文字でのメッセージ登録となりますが、音声と比べて回線の混雑に強いという利点があります。
自治体が提供する安否確認システムも積極的に活用しましょう。多くの自治体では、高齢者や障害者を対象とした見守りサービスや緊急通報システムを提供しています。これらのサービスは、災害時だけでなく、日常的な健康管理や安全確保にも役立ちます。
これらのサービスを利用する際は家族間での連絡ルールも事前に決めておきましょう。災害時にどこに避難するか、どの方法で連絡を取るか、集合場所はどこかなど、具体的な取り決めをしておくことで、混乱を避けることができます。
まとめ
高齢者向けの防災対策は、一度に完璧を目指すのではなく、段階的に取り組むことが重要です。まずは基本的な防災グッズから準備を始め、徐々に便利グッズや管理システムを整えていきましょう。継続可能な方法を見つけることが、真の防災力向上につながります。家族や地域の方々と協力しながら、安心して暮らせる環境づくりを進めていきましょう。