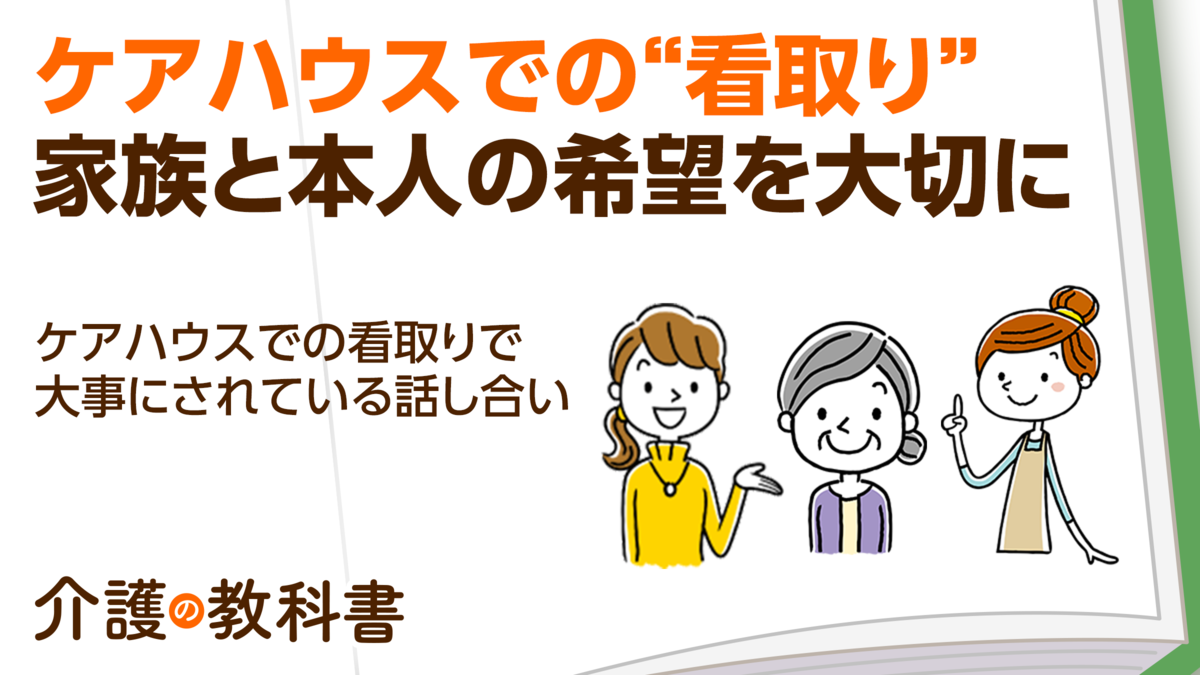終活カウンセラーは今や2万3,000人を超えますが、ターミナルケア(看取り)の知識は必須の項目でもあります。
そこで今回は終活カウンセラーでもある「あけぼのケアハウス あけぼのデイサービスセンター」(山梨県甲府市)の主任生活相談員で看護師の依田和美さんに、現在進行中の介護施設における看取りの実態について、伺うことができました。以下はその一問一答です。

親族間のデリケートな問題にも取り組む
――まず、あけぼのケアハウスの看取りケアは、今、どのような形になっていますか?
依田 弊施設の場合はケアハウスですので、特別養護老人ホームや介護付きのような看取りありきの施設とは異なり、「自宅だと考え家族に囲まれて最期を迎えたい」「家族が介護して最期を看取りたい」といったご希望に沿う施設というスタンスです。
ですから、ケアハウスで職員が看取りをしますよ、ということではありません。ほとんどが医療的なケアは最低限で、老衰、自然死を希望される方ですが、末期がんで疼痛管理などのある方もいらっしゃいます。
――コロナ禍は、ターミナルケアのさまざまな形に影響を与えたようですね。
依田 確かに、それは、あります。老健にいた方の体調が悪化したと、会えない家族から相談があったケースでは、最終的に民間救急車で入居者を運び、最期を家族で過ごした方もいらっしゃいました。
まさか、ケアハウスで終末期だけお引き受けするとは…。コロナでなければありえないパターンはありました。
――終末期はどのような体制で臨まれるのですか?
依田 看取り期はケアハウス職員が中心となって、看取りをするご家族を物心両面から介護サービスを駆使し、24時間お支えします。お部屋は約27平米の広さがありますので、ご家族はお部屋にお泊りになることができます。
――一緒に夜を過ごせるんですね
依田 昼間はご家族以外に、併設のデイサービス利用やホームヘルパー、施設職員の定期的な見守り、夜はご家族、家政婦や自費ヘルパーなどを組み合わせ、社会資源とご家族のスケジュールを合わせて配置します。
ご家族、ご本人の希望や要望、心配などは、主治医やケアマネージャーとの連携によって、都度、相談し必要なことを手配いたします。
――素晴らしい体制ですね。
依田 看取りとしてご家族に宿泊開始していただく時期の見極めと、物品の準備をして、気を張るご家族が介護に専念し、ゆっくりご本人を囲むことができるよう気を配ります。
また、ご本人が自然死を希望され、ご家族と疎遠の場合は、ご家族との連絡を代わりに取ることで、その距離を縮めていただくことを目指します。ご本人の希望を伝え、どこから関わっていただけて、どこまで受容していただけるか、を確認していきます。
――親族間のデリケートな問題にも、取り組んでおられるんですね。
依田 最後の希望を伝えることで、ご本人が安心できるよう尽力します。ただし、実費以外はすべてサービスで、特別養護老人ホームのような看取り加算などの請求もありません。
ですから一度に何人ものお看取りはお受けできませんし、何より、ご家族、ご本人と施設とのそれまでの信頼関係が看取りへの決定には大きく左右します。

看取りは家族との話し合いが大事
――あけぼのケアハウスが看取りを行うことになったきっかけは?
依田 弊施設は、自立支援型の施設。当初は自立生活ができなくなった段階で申し込んでいただいていた特別養護老人ホームや介護付き老人ホームなどに転居していただいておりました。
しかし、開設当初からご入居され、8年経過したA様から、「ここは私の家、ここで最期を迎えたい」という強いご希望があり、看取りを考えるきっかけとなりました。
――入居されていた方からの、ご希望があったんですか。
依田 A様は弟様とご入居されておりましたが、ほかにご家族はなく、弟様も離婚されており、お子様とは絶縁状態でした。お二人とも身体的に大きな疾患もなく、お元気でしたので、ぎりぎりまでおふたりが別々にならないように、と考えながら時を重ねてきました。
そして2013年、何とか介護サービスと自費サービスを組み合わせることで、初めての看取りの態勢を手探りで開始しました。それ以降、8名の方を看取らせていただきました。今年は2名、コロナ禍にあっても、ご家族には24時間面会自由とさせていただき、無事にお見送りすることができました。
―― 家族は看取りに際して、どうすればよいのですか?
依田 とにかくそばにいていただき、異変や心配事、ご本人の訴えがあれば知らせてもらっています。また、ご本人が食べたいもの、飲みたいもの、その他ご希望があれば用意してもらい、飲食の介助をしていただきます。
排泄の介助も基本的にはしていただきますが、お手伝いもいたします。あとは、ご逝去後の葬儀に関する手配などを進めていただくことになります。
――悔いのない締めくくりには、何をしておくことが大切なのでしょうか。
依田 ご家族がいる場合はよく話し合うことが一番大切。直接希望を聞いておくことも良いですが、きっとこう言う、こう希望するだろう、と想像できるくらい多岐にわたって何気なく話しておくことだけでも良いと思います。みなさん最期に「ありがとう」の言葉を残してくださいますが、その一言はご家族はもちろん、かかわった人全ての心を満たしてくれます。
“どう最期を迎えるか”よりも“どう生ききるか”
――やはり介護が本格化する前に、家族が話し合っておくことが大事ですね。
依田 十分なコミュニケーションを取り、エンディングノートなどを活用して死後の事務手続きに必要な事をまとめておくと、本当に助かるとみなさんおっしゃいます。
ご家族、ご本人、体調、そしてその最期は千差万別ですので、すべて手配済み(お墓から何回忌かまですべて手配完了)ならご家族も楽です。
ただ、葬儀等の儀式に関しては、少し残しておくのも残ったご家族の絆や話し合い、想像して個人を語る、思いをはせる時間・機会になる場合もあります。
――そうですね。私も母を送った時に、葬儀の作業の忙しさに、気持ちが救われた部分もありました。
依田 自然死、老衰を看取って感じたことは、余計な薬は飲まない方が良いということ。普段から医療に頼らない生活を送っていると良い最期を迎えられると感じています。
大切なのは、どう最期を迎えるかというよりどう生ききるか、そして自然体でいて、自分の力で生き抜くことかと思います。

――人生の終焉を考えることで、今をいかにして自分らしく、よりよく生きることができるのか。そのために必要なのが、ケアする側とされる側のコミュニケーションであることがよく分かりました。終活の基本に相通ずる部分もたくさんありました。ありがとうございました。