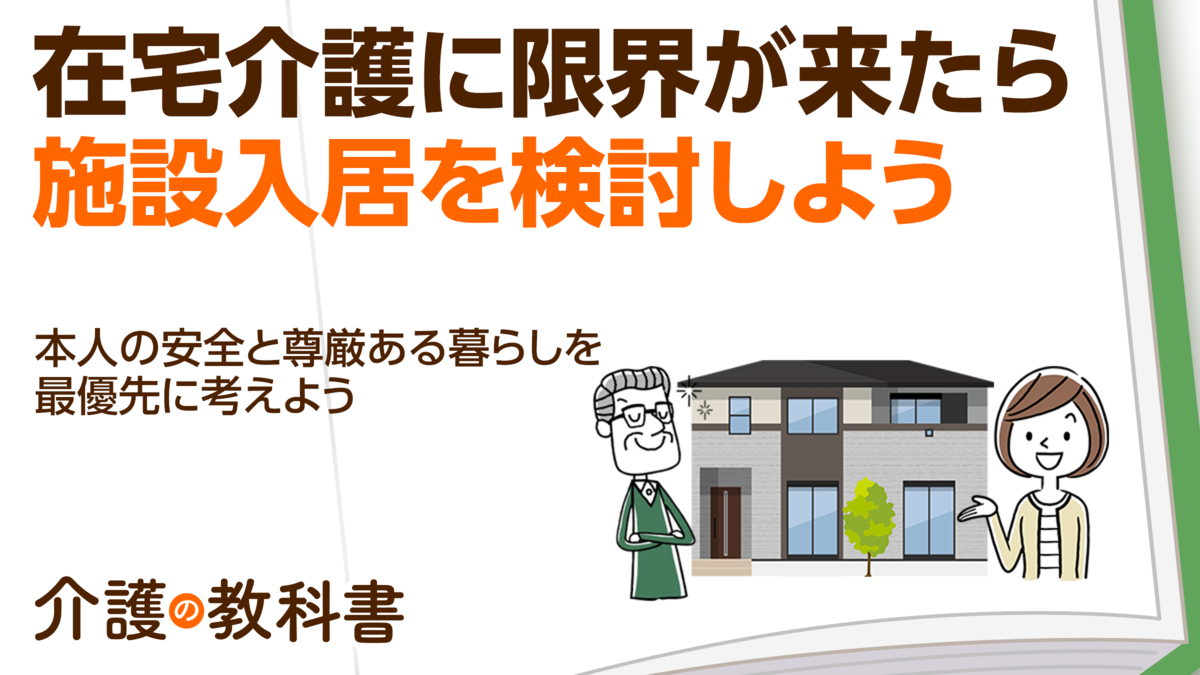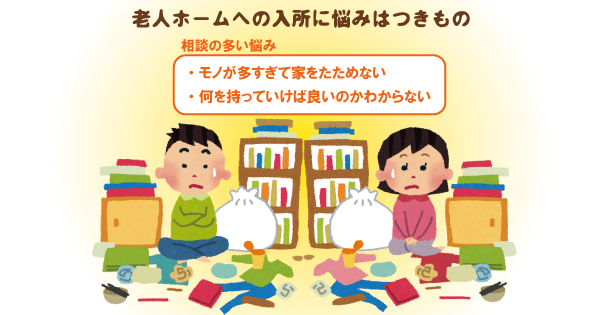私が勤める地域包括支援センターは「高齢者が住み慣れた街で安心して生活し続ける」ためにさまざまな活動をしています。
しかし、状況によっては在宅生活を継続することで、生活上のリスクが生じることがあります。そうしたケースでは、在宅生活にこだわらず、本人にとって最も安心で安全な生活様式をご提案する必要があります。
地域包括支援センターでも施設入居をすすめるケース
一人暮らしの高齢者が認知症になった場合、初期であればデイサービスやヘルパー派遣などを組み合わせて在宅生活を継続できるようマネジメントしていきます。
しかし、認知症状が進むと、どうしても自宅で入浴をしなくなったり、掃除や調理が困難となることが多いです。また、認知症ではないにしても、寝たきり状態なった場合も同様のマネジメントをすることがあります。
一方で在宅での支援にも限界があります。例えば、以下のようなケースです。
- 徘徊が顕著になる
- 排泄が自力では行えなくなりトイレではない場所や屋外で排泄してしまう
- ヘルパー派遣を一日に3~4回利用したいが、地域にヘルパーが少なく複数事業所を利用してもサービスを受けることが困難
高齢者だけの世帯に行われた実際の支援事例
一人暮らしで認知症のAさんは、ガス調理器に湯たんぽを直接火にかけ爆発させてしまったことがありました。Aさんに対して、ヘルパー派遣を午前午後の2回利用し、掃除や調理の支援、またガスの元栓の管理をすることで数年間在宅での生活を維持することができました。
その後、Aさんは排泄が適切に行えなくなり、部屋のあちこちで排便をしてしまうようになったことをきっかけに在宅生活を終了し、グループホームへの入所をご提案しました。
また、Bさんの場合は1日2回午前午後にヘルパーを派遣して、食事や着替え、掃除などの支援を受けていました。週2回のデイサービス利用で入浴やレクリエーションなどの支援を受け、2年間ほど在宅生活を続けました。
しかし、ある晩ヘルパーが帰宅して、家族による安否確認の電話の後に徘徊してしまい、屋外で転倒。地域住民に保護されたことを契機にグループホームへと入居されました。
高齢者の命の安全や人権・生活環境(実内や屋外で排泄してしまうなど)が守れないと判断したときには躊躇なく別の対応を検討する必要があります。
体重が80キロ以上ある夫・Cさんの介護を、小柄な妻・Dさんが行っていたケースでは、当初デイサービスや福祉用具の活用で在宅生活を維持していました。
しかし、Cさんの転倒が顕著となり、Dさんだけでは対応しきれなくなったことを契機に生活様式を変更しました。施設入居を決断するまでの間、転倒した夫を起き上がらせることができないDさんから連絡を受け、夜間に自宅まで支援に向かうなどの対応をしてきました。
ただ、Dさんの介護負担の増大は明らかでした。そこで、夫の特別養護老人ホームへの入居を親族と担当ケアマネで進めることになりました。
本入所に先立ち、特別養護老人ホームでのショートステイ利用中のことです。当初はDさんの負担を考えて施設入所を納得していたCさんから不満が出始めました。
それと同時にDさんからも「夫が施設に入所してしまったことで気持ちが落ち込んでしまい毎日涙が出る」との訴えも聞かれるようになりました。Dさんは夫の介護から解放されましたが、夫と離れることで、うつのような状態になってしまったのです。
そこでDさんのケアマネが夫の入所している施設に掛け合い、週1回1泊2日、Dさんもショートステイを利用して夫婦で過ごせる時間を設けることになりました。最終的に、このケースでは夫婦一緒に生活することを強く望まれたため、再度親族や各々のケアマネージャーと検討を重ねました。
その結果、夫婦でサービス付き高齢者住宅に入居することが決まり、ご夫婦での新しい形の生活が始まりました。

就労世代と同居しているときの支援事例
施設入居で忘れてはならないのが、就労世代と同居しているケースです。少子高齢化が進む我が国において介護離職は避けなければならない重要な事態です。
夫のEさんが施設入所をした後、一人残されたFさんが認知症を発症し、別居する子どものGさんが介護休暇を取って介護にあたっていました。
介護休暇が終わりに近づくにつれ、認知症状が進行する母親のことを心配されたGさんが地域包括支援センターに相談に見えました。
そこで私たちは認知症状を持ち、なおかつ在宅生活へ強い希望のあるFさんが心配なく生活し、介護者も不安なく就労できるよう地域ケア個別会議を開催しました。
その結果、小規模多機能型居宅介護を利用することが決まり、介護者も就労に戻れることになりました。
初期の認知症対象者で在宅での生活への意思が強い方には小規模多機能型居宅介護がおすすめです。このサービスは通い、訪問、泊りが一体となっており、必要に応じてサービスを使い分けることができるからです。
介護者の仕事の都合やご本人の状況に応じて泊りのサービスを利用したり、デイサービス的に日中過ごす場所を確保したり、場合によっては自宅に介護員が支援に向かうこともできるのです。
そして、サービスを利用する中で症状が進行した際には特別養護老人ホームなどへの入所にシフトしていきます。
安心安全と尊厳ある暮らしが最優先
年末年始、ゴールデンウィークなど遠方に住むご家族が帰省した際に、認知症の進行や身体機能の低下を心配され、地域包括支援センターへの相談件数が増加します。
遠方に住むご家族の心配や同居別居を問わず、介護に負担を抱えている家族であっても施設入居となると躊躇することが良よくあります。
そういった場合、高齢者の日常生活動作が比較的維持されていれば、ケアハウスという選択もあります。ケアハウスへの入居者の中には、自分で運転して外出される方もいて、比較的自由度が高い施設です。また、ケアハウスでは日常的な安否確認や食事の手配などをしっかりと行ってくれますので、遠方に住むご家族も安心できるでしょう。
高齢者の施設入居のタイミングは十人十色ですが、高齢者自身の尊厳と安心安全の確保を考えることが最優先だと思います。
無理をして在宅生活を続けると、結果として大きな事故、徘徊、火事など命にかかわる事態につながりかねません。

また、ご家族の過大な介護負担や不安を取り除き、平穏な日常を送る権利も保証するべきでしょう。
想像してみてください。
認知症によって家族の介護負担や家族の辛い心情を理解できなくなっている高齢者が、もし一時でも理解力が回復し、自分の介護のために苦しんだり、やりたいことができなくなっている家族を見たときにどう思うのか。きっとつらい思いをされると思います。
介護を必要とする方、介護をする方それぞれにさまざまな事情がありますが、すべての人が安らかに生きていけるよう、介護サービスや地域包括支援センターを活用してください。