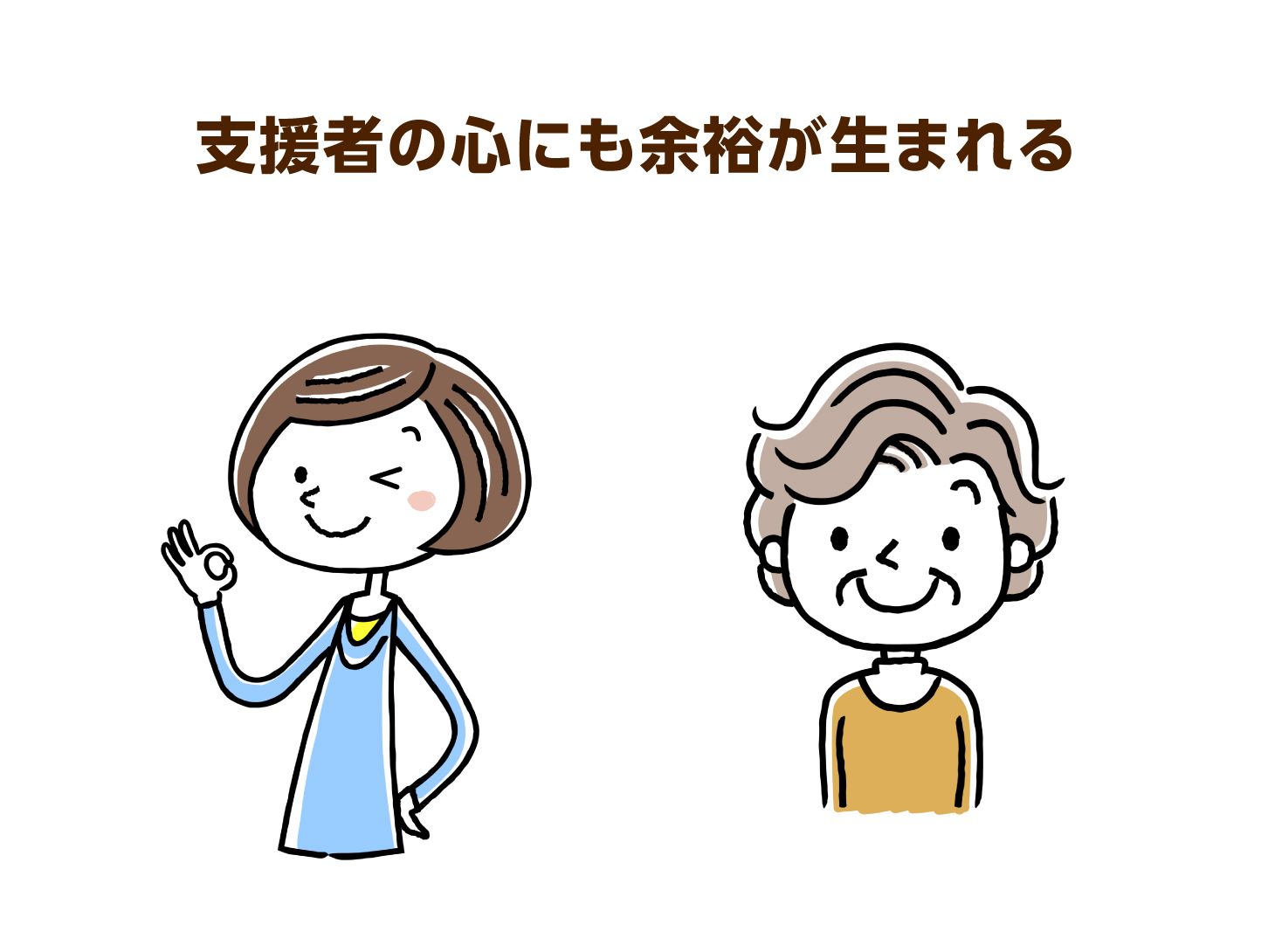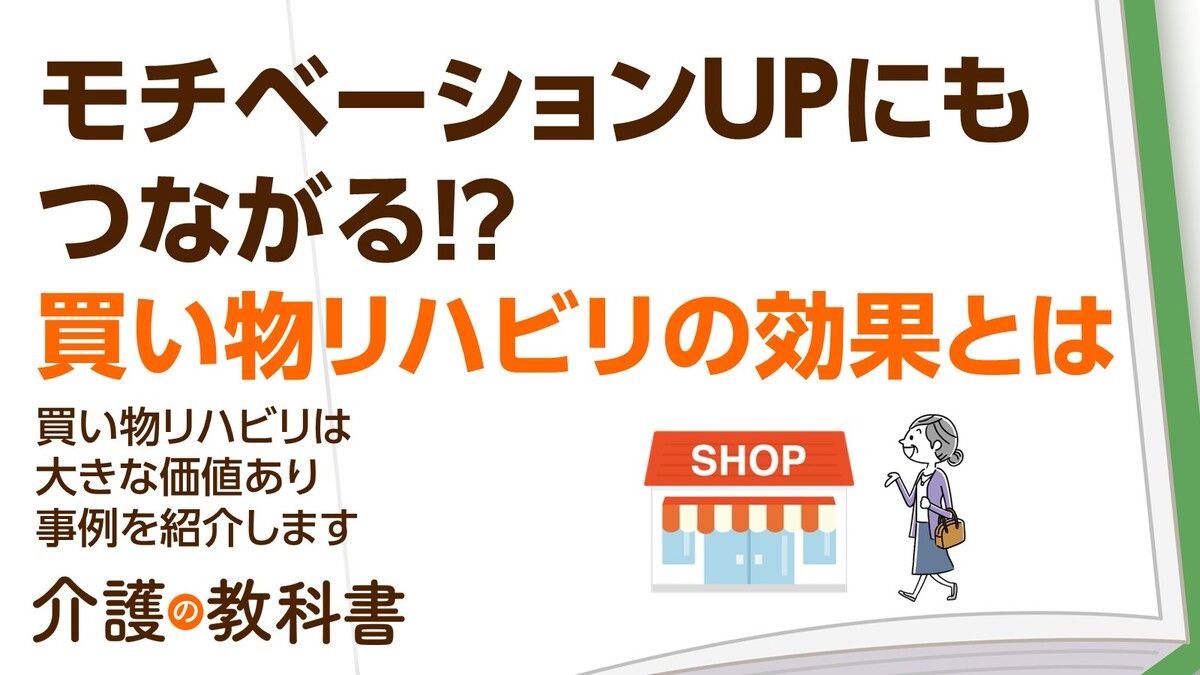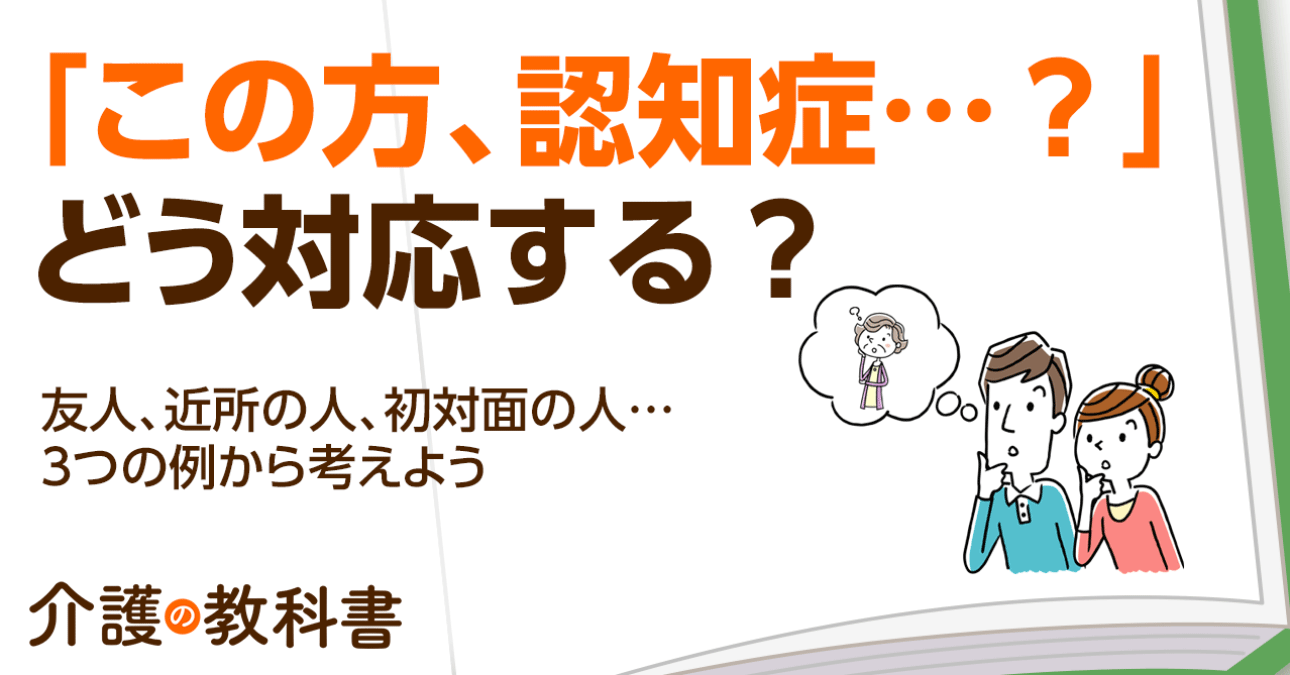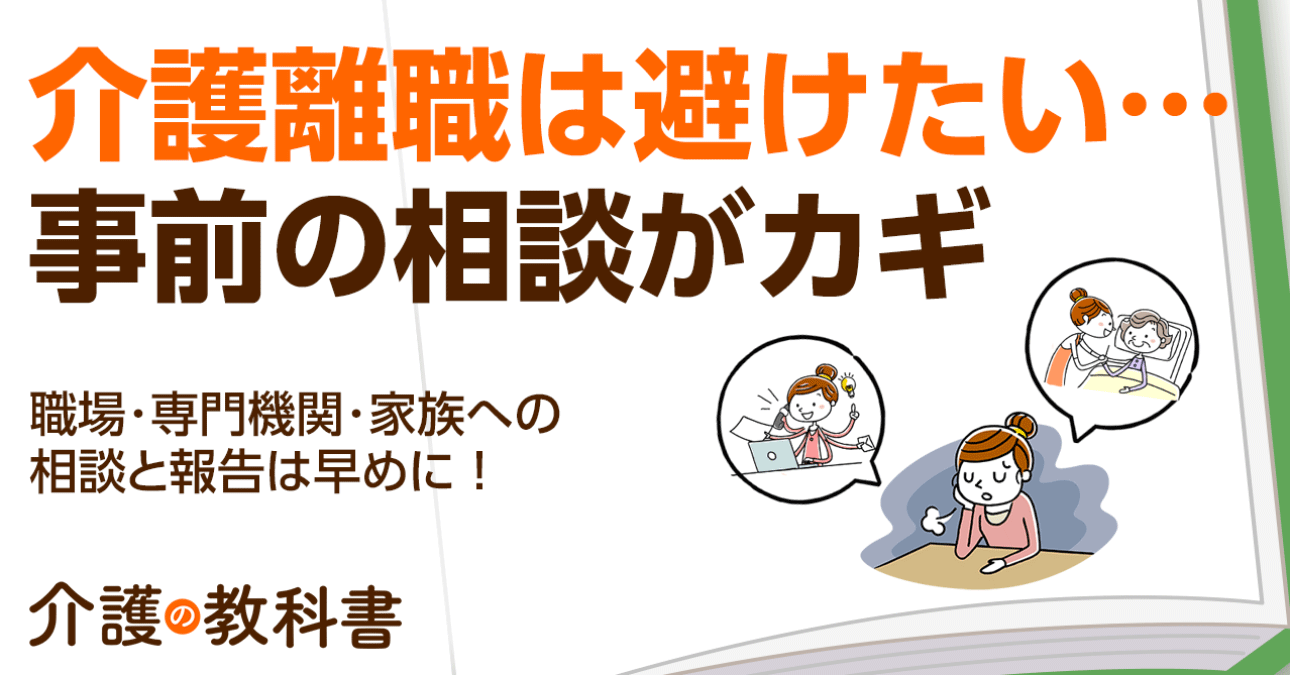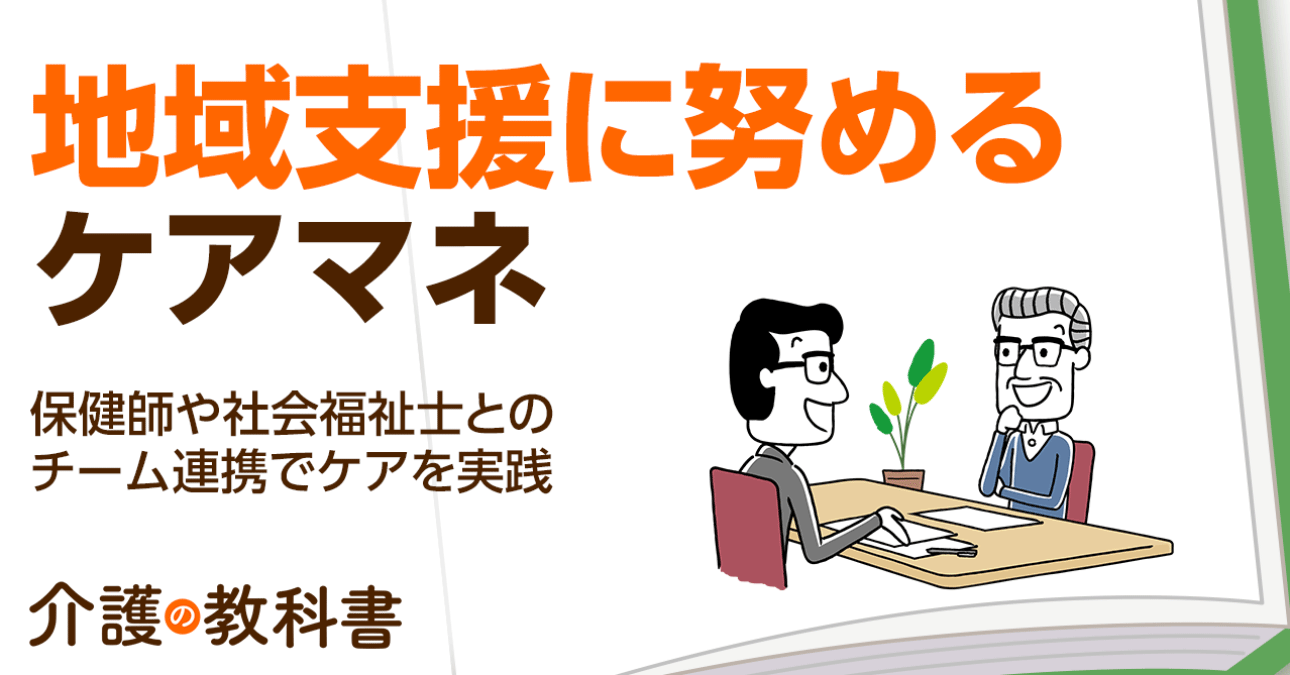介護保険では、通院や行政機関、銀行などの利用時に移動支援を受けることが認められています。しかし、買い物はヘルパーに買ってきてもらうか、ヘルパーと歩いて小売店に行くことは許されています。
私たちの地域包括支援センターでは、高齢者が自ら商店に行き、店内を自分の足で歩き、自分の目で商品を選ぶといった一連の動作が、地域での生活を継続するうえで大きなメリットがあると感じ、「買い物リハビリ」と呼んでいます。
今回は、実際の事例を基にその効果を検証していきたいと思います。
買い物リハビリを介護保険制度に!
これまで緊急対応的に買い物ができず、食べるものがなくなってしまった高齢者を小売店にお連れしてきました。
そして、屋内でも伝い歩きであったり月に1回程度しか外出しない高齢者が、カートを使用しながら1時間以上店内を歩きまわって、必要な商品を買い揃える光景を目にしてきました。
高齢者は口々に「買い物に連れて来てもらえれば店内は自分で歩ける。帰りに荷物を車まで運び、自宅についた際に家まで持ってきてもらえれば自分で買い物ができる」と話します。
こういった光景をみると、自ら店舗に赴いて品物を選ぶという何でもないような活動が、認知症の予防や歩行機能の維持に効果があると痛感します。
買い物という動作が生活におけるリハビリにつながり、生きていくうえで必要な品物を得るという観点からもモチベーションを維持できます。現行の介護保険では要介護2以上の対象者については、介護ベッドや車椅子がレンタルできます。
一方、要支援1、2の対象者は、ヘルパーやデイサービスの利用回数が週単位で制限されるなど抑制的な傾向で、介護度1以上の対象者とはサービスの利用回数に大きな隔たりがあるのが現実です。
すなわち介護度が上がることで、利用できるサービスや回数が多くなり権利が生じるという構造です。
介護保険の構造を踏まえたうえで買い物リハビリを考えてみましょう。例えば、要支援1~要介護1までの対象者の場合、移動や荷物運びの支援があれば買い物ができるという要件を付けてみてはどうでしょうか。
そうすれば、現在要介護2以上の対象者も治療やリハビリによって、介護度が軽くなれば買い物に自分で行けるというモチベーション向上や意識づけができます。結果的に治療やリハビリへの意欲も向上するのではないかと思います。
また、買い物リハビリサービスを利用するために介護保険を申請することにもつながり、早期の段階で対象者を把握できます。高齢者が介護度を下げることで介護保険の支出も減少するでしょう。
高齢者にとっても介護保険制度にとっても非常に有意義です。ぜひ介護保険制度の中に買い物リハビリを盛り込んでほしいと思います。
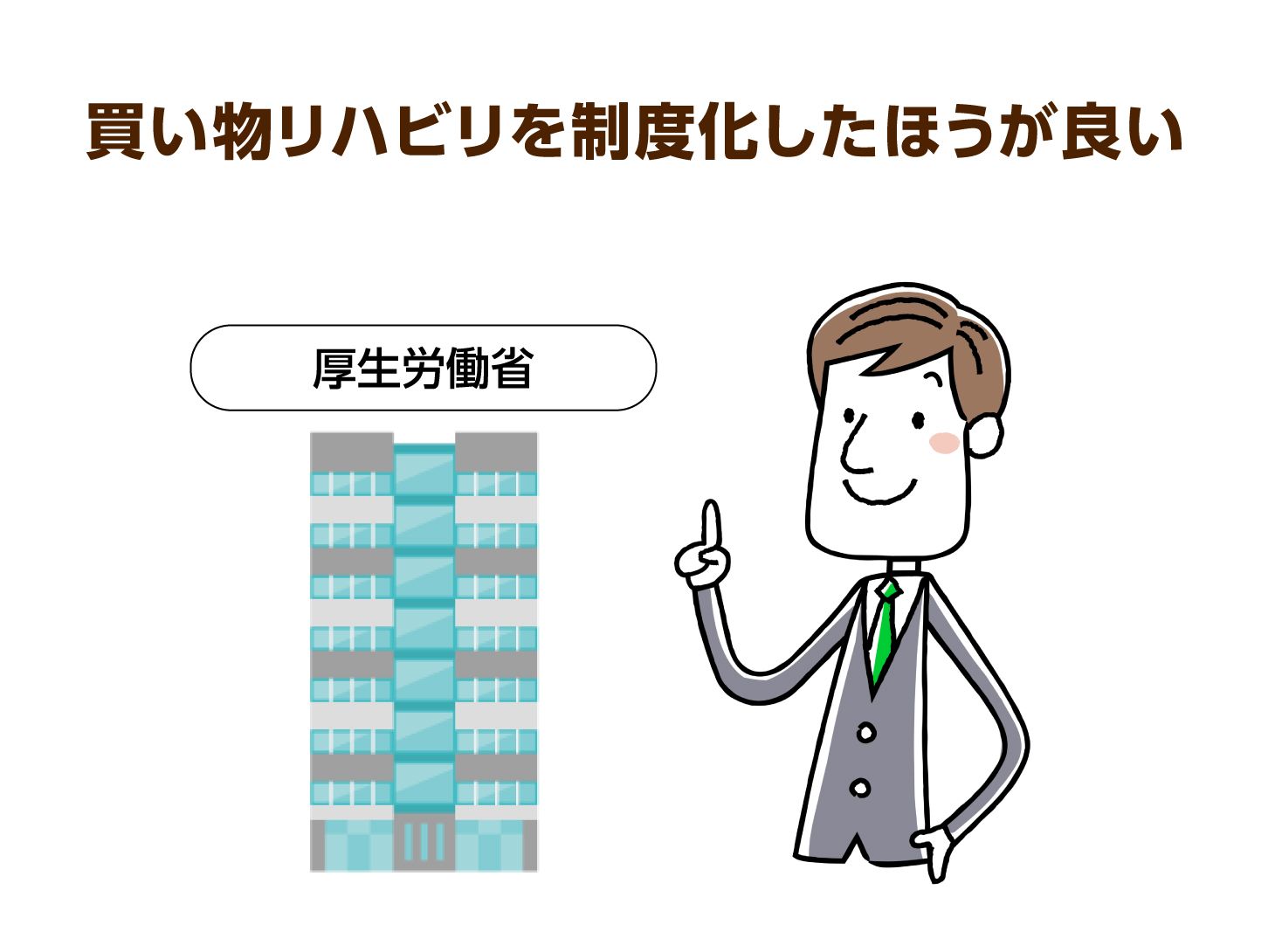
地域で孤立したAさんのケース
ここで90歳近い一人暮らし高齢者・Aさんの事例を紹介します。
Aさんは近隣住民に対して「物を盗られる」「家の中に入ってくる」「電波を飛ばしている」などとの思いから、警察に通報することもよくありました。
そのため、近隣住民との関係性はほぼ断絶している状況です。近隣住民や知人、福祉事業所の支援による買い物や草刈りは、ことごとく人間関係でトラブルとなり、支援の継続が困難となっています。
おそらくパーソナリティー障がいや妄想性障がい、統合失調症から起因する言動によって協力者がいなくなっていましたが、かろうじて地域包括支援センターとはつながりを保てていました。
そこで、私たちはAさんの心理的特性と年齢を考慮し、これまでの経緯から当面地域包括支援センターで徹底して買い物や通院の支援をしていくことにしました。
現在週1回、買い物の支援を行っていますが、1~3回目の支援は1回の買い物で1時間半ほどカートを使用しながら歩き、1万5,000円程度の買い物をしました。
しかし、約1週間に1度の買い物が安定的にできると理解されたのか、4回目の買い物では8,000円程度になり50分ほどで済むようになりました。
普段はほとんど屋外に出ることはない高齢者が買い物に行くとなると1時間以上歩きます。4回目の約50分の買い物では500mほど連続して歩けていました。1~3回目の買い物ではそれ以上歩行していたことになります。
Aさんは、近隣住民や福祉事業所との人間関係がうまく築けないことが課題でしたが、買い物中は客や店員さんに親し気に話しかけたりといった一面も垣間見ることができました。
支援者にも心理的な余裕が生まれる
店内を歩き回り、自分の目で品物を選ぶ高齢者はとても活き活きしています。
そして普段はほとんど歩かない高齢者が連続して1時間以上も歩けてしまう。こういった運動は心身ともに大きな効果があると思います。
セロトニンやオキシトシン、ドーパミン、βエンドルフィンなど、いわゆる「幸せホルモン」は、日光に当ったり運動をすることで分泌されます。
人間は買い物をして何かを手に入れたり、美味しい物を食べると、脳の「報酬系」が活性化されて、達成感や満足感が得られ「幸せホルモン」のひとつであるドーパミンが分泌されるのです。
自分の目で見て欲しいものを手に入れる。その過程で、普段はほとんど歩かない高齢者が買い物カートを押して一生懸命に店内を歩く。こういった何気ない運動が高齢者の運動機能や認知機能の低下防止に効果を発揮しているのではないでしょうか。
楽しそうに、嬉しそうに買い物をする高齢者のそばで値段や賞味期限をお伝えしたり、さまざまな品物について支援者・援助者双方の思い出や想いについて会話をする。そんな会話をしていると支援者も幸せな気持ちになります。
これまでAさんとのかかわりの中では「包括は何もできない!」などと罵倒されたり、一日に何度も電話をしてきたりと言った行動に辟易することもありました。
しかし、こうして買い物の支援をしていく中で、意外な一面を垣間見たり、楽し気な様子を見るにつけ「いろんな人とトラブルを起こして周りに誰もいなくなってしまったけど、こうして今一緒に買い物をする私は何か縁深いのかもしれないなぁ」などと思います。
そんなとき、この買い物支援がとても大切な時間に感じられたりするのです。