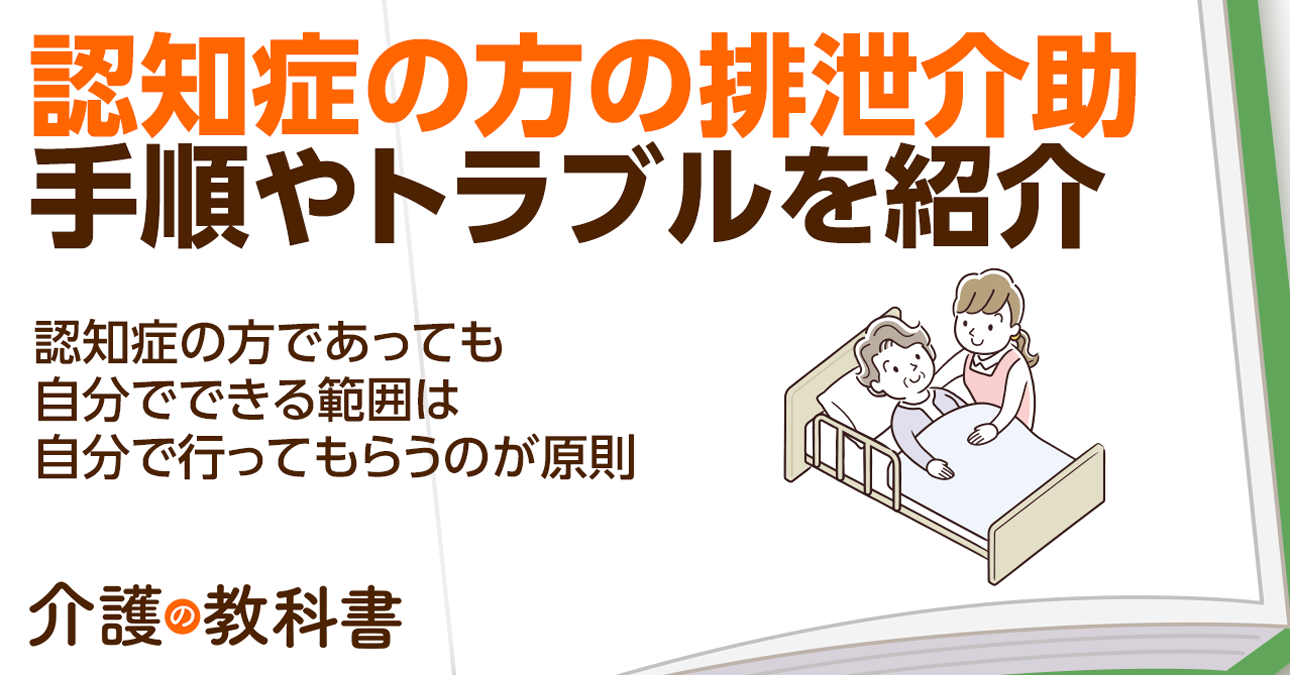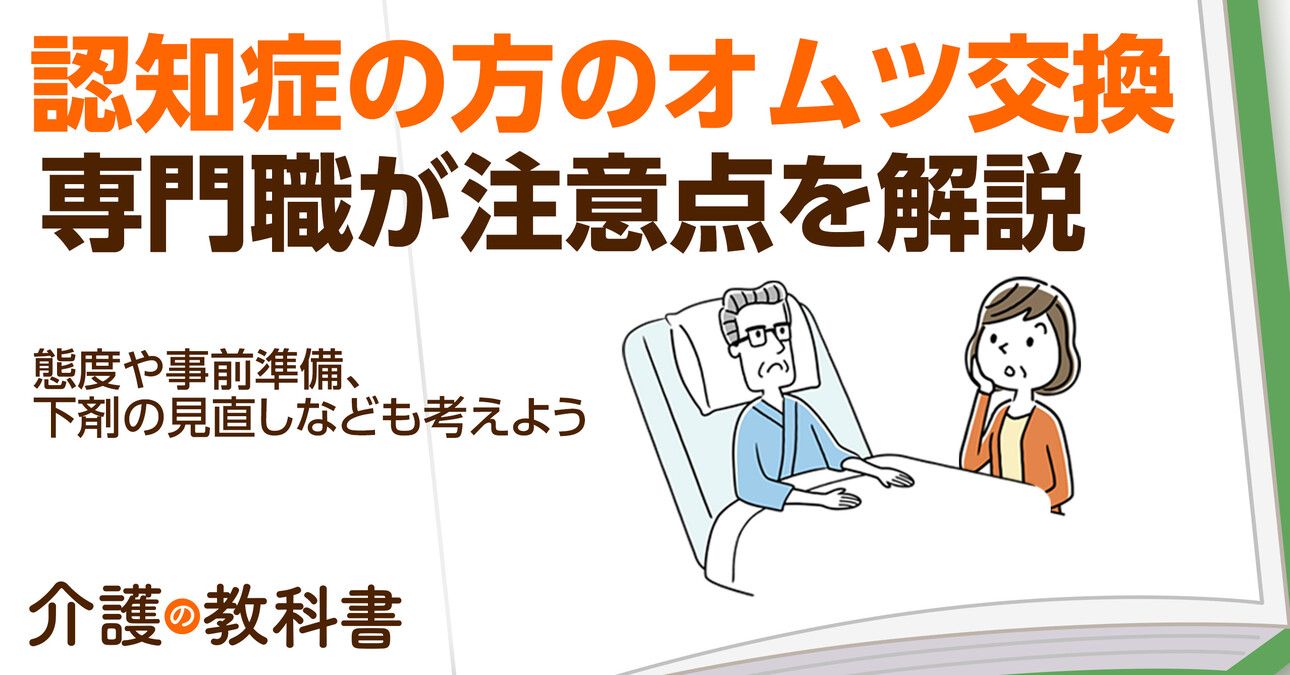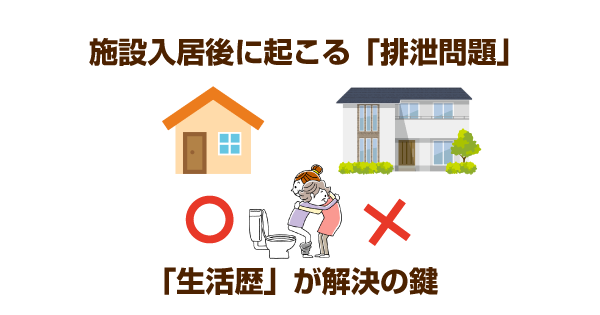在宅介護での排泄に関わるケアは、本人も家族にとっても、さまざまな面での苦労が多くあります。
本人は、排泄の失敗が尊厳を損なうことになり、介護者もサポートが難しいものです。今回は排泄コントロールについて考えていきます。
大手メーカーによるトイレセンサー実証実験
最近は、大学などの研究機関や様々な住宅機器メーカーが、排便管理機能を備えたトイレの開発にしのぎを削っています。現場での実証実験も既に始まっているそうです。
排便管理のデジタル化が実現すれば、入居者に対する健康ケアのレベル向上はもちろん、介護職員の負担軽減にも繋がると期待されています。
現在開発中のAI技術を使えば、次のようなことを自動で判定・記録・管理できるといいます。
- 排便のタイミング
- 便の形
- 便の大きさ
現在、高齢者施設では排便記録を手書きで行っていますが、記録をつけるだけでも難しい利用者もいます。これを自動化することで排便状況を正確に把握することができるのです。
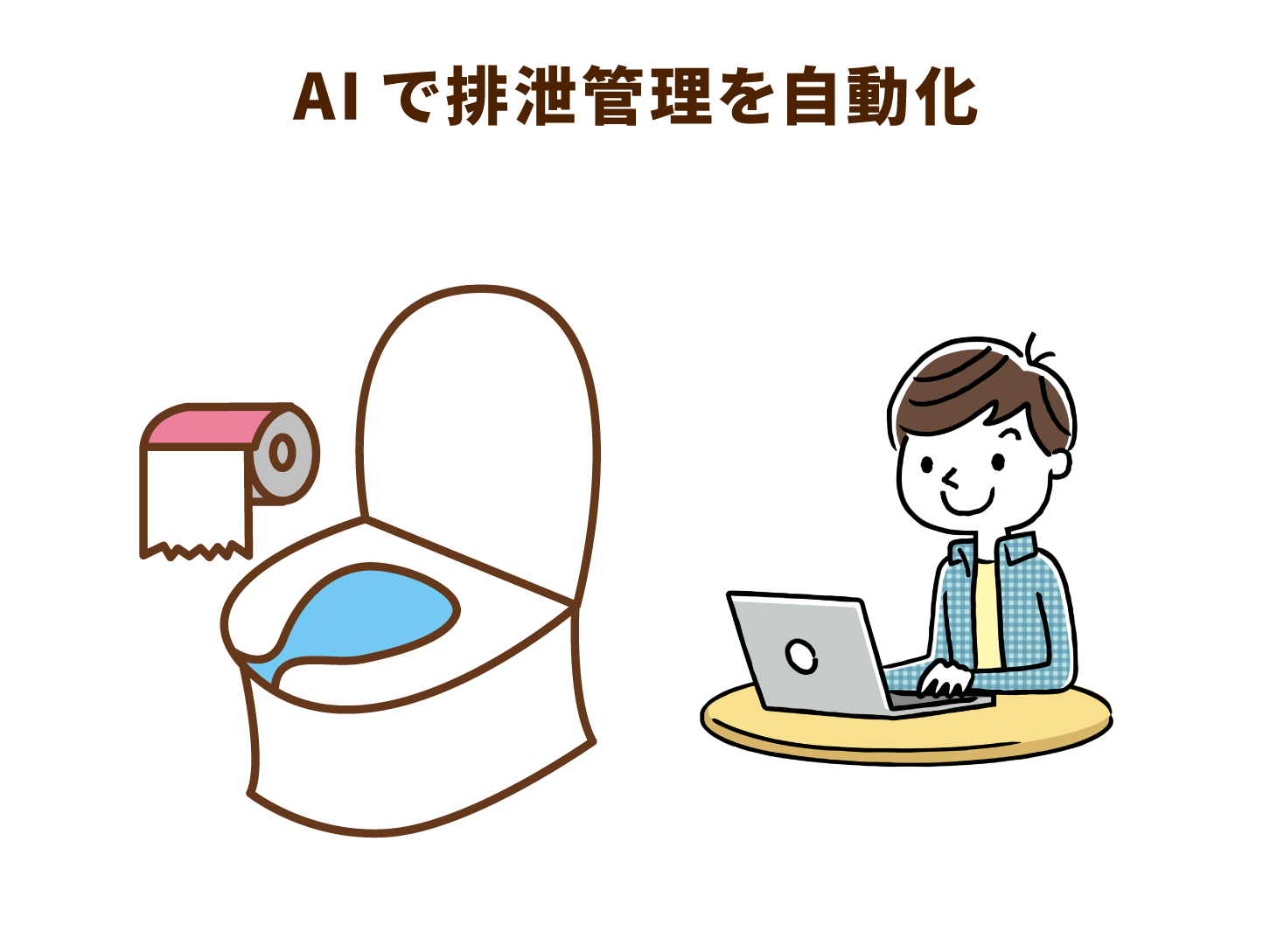
在宅介護でもチェックしたい便
そもそも便の状態を管理するにはブリストルスケールという基準があります。これは、イギリスのブリストル大学で開発されたもので、「便」の状態を色や形に基づいて分類しています。
この基準を使用すると、客観的に便の形状を評価できるため、介護する家族が医療介護の専門家との話を円滑に進めることができます。
その分類は以下の通りです。
| タイプ | 便の形状 |
|---|---|
| 1 | 硬くてコロコロした木の実のような便 |
| 2 | いくつかの塊が集まって形作られたソーセージ状の便 |
| 3 | 表面にヒビ割れがあるソーセージ状(バナナ状)の便 |
| 4 | 滑らかで軟らかなソーセージ状(バナナ状)の便 |
| 5 | 軟らかな半固形状の便 |
| 6 | 境界がはっきりしない不定形の便 |
| 7 | 水様便 |
ブリストルスケールでは、数字が小さいほど便が含む水分が少なく硬くなり、数字が大きいほど水っぽくなります。
ブリストルスケールのタイプ3から5までが正常な範囲の便とされ、タイプ4にあたる適度な軟らかさを持ち、ソーセージ状やとぐろを巻いた形の便が理想とされています。
しかし、在宅で介護するにあたり、チェックしておきたい点はほかにもあります。
- 排泄のタイミング
- 便の形や大きさ
- 食事や水分
- 運動の頻度や強度
- 投薬状況
- 生活環境など
このように、便にまつわる多様なチェックが必要になります。高齢者施設の職員でも大変な排便管理を、在宅介護でもれなく行うのは非常に困難です。
そして真面目なご家族であればあるほど、すべてをきっちりと行わないといけないと感じてさらに疲弊してしまうことがあります。
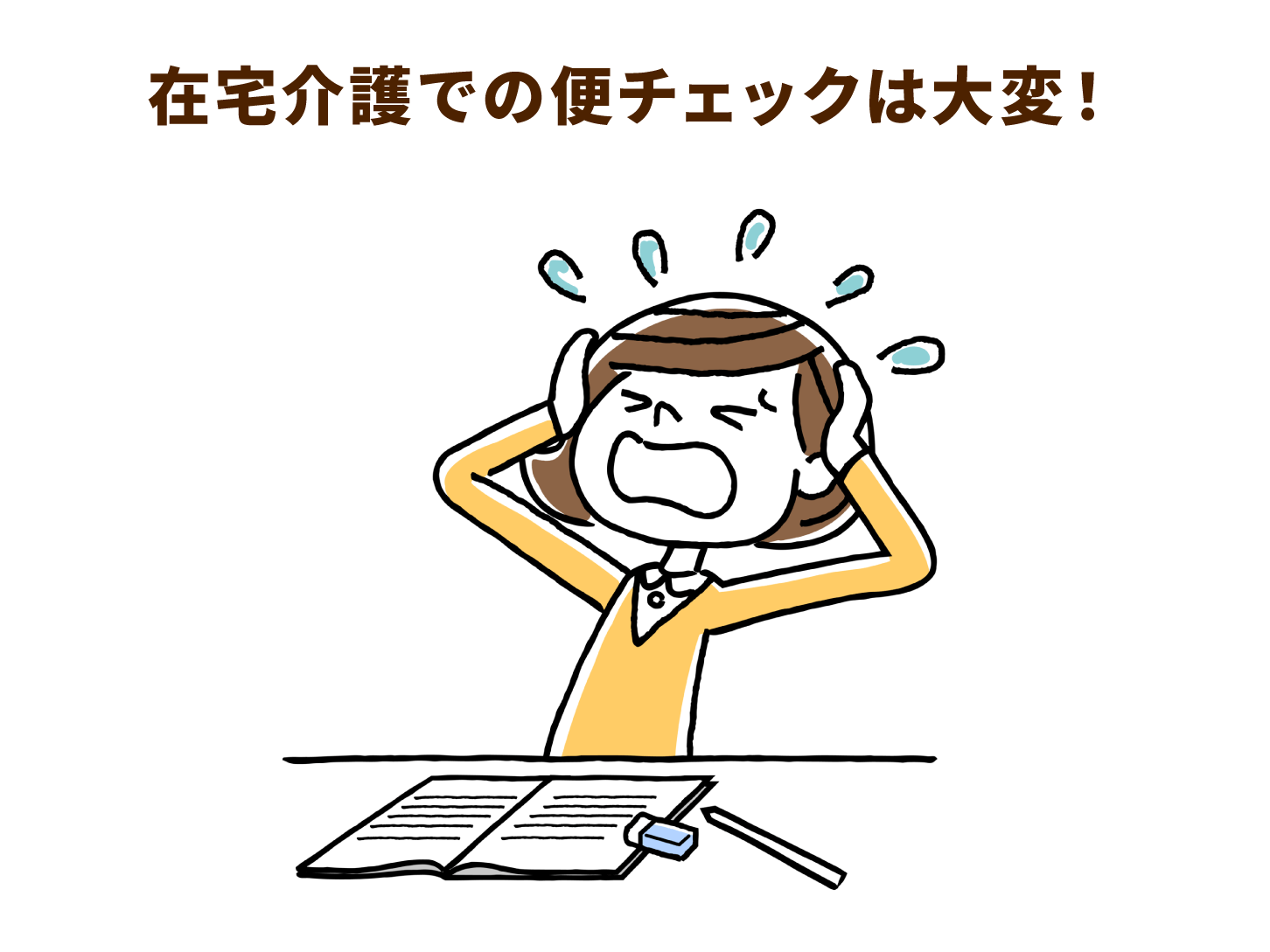
困ったときは相談しよう!
便ひとつとっても、これだけ多くの情報を集めないといけないのかと不安に思ってしまう家族も多いでしょう。
少しでも困難や苦労を感じたときは、医療機関、ケアマネージャー、訪問看護師などの専門家への相談も大切です。介護している家族が疲弊しすぎてしまうのは、要介護者にとっても本意ではないはずです。
AI等を活用した排便管理のデジタル化が進めば、将来的には、自宅のトイレでも高度な排便管理が可能になるはずです。そうすれば、きっと、在宅介護が楽になるのではないかと思います。
時代はどんどん便利に変化しているので導入できるところからしていきたいですよね。
生活の中で排便の時間はそんなに長くありませんが、これがうまくできるかできないかは、その人の尊厳にも関わる非常に大きい問題です。
排泄がうまくコントロールできないことで外出範囲が狭まり、場合によっては精神的な不安を抱えてしまうこともあります。その悩みや問題が、介護する家族の負担になることもあるでしょう。
本人が気持ちよく排泄し、家族はなるべく楽にサポートできる環境をつくるため、排泄管理に関しては家族が負担なく無理なくできる部分だけ行い、そのほかの部分は専門家を頼ったり、新しい機器を利用してみましょう。