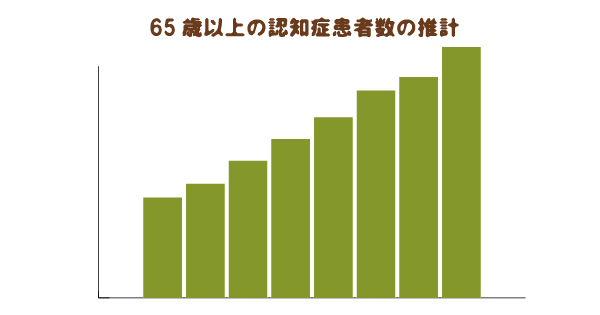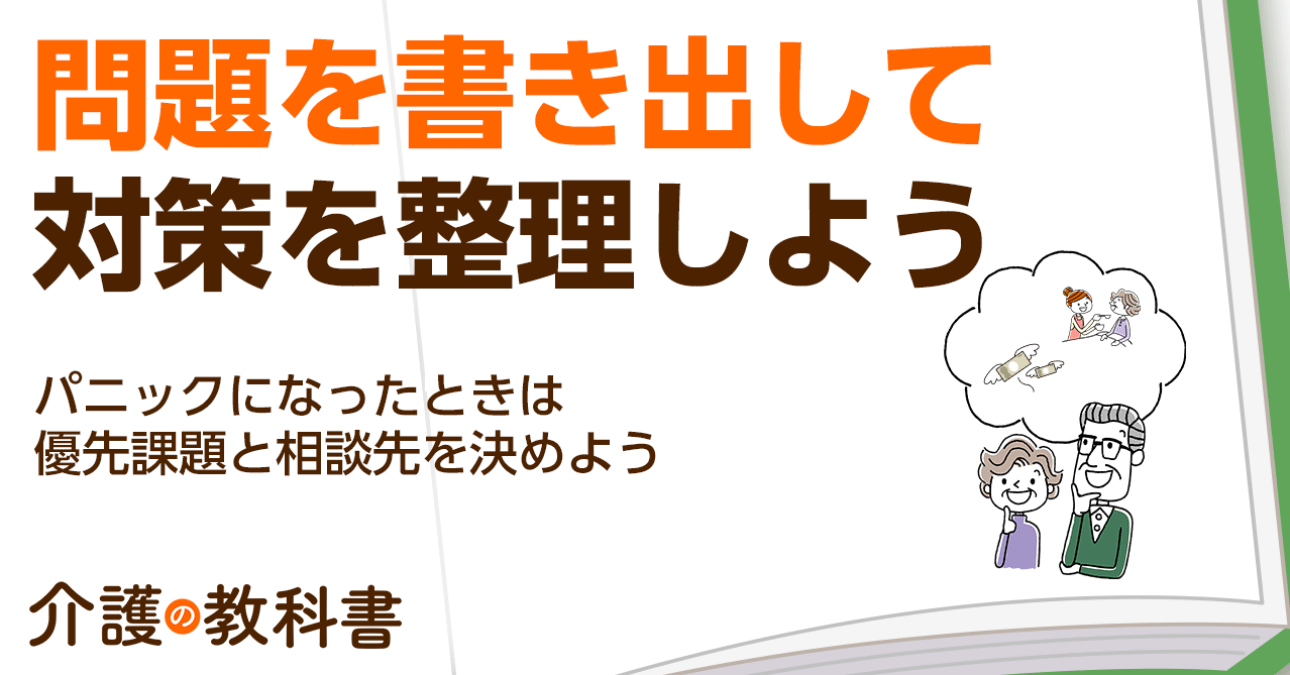高齢者の中には、ごく少数ではありますが、残念ながら地域住民とトラブルを起こしてしまう方もいらっしゃいます。時に、支援者や福祉事業所を「どうしたらよいかわからない」と困惑させてしまうようなケースもあります。
共通しているのは被害妄想が強く、周囲からの支援を自ら断ち切ってしまう点です。
もしかしたら、皆さんの身の回りにもいらっしゃるかもしれません。
私が勤める地域包括支援センターにもそうした事例があります。今回はその方への支援を通して、どのようにかかわっていくべきかを考えます。
対応に苦慮する高齢者の事例
「食べるものがない!買い物に連れて行って!今日でないとダメ!」
私が勤める地域包括支援センターには、朝イチで90歳近い一人暮らしのAさんからの電話がかかってきます。
Aさんは近隣住民とのトラブルが絶えず、これまでいくつもの事業所や住民と引き合わせてきましたが、すぐに喧嘩をしてしまいました。
連日電話をかけ「買いものに連れて行け!病院に連れて行け!」と高圧的な態度で迫るため、心優しく真摯な方ほど気に病んでしまい関係性を断ち切るといったことを繰り返しています。
また買い物が思うようにできなかったり、体調が悪い状況になると、警察署にも連絡をしてしまうなどの行動も年に複数回も生じています。
5年間、同じことの繰り返しで、私たちとしても、もうご紹介するサービスが尽きてしまいました。当然「地域ケア個別会議」も開催し警察署、区長、民生委員、行政、福祉事業所と情報の共有もしましたが、それが課題解決に直結することは困難でした。
専門医につなげることや主治医と連携して心身状況の把握にも努めましたが、いずれもご本人の拒否にあい実現できませんでした。
ただ、このような方は経験的に何らかの障がいを抱えているのではないかと推測できます。私は次の4つのどれかに当てはまるのではないかと考えています。
- 統合失調症
- パーソナリティー障がい
- 妄想性障がい
- 初期の認知症
この方は、5年間のかかわりの中で、ある特定の条件によって態度が変わることがわかりました。
- 亡くなった母親のことを話題にすると表情が柔和になる
- 犬や猫が好きで動物の話をすると態度が変わる
- 近隣住民からは孤立しているが野良猫に餌をやりかわいがるなどの行動がみられる
幸い地域支援活動の電話連絡が週3回あるため、電話や電気料金の未払いなどの情報は、担当者が連絡してくれるのでライフラインに関するリスクに対しては何とか対応できています。
しかし、銀行にまったくお金を預けていなかったにもかかわらず「銀行に盗られた」などの被害妄想が生じるため、地域包括支援センターでは日々対応に苦慮していました。

支援者側のかかわり方を見直す
しかし、転機は訪れました。我々支援者側のかかわり方を見直すことから始めたのです。近隣住民や知人、福祉事業所の支援はことごとく人間関係でトラブルとなっていました。
支援の継続が困難となり近隣住民に対しては「物を盗られる」「家の中に入ってくる」「電波を飛ばしている」などとの思いから警察に通報することも1度や2度ではありません。
しかし、よく考えてみると、かろうじで地域包括支援センターには「食べるものがない」「薬がない」などと発信することができていました。
そこでご本人の心理的特性と年齢的な部分を考慮、またこれまでの経緯から、当面地域包括支援センターで徹底して買い物や通院の支援をしていく方針を決めました。
その決定後、すでに4回買い物支援を行い通院支援も1度実施。主治医ともお話をすることができました。
その受診後に「泥棒が入るから神経科にかかって相談したい」とご本人の口から要望が出ました。看護師さんとも相談し、次回受診時に主治医にその旨を伝え、紹介状を書いていただくことになりました。
これまでもメンタル的な部分に関して専門医につなげるアクションは取ってきましたが、ことごとく本人の拒否にあい頓挫してきました。
しかし、今回はご自身の口から専門医への受診について要望が出たので、精神的な安楽に繋げられるよう大切に支援していきたいと思っています。
お互いの心が通じ合い始めた買い物支援
Aさんに日常的に行っているのが買い物支援です。1~3回目の支援は、1回の買い物で1時間半ほどカートを使用しながら歩き、1万5,000円程度の買い物をしていました。
しかし、おおむね1週間に1度の買い物が安定的にできると理解されたのか、4回目からの買い物では8,000円ほどの買い物を約50分で済ませるようになりました。
普段ほとんど屋外に出ることはない高齢者が買い物に行くとなると1時間以上歩きます。4回目の買い物では約500mを連続して歩行することができていました。
また、近隣住民や事業所との人間関係が上手く築けないことが一つの課題ではありましたが、買い物中にはほかの客や店員さんと親しげ気に話をする場面もありました。
高齢者が自ら歩き、品物を選び、買い物をする「買い物リハビリ」にはさまざまな効果があることを実感していますが、副産物として支援者の心理変化も強く実感しています。
店内を歩き回り、自分の目で確認しながら品物を選ぶ高齢者はとても生き生きとしています。
また、楽しそうに買い物をする高齢者のそばで値段や賞味期限を伝えたり、品物について支援者・援助者双方の思い出や想いについて会話をするといった何気ない行動が、支援者にとってもうれしく感じます。

Aさんとのかかわりの中では「包括は何もできない!」などと罵倒されたり、一日に何度も電話をしてきたりといった行動に辟易とすることもありました。
しかし、こうして買い物の支援をしていく中で、意外な一面を垣間見たり、楽し気な様子を見ていることは、私自身とても大切な時間に感じられたりするのです。
私たちが今取っている対応が100点満点だとは考えていません。同様の事情を持った対象者が100人いたらとても対応しきれないのも現実です。
しかし、私たちはAさんのような方の支援を今後の活動に活かしていけるよう全力で対応していきたいと考えています。
ご家族の対応でお困りごとがありましたら、お気軽に近くの地域包括支援センターへご相談ください。