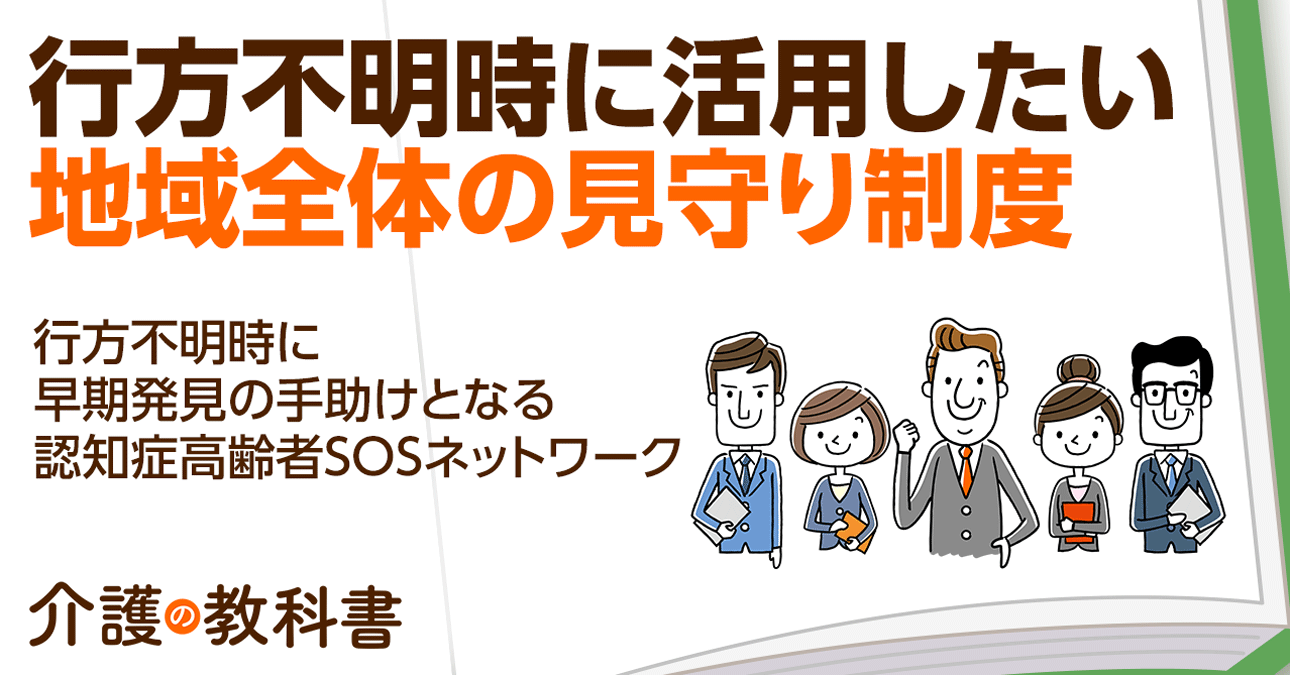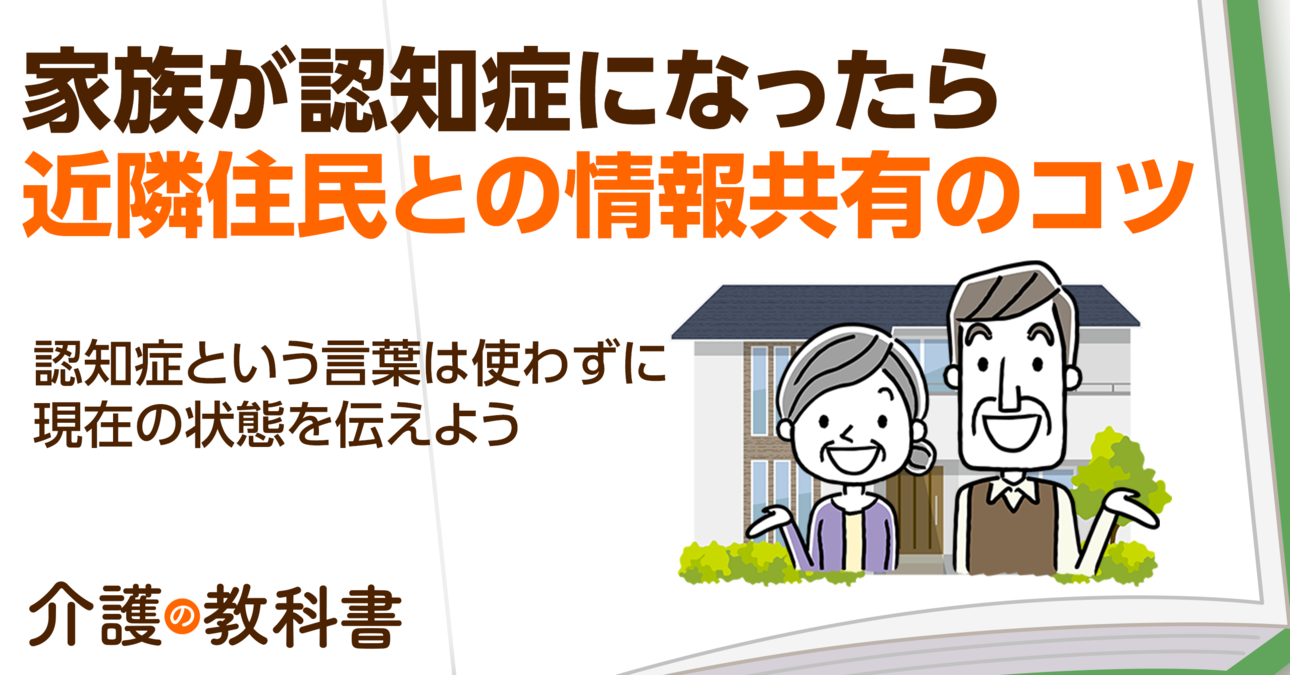千葉県の地域包括支援センターで社会福祉士として勤務する藤野です。
私が担当する地域は、高齢化率が47%に達していることに加え、担当する総面積が市内の70%近くと広大です。そんな地域に市内人口の25%程度しか居住していません。
つまり、広大なエリアにほんの少しの住民しかいないわけで、人の目も大幅に低下します。日中の出勤のため若い世代がいなくなれば、さらに手薄になります。
そんな中、2022年3月初旬、2件の認知症徘徊が発生しました。
今回は、この事例から地域包括支援センターを始めとした地域の各団体がどのように対応するのかを紹介します。
地域包括支援センターで行われる捜索の手順
1件目は、90代の女性が早朝に自宅を出てから見当たらなくなってしまったといったケースでした。
この女性は認知症状が見られていましたが、デイサービスを利用しており、これまで徘徊したことはありませんでした。
その日はちょうどデイサービスが休日で、ご家族が出勤する直前に姿が見えなくなってしまったというのです。
ご家族は、最寄りの警察署と担当ケアマネに連絡しました。すぐに防災無線で行方不明になったという放送が発信され、市で行っている安心安全メールも送信されました。
その後、私が勤める地域包括支援センターに担当ケアマネから連絡が入りました。
そこで私たちは、まず以下のような情報を把握することから始めました。
- 行方不明になった女性の自宅
- いなくなった時間から想定して、どの程度の距離を移動したか
- 自宅から人通りのある道までのルート、周辺の危険個所
- 周辺の知人や親族の有無
- 公共交通機関の使用の可能性
その結果、次のような3つの仮説を立てることができました。
- 所在がわからなくなってからの時間と移動速度を勘案すると、自宅から5km以内にいる可能性が高い
- 人通りのあるエリアまでたどり着いていれば、すでに発見されているはず
- 公共交通であるバスは本数が極端に少なく、利用している可能性は低い。金銭を保持している様子はなく、バスに乗った場合は降車の段階で把握されるはず
ここまで絞れると、捜索する範囲はかなり絞られます。そこで私たちは「自宅近辺の人通りのないルート」「自宅周辺の危険個所」「導き出した行動範囲から予測されたエリア」の集中捜索を行うことになりました。
結果的には、防災無線を聞いた地域住民がいち早く警察署に通報したことで無事早期に保護されました。
防災無線は早い段階で使用することが重要
この90代女性のケースで早期の保護がなされた要因として、防災無線の存在が挙げられます。
注意点としては、防災無線の使用には、ご家族が同意してから依頼する必要があるということです。しかし、担当ケアマネがついていたことで、早期に無線を使用することができました。
私たちの地域包括支援センターでは、徘徊などの事例が発生した際、防災無線の使用をケアマネや民生委員などに推奨しています。
それと同時に、「見守りウォーキング・わんわんパトロール」と称して、地域での見守りの目を強化する活動を行い、未然に防ぐような啓発も行っています。

防災無線は早ければ早いほど効果を発揮します。
例えば、夏季や冬季は、発見が遅くなった結果、熱中症や凍死など生命にかかわる事態を生じかねません。夜間や危険箇所の捜索では、捜索者の二次災害が起こるリスクもあります。
また、公共交通機関を使用した場合、防災無線や行政メールで情報が届かない範囲に移動してしまう可能性もあり、そうなると防災無線の効果が薄れてしまいます。
そのため、行方不明がわかったらすぐに防災無線を使用することをおすすめします。もし担当ケアマネがいない場合は、近くの警察署や地域包括支援センターに相談しましょう。
行方不明時に大切な地域のつながり
次のケースは、福祉サービスを利用している認知症高齢者が行方不明になったケースです。
15時頃、ご家族から担当ケアマネに行方がわからなくなった旨の連絡が入りました。担当ケアマネは、地域包括支援センターに応援要請をするとともに、ご家族の了承を得たうえで所轄警察署に防災無線の要請をしました。
前述のケースと同様に、仮説を立てて担当ケアマネとそのスタッフ、地域包括支援センターのスタッフ総出で地域を捜索しました。
このケースでは、私たちがご高齢者を探している過程で次々と地域住民にも情報が伝わっていきました。
その結果、捜索が1時間、2時間と経過するごとに捜索に協力してくれる地域住民の数がどんどん増えていったのです。
しかし、このケースでは19時を過ぎても発見に至りませんでした。
そこで所轄の警察署により警察犬が導入されました。行方不明となってから計3回、警察犬による捜索が行われましたが発見には至らず、この日の捜索はいったん中断となりました。
警察関係者からの話では、警察犬が臭いを拾えないこともあるそうです。
結局、約2時間後に、本人が自ら帰宅して無事解決しました。
このケースでは、認知症の人が福祉サービスやケアマネとつながっていることが支えになると強く感じられました。
認知症徘徊ケースが発生した際、通報を受けた警察は主に次のようなことに苦慮するといいます。
- 最近撮影した写真がなく、加齢による容貌の変化に戸惑う
- 行方不明になる直前の服装などの把握が曖昧で、防災無線での情報提供や実際の捜索に支障が出る
- 本人を確認する手段がない
しかし、今回のケースでは、デイサービスを利用していて、誕生会で撮影した写真があったため、ご家族の了承を得て捜索メンバーで画像を共有できました。
また、担当ケアマネがついており、対象者の近況や成育歴、認知症の程度、歩行状態などもわかり、捜索に必要な情報を集められました。今回は発見には至りませんでしたが、こうした情報があるだけで捜索がうまくいく可能性が高まります。
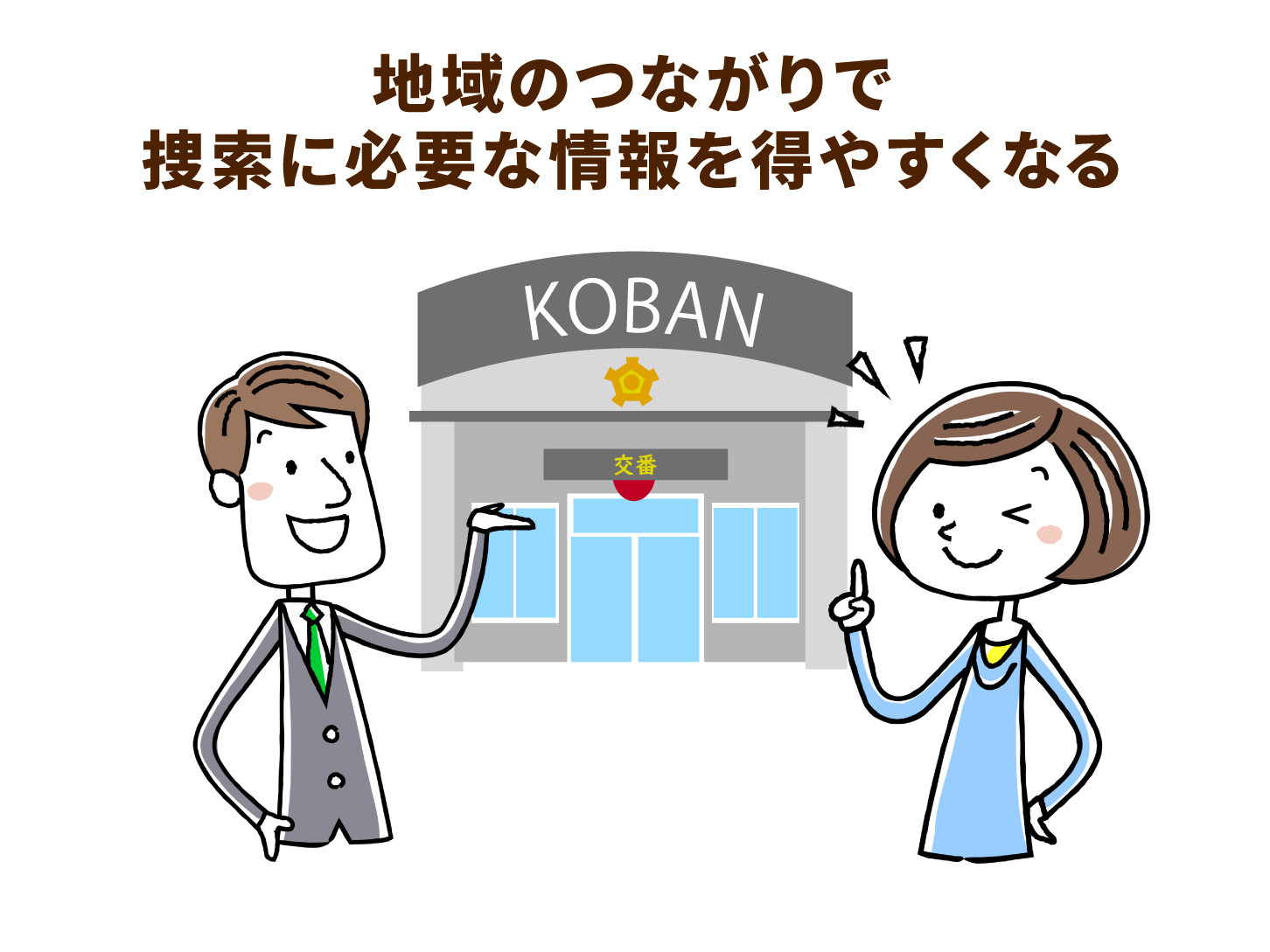
認知症高齢者の徘徊が発生した際、警察はそのエリアの防犯カメラを確認するなどの対応をします。しかし、私たちの担当するエリアのように都市部ではない地域では防犯カメラがあまり存在しません。
こうした事情は全国の過疎地域に当てはまるのではないでしょうか。認知症の高齢者がいる家庭では、緊急時を想定してケアマネや民生委員と日頃から接することが大切です。
また、私たち地域包括支援センターは、地域住民、福祉事業所、警察署など多くの方々の目と手を借りて、高齢者の安全と心豊かな生活を支援しています。何か困ったことがあれば、積極的に地域包括支援センターを活用してください。