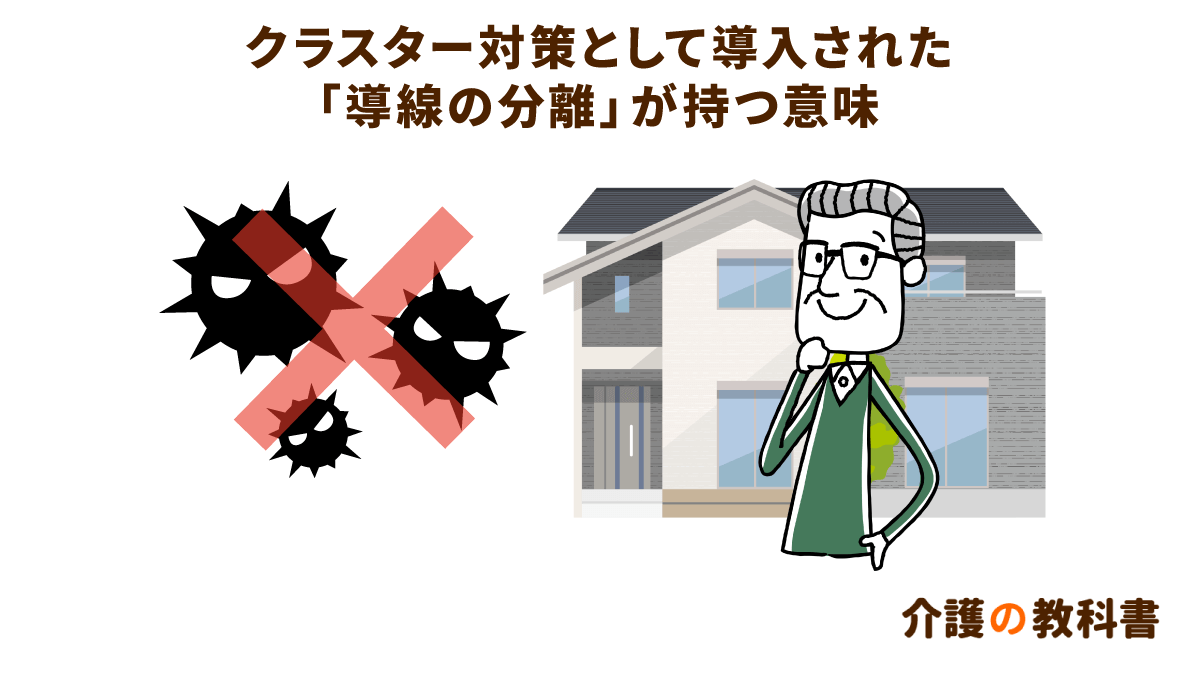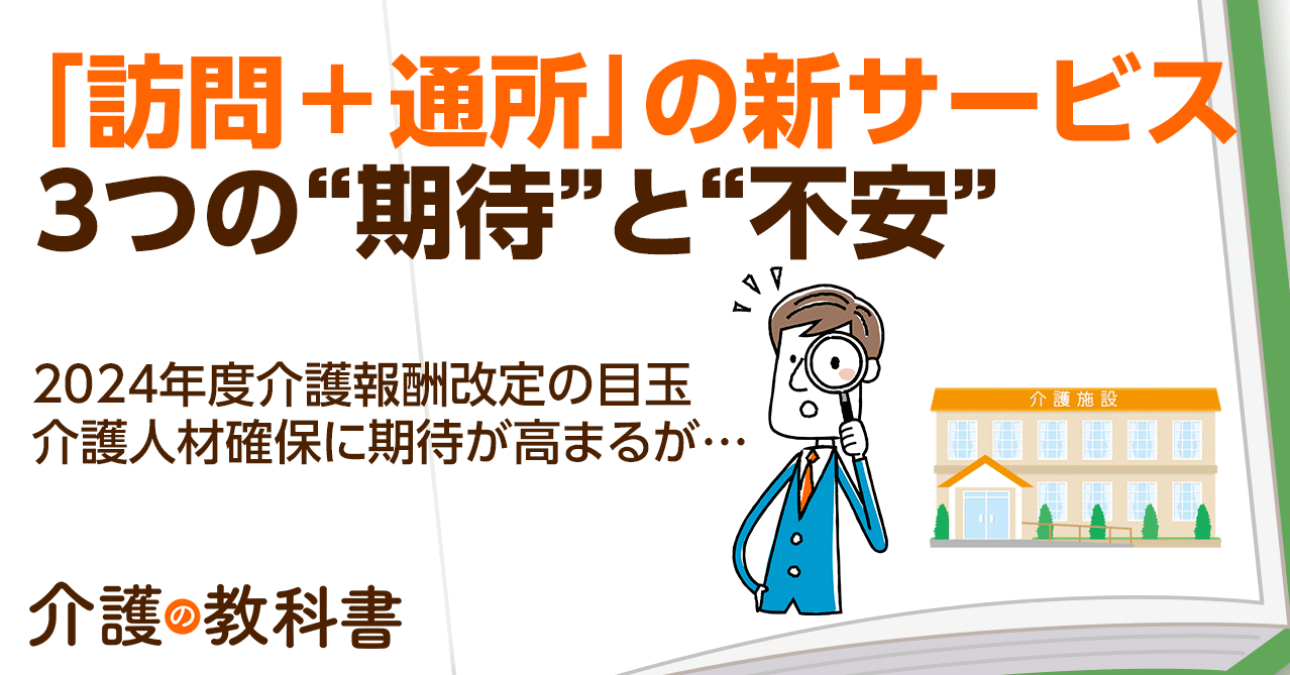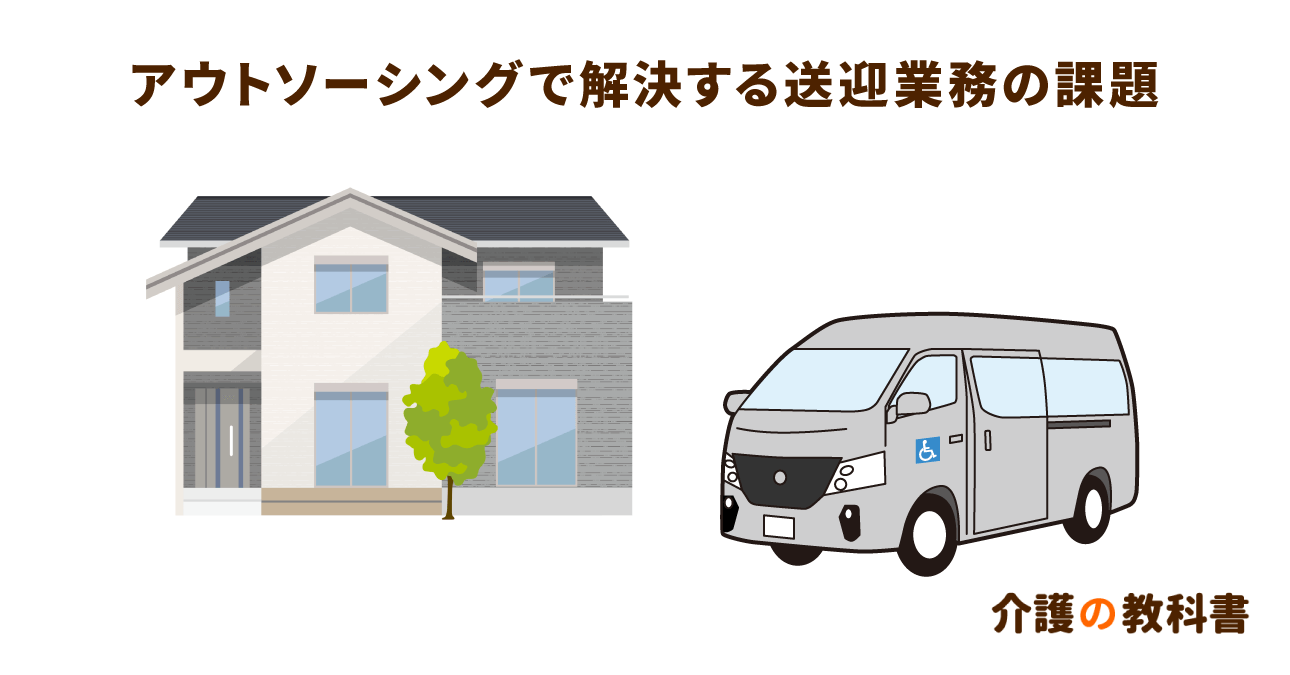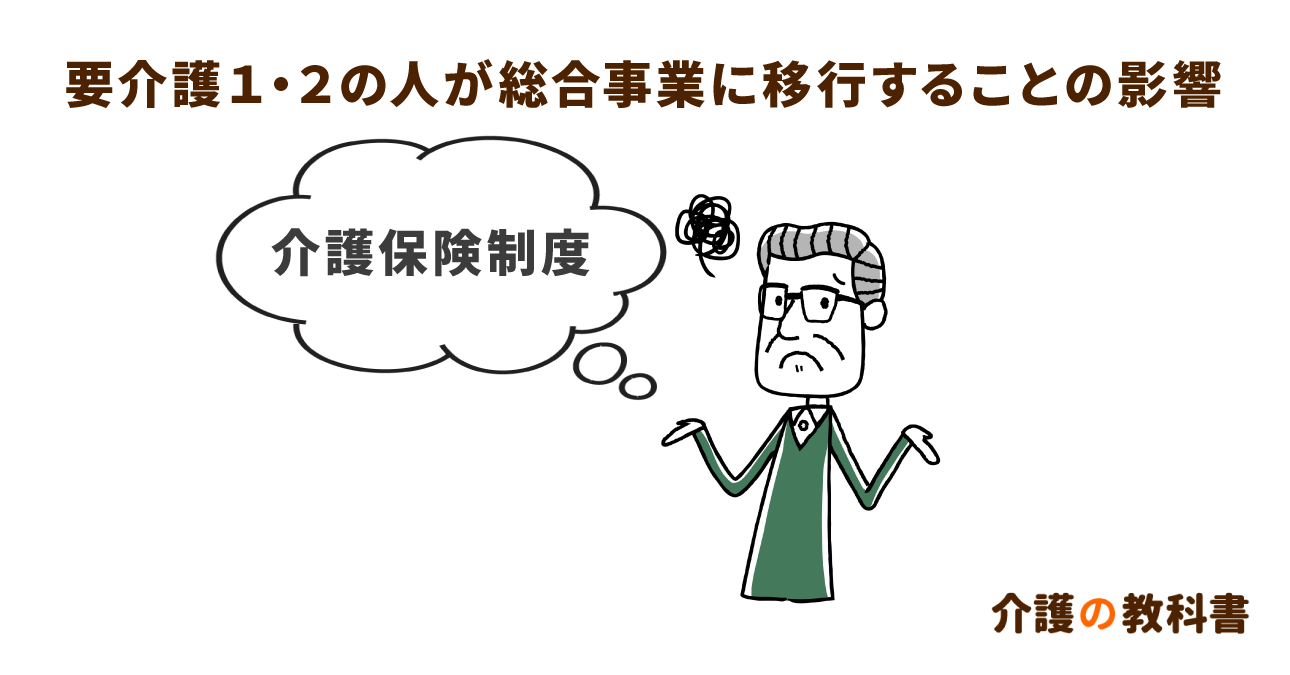オミクロン株を中心とした新型コロナウイルス感染症の第6波ですが、まん延防止等重点措置が全国的に解除されることとなりました。
まん防解除に伴い、厚労省が2022年2月9日に発表した「導線の分離」などの工夫を行った事業所に対する介護報酬の特例も適用期間が終了します。
この特例が発表されたのは第6波が広がってから、かなり時間が経ってからでした。そのため、適用条件を満たすことができた事業所はほとんどなかったものと思います。
コロナ禍以後、引きこもり状態を余儀なくされた高齢者が増えたこともあり、身体機能低下や認知症症状悪化の報告事例が相次いでいます。そういった実情から、通所介護事業所が担う役割が非常に大きいことを認めたうえでの特例措置であったと言えるでしょう。
「まん防」は全国的に解除されましたが、今後第7波、8波が来ることは十分考えられます。そこで、改めて「導線の分離」について考えます。
これまでも実践されてきた空間のゾーニング
第6波では、高齢者施設や事業所において相当数のクラスターが発生しました。ひとたびクラスターが発生すれば、介護事業者はサービスの中止を余儀なくされ、事業者と利用者双方が大きな影響を被ります。
通所介護事業所はその名の通り「通い」であり、常に利用者の出入りがあります。「ウイルスを持ち込まない」という基本の感染症対策が非常に困難な事業形態です。
そこで、大切になるのが「導線の分離」です。コロナ禍以前と比べれば理解は進んでいるとは思いますが、まだまだ聞きなれない方も多いのではないでしょうか。私の場合は「ゾーニング(区域の分離)」という言葉が思い浮かびました。
「清潔部」と「汚染部」のゾーニングや汚染物の処理の手順、汚染域を拡げないための導線の引き方、といったゾーニングがコロナ禍以前から感染症対策の基本的事項としてマニュアルに記載され実践されてきました。

時間的なゾーニングで、クラスターを未然に防ぐ
コロナ禍では対策が不十分だった点が見直され、感染症対策のマニュアルが大幅に更新されました。
その結果、現在では多くの事業所で有効な感染防止対策が講じられていることでしょう。
今回も次のようなことが重ねて呼びかけられました。
- 基本的な三密の回避、手指衛生、空間衛生対策
- レクリエーション時のマスク着用
- 送迎時の窓開けなどの徹底
利用されている高齢者の中にはマスクの着用が困難な方や、換気の徹底やパーティションの必要性などが理解できない方もいらっしゃいます。
厚労省の通知内容が「マスクをすぐ外してしまうケースへの対応」について「着用し続けるよう努めるように」と、現実とは乖離しているケースも珍しくありません。そもそもマスクの着用を嫌がる利用者に対して、強要することは困難です。
咳エチケットの励行などといった初歩的な感染防止策でさえ、利用者全員に徹底することが難しいのです。
そうした経験を踏まえ、今回の特例で示された「導線の分離」は、エリアだけでなく、時間的なゾーニングも示されました。
- 利用者の一部を訪問サービスに切り替える
- 午前と午後に利用時間を分ける
- 一週間の利用である場合、半分程度の曜日に調整する
つまり、物理的にではなく時間帯が重ならないように分離するということです。
もちろん、各事業者が好き勝手に解釈して、今回の「導線の分離」を推し進めることは慎まなければなりません。まん延防止等重点措置等が実施されていることと利用者への十分な説明と理解を得ることなどが条件となります。(介護保険最新情報Vol.1034参照)
とはいえ、空間的・物理的な制限を利用者にお願いし続けることに比べれば実施しやすいうえ、確実にクラスターの発生率を抑えられる措置と言えます。
また、こうした工夫をする事業所に、介護報酬の特例適用が発表されたことは今後の感染症対策において新たな前例がつくられたことになります。

新型コロナウイルス感染症対策のマニュアルは、これまでも何度も繰り返し更新されてきました。しかし、感染状況が落ち着いてきた今だからこそ、もう一度特例措置を踏まえた内容に更新することが大切です。
さらに、まん延防止等重点措置が再発出された場合に、特例措置について自事業所ではどのような形態でサービス提供を継続していくのか、利用者やその家族にはどのように周知し理解を求めるのか、そしてマニュアルの更新だけでなく、その内容を予め従事者に周知しておく必要があるでしょう。