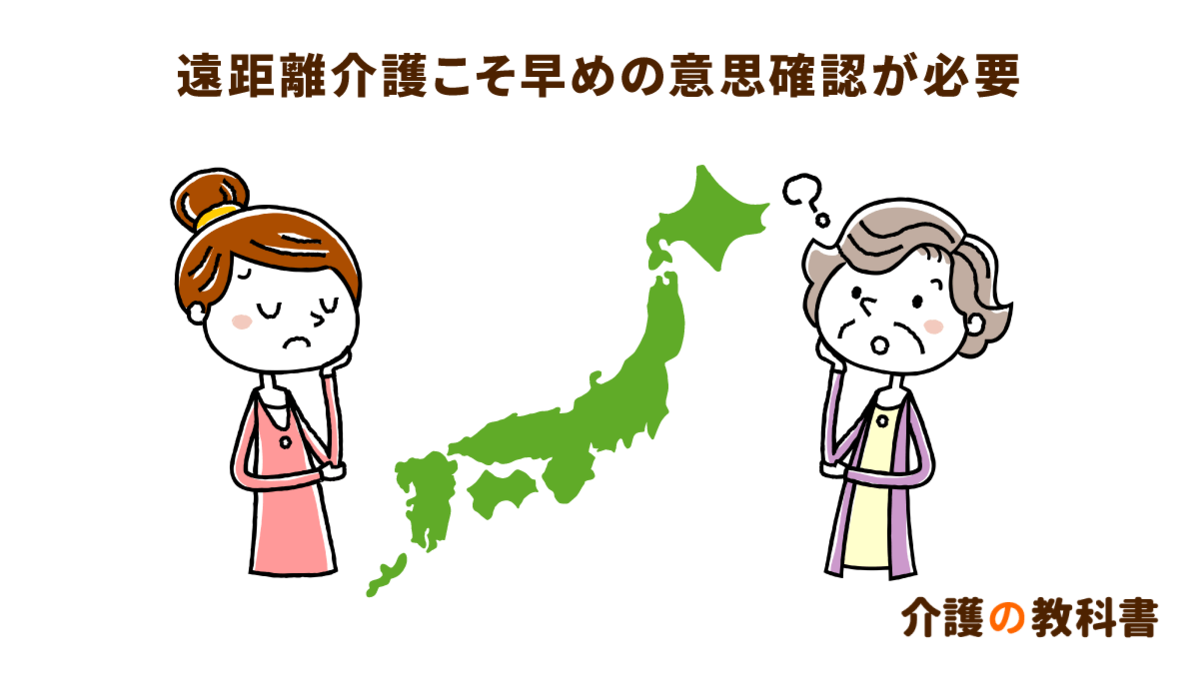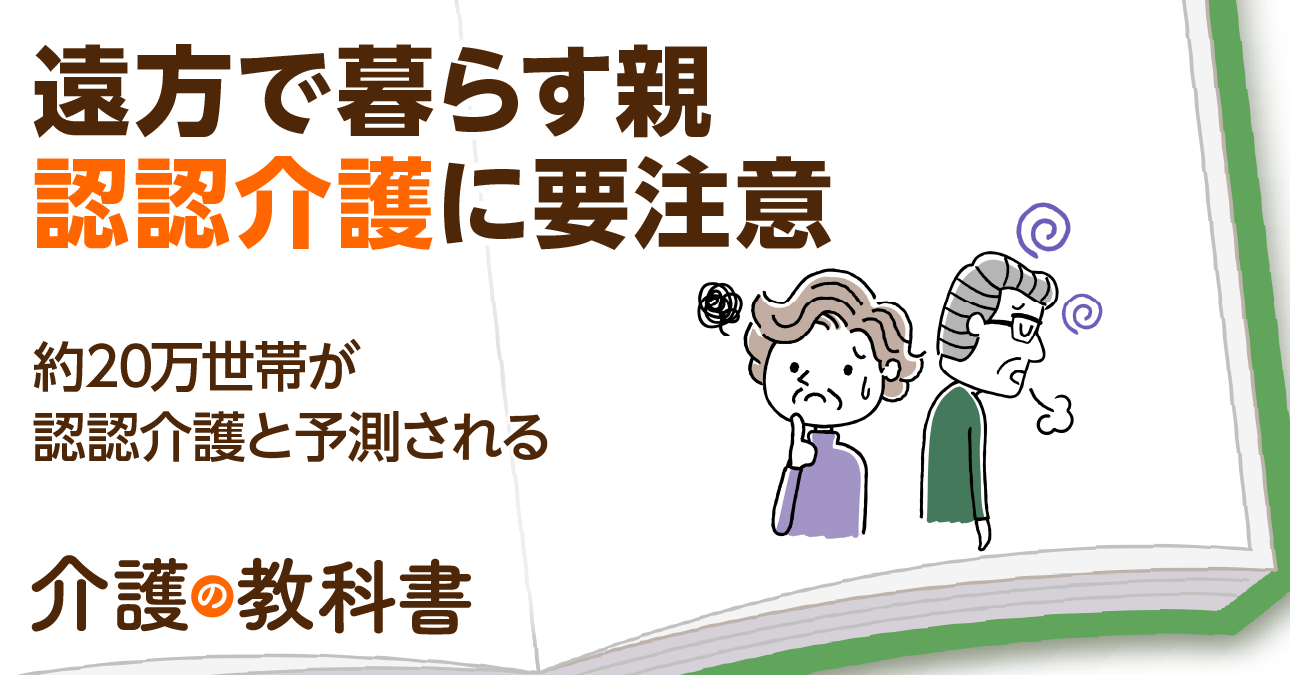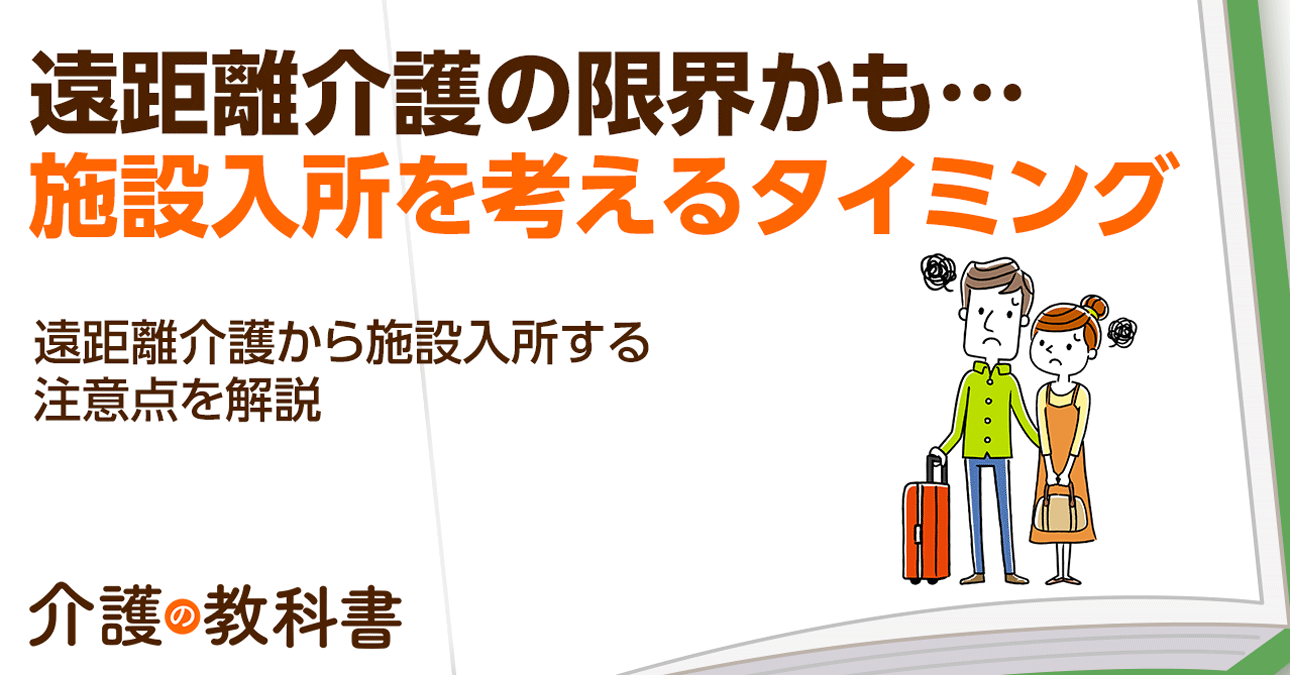皆さんこんにちは、終活カウンセラー協会認定終活講師でジャーナリストの小川朗です。今回は遠距離介護にまつわる問題についてお話したいと思います。
介護者と要介護者のコミュニケーションが大切
老老介護の末におひとり様となって認知症の症状が出始めた親を、遠距離介護の末に看取ったという体験談を、最近もいくつか耳にしました。その中には介護生活を振り返り、自らを責める方もおられました。
その原因となっていたのが、「介護される側」と「介護する側」のコミュニケーション不足。良かれと思って選択したことが、「実は本人の望む形ではなかった」ということがわかってしまったために、自責の念にさいなまれているというのです。
裏を返せば、介護される側とのコミュニケーションが円滑で、その意向に沿った介護の形が選択できれば、後悔するような事態は回避できるのです。私が以前取材したAさん(女性)のお話は、その両方を体験しているレアなケースでした。
遠距離介護をしていたAさんの事例
Aさんのご実家は、地方の都市にありました。そして、Aさんは成人前に上京。両親は故郷の実家で生活していましたが、先に父親が亡くなりました。一人暮らしとなった母親も後に認知症の兆候が出始め、介護が必要になりました。
遠距離介護の5文字が、Aさんの眼前にどっかりと横たわった瞬間でした。身内は別居していたため、介護施設への入居を選択。下見のときには気に入った様子を見せていた母親でしたが、いざ荷造りが始まると渋り始めました。在宅での療養を希望している気持ちがひしひしと伝わって来て、Aさんはこのときから深い自責の念に苦しめられることになります。
Aさんはそんな気持ちに突き動かされるかのように、帰郷するたびに介護施設から実家に連れ帰り、数日間介護するようになりました。遠距離介護が続き、その交通費による経済的な負担も相当なものになったはずです。
その後、母親のオーラルフレイルが深刻な状態まで進行。ここでAさんは悩んだ末に休職を選択。実家に戻り、在宅での介護に専念しました。つきっきりの介護をした末に、Aさんの母親は天へと召されました。
最後になって母親の望んでいた自宅での生活を実現できたことで、施設での介護を選択したときに感じた自責の念は、在宅介護による満足感に変化したと言います。Aさんに、多くの人が看取りの後に引きずる「自責の念」がないのは、結局のところ「どこで介護を受けたいのか」というご本人の意思を、在宅介護により実現できたからにほかなりません。

まずは本人の言葉に耳を傾ける
「認知症の人と家族の会」の鈴木森夫代表理事も、遠距離介護で優先すべきは「ご本人の思いを大事にすること」であると強調します。
こうしたときに、最も有効なのが、親と一緒に開くそれぞれの終活ノート。終活カウンセラー協会にも「マイ・ウェイ」という公式終活ノートがあります。このノートは、一般的な終活ノートに比べて字が大きく、さほど厚くないため、年配も方々に使いやすいのが特長です。
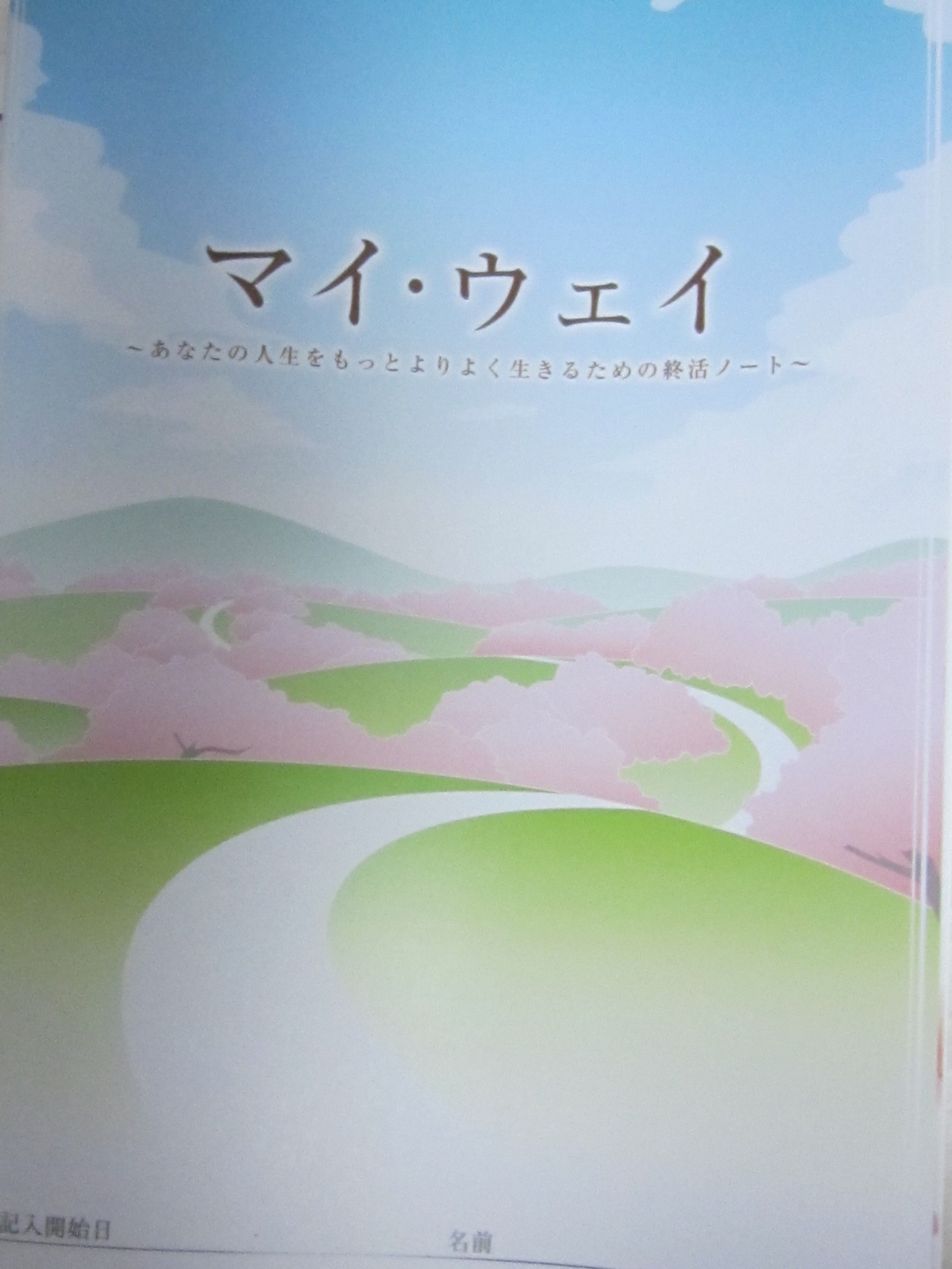
まず、親子でそれぞれ自分のノートの「介護が必要になった場合」というページを開きます。そして「私も書くから、母さん(父さん)も書いて」と言って、「どこで」「誰に」介護を受けたいかなどを一緒に書き出していくのがおすすめです。ノートに書き出すことで、本人の意志をはっきりさせることができます。それにより、介護する人が介護される人の思いを共有できるのです。
そのうえで、自宅に住み続けるのか、施設への入所を考えるのか、それとも子世代との同居を選択するのかなどの本人の希望を反映させなければ、意味がありません。このプロセスを本人抜きで周りの人だけで行った場合、のちのち介護した側が後悔するケースが少なくないのです。
仮に施設に入居しても、良い面もあれば悪い面もあります。環境の変化が、本人にとって大きな負担となることも多いのです。ただ、変わってみたら良かったというケースもあり、一概にどちらが良いとも断言できません。結局のところ、100%満足できる施設はそうそうないのです。後悔しないためには、本人の意思を聞いて、それに沿って進めることが大切です。
意思の疎通を図る作業は、認知症になる前の方が良いには違いありません。しかし、「実は認知症になっても遅くはない」と、「認知症の人と家族の会」の鈴木理事は言います。
認知症が進行していく中でも、意思の疎通を図りながら物事を決めていく。終活カウンセラーが、最も重視するスキルのひとつに「傾聴」があります。「聴」は旧漢字で、「耳を王様のようにして十四の相手の気持ち(楽しい、悲しい、うれしい、寂しい、辛いなど)に関心を持ち、理解しながら聴くという意味を持ちます。
遠距離介護に直面したとき、まずは本人の言葉に耳を傾ける。これが外してはならない、最初のステップであることは確かなようです。