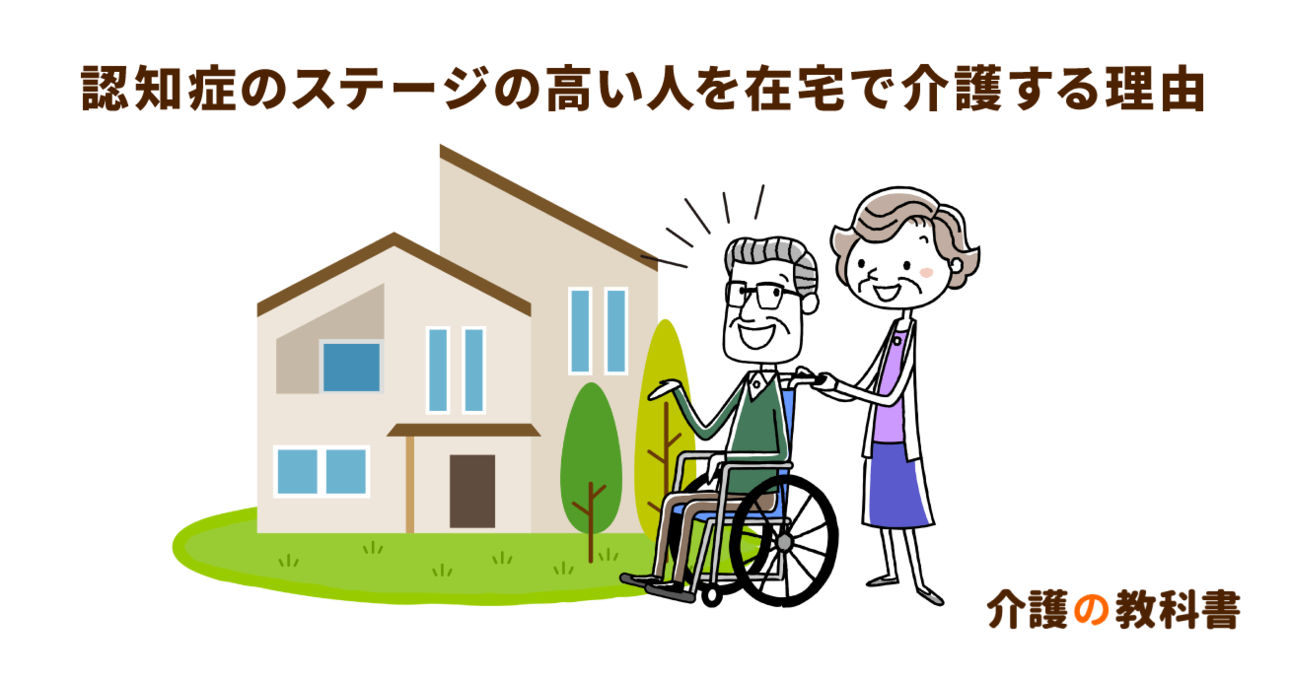こんにちは。REASON代表で、理学療法士の中川恵子です。「介護の教科書」の連載では、介護を経験した方へのインタビューをご紹介させていただきます。
「もしかしたら親が認知症かも」「元気だった親が認知症だとは思いたくはない」「認知症と診断されたけれど、これからどうしよう」などと悩んでいませんか?
今回は、アルツハイマー型認知症になった母に13年寄り添ったレクリエーション介護士の小山久子さんに、お話を伺いしました。
転居をきっかけに始まった介護とその苦労
阪神淡路大震災でアルツハイマー型認知症の母とともに引っ越しを決意
私(小山久子さん)の母は、1990年頃から認知症が疑われる症状がありました。しかし、家族は認知症だと認めることができずにいました。1994年頃、旅行先で母がいなくなったことがきっかけで、脳神経外科を受診。その結果、アルツハイマー型認知症だと診断されました。
そして1995年1月、父と母、夫と子どもたちで住んでいた我が家は阪神淡路大震災で被災。認知症の母にとっては、弱り目にたたり目でした。
地震のショックだけでなく、近所で知人が亡くなったことにより、母は意識が混乱していました。喪服を着て、裸足で外へ出かけることもあったほどです。
私は、母の状況が悪化することを考えて、仮住まいをしながら家を再建することを考えましたが、子どもの将来のことや自分たちの未来を考えて、転居を決断しました。
その頃はまだ、母と普通に会話もできていました。そのため、私は様子を見に来ることを約束して、父と母とで自宅に残って暮らすことを提案しました。しかし、父は私たちについてくることを決めました。
引っ越し後、大変な在宅介護が始まる
1996年1月、西宮市への引っ越しを機に在宅介護が始まりました。それは大変なものでした。
神戸市長田区に住んでいた頃は、地域住民の皆さんが母を支えてくれることもありました。例えば、母が郵便局で出金するのを見た人が、数日後にまた出金に行こうとするのを見て、私に報告してくれたこともあります。
しかし、新居に引っ越してからは、母はどこにいるのかわからなくなったようでした。そして「何もすることがない」「どこへも行けない」など不満ばかりを言うようになりました。
私は、少しでも認知機能の低下を遅らせるために、神戸市の教会や花の展覧会、手芸の作品展に連れて行ったり、家族旅行に出かけたりしました。しかし、母はパンやお寿司などを部屋に隠したり、排泄の失敗を隠したりすることが目立ってきました。そしてその後もどんどんできないことが増えていったのです。

介護への見方を変えた「子どもの言葉」と「母の笑顔」
子どもたちの言葉が、気持ちを切り替えるきっかけに
1998年頃になると、夜ごはんを食べたと伝えても、家の中をぐるぐると回って「晩御飯はまだ?」と言ったり、トイレに何回も立っては違う場所でしてしまったりすることが増えてきました。
私は「なんでそんなことするの」と母を責めてしまい、自分の言葉に自分自身も傷ついていました。そして自分を責めた娘に母が逆上するというような負のスパイラルが起こり、家の中が暗くなってしまったのです。
ある日、小学生の息子に「おばあちゃまはお年寄りになったから、神様にひとつずついただいたものを返しているんでしょう。だから赤ちゃんみたいに戻っていくんでしょう」と言われました。
中学生になった娘は、「いつも優しくしたいと思っているのにできない自分が悲しいの。学校から帰るときの自転車に乗るときに、今日は優しくしよう、今日は優しくしようってずっと言いながら、自転車をこいで帰ってくるの」と言いました。
二人の言葉を聞いて、頭から水をかぶせられたようでした。子どもたちにも謝って、これからできるだけみんなで優しくしようと伝えました。
そうすると、今の状態で楽しめることを探すようになり、在宅介護が違う方向に動き出したのです。
私が笑えば母は笑いました。笑顔は鏡であることに気づいたのです。
母に笑ってもらいたい一心で、音楽レクリエーションを学び始める
2000年に介護保険制度が施行されると、母は要介護度4に認定され、デイサービスやショートステイが利用できるようになりました。
こうしたサービスを利用することによって、認知症の進行を遅らせることにつながると思いましたし、自分のほっとする時間が欲しかったのです。
ところが、デイサービスから帰ってくると、母はいつも不機嫌でした。
デイサービスのレクリエーションを参観させてもらったことで、私は母も含めて皆さんを笑顔にしたい思い、音楽レクリエーションの勉強を始めました。そして、非常勤職員として特別養護施設に勤めることになりました。
その後、ほかの職員さんともディスカッションできるように、日本福祉大学へ編入して学びました。一人の職員として、一人の介護家族として視野が広がっていきました。

施設から自宅に戻り、半年後に最期を迎える
2001年4月、特別養護老人施設が車で10分ほどの距離に新設されました。当時は既設の入所は100人待ち状態のため、周りからも「とりあえず申し込んだ方がいい」との助言を受け、悩みながらも申し込み、入所することになりました。
しかし、入所から2~3ヵ月で車椅子での移動になり、自分で食べることもできなくなりました。また、トイレに誘導すれば排泄できるのに100%オムツになってしまうなど、後悔する気持ちもありました。
週末と盆、年末年始は母と自宅で過ごし、福祉タクシーを使って教会へ行くなど、母のサポートを続けていました。2006年には自力で動くことはできない状態だったので、環境を整えれば在宅介護も可能だと思い、再び自宅に戻すことを決心しました
そして2007年、母は風邪から高熱をだして救急搬送となりました。検査の結果、腫瘍があることが判明。しかし、手術をせずに家で看護することを決め、熱が下がった時点で病院から自宅へ戻りました。
施設から自宅に戻って半年後、母は亡くなる前に満面の笑みで私にいっぱい語りかけ、家族に見守られて静かに旅立っていきました。
介護中は来る人来る人が、「すごく明るくて、優しいお母さまだったんですね」「いつも笑顔ですね」とおっしゃってくださるほど、笑顔が絶えず、母にただ笑ってもらいたいと思っていました。私も学んできたことが報われた瞬間でした。
亡くなった後、すごく素敵な介護をさせてもらってありがとうと、出棺までにヘルパーさんが全員揃ってくれたことも、良い思い出になりました。