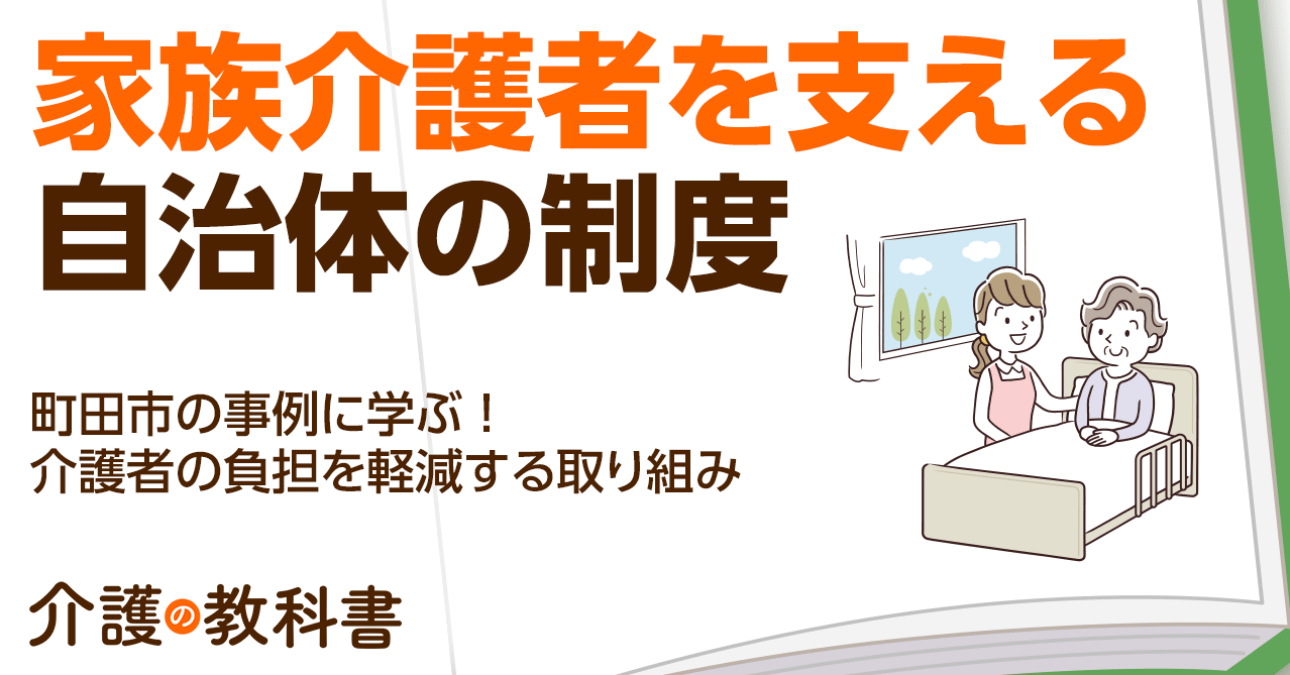皆さん、こんにちは。介護作家・若者介護支援者・メディア評論家などとして活動中の奥村シンゴです。
私は、30歳過ぎからがんや精神疾患などを抱える母親と、認知症や壊死性軟部組織感染症などの祖母を介護して9年目になるケアラーです。
近著『おばあちゃんは、ぼくが介護します。』(株式会社法研)は、ジュンク堂で1位、読売新聞・朝日新聞・共同通信・全国、地方職員共済組合の広報誌『地方共済』など多数のメディアで紹介されて話題になっています。また、まもなくヤングケアラー、若者ケアラー、就職氷河期ケアラーの支援コミュニティーを開設する予定ですので、気軽に遊びに来てください。
さて、ヤングケアラーとは「家族にケアをする人がいる場合に、大人が担うようなケアを引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行う18歳未満の子ども」(日本ケアラー連盟ホームページより)とされています。
国の実態調査では、ヤングケアラーは中学生17人に1人、高校生24人に1人がいることがわかっています。
厚生労働省と文部科学省は、ひとり親家庭の生活支援、子供たちの交流サイトの開設、相談窓口の設置、当事者らが相談対応にあたる「ピアサポート」、自治体の福祉・介護・教育担当者らの合同研修を検討。2022年~2024年度を集中的に取り組む期間と位置づけています。
そこで、今注目を浴びている「ヤングケアラー」の実態を取材するため、佐藤さん(仮名)のケースをご紹介いたします。そして、ケアラーとしての体験とともに問題点を浮き彫りにしていきたいと思います。
中学から生活保護を受給し、母親を介護する日々
佐藤さん(仮名)は、中学2年生の頃に両親が離婚し、母子家庭で育ちました。離婚理由は、「父親の度重なる浮気」です。母親は、父親の女性関係が原因で重度の精神疾患を抱えるようになっていました。
母親の周囲に兄弟や親戚はおらず、母親をケアするのは佐藤さんだけでした。もちろん、ケアを手伝ってくれる人は誰もいません。
私の家庭も兄弟は結婚して家庭があり、祖母とも疎遠だったため、なかなか協力を得られませんでした。若い介護者が発生する原因に「家庭問題の複雑さ」が絡んでいるケースは、往々にしてあります。
佐藤さんは、母親の介護をしながら、離婚した父親に支援を求めました。父親は「お母さんは、病気なんだ。生活保護を受給させて、精神科病院へ入院させろ。そうすれば、医療費や入院代がタダになるし、佐藤さんの学費だって支給されて困らないし、俺の負担も最小限で済む」と答えたそうです。
母親が大好きな佐藤さんにとって、父親のあまりに自己中心的な考えはショッキングなものでした。
とても母親に伝えられる内容ではなかったため、母親からお父さんの返答を聞かれた佐藤さんは、「お母さん、私がさ、高校を卒業したら働くね。将来、工場で社長になるのが夢なんだ」とその場をごまかしました。母親は、佐藤さんの言葉に「ありがとう、ごめんね」を繰り返し、涙を流してお互い手を合ったそうです。

学生時代は友達との普通の日常が過ごせなかった
佐藤さんは、中学3年生の頃から母親のケアを1人で始めました。ところが、母親は57歳と年齢が若く、介護保険対象外だったために介護サービスが受けられませんでした。佐藤さんが登校している間、母親はずっと1人で過ごしていました。
佐藤さんには母親から「早く家へ帰ってきてほしい、寂しい、辛い、生きている意味があるのかな」と繰り返し連絡が送られてきます。佐藤さんは「お母さん、大丈夫。私が守るからね」と心配で泣きながら帰る毎日を過ごしたそうです。
母親の精神的なケア以外にも、買い物、洗濯、掃除と日常生活を1人でこなしていたため、友達から「佐藤ちゃん、今日一緒に家でゲームしようよ」と誘われても断らなくてはなりませんでした。
佐藤さんのケースでもわかるように、少子高齢化や核家族化により、介護者が低年齢化する中、介護保険制度が時代の流れにまったく追いついていないのです。そろそろ制度の見直しが必要ではないでしょうか。
佐藤さんは次のように話していました。
「親の介護をして一番大変だったのは、『周囲の友達と同じように振舞うにはどうしたらいいか』ということでした。友だちに『遊ぼう』と言われても、すぐ家へ帰らないといけず、理由を聞かれても答えられませんでした。そうすると、だんだん仲間外れになって、学校へも行きにくくなりました。学校の先生は全然気がついてくれませんでしたし、近所の人と付き合いもなかったです」
ヤングケアラーの特徴的な課題は、ケアの大変さだけでなく、学校の仲間と対人関係の難しさが生じることでしょう。大人になっても続く関係を築く大事な時期であるにもかかわらず、介護のために関係が崩れてしまうのです。私も、若いうちから介護していた経験上、時間が合わなくなり疎遠になっていく友だちが何人かいました。とはいえ、何か悩んだり困ったりしたときに相談する相手は学生時代からの気のおけない友だちでした。いかにその存在が大きいということを痛感させられたものです。
ヤングケアラーは、大人になって再び親の介護をするケースも少なくなく、学校時代からの仲間は不可欠だと思います。こうした事態を防ぐためにも、ヤングケアラーを支援するためには、教師、ソーシャルワーカー、自治体、民間団体、近所の住民などが一体となって早期発見に努めることが大切です。

大学進学・弁護士の夢をあきらめ、就職を決断
佐藤さんには、経済的な負担も大きくのしかかりました。佐藤さんは、公立高校に進学し、将来は弁護士になる夢を抱いていました。そのため、大学進学を望んでいました。
佐藤さんの家庭は、両親が離婚後、生活保護を受給し、入学準備費・学費・授業料・交通費などが支給される状況でした。ところが、佐藤さんが大学へ進学するには、現行の生活保護の制度上、世帯分離が必要で、母親と別々に暮らす必要があります。
その苦悩を佐藤さんはこう語ります。
「悩み続けましたね。お母さんと一緒に過ごしたいという思いと、自分の将来を歩みたい気持ちが半々でした。それでも、お母さんのそばにいたいと思い、大学進学をあきらめました。今は大人になって働きながら夜間の大学に通ってもいいと思うようになっています」
高校の担任には「コロナ禍で就職率が下がって雇用情勢が不安定なので、大学へ進学しながら様子を見たほうがいい」と強く勧められたと言います。母親も「私は大丈夫だから安心して大学へ進学しなさい。日本はまだまだ学歴社会。助けてほしいときは必ずSOS出すからね」と佐藤さんの大学進学を強くプッシュしたそうです。
それでも、佐藤さんは、大学と弁護士の夢をいったん置いて、自宅近くの工場に就職しました。2005年に最高裁判決の判例で、高校進学の際の生活保護の支給は認められていますが、大学進学はまだ認められていません。
このように、ヤングケアラーは、介護保険が適用外だったり、大学進学や就職が希望通りにならないことが多くあります。また、周囲にケアを支援してくれる仲間がおらず、孤立するといった独特の問題もあります。
いち早くサポート体制を整えるとともに、ヤングケアラーが生まれないようにする予防の観点も今後、重要になるのではないでしょうか。