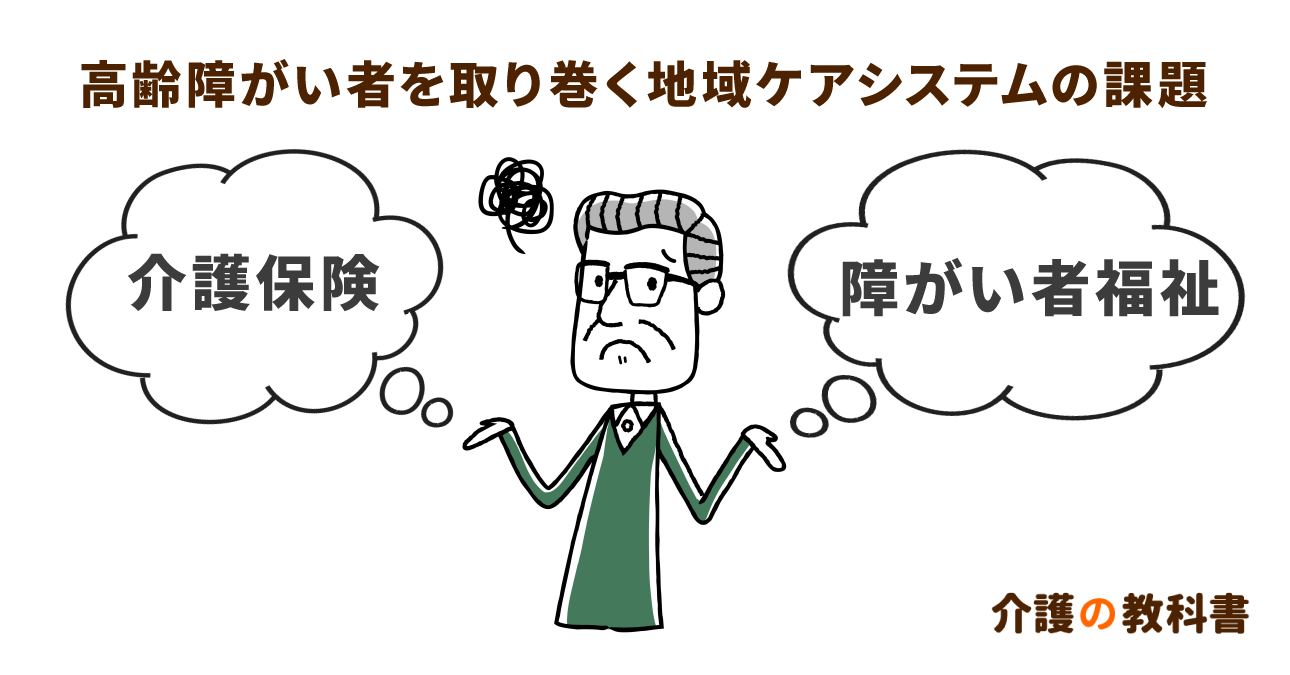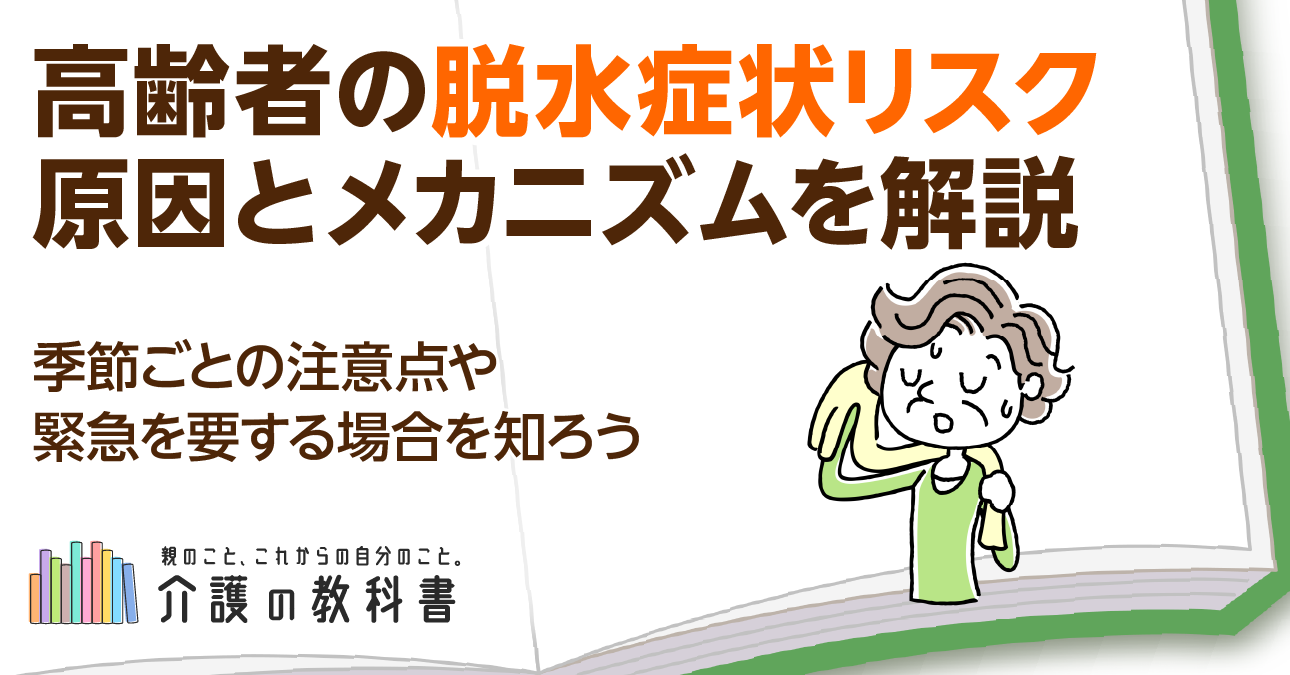皆さんこんにちは。株式会社てづくり介護、代表取締役の高木亨です。
以前にデイサービスの利用に関して書いた記事で、筆者の思いもよらない新たなサービスが今も生まれ続けていることを説明しました。例えば、幼児教育や障がい者のサービスを事業に取り込んだデイサービスなどです。
そこで今回は、その後に誕生した新しいデイサービスについて解説いたします。
「共生型」では高齢者も障がい者もサービスを受けられる
今後、増加が見込まれているのが「共生型サービス」です。
地域共生社会の実現と各地域に地域包括支援体制の構築を目指すことを目的とした2018年の介護保険制度改定により、介護、障がい両方の分野にとって斬新かつ革命的な仕組みとして共生型サービスが盛り込まれました。
それまでの制度では、障害者総合支援法に基づいて、障がいのある方々は65歳になると障がい者福祉制度から介護保険制度が適用されていました。そのため、長年利用していた障がい福祉事業所を利用できなくなるという問題がありました。
もっとも、少ないながら、これまでもそうしたデイサービスなどがなかったわけではありません。しかし、報酬面での課題が大きく、普及しにくかったのです。
2018年の制度改定により、体制や報酬体系も整えられ、「デイサービス」「ホームヘルプサービス」「ショートステイ」の3つのサービスが「共生サービスを提供する事業所」として指定を受けられるようになりました。そのため、介護サービス事業所は障がい者に、障がい福祉事業所は高齢者に、それぞれ両方のサービスを提供できるようになったのです。
これにより、指定を受けた事業所では65歳を過ぎても長年利用してきた障がい福祉事業所を、引き続き利用できるようになりました。
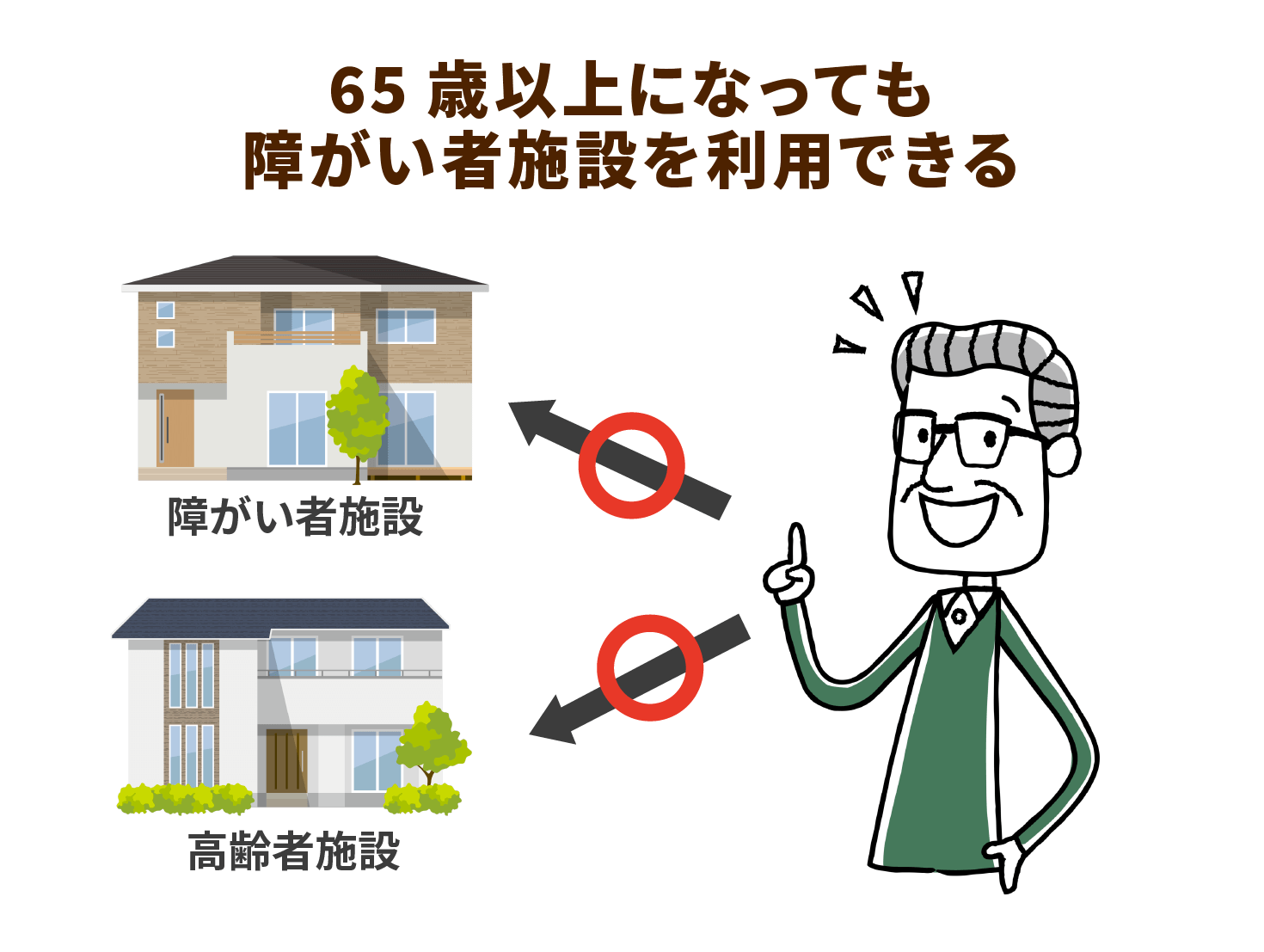
共生型サービスのメリット・デメリット
障がい者と高齢者介護を行う共生型サービスの誕生を皮切りに、「幼老一体型デイサービス」や「訪問看護一体型デイサービス」など、これまでは困難とされてきた革命的な仕組みを導入したデイサービスが生まれてきています。
背景には、団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となることで、社会保障費の増大が懸念される「2025年問題」や、介護職員の人材不足などがあります。そうした問題の解消を図るため、共生型サービスは介護保険制度と障がい福祉制度の一体化を図り、限られた人材の確保と効率化を目指した結果、改定されたのです。
こうした考え方が普及した際の、メリット・デメリットを考えてみましょう。
メリット
- 1.多彩な人間の交流によって活気が生まれる
-
「人間」という字は「人」の「間」と書くように、人間はさまざまな関係性の中で活性化していくものです。
子どもたちや障がいを持った方々の存在は、高齢者の「支えなくてはならない」という役割意識や生き甲斐を創出し、彼らの笑顔も増やします。同時に高齢者のみの集まりに比べ、異なる世代と行動を共にすることは運動量の増加を促します。ほかにもかかわる人が増えることによって脳が活性化し、認知症の各症状にも効果があるのではないかと期待されています。
- 2.利用への抵抗感や手続きの負担が軽減される
-
共生型サービスの場合、利用者はこれまで障がいサービスで通っていた事業所から場所や環境を変更する必要がなくなります。そのため、手続きの煩雑さや混乱などが大幅に軽減できます。
共生型サービスの導入により、慣れ親しんだサービス事業所およびヘルパーの継続が可能となったのは利用されている方々からすれば画期的と言えるでしょう。
- 3.コストの効率化
-
運営側としては業務コストの効率化が期待できます。
例えば、共生型サービスの場合、運営基準や指定基準は介護サービス事業所か障害福祉事業所のいずれかの基準を満たしていればいいとされています。そのため、1つの事業所で、介護・障がい事業所の両方の指定を受けられます。
土地や建物といった固定資産も1事業所分で済みますし、各業務の効率化や介護職員の人材確保の負担軽減、サービス内容の向上も期待できます。さらに、一体型でしかできない特色あるサービスも提供できるようになります。
デメリット
- 1.従事者の労力の増大と各サービス提供レベルの低下
-
従事者は、これまでそれぞれの分野において国家資格やそれに準ずる資格を必要とするエキスパート職でした。そのため、今後は異なる技術や知識を身につける必要があります。似たような業務と一括りに考えられがちですが、実際には大きく異なる業務や知識も多岐にわたり、スタッフの労力や心労は増大することになります。
高齢者との共生により、前例のない事故やトラブルも起こりやすくなります。状態や体調が1日の間にも変わりやすい高齢者と、若い障がい者・幼児などを一体的に状態把握することも厳しいことでしょう。また、サービスを受ける側からすればサービスの質の低下と受け取られかねません。
- 2.感染症の危険性
-
幼老共生型などの場合、頻繁に社会に出入りする子どもがウイルスや細菌の媒介役となる危険性は極めて高くなります。感染症などによるクラスターを招く、大きなリスクともなりかねません。しかし、幼児に衛生面での教育を施すのは容易ではありません。
一方で、高齢者側は一般的に抵抗力が弱まっています。高齢者は、新型コロナやインフルエンザで重症化しやすく、肺炎を引き起こす可能性もあります。

必要なのは国家による投資
共生サービスは、新たな介護の可能性を切り開くと同時に、リスクも含んでいます。しかし、深刻化する人材不足を解消するうえでは、ある意味やむを得ない流れとも言えます。
しかし、こうなる未来は、何十年も前から確実視されていました。にもかかわらず、積極的な投資はされず、むしろ苦肉の策と思われるような制度の方針転換や解釈変更、対象の変更をことあるごとに繰り返しているように見えます。そして、こうした共生化の流れは、それぞれのサービスがもはや単独では運営できない状況に陥っていることを暗に示しているとも言えます。
介護をはじめとした福祉は「儲からないからやらない」というわけにはいきません。なぜなら、国家の義務であり責務だからです。民間の創意工夫に頼るばかりではなく、安定的で恒久的な福祉の供給体制を築くためには、積極的な公的資金の投入を行っていく必要性があるのではないでしょうか。