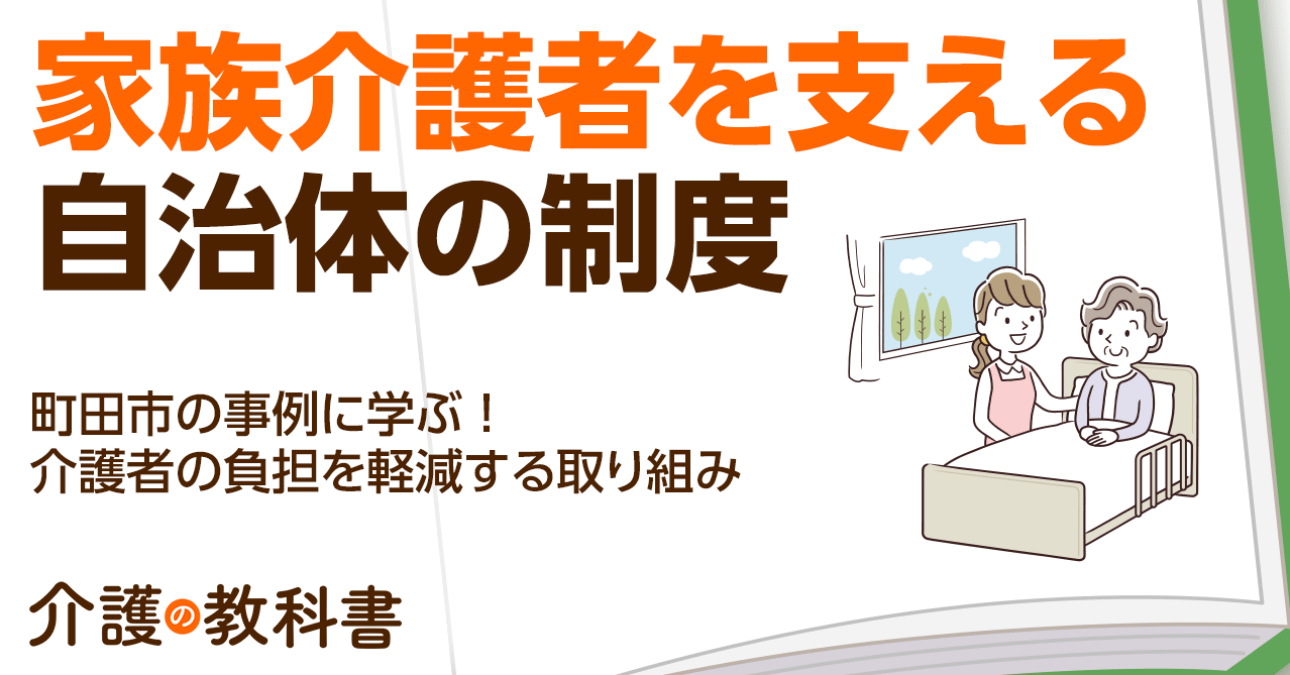こんにちは、介護作家・若者・就職氷河期支援、メディア評論家の奥村シンゴと申します。
最近、家族の世話や介護を担う18歳未満の子ども「ヤングケアラー」の支援や課題についてクローズアップされることが増えています。テレビや新聞などの多くのメディアが取り上げるようになりました。
私は、ケアラーの支援活動・講演・取材を行っているため、実際にヤングケアラーと話す機会があります。あるヤングケアラーは、「高校生から母親を1人で介護しています。でも、学校ではみんなと変わらず元気に過ごしています。なので、先生も気がついていません。親しい友達だけに自分が介護者だと伝えて、『あまり日常でお金を遣えないから、ごめんね』と断ったうえで遊んでいます」と打ち明けてくれました。このような話を聞くと、家族のケアをしている子どもの支援は急務だと実感します。
他方、18歳以上から30代くらいを指す「若者ケアラー」や、40代以上も含めた「ケアラー」全体へのサポートが不十分なのも事実。かといって、マンパワーや予算が限られた中で、全員をサポートするのは非現実的です。そこで私は、ヤングケアラーからケアラーまで全世代型の重点的な支援が必要だと考えています。
詳しくは、近著『おばあちゃんは、ぼくが介護します。』(株式会社法研、ジュンク堂1位、読売新聞・朝日新聞・共同通信・現代ビジネスなど多数紹介)をお読みいただければと思いますが、一部を抜粋してご紹介します。
ヤングケアラーと若者ケアラーの共通課題
国の実態調査では、「ヤングケアラー」は中学生で17人に1人、高校生で24人に1人存在することがわかりました。これは国内の中学生321万1,000人のうち18万2,970人、高校生309万2,064人のうち12万6,774人がヤングケアラーだということになります。
厚労省の調査結果から、ヤングケアラーは「勉強時間と睡眠が取れない」という悩みを抱えていることがわかっています。こうした悩みに対して考えられる支援は、「ショートステイサービスの割引や補助」「介護保険外の夜間から早朝レスパイトサービス拡充」「教員や塾講師による補講授業」などです。
次に、「若者ケアラー」と「ケアラー」への支援も考えてみましょう。総務省の調査では、「若者ケアラー」は、15歳以上から30歳未満で約33万人、30代で約33万人いると推計されています。さらに上の世代となる「ケアラー」は、40歳から49歳で89万5,000人、50から59歳で188万人、60~69歳で97万8,000人と万遍なく存在します。
こうした「ケアラー」の悩みやストレスの原因をみると、男性は「自分の病気・介護」33%、「収入・家計・借金など」23.9%、「自分の仕事」18.9%などが挙がっています。上位を占めているのは、ほとんどがお金と仕事に関するものでした。対して女性は「自分の病気や介護」27.1%、「家族との人間関係」22.4%、「自由にできる時間がない」20.8%と、家族関係と余暇に関する悩みが上位を占めています。
こうして「ヤングケアラー」とそれ以外の「ケアラー」の悩みは、「勉強」か「仕事」かという点で違いがある一方、「余暇時間が取れない」「人間関係」といった点で共通する部分もあります。

年齢よりケアレベルに応じた重点的支援を
現在、厚労省や自治体は「ヤングケアラー」への支援を充実させるべく、対策を打ち出そうと議論を進めています。しかし、年代ごとで支援を分けるよりも、根本的な悩みを解決することが先決なのではないでしょうか。
特に、私は「介護疲れの自殺者」と「介護殺人」に対するアプローチをより重点的に考えていくべきだと思います。
精神看護の分野に、「ケアレベル」という考え方があります。『精神科看護ガイドライン』によると、次のように定義されています。
簡単に要約すると、患者の病状などをレベル分けして、どの程度の看護や介入が必要なのかを推し測る目安のようなものです。ケアレベルが高ければ高いほど、その人の精神的な健康は害されている状態ということになります。
介護疲れでの自殺者は、ケアレベルが高い場合が多いとされています。ケアレベルが高い人は50~60代に多いとされていますが、若い世代では表面化していない可能性もあります。そもそも「ヤングケアラー」も最近になるまで、存在自体が埋没していました。悩みは異なっても、その深刻さには世代間での格差はないように思います。
一方、介護殺人は、1998年~2015年まで716件発生しています。日本福祉大学の研究によると、介護殺人発生率のうち37.45%にあたる275件が親子などの二人世帯で発生しています。さらに、26.85%の被害者が寝たきりの状態だったことがわかっています。つまり、「ワンオペや多重介護の状態」で「要介護者の介護度が高い」と、介護殺人が起こりやすいのです。介護者が精神的に追い詰められた結果、殺人という悲劇が起こるのだと推測できます。

多重介護の恐怖
「ケアラー」の支援と同時に支援が急務なのが、「多重介護」の問題です。多重介護とは、ケアラー1人で複数人の介護を迫られた状態です。
私は、30歳過ぎのとき、母親が脳梗塞で倒れたのと同時期に祖母が認知症を発症し、突然介護を始めることになった多重介護者の1人です。
家には弟と妹もいましたが、既婚で子どもがいたり、祖母への愛情の温度差で協力が得られず、私が一人で介護をしてきました。祖母は、要介護度1の判定ではあったものの、認知症のために目が離せない状態でした。
例えば、料理で火を使っているにもかかわらず突如消したり、自宅の場所をたびたび忘れたり、同じことを何度も話したりしていました。要介護が低いから介護が楽というわけではないのです。
加えて、1ヵ月の介護サービスが月1回のショートステイ、週2回のデイサービス、週2回各30分のヘルパー支援、福祉用具のレンタルで手間も金銭的にも手一杯の状態です。
ある日、祖母が自宅で転倒して打撲してから、3週間の入院が必要になりました。そのとき、要介護度は2から4に上がりました。そして週2回のお泊まりデイサービスかショートステイ、週3回のデイサービスなど、介護サービスの利用時間が増加。排便・排泄の失敗、着衣着脱不可、異食(食べもの以外を口に入れてしまう行為)、徘徊、歩行不安定などで、私の負担は重くなり、正社員で仕事ができる状況にありませんでした。
2019年1月、祖母は認知症の進行で精神科病院に入院しました。その後も、急性腎う炎、尿管結石、普通の風邪、2021年3月には壊死性組織軟部感染症でたびたび呼び出されました。一方、母親も腹痛に悩まされ、複数の病院を受診・検査。原因不明で身体表現性障がいと診断され、情緒不安定な毎日を送ることになりました。突然、母親から「肺がはがれそうや、死ぬ、助けて」と連絡があり、そのたびに病院へ連れて行きました。今もケアマネージャーと相談しながら、一緒に過ごす日々が続いています。
こうみると、ケアラー支援は「ヤングケアラー」から「ケアラー」までの幅広い年齢を対象にし、シングル・多重介護者・重度要介護者にも考慮したうえで行うのが望ましいと思います。
そうすることで、介護殺人・介護自殺だけでなく、介護離職などへの予防効果も期待できるのではないでしょうか。