みなさん、こんにちは。フリーライターの奥村シンゴです。
私は30歳過ぎから約6年間、認知症の祖母を在宅介護していました。
祖母は一度、介護老人保健施設(老健)に入りましたが、「認知症による周辺症状によりほかの利用者に迷惑をかける」という理由で退所。
現在は、精神科病院の急性期病棟に入院中です。
そんな祖母について、今年の夏ごろ、主治医から「近い将来、おばあさまの延命治療についてお話をするときがくると思います」と言われました。
今回は、延命治療の是非について、私と祖母の体験談や統計を交えながらお話していきます。
延命治療について相談していなかったことを後悔した
今年の夏、祖母が入院している精神科病院の主治医から、ある電話がかかってきました。
「おばあさまのことで、少しお話ししたいことがあります。お時間をいただいてもよろしいですか?」ということでした。
私が精神科病院へ行くと、主治医、看護師、介護士、ケースワーカー数人がズラリと勢ぞろい。
不安になっている私に、主治医は「おばあさまの食欲が少しずつ落ちてきていて、食事を拒否することも増えています。
近い将来、胃ろうによる栄養補給や、人工呼吸器の装着といった延命治療をご希望されるかを考えておいてください」と告げました。
そのとき、私は「30年以上も一緒に住んでいるのに、なんでこれまで延命治療について話し合いしてこなかったんやろ」と思い、祖母に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。
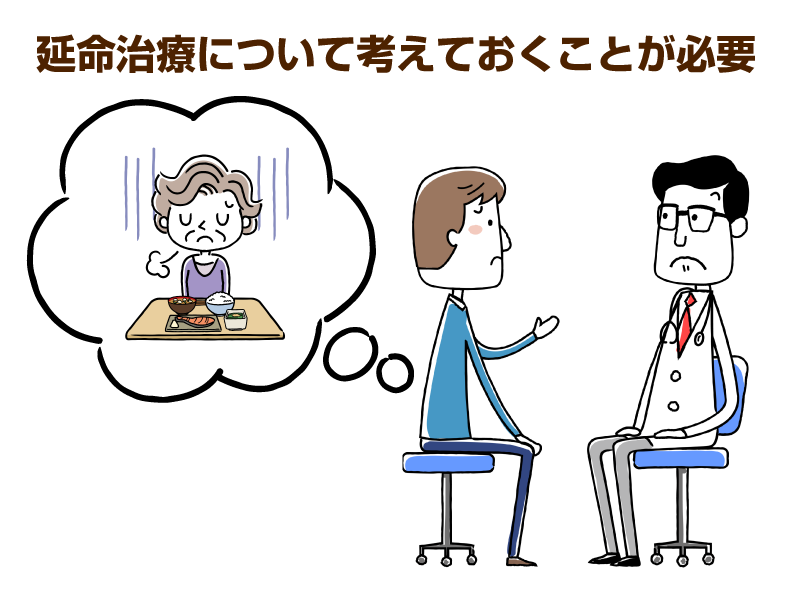
後になって調べてみると、私だけでなく、世間一般的にも終末期や延命治療について話し合っている家族は少ないようです。
厚生労働省による終末期の医療に関する意識調査によると、終末期の医療について家族と「詳しく話し合っている」が2.7%、「一応話し合っている」が36.8%、「話し合ったことはない」が55.1%、「無回答」が5.4%です。
家族と「話し合ったことがない」人が一番多いという結果を見てもわかるように、「死期が迫ったときに、どんな治療を希望するのか」は、家族間では話しづらく、実際に病気にならないと身近に感じないテーマなのかもしれません。
ですが、私と祖母のように、事前に話し合っておかなければ、いざ延命治療の選択を迫られたときに後悔することがあります。
病気になる前から、家族で話し合いをしておくのをおすすめします。
面会で「本人の意思」のヒントをつかむ
ただ、私のように「話し合うことなく延命治療の選択を迫られた方々」でも、まだチャンスは残されていると思います。
大切なのは「本人がどうしたいのかを一生懸命考えること」です。
私は、祖母が認知症によって延命治療の是非を判断できないので、「祖母が元気でいる間にできるだけ面会に行き、意思を確認しよう」と考えました。
それ以降、最低でも週に1回は病院へ行って、2時間ほど祖母と一緒に過ごすようにしています。
そして食事介助をしながら、祖母の食欲と表情を見るようにしていました。
すると、医師が言っていた通り、何口か食べて「これやって、これ!」と理解できないことを言いながら怒り、食事拒否をするときがありました。
祖母は会話ができないので、エプロンを上に持ち上げて、一生懸命「もうお腹いっぱい」という合図を伝えてきます。
しかし一方で、私に「これ食べようかいな」とうれしそうに言いながら、病院のおかずを指さす日もありました。
さらに、私が「ばあちゃんは、元気でいたいと思う?思わない?」と聞くと、祖母はよく「元気でいたいと思うよ」と笑って答えてくれます。
ときには、「あんたの家族は元気かいな」と返してくれることもあります。
祖母は重度の認知症なので、普段は「ご飯は食べてる?」「よく寝てる?」と問いかけても、「チンチラリ~チンチラリ~」と歌を歌ったり、理解できない日本語で返事をしてきたりします。
祖母がそういった状態なので、「元気でいたい?」の問いかけをしたときだけ通じることが多いのは不思議ではありますが、それこそが祖母の意思の表れなのだと思います。
主治医にも、祖母の延命治療について相談してみると、「医師とはいえ第三者ですから、軽率なことは言えませんが…普段の様子を見ていると、おそらく元気でいたいと思っているんじゃないかな」と言っていました。
延命治療について本人の意思を確認できない場合、かつ本人が施設や病院で過ごしている場合には、家族が1回でも多く面会へ行くことで、ヒントを見つけられると思います。
私は祖母と過ごしていく過程を経て、少しでも長生きをして元気でいることが、祖母の意思なのだと思いました。

面談に行って本人の意思を確認してほしい
厚生労働白書によると、延命治療を望まない人が7割を超えています。
祖母の主治医からは、延命治療についてこのような話を聞きました。
「認知症の方への延命治療はね、批判が多いんですよ。ご本人の意思がわからないので、ご家族様の意向に委ねることになりますから」
この「家族が延命治療を判断すること」について、さまざまな意見があるとは思いますが、私は「ご家族のなかでも、本人と一緒に過ごした時間が長い方には、延命治療をする選択があって良い」と思っています。
なぜなら、本人と過ごした時間が長いからこそ、本人の意思を第一に尊重して、延命治療を選択することができると思うからです。
しかし、時折、介護職や看護職の方々からこんな話を聞きます。
「施設に預けたまま、ほとんど面会に来ていないのに、延命治療を選択するときだけ口を出し、なんでもっと長生きをさせなかったのかとほかの家族に怒る方もいます」とのこと。
こういう話を聞くと、それぞれ仕事や家事、育児などで忙しいのだろうと理解はできても、せめて月1回くらいは「顔を見せてあげてほしいな」と思います。

これは私個人の考えですが、延命治療は家族の意思で選ぶのではなく、本人の意思に基づいて選ぶべきです。
面会にも来ない家族に、その意思を把握することは難しいと思うので、延命治療のことにだけ口を出すご家族は、それを選択すべきではないと思うのです。
延命治療の選択は、本人や家族にとって大変つらく、苦しく、重いテーマです。
本人が認知症などによって意思表示ができない場合は、家族にはなおさら、負担がかかります。
その責任を受け止めたうえで、愛情深く本人のことを考えることができる家族に、延命治療の是非を選択してほしいと思います。




















