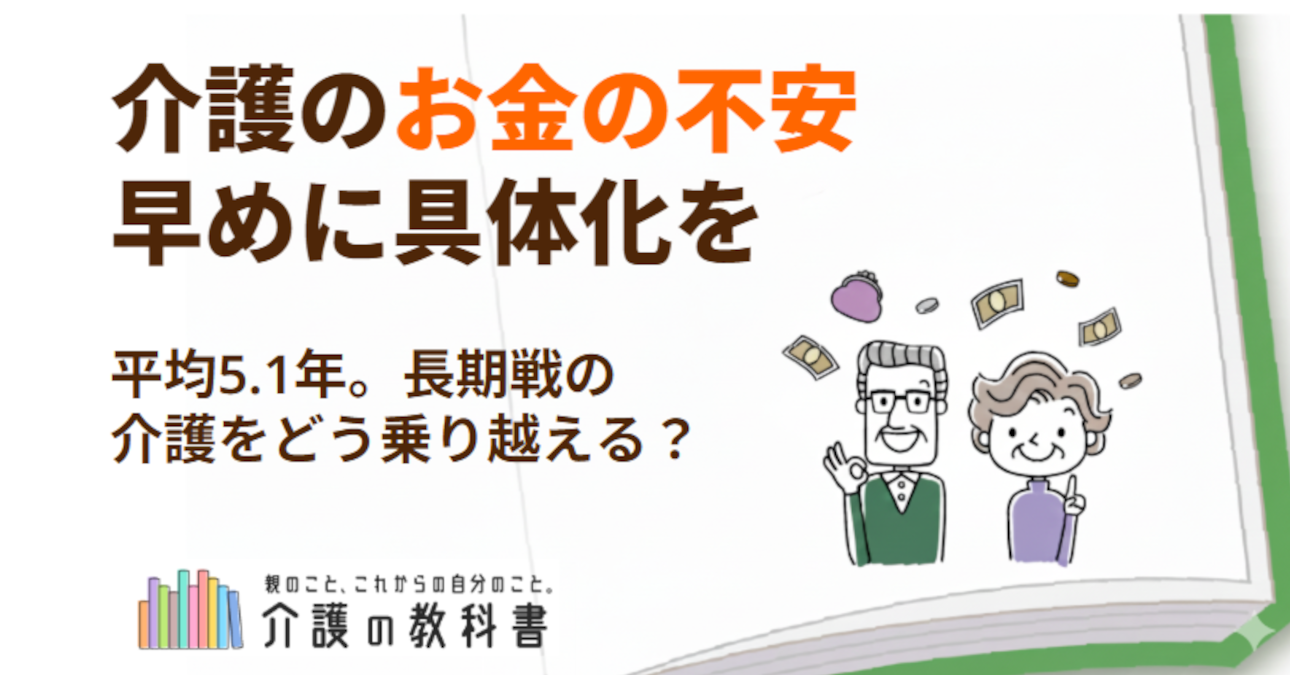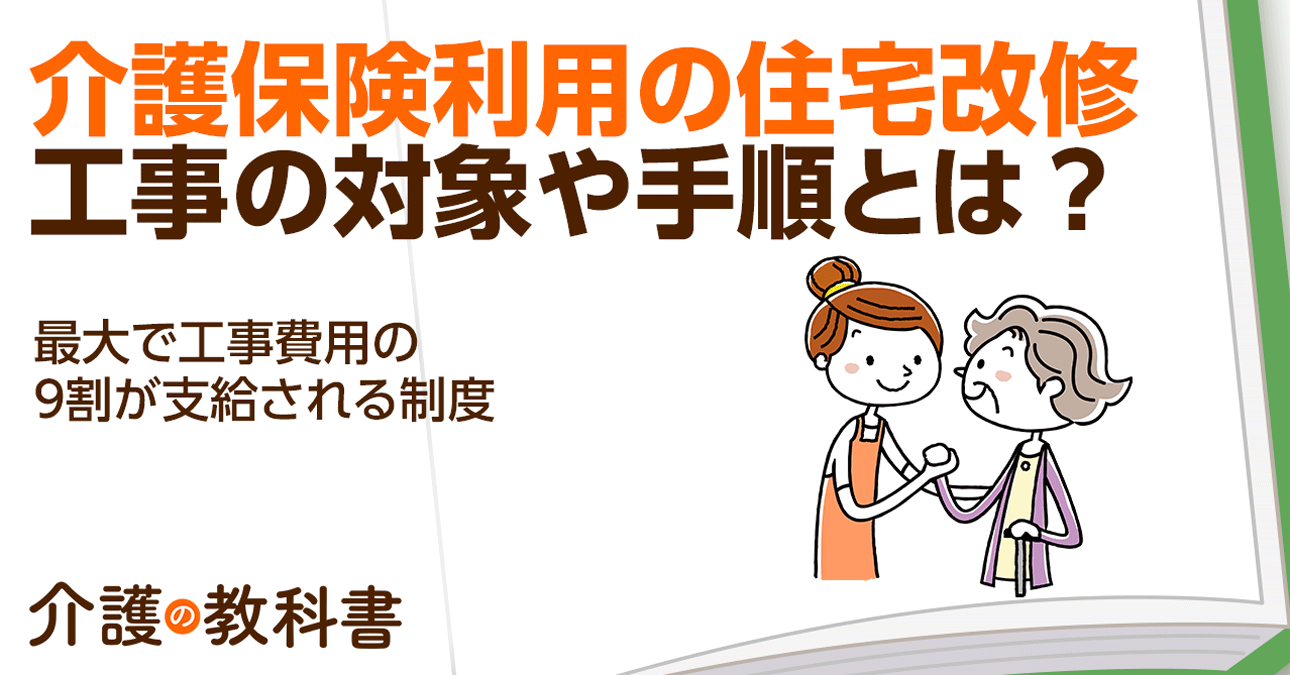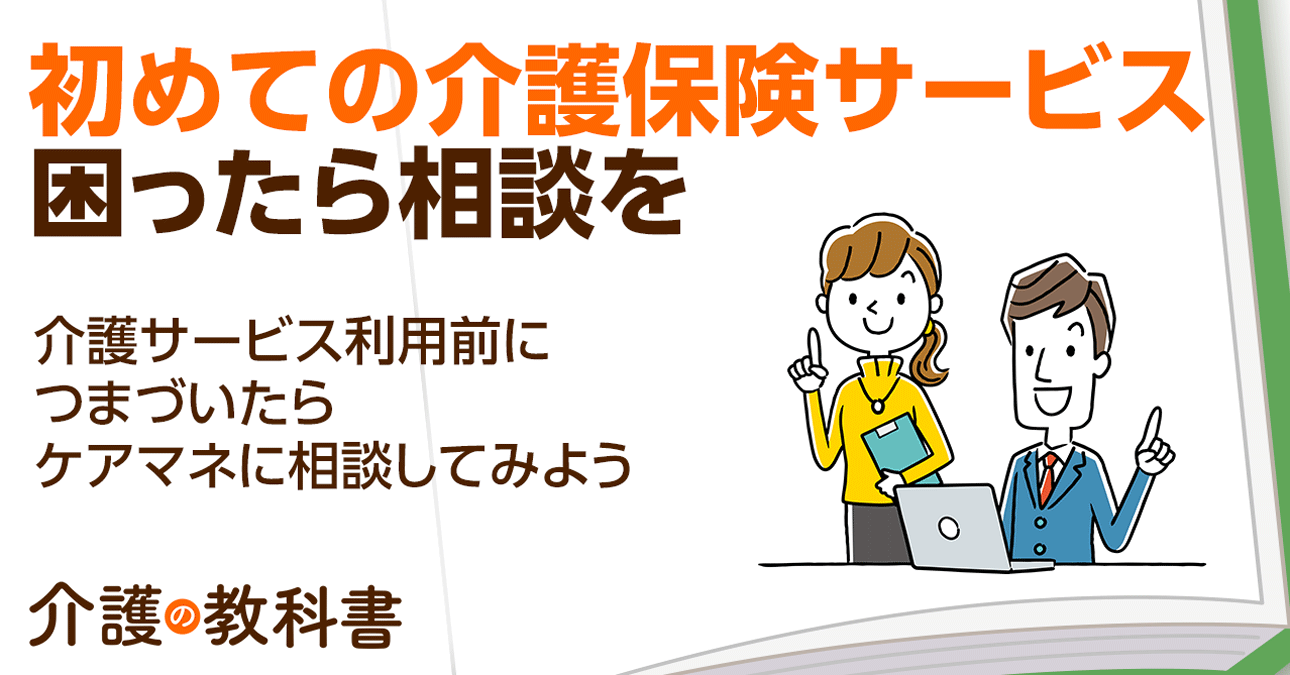みなさん、こんにちは。終活ジャーナリストの小川です。
今回は悪徳商法の被害に遭ってしまった阿部進さんの事例をもとに、介護タクシーについての複雑な介護保険の仕組みついてお話しします。
介護保険の内容は複雑ですが、その内容は広く知られる必要性があると思います。
それでは、早速事例を見ていきましょう。
40代という若さで介護状態に陥った阿部進さん
「ゴルフスタジアム(以下GS)事件」という、悪徳商法の事件をご存知でしょうか。
ゴルフのレッスンプロや練習場の経営者などに対し、「ホームページを実質、無料で作ることができます!」という謳い文句で、レッスン用のソフトを数百万円で買わせた事件です。世間でも注目され、各マスコミもこの事件を一斉に報道。すぐに被害者の会が立ち上がりました。
阿部進さん(現在49歳)も、被害者の一人でした。

阿部さんは日本で最高峰の大会・日本オープンゴルフ選手権にも出場。決勝ラウンドに進出した経験も持っています。
その後、レッスンプロに転向したところお客さんは1,000人に達し、10年近くコンスタントに5,000万円以上を売り上げていました。
そんなとき、この悪徳商法の被害にあってしまったのです。
2017年3月の事件発覚と同じ時期から、阿部さんは突然の体調不良に苦しみます。
「異常に疲れやすくなって、仕事が終わると本当に動けない。足が全然ついてこないんです」
さまざまな検査を受けた阿部さんは、筋萎縮性側索硬化症(ALS)だったことが発覚します。40代後半の若さでありながら、「第2号被保険者」として介護保険を利用することになり、現在は要介護3。日中はほとんどベッドの上で過ごし、車イスから立つこともできません。
詐欺事件の被害者でありながら、そのような状況にあった阿部さんは、周囲に迷惑がかかることを憂慮し、債権者集会に参加を控えていました。
しかし、今年の3月26日に、最後の債権者集会が行われることになったのです。
そこで阿部さんは、東京・霞が関の東京地裁まで、介護タクシーで出かけることを決断します。
しかし、ここで問題が生じました。区役所から、債権者集会に参加する場合、介護タクシーの利用は介護保険の適用外になると回答を受けたのです。
一体どうしてなのでしょう。
介護タクシーは利用目的により保険適用の制限がある
当該区役所の高齢介護課に取材してみると、こんな答えが返ってきました。
「介護タクシーは日常生活や社会生活上、最低限必要な場合に使用が認められます。債権者集会への参加は任意によるもので、それは最低限の日常生活の範囲から外れているという判断です」
阿部さんは、埼玉県内の自宅から都内の病院を往復するときに介護タクシーを利用しており、その運賃には介護保険が適用されていると思っていました。
そのため、介護タクシーでの移動であれば、どのような目的であっても介護保険サービスが利用可能だと思い込んでいたのです。

すべて自費負担を覚悟して東京地裁に行った阿部さんは、次のように語ります。
「介護タクシー代が約4万円、ヘルパー代が約3万5,000円と、合計で約7万5,000円かかりました」
ゴルフで生計を立てていたところ、詐欺に遭い、介護状態にまでなってしまった阿部さんにとって、この負担は非常に大きかったはずです。
乗降のための介助のみが保険適用になる場合も
介護タクシーは基本的に、介護保険適用外のサービスになります。
そのため、運賃などに介護保険を適用することはできません。ただ、通院時等の必要が認められた場合のみ、訪問介護サービスの「通院等乗降介助」を使うことができます。
この「通院等乗降介助」は、要支援の方は使えず、要介護1以上の方だけが利用できます。介護タクシーは、車椅子のまま乗り込めること、別途料金で介助を受けることができることにメリットがあります。
このサービスを行っている事業所は少ないのですが、合わせて介護タクシーも行っているケースが多くあります。
その場合は運賃が普通のタクシーよりも少額に設定している場合が多いので、運賃にも介護保険を適用できると思っている方が多くいます。
しかし、この場合、自己負担は大きく軽減できますが、運賃部分が介護保険適用となるわけではないのです。
そして訪問介護サービスの通院介助は、自宅と病院の行き来のみ。
それを踏まえて、阿部さんの介護保険の適用について再度当該区役所に取材したところ、「(病院から自宅までの)帰路の分は認められます。 ケアマネージャーさんと相談していただければ」との回答を得ました。
つまり、阿部さんは病院から自宅に向かうときの乗降介助の部分については、介護保険サービスの適用を受けることができたのです(※ただし病院に立ち寄った場合には必ず保険適用となるわけではなく、市町村によって規定が異なったり、条件がつく場合があります)。

私が講師をしている、終活カウンセラー協会の初級検定の「介護」の科目においては、阿部さんが適用を受けている「第2号被保険者」の項目は重要なポイントのひとつに置いています。
介護保険の被保険者は40歳以上の方全員で、加入手続きは必要ありません。
サービスの利用ができるのは介護が必要と認定された方で、そのうち64歳以下の方は、16種類の特定疾病が原因で認定された方のみ利用できます。
その16種類の中に、阿部さんが闘病中のALS(筋萎縮性側索硬化症)も含まれています。
第2号被保険者の阿部さんは、今回の件で介護保険についても多くのことを知ったようです。
一方で、今回の件では介護保険の複雑さを垣間見る機会にもなりました。
介護はいつ始まるかわかりません。阿部さんのように早く介護生活が始まる方もいるため、現役世代で働いている方々にも介護保険の内容は知られる必要があるでしょう。
また、それぞれの現場でケアマネージャーさんからの丁寧な説明、行政からのシンプルでわかりやすい情報提供が、切に求められていることは確かです。