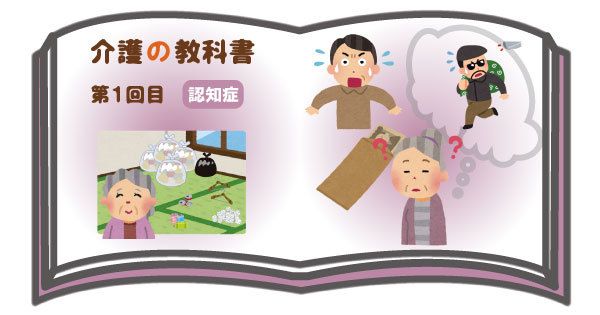みなさんこんにちは。デイサービスで看護師として勤務している、認知症LOVEレンジャーの友井川 愛です。
認知症の症状や問題行動には個々人によって差があり、「葛藤型」「遊離型」の3つのタイプに分けることができます。
第92回では「葛藤型」、第93回では「回帰型」についてお話をしました。
今回は、「遊離型」についてお話ししていきますね。
遊離型の方の特徴
遊離型の方は、自分の心のなかに閉じこもって、周囲との関係を断とうとします。
現在の自分を受け入れられず、現実から逃げようとしている点では、回帰型と似ていますね。
しかし、回帰型の方が現実を受け入れられず、若かった頃の言動が見られる状態になるのに対し、遊離型の方は自分の心のなかに閉じこもってしまいます。
つまり、遊離型の方は自分の心のなかだけで生きることで現実を断ち切り、自分自身を保とうとするのです。
しかし、現実の世界を断絶しようとすることによって精神状態が荒廃してしまい、やがて病的なものとなっていきます。
遊離型になりやすい傾向の高齢者の方とは
遊離型になる方は、若い頃から困難にぶつかることがあっても解決せず、人間関係が複雑になることがあっても逃げることで回避していたような方が多いと言われています。
遊離型になったときの症状
先ほども述べたように、遊離型の方は自分の心のなかに閉じこもって、現実の世界を絶ってしまうため、周囲の人が声をかけても反応がありません。
独り言のようにブツブツとつぶやいたり、ひとりで笑ったりすることがあります。
能動的に何もせず、自分の心を閉ざしてしまう無為・自閉症状になった場合は、目の前に食事が準備されていても興味を示さず、自分で食べようとしません。
お風呂に入るときも、衣類の着脱を自分でしなくなることが多くあります。

何を考えているのか?
遊離型の方は、生きることに対しても諦めている状態です。
「年を重ねて生き甲斐もないのに、ご飯を食べても意味がない」「もう何もしたくないし、放っておいてよ」という心境になっています。
遊離型の方に対応するときのポイント
遊離型の方に対して、周囲が現実の世界に引き戻そうとするのはおすすめしません。
どちらかというと、現実の世界で生きていて良かったと思ってもらえるかかわり方が良いと私は思います。
五感を刺激したり体を動かしたりしてもらおう
遊離型の方は心のなかに閉じこもっていますが、当然ながら身体は現実の世界にあります。
そのため、まずは五感を刺激できるように関わりましょう。
例えば音楽を聞いたり、歌を歌ったりすることで聴覚を刺激し、鮮やかな色の絵や花を見ることで視覚を刺激します。
本人が好きな食べものや飲みものがあれば、食べてもらって味覚を刺激することもおすすめです。
ほかには、うちわを使って卓球したり風船バレーをしたり、介護の現場ではおなじみの遊びリテーションも効果的ですね。
このようなレクリエーションは、複数の刺激が同時に起こるので効果的だと言われています。
また、握手をするなどのスキンシップにも効果があります。
ただし、他人に触れられることを嫌がる方もいるため、本人に触れても良いかを確認をしましょう。

いつも自分の世界に引きこもっているCさんの事例
それでは、遊離型でいつも自分の世界に生きているCさんの事例で考えてみましょう。
Cさんは、85歳の男性です。
製造工場で定年まで働いており、若い頃から積極的に他人に関わる性格ではなかったそうです。
数年前に奥さんが亡くなり一人暮らしをするようになって以来、ひとり言が増え様子を見にきた娘さんが異変に気づいて心配になり、施設へ入所となりました。
奥さんがいた頃はご近所付き合いがありましたが、Cさん自身は人と関わることが苦手な性格だったため、奥さんが亡くなってからはご近所付き合いもなくなりました。
Cさんは施設に入所してからも、ほかの利用者さんやスタッフの声かけにほとんど無反応で、自分の居室でブツブツ言ったり、笑ったり怒ったりしていました。
そのため、ほかの利用者さんがCさんのことを怖がるようになり、ますます周囲との壁ができてしまいました。
常にボーッとしており心ここにあらず状態。
スタッフはどうにか刺激を与えようとレクリエーションに誘いますが、なかなか反応してもらえず、動いてもらえません。
そこで私は、ソファーに座っているCさんの隣に、何も語らず座りました。
そしてCさんの呼吸に自分の呼吸を合わせながら、Cさんに聞こえるように歌いました。
Aさんの好きな星影のワルツを。
それからしばらくすると、隣にいるCさんが小さい声で歌い始めたのです。
先ほどまでは目の焦点も合わないようなうつろな表情だったのに、いつもより眼に力があるようにも見えました。
私は歌い終わったCさんに「お上手ですね」と伝え、握手を求めました。
するとCさんは、少し照れたように微笑んで「そうかな?」と返事をして、握手してくれたのです。
この反応を私はチャンスだと思い、Cさんの手を優しくさすりながら、手のひらをマッサージしました。
Cさんの手は冷たかったので、ツボもやんわり押しながら。
最初こそ驚いたような表情になったCさんですが、その後は何も言わずマッサージを受けてくれました。

私はそれからも同じように、歌ったり、ハンドマッサージを繰り返し行ったりするようになりました。
それが習慣になっていたある日、レクリエーションでカラオケを行っていると、Cさんが自ら、利用者さんが多く集まっている場所の近くにやって来ました。
マイクを持って歌うことはありませんでしたが、ほかの方が歌っているときに口ずさまれるようになったのです。
それは毎回ではありませんでしたが、スタッフだけでなく利用者さんのなかに相性の良い方が見つかり、時々その方とカラオケをするようになりました。

今回のケースで私はハンドマッサージを行いました。
手にはたくさんの神経があるので気持ちよさが伝わりやすい場所でもありますし、本人も自分の目で見られるので安心感もあります。
最後に一言
Cさんのように、もともと人と関わることが苦手で遊離型になってしまった方でも、他者と関わるきっかけさえつくることができれば、現実の自分を取り戻そうとしてくれることがあります。
まずはいきなり引き戻さずに、ちょっとした刺激をするような関わり合いから始めてみましょう。
これまで、認知症の問題行動について3回に分けてお話してきました。
3つのタイプが入れ替わりで起こる方もいるので、それぞれの対応方法を組み合わせてケアすることも必要ですね。