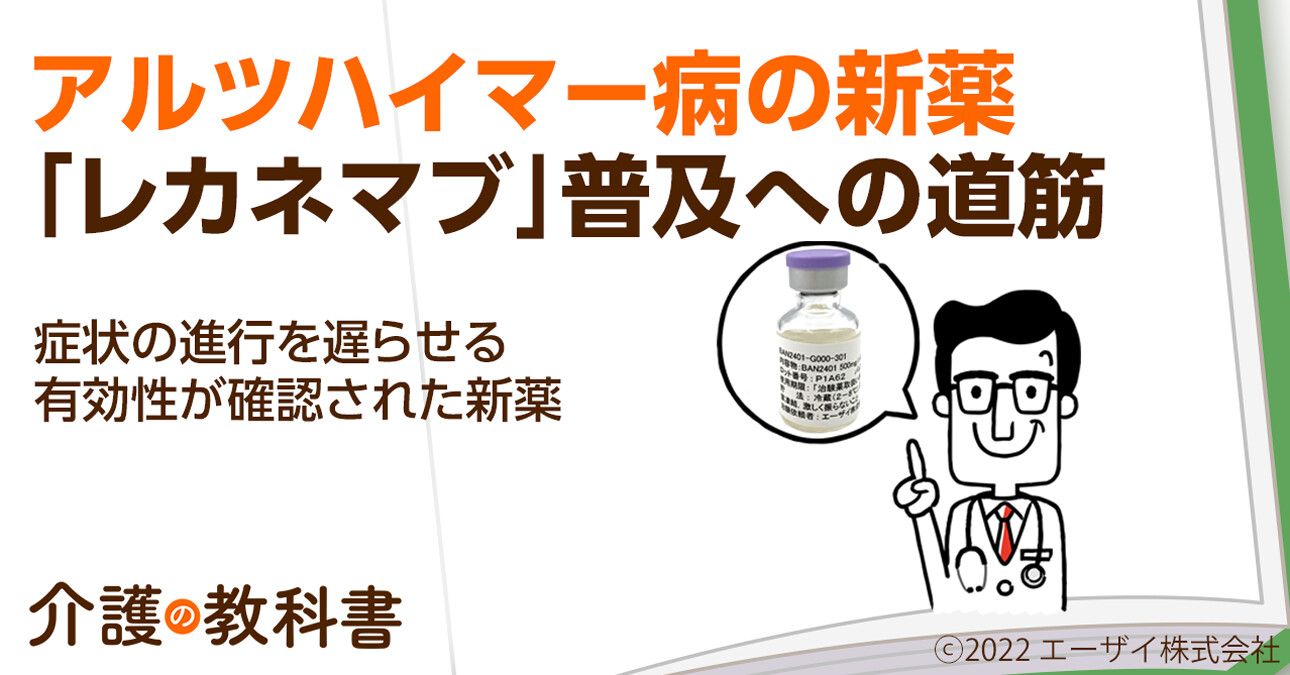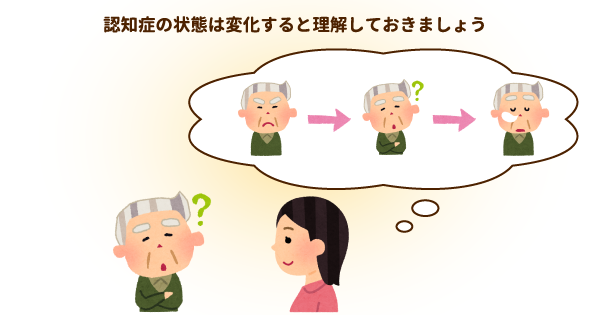株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
認知症の状態は、新しいことを覚えるのが難しいと言われることがあります。
そのため、支援者のなかには、「何も覚えられないから」「できないから」と、認知症の方に何もさせないようにする方もいます。
しかし、同じことを地道に繰り返すことで、新しい環境や習慣をインプットし、自分の力でできること、わかることを獲得できる認知症の方もいます。
今回は、そんな繰り返しの支援についてお話しします。
グループホームに入居したみやこさんの事例
繰り返しの支援のお話をするために、ひとつの事例を紹介します。
僕がホーム長を務めていたグループホーム(認知症対応型共同生活介護)に、みやこさんという女性が入居していました。
彼女がグループホームに入居して半年が過ぎた頃のことです。
ひとりで牛乳を買い物に行くみやこさんの事例
介護職員:「みやこさん、牛乳を2パック買ってきていただいてもいいですか?私、掃除をしなくちゃいけないもので」
みやこさん:「いいわよ。私が買ってきてあげる」
介護職員:「ありがとうございます。助かります」
そして、財布と牛乳2パックと書かれたメモを持って玄関を出ていくみやこさん。
職員はみやこさんに気づかれないように後を追いかけます。
実は掃除をするというのは、職員に頼らず自分の力だけでみやこさんがスーパーに行くための口実で、職員はいざ何かあったときに助けられるようにみやこさんを見守ります。
そんななかみやこさんは、道に迷うことなく無事にスーパーにたどり着き、店員さんに牛乳の場所を尋ね、会計も無事に済ませ、帰り道も迷わず、グループホームに帰ってきました。

みやこさんが買い物に行けるようになった背景
入居した当時のみやこさんにとって、グループホームが所在する街は、見知らぬ場所でした。
みやこさんはご主人が他界され、一人暮らしをするようになってから数年後、薬を飲んだことを忘れてしまって何度も病院に行ったり、ヘルパーさんが来たことを忘れてしまうといったことがあったので病院で検査を受けると、診断はアルツハイマー型認知症。
それでも頑張って一人暮らしを続けていましたが、訪問販売に騙されるなどの被害に遭い、安心を求めて「私ここに住むわ」とグループホームへの入居を決断しました。
しかしそれは彼女にとって安心を手に入れたと同時に、住み慣れた街を離れ、見知らぬ街に身を置くことになったということだったのです。
そんなみやこさんは当時、職員にピッタリと張り付かれることなくひとりで外出する「ごくふつうの姿」は彼女から失われていました。
そこで介護職員は、こんなアプローチをかけていました。
介護職員:「みやこさん、牛乳がなくなったので、一緒に近所のスーパーへ買いに行きませんか?」
みやこさん:「はいはい、いいですよ」
こうしてみやこさんは、介護職員と並んで近所のスーパーに出かけていきます。そして、同じ日の夕方。
介護職員:「みやこさん、夕飯の買い物に近所のスーパーへ行くんですけど、一緒に行きませんか?」
みやこさん:「はいはい、行きましょう」
今度は夕飯の材料の買い出しに出かけ、牛乳を買いに行った昼間と同じ道を通ってスーパーに向かいます。
このようにみやこさんと介護職員はほぼ毎日、ときには他の入居者さんと一緒に、雨が降っても風が強くても、同じコースで買い物に出かける日々を繰り返していきました。
そして少しずつ、スーパーまでの道のりを見慣れた景色、通い慣れた道として身体で覚えていき、スーパーを使い慣れた社会資源とし、顔を合わせるスーパーの店員さんとの間に慣れ親しい人とのつながりを持ち、見知らぬ街を住み慣れた街としていったのです。
そして半年。みやこさんは職員にピッタリと張り付かれることなく、ひとりでスーパーに牛乳を買いに行けるようになりました。
つまりみやこさんは、ひとりで外出する「ごくふつうの姿」を取り戻したのです。
“慣れ”はインプットすることができる
この事例からもわかるように、みやこさんは住み慣れた街を離れてから半年かけて、転居先のグループホームがある街を職員と歩き、新しい環境に慣れていきました。
住み慣れた街を離れることは、寂しいといった心情だけの問題ではなく、住み“慣れた”(違和感がなく、通常のこととして受け入れられる状態)を手放すことでもあります。
見慣れた景色、通い慣れた道、使い慣れた社会資源、慣れ親しんだ人とのつながりなどを失うため、日常生活に支障をきたす状態になりやすいのです。
さらにみやこさんはアルツハイマー病を罹患し、認知症(脳の器質的な変化により記憶機能やその他の認知機能が低下し、日常生活に支障が生じる状態)ですから、見知らぬ街(新しい環境)に身を置くことはより一層、日常生活に支障が生じる度合いが高まる可能性が高いわけです。
そこでみやこさんは、見知らぬ街を住み慣れた街にするために、半年かけて「慣れ(景色・道・社会資源・他人など)」をインプットし、住み慣れた街づくりをしたのです。

できないと決めつけずに取り組むことが大切
認知症の方なら誰でも半年で慣れをインプットできるかといえば、そうではありません。
もっと時間が必要な方もいれば、半年もかからない方だっています。
また、認知症の状態によっては、そもそも慣れをインプットすることができない方、インプットできたとしても、アウトプットした際の行動や表現が上手くいかない方もいます。
これは、慣れをつくる支援だけでなく、支援全般において認知症の方を画一的に考えるのは間違っているということです。
一方で、認知症の方を“みんな”新しいことをインプットできない(何も覚えられない)人と思い込むのも間違いです。
「覚えられないから」「わからないから」「できないから」という決めつけは、「何もさせない」「何もやらせない」ことになり、機能や能力の回復・維持を“支援する側ができない状態”にさせる可能性があるからです。

繰り返しの支援の課題
改めてですが、みやこさんの見知らぬ街を住み慣れた街とする支援は、同じコースで、同じスーパーに出かけることをほぼ毎日“繰り返した”わけです。
人は新しい仕事、道順など繰り返すことで慣れ、覚えていきます。
そして彼女は新しいことに慣れる(インプットする)ことが苦手な認知症の状態にあったので、“繰り返しの強度を高める”=繰り返し続けたわけです。
これは日常の生活行為(食事・排せつ・整容<着替え、洗面、歯みがき、整髪など>・移動・入浴など)も同じで、人は繰り返すことで機能や能力を獲得・維持することができ、繰り返すことで機能を取り戻す可能性もあります。
ただ、繰り返しの支援は、“続けることの難しさ”があります。
まず、同じことを続けるので根気が必要です。
また、入居型施設では人員配置の課題があります。
僕がホーム長を務めていたグループホームは「1日あたりの人員(日中の時間帯に入居者3:介護従業者1以上の比率)で配置」というグループホームの人員配置基準(結果、9人の入居者さんに対し介護職員2~3人で支援)だったため、その他の支援も含め、満足できるだけの繰り返しを提供できるわけではありませんでした。
そのため、繰り返しの支援を十分に実践するのが難しい、という介護施設も多いと思います。
さらに、人には感情があります。
認知症の方が「やりたくない」「今日は嫌だ」と思っているまま職員が無理に“やらせる”のは、本人にとっては苦痛でしかありません。
繰り返しの支援(に限らずですが)は、まず本人のなかに「やるよ」「やってみたい」といった能動的(進んで物事をしようとするさま)な感情を作ってあげることがスタートなのです。