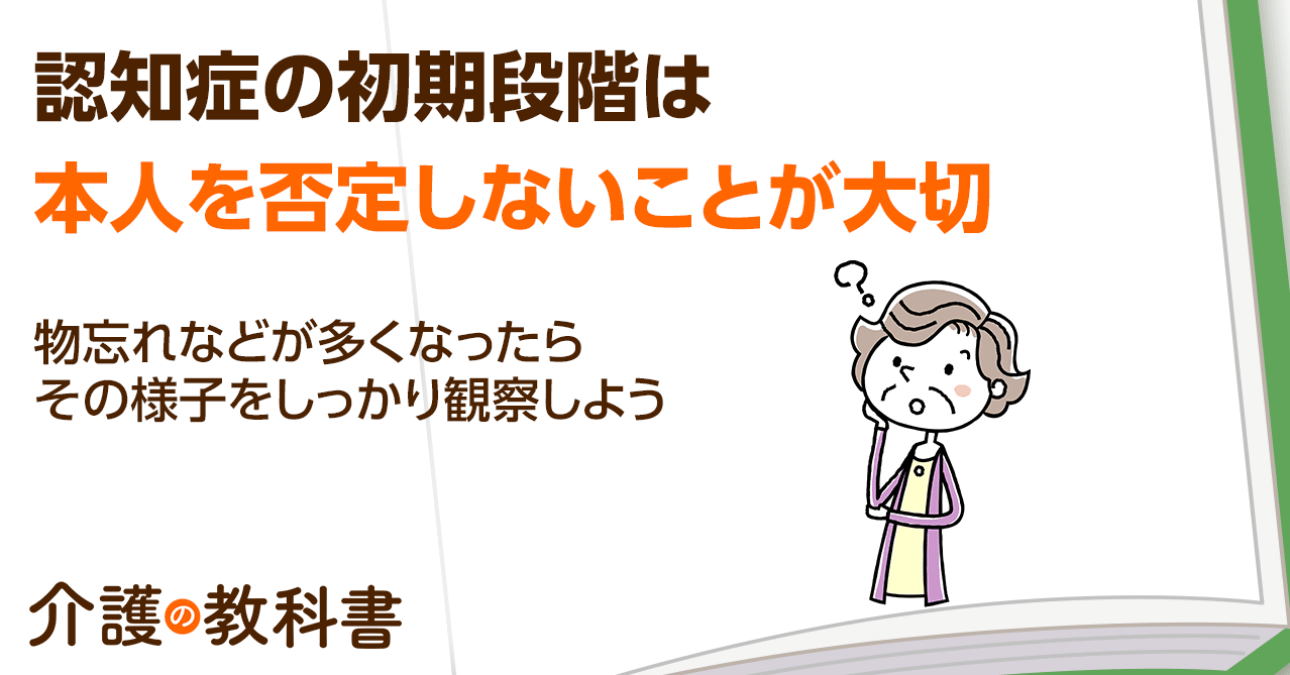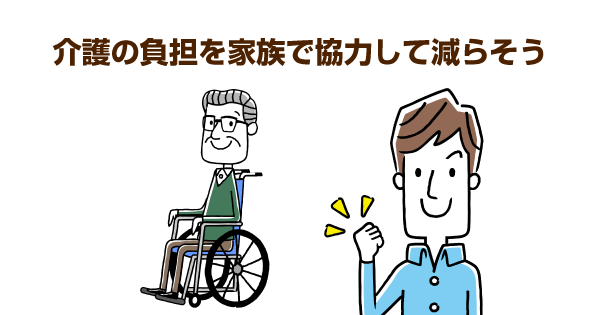要介護者の家族が、自宅で介護をするケースは多くありますね。
そんななかでも、認知症の方を介護する家族の前にはいくつもの壁が立ちはだかる、と私は思うのです。
その壁は、障がい者が自身の障がいを受け入れるまでの過程とよく似ているように思います。
今回は、その壁を順に見ていき、家族はどう向き合えば良いのかを考えていきましょう。
「ショック」の壁との向き合い方
家族が認知症になったとき、介護者は大きなショックを受けてしまうことになるでしょう。
これは冷静に考えれば当たり前で、自分の家族が認知症になって喜ぶ人などいるはずはありません。
であれば、誰でもそうなのだと考えることで少しは気が楽になるはずです。
「否認」の壁との向き合い方
ご家族が認知症になった、というショックを乗り越えたあとは、家族が認知症になった事実を否認する段階に入るでしょう。
人によっては、この辺りからうまく介護サービスを利用すると良いかも知れません。
多くの人が、家族が認知症になる前の状態と、認知症になっている目の前の状態を比べる傾向にあります。
そして、その差を認めることができず十分な介護ができなくなるのです。
その点では、仕事で介護をしている介護職員などは、認知症になってからのその人しか知らないので対応がしやすいかもしれません。
この時期に限ったことではありませんが、介護者は自分の気持ちに正直に向き合って、余裕がないときは無理をせず、介護保険サービスなどを活用することが大切です。

「混乱」の壁との向き合い方
家族が認知症になった事実を否認する段階を過ぎると、家族が認知症になってしまった事実に混乱してしまう段階に入るでしょう。
否認の段階を上手く乗り越えることができれば問題ないのですが、そうとも限りません。
認知症になる前との差が大きければ大きいほど、家族は混乱を引き起こすのです。
この場合、どんなに差を埋めようとしても認知症になる前の状態は変えられないので、今の状態に対する認識を改める必要があります。
認知症になる前も後も知っているご家族としては難しいかもしれませんが、元からそういう人と新たに付き合いを始めていると考えてはどうでしょうか。
例えが悪いかも知れませんが、私たちは、赤ちゃんの言っていることが理解できなくてもその存在を大切にしますよね。
そんな赤ちゃんに対して「言っていることが理解できない」と腹が立つ人がいるでしょうか。
「理解できなくても何とかわかってあげよう」とみんな優しく声をかけると思います。
この「何とかわかってあげよう」という思いを認知症の人に向けるだけでかなり見方が変わり、良い対応ができるようになります。

「解決への努力」の壁との向き合い方
色んな葛藤を乗り越えたあとも、ご家族はより良い状況にするべく解決への努力をする段階に入るでしょう。
この段階までくると、認知症の方を受け入れる、受け入れないという段階を越えて、「とにかく介護しなくては」という思いに変わってきます。
ただ、ここでも決して無理をしないことが大切。
うまく介護サービスを使うことも必要ですが、個人的には介護者の集まりに行くことがおすすめです。
そこには、介護職員のような仕事で介護をしている人が参加している場合もありますが、認知症の家族を介護している人、つまり同じような立場にある人たちも来ている場合があります。
そしてその人たちの助言が何より力になるのです。

まとめ
ここまで説明してきたような経過を経て、要介護者の家族は要介護者を受け入れることができるようになります。
ただし、この経過には個人差があり、ショックを受けてもすぐ受容できる方もいれば、否認と混乱を行き来しながら苦しむ方などさまざまです。
それでも最終的には受け入れることが大切で、そうでないと被介護者を虐待するような事態に発展しかねません。
そんな最悪な事態を避けるためにも、うまく介護サービスを使っていくことが必要だと思います。
しかし、私たちのような介護を仕事としている者は、理屈だけの対応や話しかできません。
そのため、同じ立場にいる方と話ができる介護者介護者の集まりにも出掛けてみてください。
介護の本当の苦しみは、それを経験した人にしかわからない。
どこかの集まりで私が聞いたその言葉は、今も頭から離れません。