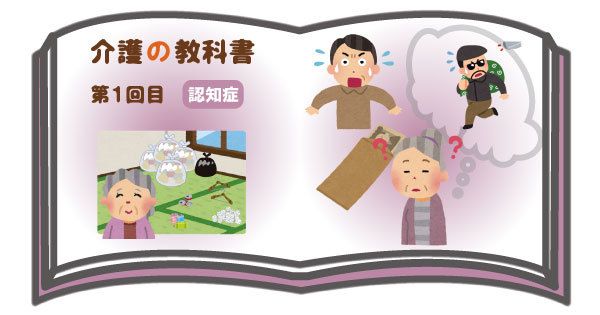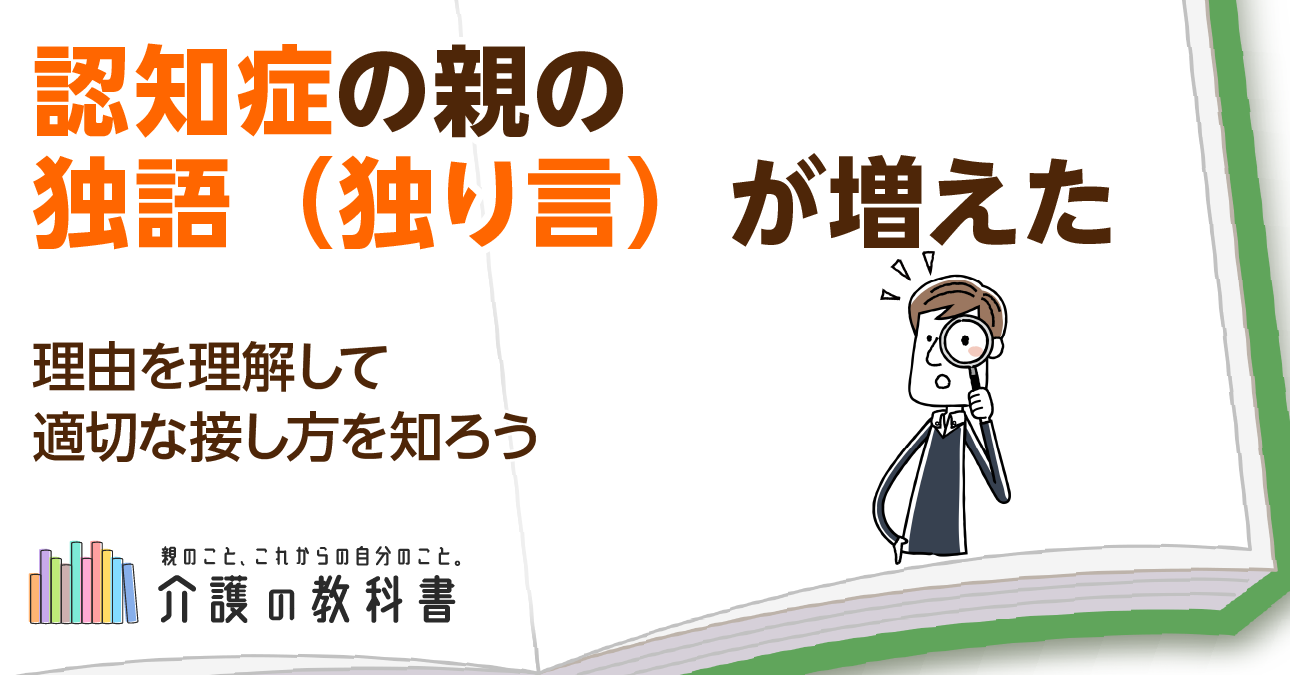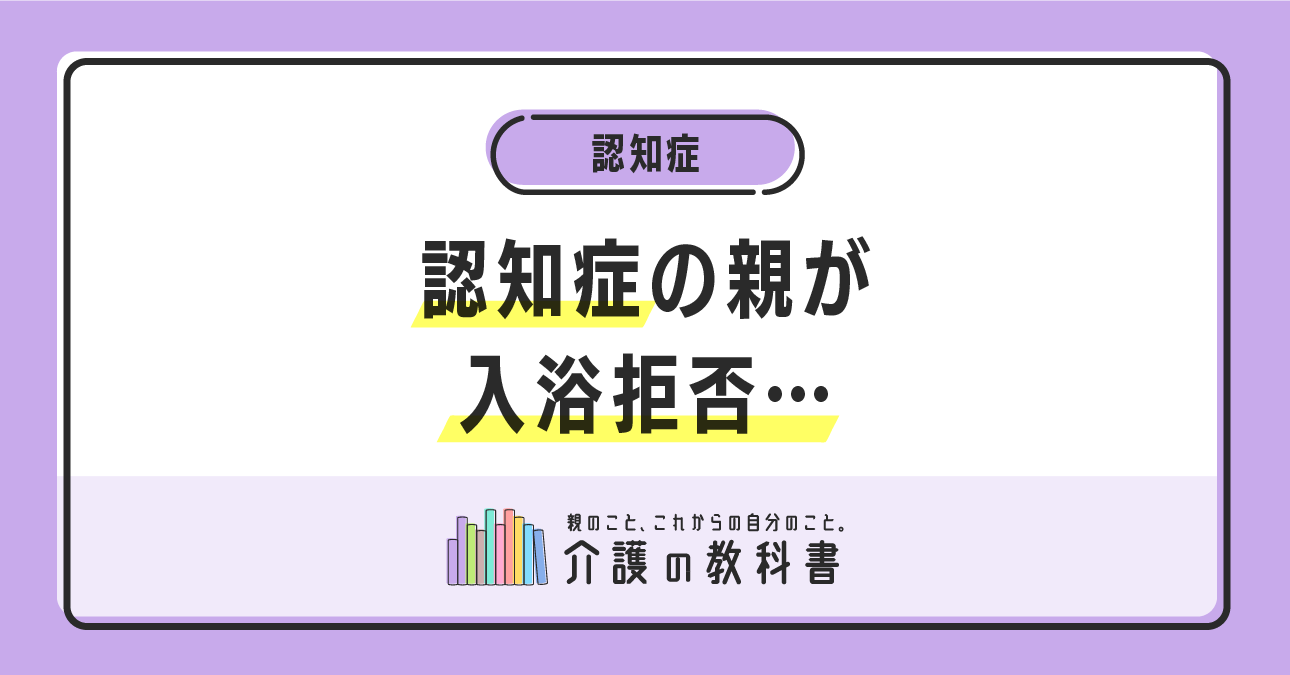みなさん、こんにちは。デイサービスで看護師として勤務している、認知症LOVEレンジャーの友井川 愛です。
認知症の症状や問題行動には個々人によって差があり、「葛藤型」「遊離型」「回帰型」の3つに分けることができると言われています。
その3つについて、これから3回の記事に分け、それぞれの対応方法についてお話しします。
今回のテーマは葛藤型の認知症の方への対応です。
葛藤型の方は自分の理想像をしっかり持っている
葛藤型とは?
認知症の症状によって、今まで自分でできていたことが思うようにできなくなり、本来あるべき自分のイメージと現実がかけ離れてしまったことに納得できず、何とか自分を取り戻そうとしているタイプを言います。
老化現象や身体障がいなどにより、介護者の手を借りなければ生活を送ることが難しくなったという事実を受け入れられないため、どうにか前の状態に戻りたいという葛藤が生まれるのです。
どんな人が葛藤型になりやすいのか
葛藤型の方に多い傾向としては、自分の考えをしっかり持っているような方だと感じています。
若い頃から社会の第一線で活躍するような方が多く、しっかりと自分の目標や理想像を持っているような方ですね。

葛藤型の特徴とは
葛藤型の方は、リハビリを一生懸命に頑張ることができ、効果があるとさらに頑張ろうと思ってまた努力をするような、ひたむきな方が多いように思います。
ただ、一生懸命さの反動により、物事がうまくいかなくなるとモチベーションが下がり、情緒不安定に陥ってしまいやすい方も少なくありません。
また、介護者の何気ない言葉に反応し、興奮して粗暴行為をしてしまうことがありますので、注意が必要です。
もし粗暴行為がある場合は、無理に抑制したり隔離したりなどせず、過剰に接しないようにしましょう。
そのほか、葛藤型の方にある問題行動としては、異食行為や被害妄想などもみられることもあります。
葛藤型の方との関わり方
葛藤型の方は何を考えているのか?
葛藤型の方は、介護者の手を借りて生活している現状を受容できず、自分にとって理不尽な現実と戦っている状態です。
そのため、介護者に対して"見返してやりたい"などの思いを持っていることがあります。
このような葛藤を軽減していくには、人と会話したり役割を担ったりして現実の自分を再発見し、受容していくことが大切です。
それでは、葛藤型の方を介護するときはどのように接すれば良いのでしょうか。
信頼関係を構築しましょう
葛藤型の方は、自分自身に対して憤りを感じており、そんな気持ちを受け止めてくれる介護者を探しています。
つまり、本人が自分を容認することができない代わりに、介護者が本人を認めてあげることが大切なのです。
そのためにも、"元気だった頃のご本人"と"今目の前にいるご本人"の両方を理解してくれる介護者がいることで、落ち着かせることができる場合があります。
このような傾向から考えると、相性が良いのは同年代の方、もしくは似たような経歴を持っている方かもしれませんね。
また、葛藤型の方は複数の介護者で関わるよりも、一人ひとりに関係を求める方が多いように思います。
もし被介護者が葛藤型の方だな、と思ったときには、その方の努力や生い立ちを肯定するような対応で、関係を築いてみてください。
役割を作りましょう
葛藤型の方は、自分の役割を見つけ、それを果たすと精神的に安定することがあります。
自信があった頃の自分に近づくことによって、自信の回復につながるのです。
そのため、現在の身体状態でできることで、かつ周囲の方が一目置いてくれるような役割を担ってもらいましょう。

葛藤型の方の事例と対応
最後に、これまでの葛藤型の方の特徴と対応方法を踏まえて、Aさんの事例をみてみましょう。
Aさんは会社の社長をしていましたが、ある日、脳梗塞で倒れて血管性認知症と片麻痺の状態になりました。
Aさんには2つの悩みがありました。手足に麻痺があったため、以前のように手足が自分の思うように動かないこと、そして記憶障害によってときどき何かを思い出すのに時間がかかることです。
リハビリに挫折したAさん
Aさんは入所した当初から、一生懸命リハビリを頑張っており、少しずつ効果が出ていました。しかし、時間が経つにつれて自分が想像していたような劇的な回復ができないのではと、後ろ向きに考えるようになりました。「頑張りましょう」と声をかける理学療法士に対して、リハビリへの熱意が薄れていくAさんから暴言が聞かれるようになりました。

また、Aさんが日課の新聞を読んでいるときにも、コミュニケーションをとろうとしたスタッフに新聞の内容を尋ねられ、激高したことがありました。血管性認知症により、すぐに内容を答えられなかったことを馬鹿にされたと思ったのです。
それ以来、食事以外は自分の部屋で過ごすようになり、スタッフや他利用者とのコミュニケーションを嫌がるようになりました。
Aさんにどう対応すれば良いのか?
このような状況になった原因は、スタッフや理学療法士が本人の気持ちを理解していなかったことにあります。
残念ながら、脳梗塞後に麻痺が残ることは珍しくありませんし、どんなに早くリハビリを始めても、完全に元の状態に戻るのは簡単ではありません。
しかし、残存機能を活かした生活を送るようにすることはできます。
治していくだけではなく、生活できるようにしていくこと。それこそが医療と介護の違いなのです。
介護は"これ以上は回復しない"という状態になっても、普通の生活を送ることができるようにお手伝いします。
このことを踏まえて、例えばリハビリに前向きに取り組めなくなったAさんの事例の場合は、きちんと本人と話し合い、気持ちを聞いたうえでリハビリの目的や効果を伝えるべきでした。
そうすれば目標を再設定して自分なりの目標を達成し、熱意を失わずにリハビリを継続できたかもしれません。
本人の気持ちを引き出すには、真摯に向き合い、信頼関係を築くことが大切ですね。
次にスタッフですが、Aさんがなかなか記憶を思い出すことができない事情は知っていたわけですから、不用意な言葉かけをするべきではありませんでしたね。
しかも、施設には他の利用者やスタッフがいるため、人前で恥をかかされたと本人が思うと、自尊心も傷つけられてしまいます。
また、Aさんは元気な頃、会社の社長をしていたので、社員を束ね、バリバリ仕事をされていた経歴があります。
そのため、Aさんを以前の立場に近づけて、Aさんの自尊心を守るような環境を作ることが必要です。
例えばAさんの場合は、レクでのリーダー的存在になってもらうことで周囲から一目置かれるように工夫したのが良かったと思います。
また、スタッフにもいろんな方がいるため、Aさんに年の近い男性スタッフがコミュニケーションをとり、信頼関係を築自分を理解してもらえた事でAさんは少しずつ落ち着きを取り戻したのでした。
最後に一言
認知症の症状や老化、障害と、高齢者になって今まで経験したことがない生活を余儀なくされた場合、多くの方が“以前の状態に戻れない”自分自身に対しての葛藤が生まれます。
その苦しい状況を正しく理解し、寄り添うことが介護者に求められているのです。
次回は「回帰型」についてお話しします。