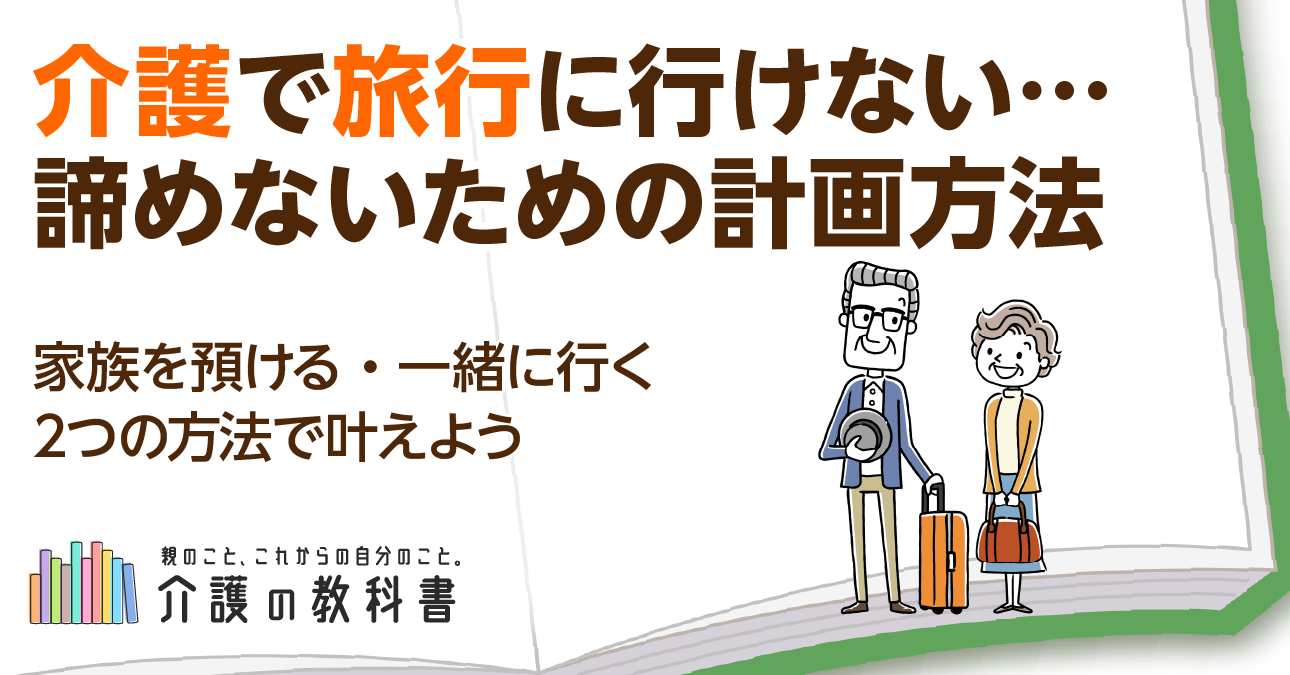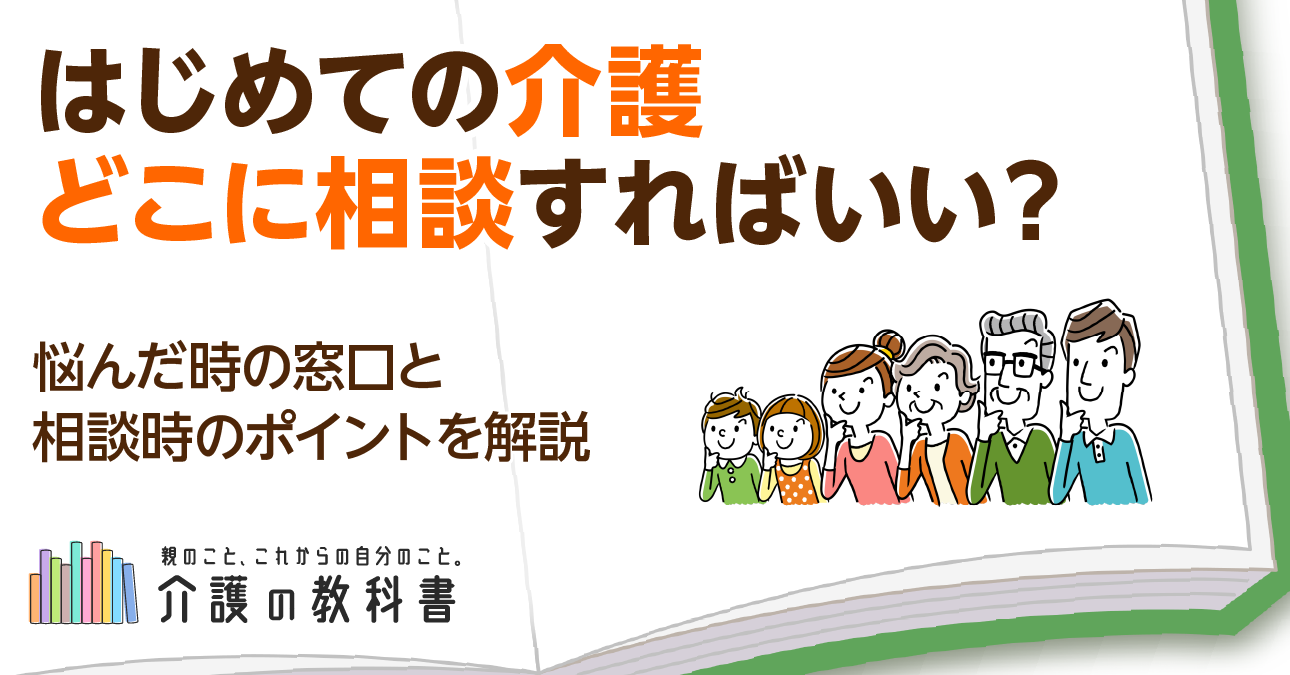株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
今回は、介護施設における身体拘束をテーマに書いていきます。
身体拘束が当たり前だった時代
今から22年前、僕が特別養護老人ホームの生活指導員として面接に伺った病院や施設で、こんな光景を目の当たりにしました。
便を弄り、他の患者さんに迷惑をかけるからと、ベッド柵に手足を縛られている認知症の状態にある女性。
大量の向精神薬を飲まされた彼女の目はうつろで、天井を見つめたまま動きません。
また、立ち上がって歩き出してしまうと転倒する危険があるからと、Y字型拘束帯で車椅子に縛られていた男性。
それでも立ち上がろうとする彼は車椅子ごと前のめりに転倒する可能性があるので、車椅子も壁の手すりに括りつけられていました。
そして僕自身は25年前、当時寮父(介護職員)として勤めていた入居型施設の入居者の方々に、自分でおむつを外すことができないようにつなぎ服を着せていました。
僕がこの業界に入った当時(1996年)、多くの介護現場では「かわいそうだけど…」と思いつつも、拘束帯・つなぎ服・施錠による隔離などが身体拘束に含まれるとは思っていなかったため、それらの行為を当たり前ように行っていました。
また、拘束の理由は「事故防止・安全確保のため」というのは建前で、介護・看護にとって「迷惑・面倒な行為をさせないため」というのがほとんどでした。
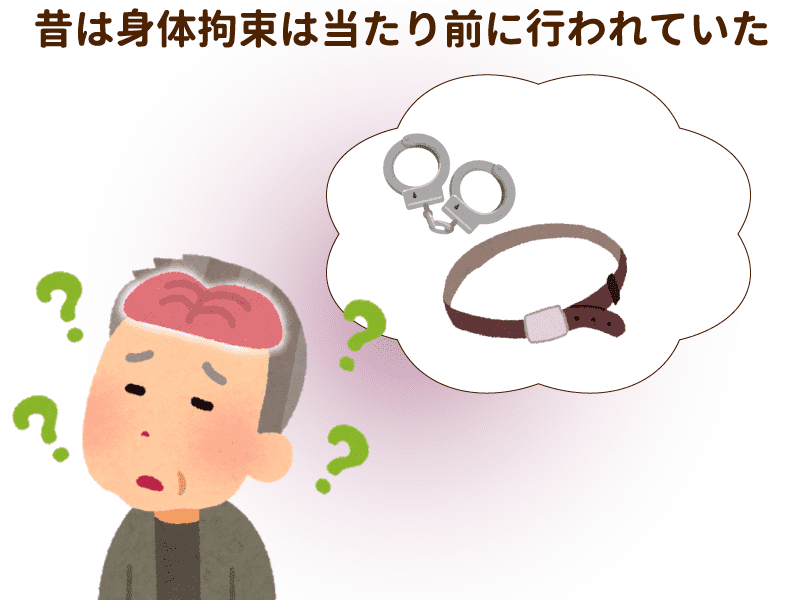
時を経て1999年3月、厚生省令において「生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行なってはならない」と身体拘束禁止が規定され、やむを得ない場合とは、次の3つの要件がみたされている場合とされました。
- 切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
- 非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がない
- 一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものである
また、三要件を満たす場合でも、以下の慎重な手続きが必要となっています。
- 「緊急やむを得ない場合」に該当するかを施設全体として判断する(判断は担当のスタッフ個人、または数名では行わない)
- 利用者本人や家族に対してできる限り詳細に説明する
- 要件に該当しなくなった場合には直ちに解除する
さらに、介護保険の運営基準には「身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむをえない理由を記録しなければならない」ことが定められています。
このように今では、身体拘束を行うのは緊急やむを得ない場合であり、その場合でも切迫性・非代替性・一時性の三要件を満たし、さらに慎重な手続きを行い、記録を残す…という当たり前のことが、2000年の介護保険施行前では当たり前ではなく、身体拘束を行うことそのものが当たり前のことだったのです。
僕も、決まりだから、上司・先輩に言われたからという理由だけで、入居者さんにつなぎ服を着せていました。
しかし、現在の介護現場では「身体拘束はしてはいけないこと」という意識が浸透しています。
身体拘束を無くすために介護現場で行われたこと
身体拘束について、やってはいけないことだという認識が一般的になったものの、それでも介護現場における不当な身体拘束や虐待は未だに取り沙汰されています。
国も介護施設での不当な身体拘束を防止しようと、「2018年介護報酬改定」で身体拘束廃止未実施に対するペナルティを強化しました。
そういった現実を踏まえ、「不当な身体拘束の根絶には至っていないじゃないか」と言われれば、確かにそうだと思います。
ただ、僕と同じ支援専門職の先人たちが、身体拘束を無くすことに尽力した事実があったことも、忘れてはいけません。
例えば、僕が介護の仕事に就いた25年前、多くの施設でつなぎ服を着せられた入居者さんをたくさん見かけましたが、現在の介護現場でそのような方を見かけることはほとんどありません。
弄便防止のために誕生したつなぎ服ですが、先人方は弄便防止のために安易につなぎ服を着せるのではなく、そもそも「なぜ便をいじるのか?」というもっとも大事な視点を持って弄便の原因をとことん追求しました。

そして、排便のリズムをつかんで、排便する前にトイレ誘導をする、排便したらすぐにオムツ交換をするといったことを実践し、結果、つなぎ服は介護現場からほぼ姿を消したのです。
この取り組みは、「今、目の前で起きていることは何が原因で起こっているのかを探り、さまざまな事実を把握して検証し、課題を明確にして支援策を見出すこと」から成り立っています。
僕は、これこそが支援のプロ(専門職)のあるべき姿であり、専門性だと思っています。
というのも、目の前で起きていることの原因を探らず、ただ「縛る・閉じ込める」といった手段をとることに、専門性は必要ないからです。
身体拘束をしないだけでは無策と同じ
介護現場において、身体拘束に頼らざるを得ない瞬間(緊急やむを得ない場合)が存在することは否定しませんが、厳守しなければならないのは「切迫性」「非代替性」「一時性」の三要件であり、さらに、「カンファレンス」「説明と同意」「身体拘束の記録」「拘束解除のための検討」といった慎重な手続きです。
特にカンファレンスと拘束解除のための検討という事項については、専門職が集まっている施設・事業所だからこそ、専門職が結集してとことん知恵を絞り、支援策を見出してほしいということを示しているわけです。
それをすることもなく、安易に身体拘束を解決策(になっていませんが)としてしまうなら、それは介護の専門職に求められている専門性に裏打ちされた仕事をしていないということだと思います。

また、求められている手続きを踏まずに身体拘束を行う施設・事業所があることも耳にします。
このような施設がある限り、プロによる介護への社会的信用を得ることはできません。人手不足が叫ばれる介護業界ですが、「人手が足らないから守るべきことを守らなくて良い」というものではないはずです。
さらに、安易な身体拘束を行ってしまう施設・事業所が存在する一方で、身体拘束はしないが代替の支援等についても考えていない・実行していない施設・事業所が存在します。
これは、身体拘束はしないというスローガンに自己満足しているだけで、言わば無策です。
安易な身体拘束と同様、理想を掲げているだけの安易な無策も、介護のプロが行うべき仕事とは言えないと思います。
- 専門職でしか考えつかないような支援策を見出すことができる
- 「もう無理。他に支援策はない」と言い切れるまで思考と試行を重ねる
そんな支援専門職の専門性を発揮した仕事(っぷり)を通じて、身体拘束という非人道的な策からの脱却を目指す。
これまでの身体拘束の歴史を踏まえ、今は、そしてこれからは、その時代なのです。
次回も「介護施設における身体拘束」をテーマにお話しします。