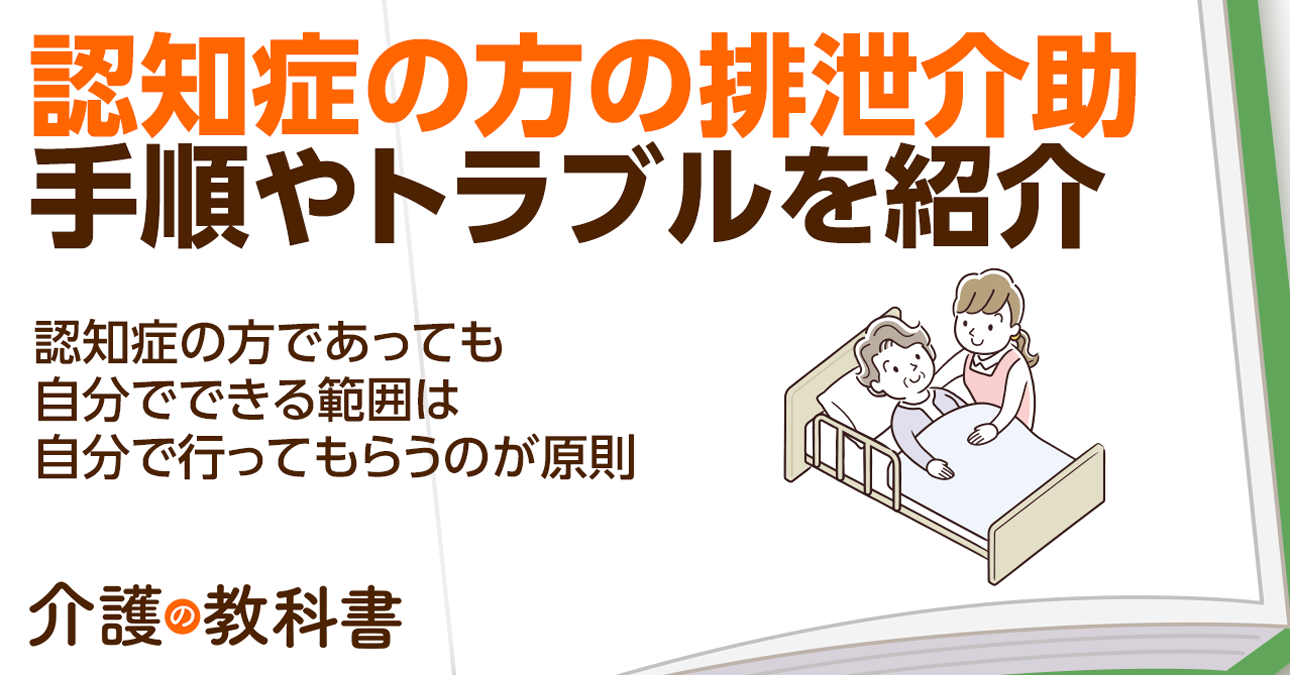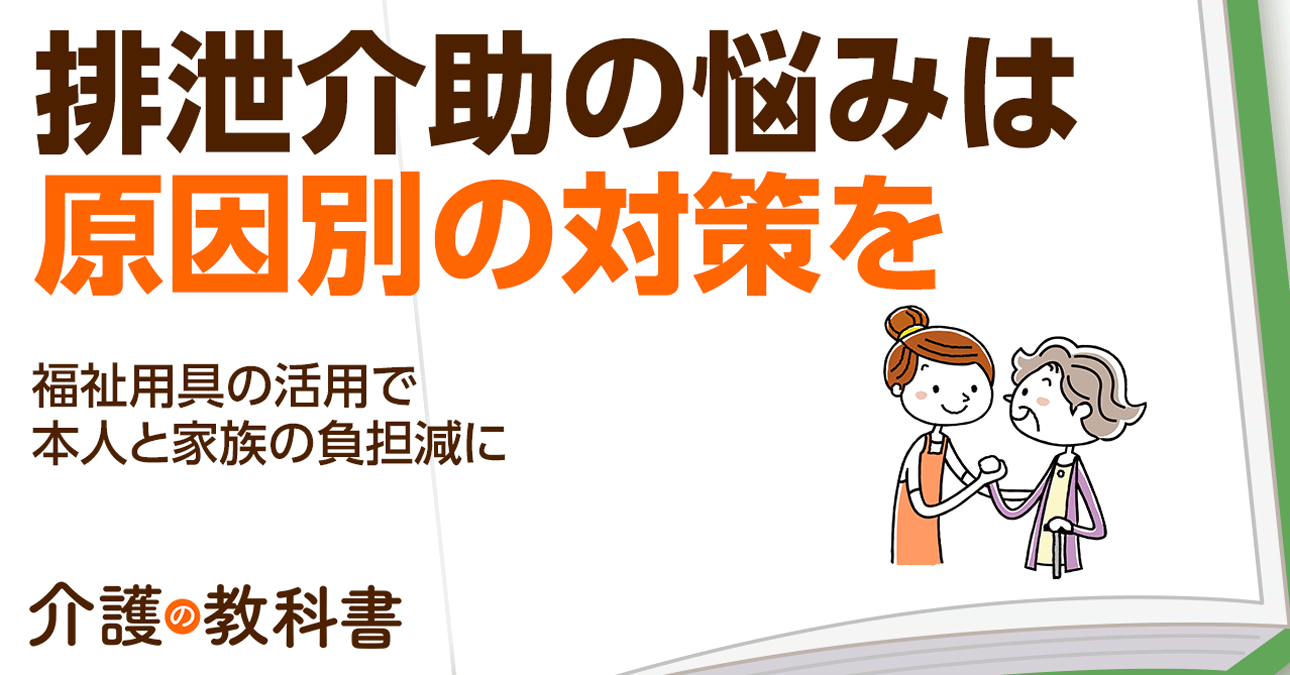こんにちは。デイサービスで看護師として勤務している、認知症LOVEレンジャーの友井川 愛です。
今回は、認知症の方と切っても切り離せないトラブルのひとつ「認知症の方の便秘」についてお話ししたいと思います。
まず、介護をしているみなさんに知っていてほしいことは、年をとったり認知症になると神経の伝達は遅くなるかもしれませんが、便意そのものはなくならないということです。
認知症の症状で便意を訴えることができない方もいるため、介護者が気を配ることはとても大切なのです。
排泄最優先の原則とは
私が介護職になってすぐ先輩に教えて頂いたのは、「排泄最優先の原則」でした。
どんなものかというと、他の介助を行っている最中でも、排泄の訴えがあれば必ず「排泄ケア」を優先しなさいというものです。
認知症の方に限らず、便意はコントロールが難しく、そして本人の「トイレに行きたい」という意思を尊重をするためにも、この原則はとても大切なのです。 
繰り返しになりますが、認知症の方にも便意はあります。
そして、言葉で訴えることができない認知層の方の場合、落ち着きがないといった様子などから介護者が便意を察知する必要があります。
そのため介護者は、普段から認知症の方の行動をよく観察しておくことが大切ですね。
認知症の方が便秘になる原因と改善策
認知症の方が便秘になる要因は、人によってさまざまなのでいくつか解説しますね。
1.身体活動の低下
人の身体は、何かを食べたときの刺激によって、蠕動(ぜんどう)運動を始めます。
その運動によって便が直腸まで送られ、便意を催すのです。
しかし、高齢者になると蠕動(ぜんどう)の動きが弱くなりやすいので、日中はなるべく活動したり、手始めに運動してみることをおすすめします。
2.水分摂取量の低下
水分不足になると、便が出しづらくなると言われています。
高齢になってくると喉の渇きを感じにくくなったり、夜間のトイレを気にすることで、水分を摂取しないようになります。
さらに認知症の方のなかには、テーブルに置かれている飲み物を「飲み物」だと認識できない場合もあるため、介護者の方から声かけをすることで水分摂取してもらいましょう。
本人が好んでいる飲み物があるなら、それを主におすすめするようにして、たまに他の飲み物をおすすめするという方法もあります。
3.食事量の減少
認知症になると、毎日の食事量が減少したり、食事内容が偏る傾向があります。
また、認知症の方のなかには食べ物を認識できなかったり、バランスの良い食べ方が わからなくなってしまう場合も。
食事量が少ないと、腸のなかに便として押し出すだけの量が足りなくなってしまい、排便まで行きつかないことがあります。
こうして便塊(べんかい。便の塊のこと)が少しずつ腸内に留まってしまうことで、便秘になってしまうのです。
この場合の対策としては、腸の動きを良くしてくれる発酵食品や、水分を多く含んだ食べ物を摂取できるようにサポートしてみましょう。
4.服用しているお薬の副作用
認知症の方の場合、服用している向精神薬の副作用から便秘になるケースもあります。
新しいお薬を服用してから便秘になったという場合は、医師や専門家に相談してみると良いでしょう。

下剤が要因にもなる
そもそも、どれくらい排便がないことを便秘とするのかについて、私は個人差があると思っています。
3~4日排便がないと病院や施設の現場では、職員がみな当たり前のように「排便がない」と大騒ぎになり、下剤の服用、浣腸、摘便を横行します。
また、認知症の方のなかには毎日のように下剤を服用している方もいます。
しかし下剤を服用するということは、薬で無理やり直腸に異常収縮させるので非生理的な排泄になるのです。
下剤で排泄を繰り返すと排便反射での生理的排便ができなくなってしまうため、私は習慣的な下剤の使用をおすすめしたくないのです。
高齢者の方の多くは、直腸性便秘(習慣性便秘)と言われているため、まずは生活リズムを変えることが大切だと思います。
では、具体的にどうすれば良いのかというと、まずは「認知症の方が便意を訴えたらすぐにトイレへ誘導する」という、当たり前の事を行ってほしいと思います。
認知症の方の自然な排便のタイミングを逃し、そのうえで下剤に頼るというのは、あまり良い対応とは言えません。
また、排便の周期には個人差があり、毎日する方や3日に1回するのが当たり前という方もいると思います。
もし下剤の使用について悩まれている方は、排便の頻度を記録したうえで、医師に相談してみるのも良いでしょう。
排泄する姿勢やタイミングも大切
便意を催しているのに排便できない…というときがあると思います。
そういった場合は、排泄時の姿勢がとても重要です。
まず、洋式トイレであれば、きちんと座ってもらいましょう。
座ることで重力が排便を手伝ってくれるのです。
そして、腹圧がかかることで自然と踏ん張ることにつながります。
もし踏ん張りにくそうなら、足元に台などを置いてみると自然に前かがみの姿勢ができます。 
次に、トイレ誘導のタイミングです。
いつトイレに誘導するのが良いのかというと、朝食を食べた後です。
なぜかというと、排便は交感神経よりも副交感神経が活発なときの方が出やすいとされているからです。
朝はまだ交換神経が働いておらず、朝食を食べることで副交感神経が活発になる為、トイレに行く習慣をつけていくと排便がしやすいそうです。
もし便意が感じにくい方でも、毎朝トイレに行き踏ん張ることを習慣づけると、便秘予防につながりますよ。
認知症の方はトイレの場所がわからない場合もありますので、トイレの場所がわかる目印や案内を文字にしてみることも必要です。
最後に一言
便意を感じられて落ち着かない認知症の方を、「問題行動」があると捉える方がいます。
認知症の方が「何をしたいのか」を察してあげられるように、普段から観察しておくことが大切ですね。