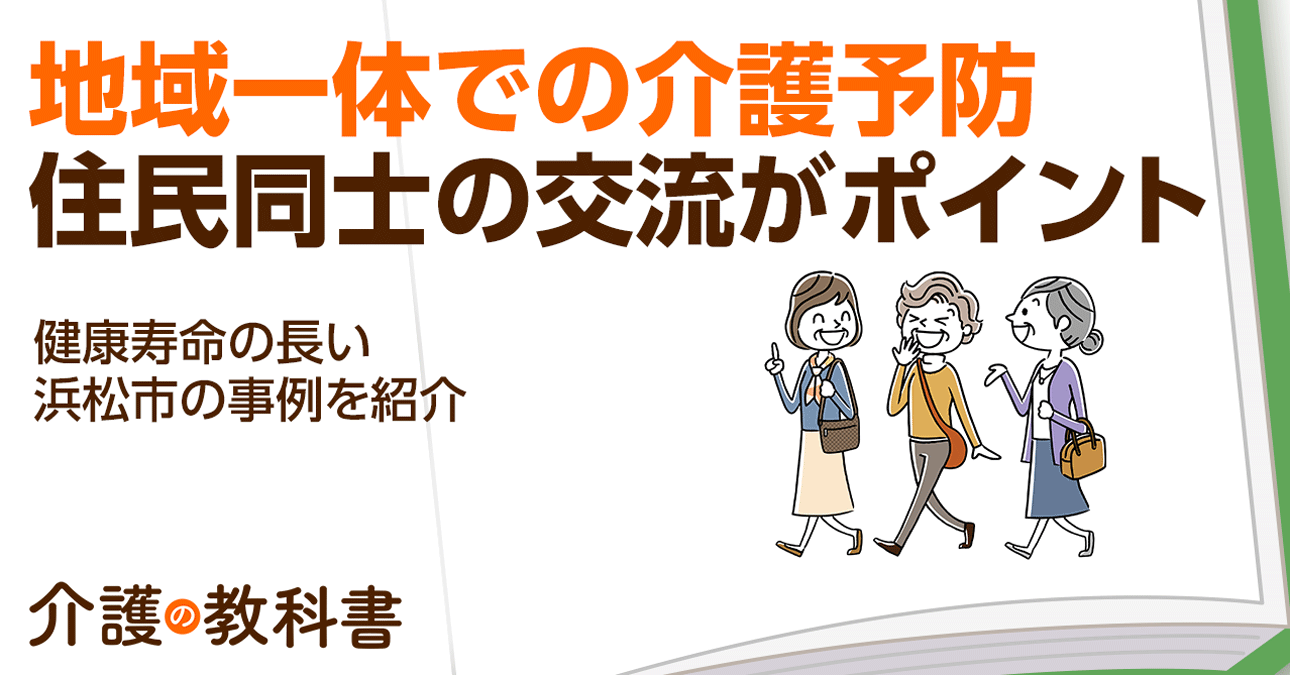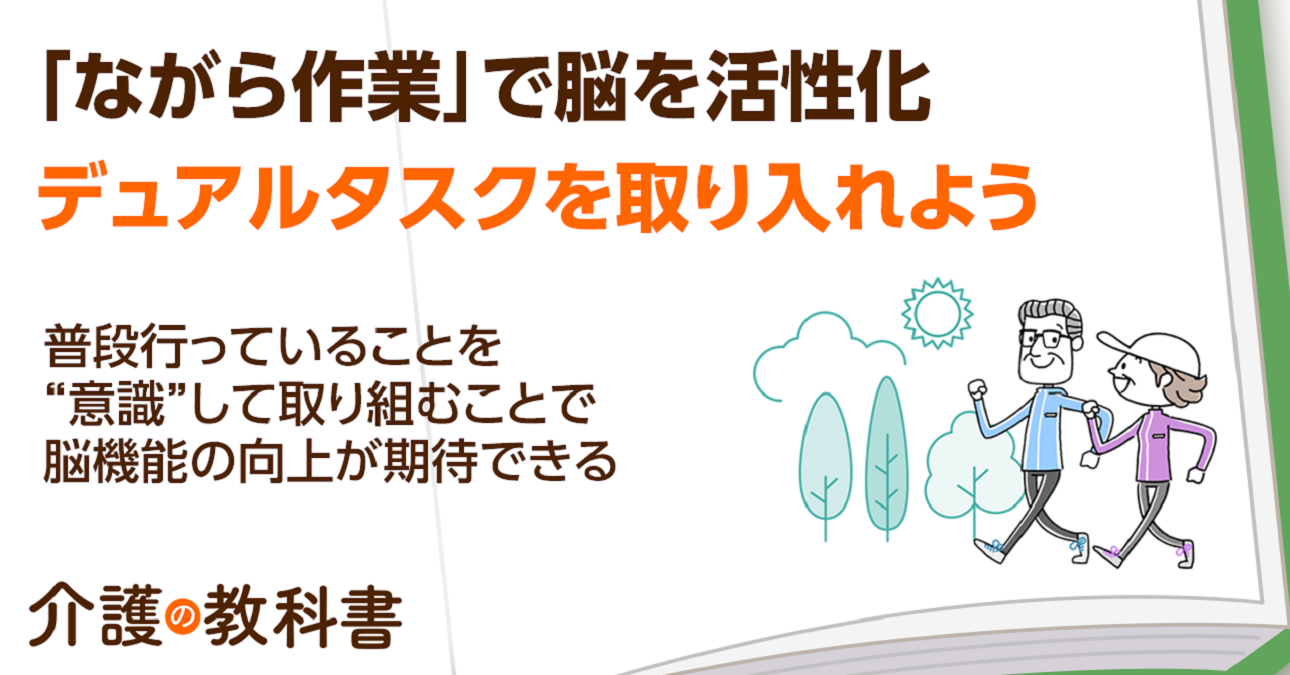こんにちは。一般社団法人元気人の理事・向川 誉です。当法人では、認知症ゼロ社会の実現を目指して、地域の認知症予防活動をサポートする「認知症予防活動支援士」の育成と支援に力を入れております。
以前、認知症は「怖い病気」「人生が終わる」などとネガティブなイメージで認識されていましたが、予防と対策を心がけることで、そうでもないことが理解されるようになりました。しかし、できることなら、認知症にならずに天寿をまっとうしたいものです。
認知症には、発症リスクを高める”危険因子”と発症リスクを下げる”抑制因子”の二つがあることがわかっています。認知症になるかならないかは、この二つの因子の勝敗によって決まるといえましょう。
もし戦いに勝とうと思ったら、敵を弱くするか、味方を強くするか、もしくはその両方が必要ですよね。認知症の場合、遺伝子や加齢など、自分では修正不可能な危険因子がありますが、修正可能な危険因子を減らし、抑制因子を増やすことで、認知症の予防や発症の先送りが期待できます。
では、具体的に「何を」「いつから」気をつけたら、抑制因子は危険因子に勝てるのでしょうか?
最も評価の高い世界五大医学雑誌の一つである『ランセット』に、認知症の発症リスクに関する発表が掲載されました。十分に信頼性の高いものとして、ライフステージごとに九つの危険因子が挙げられており、同誌の委員会によると、九つすべてを改善できれば「世界中の認知症の約3分の1が予防可能である」としています。この発表をベースに、今回は「認知症に対しての年代でわけた予防法」について、まとめていきたいと思います。
若いうちから認知症予防を!

誕生~30代(幼年期~青年期)
この時期から取り組める認知症予防としては「高等教育」があります。学ぶ時間が長いほど、神経ネットワークが強化されるので、認知予備力(認知力の蓄え)を高められると考えられているのです。
何十年後に脳に病変が生じたとしても、認知予備力がある分、認知機能が日常生活に支障をきたすレベルまで低下するのに時間を要し、その分認知症の発症を遅らせることができます。
ちなみに、ここでの高等教育とは、学歴(学業の経歴)という意味よりも、若いうちからどれだけ考えてきたか、新しいことにチャレンジしてきたかなど、頭を使ってきた経歴という意味合いのほうが強いです。そのため、「学校を出て、もう何十年になる」という方でも、今、頭をどれだけ使っているかが大切です。
また、生活習慣が確立されるこの時期には、「習慣力」(習慣を習慣化するために必要な能力)を身につけておきたいものです。習慣力は、一般的には「生きる力」ともいわれている「自己肯定感」「自制心」「やり抜く力」などが土台になっていますが、これは教育やしつけがもたらす、一生涯にわたる効果です。
認知症になる大きな原因の一つは脳血管障害ですが、そのほとんどは動脈硬化が原因で起こります。そして、その動脈硬化は10代からすでに始まっているといわれており、それを促進する喫煙や運動不足、過度な飲酒、偏った食事などは若い時期から避けたいですね。
「運動不足」は、認知症の危険因子の中でも特に危険度が高い言われていますので、若い頃から運動をして、運動意識や習慣をつけておきましょう。運動習慣は認知症の危険因子を減らしながら、抑制因子を増やす一石二鳥の予防法になります。目安としては一回30分以上の運動(息が少しはずむ程度)を週二回以上行うことを心がけます。
40代~50代(中年期)
中年期には、生活習慣病でもおなじみの「高血圧」と「肥満」に加えて、「難聴」が認知症の発症リスクを高める危険因子になります。難聴は、危険度では最も影響力があるとする研究論文があるほか、厚生労働省の『認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)』でも、難聴は危険因子の一つとされています。
高血圧や糖尿病などの疾患は難聴になるのを早めますので、食品を選ぶときは塩分とカロリーを意識しましょう。厚生労働省が発表している『日本人の食事摂取基準(2015年版)』では、高血圧予防のための塩分摂取は男性8.0g/日未満、女性7.0g/日未満、体格指数(BMI)は男女とも40代は18.5〜24.9、50代は20.0〜24.9を目標値に定めています。
仕事や家庭、子育てなどで忙しい時期と重なりますので、運動が効果的とわかっていても、運動する時間がなかなかとれない方も多いようです。そのような方は普段から歩く習慣をつけるだけでも違ってきます。都会ならエレベーターに乗らずに階段を使う、地方なら駐車場で車を遠くに停めるなどの工夫をすると良いでしょう。
また、10代から始まっている動脈硬化は、40歳を過ぎる頃から症状としてだんだんと現れてきます。生活習慣の改善による効果は小さく徐々に積み重なっていくものなので、効果を実感できるまでにはそれなりの期間が必要です。その意味では、遅くても40代から認知症予防を意識した生活をスタートして、生涯を通じて継続していくことが大切になります。
高年期に襲いかかる危険因子を排除するには?
60代(高年期)

これ以降の年代では、「喫煙」「運動不足」「うつ」「糖尿病」が危険因子として、認知症の発症に大きく影響してきます。
特に喫煙は、認知症の危険因子の中でもトップクラス。できるだけ早い時期から禁煙し(20歳になっても吸わないのが一番です!)、自分自身の予防につなげるほか、受動喫煙による家族や周囲の人への被害をゼロにしましょう。
また、運動に関しては、高年期から始めたとしても、認知症の発症リスクが抑えられる、有酸素運動は記憶を司る海馬を大きくするなどの研究報告があるので、この時期からでも運動を心がけます。
「うつ」もこの時期にかかると、認知症の発症リスクを高めます。うつの状態では、脳内のセロトニンという神経伝達物質が不足しています。このセロトニンを増やすには、動きが規則的に繰り返されるジョギングや水泳、早歩きなどのようなリズミカルな運動が良いそうです。
「認知症気づきリスト」を使って自分の認知度をチェックしよう
糖尿病に関しては、血糖を管理することで認知症の発症リスクが抑えられることになります。健康的な食事が望ましいことになりますが、高年期は「低栄養」に陥らないことも大切になります。
脳細胞を構成する主成分には、たんぱく質や脂質があり、栄養状態も脳機能に影響を及ぼします。魚ばかりではなく、肉も含めてバランスよく食べるようにしましょう。いろいろな食材を美味しく食べるためには、歯や口腔の健康も大切になります。
また、認知症の重症化を予防するという意味では、「早期発見」もこの時期には意識したいところです。東京都が作成した「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」を活用すると、認知機能や生活機能の低下を簡単にチェックすることができます。
一部の認知症には適切な治療で治るものもありますし、早い段階で取り組めば、認知症の重症化の先送りも可能になります。ちょっとでもおかしいなと感じたら、地域の相談窓口や医療機関に相談するようにしましょう。
認知症予防は積み重ねが大事

今回は、年代別に認知症予防をみてきました。認知症予防としてはほかにもたくさんの方法が提唱されていますが、まずはこのポイントを落とすと、認知症の危険因子と抑制因子がせめぎ合う団体戦では、大きくビハインドを負ってしまうものを中心に取り上げました。
また、その年代だけ取り組めばOKと捉えるのではなく、遅くてもその年代から取り組みを開始して、一生涯かけて取り組むつもりで捉えていただけると良いと思います。今日取り組んで、明日劇的に効果がみられる予防法はなく、日々の小さな積み重ねが長い年月では大きな変化となって現れます。どの予防法についても”前倒し”で取り組むことが勧められます。
以上を踏まえますと、「認知症予防はいつからはじめたらいいのか?」という問いについては、今ではお決まりな表現になりましたが、「今でしょ!」がその答えになるでしょう。