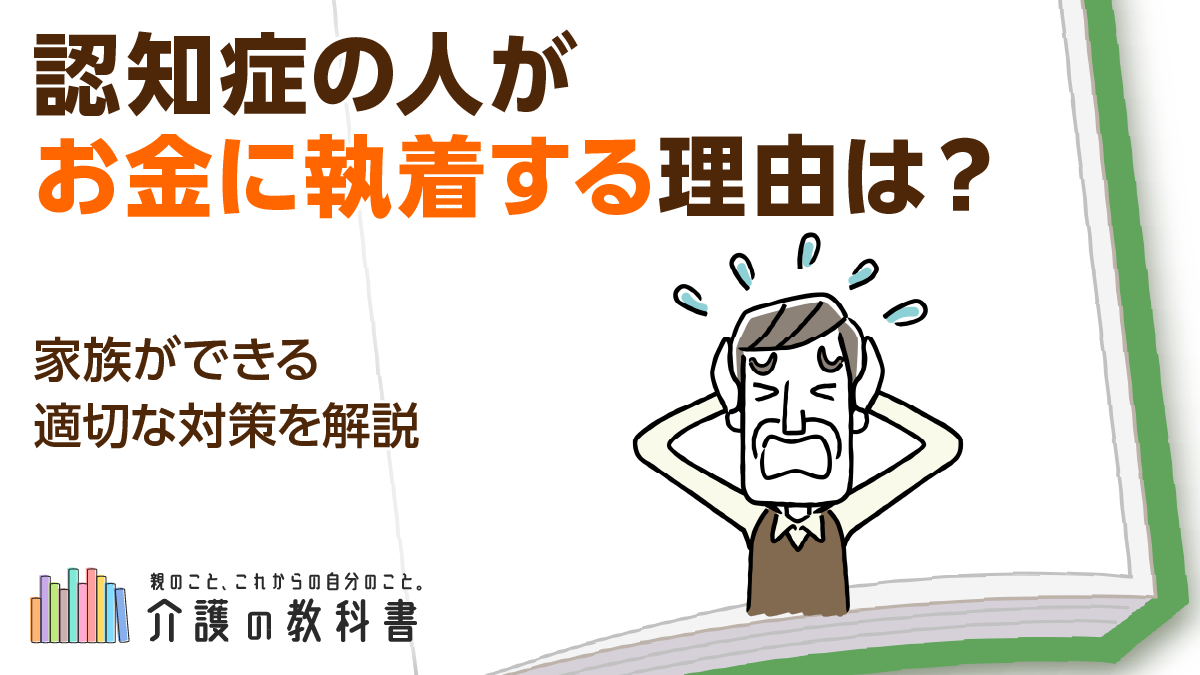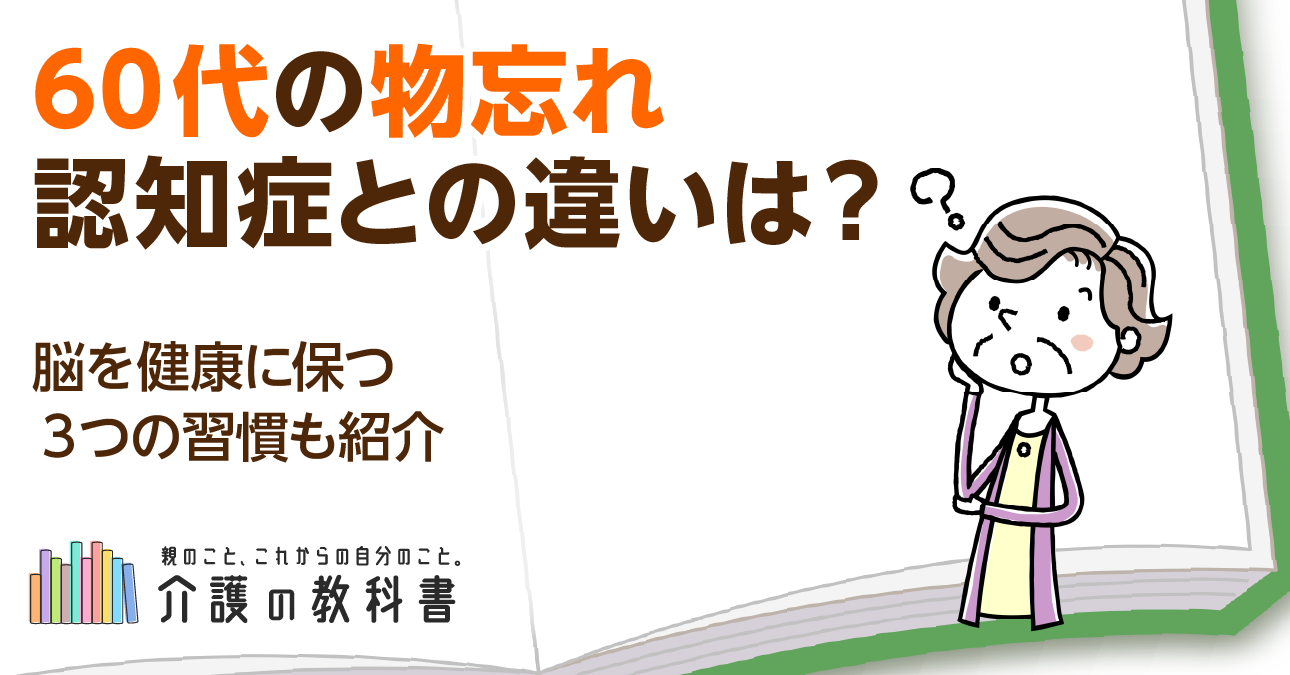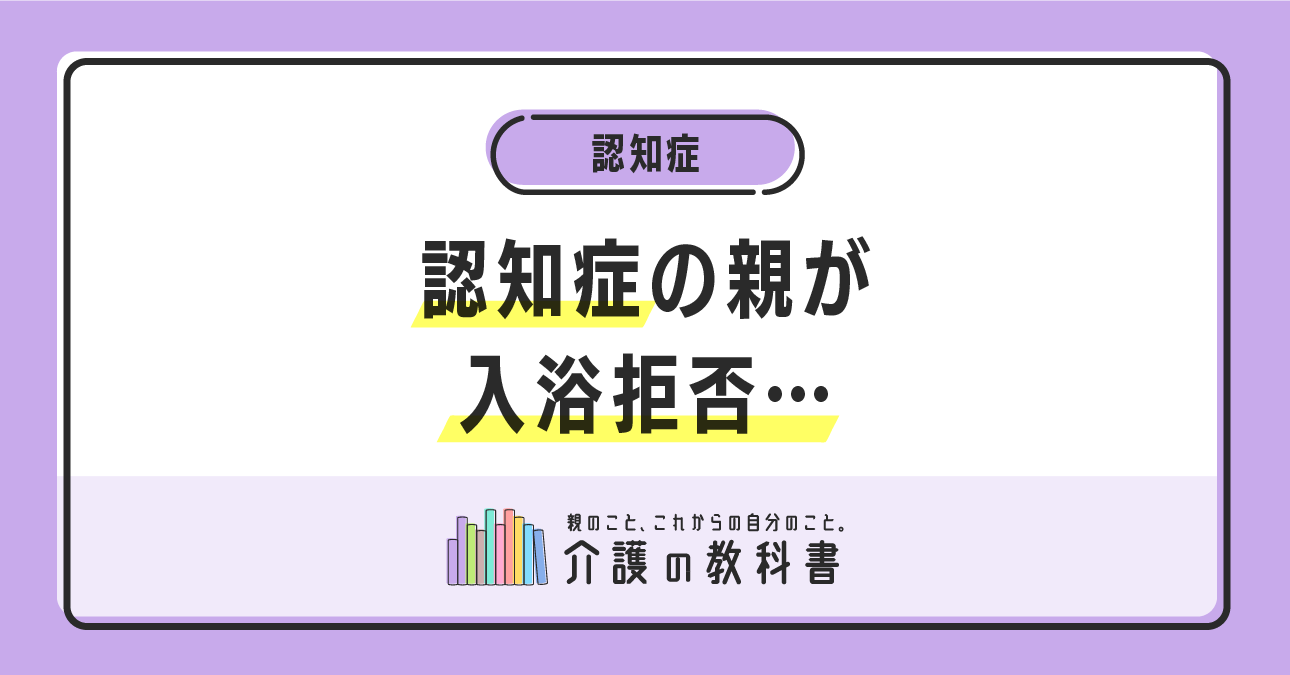認知症の人がお金に執着するのはなぜ?
認知症の人がお金に対して見せる様々な行動には理由があります。ここでは、なぜ認知症の人がお金に執着するのか、その仕組みと心理について詳しく解説します。
認知症の人がお金に執着する医学的メカニズム
認知症の人がお金に対して強い執着を示すことは、決して珍しいことではありません。この行動には医学的な背景があります。
認知症が進行すると、脳の中でも特に記憶を司る海馬や、判断力をコントロールする前頭葉の機能が低下します。これにより、「お金を使った記憶」や「現在の財産状況」を正確に把握することが困難になります。
例えば、朝に銀行からお金を引き出したにも関わらず、その記憶が薄れてしまい「お金がない」と不安になってしまうケースがあります。
脳の機能低下により、時間の感覚も曖昧になります。昨日のことが何年も前のように感じられたり、逆に何十年も前の出来事が昨日のことのように思い出されたりするため、現在の経済状況を正しく認識できなくなってしまうでしょう。
このような脳の変化により、お金への執着は認知症の症状の一つとして現れるため、ご本人を責めるのではなく、病気による症状として理解することが重要になります。
お金に対する不安からくる行動とその理由
認知症の人が示すお金に関する行動パターンには、いくつかの特徴的なものがあります。最も多く見られるのが「お金がない」という訴えですが、さまざまな背景があるのです。
- 自分の金銭管理能力への不安
- 認知症の初期段階では、軽度の記憶障害により金銭管理に不安を感じることが増えます。例えば、買い物をした際に必要以上のお金を相手に渡してしまったり、お釣りの計算ができなくなったりすることで、自分の金銭管理能力に対する不安が高まることがあります。
- 過去と現在の区別がつきにくくなる
- 若い頃の経済的に厳しかった時期の記憶が鮮明に蘇り、現在も同じ状況にあると錯覚してしまうケースがあります。戦時中や高度経済成長期前の貧しい生活の記憶が強く残っている高齢者の場合、特にこの傾向が顕著に現れることがあるのです。
- 財布を複数持つ
- これは「お金を失う不安」から生じる防衛行動といえます。一つの財布だけでは不安なため、リスクを分散させようとする心理が働きます。また、お金を隠す行動も同様で、「誰かに盗まれるのではないか」という妄想的な不安から、安全だと思われる場所にお金を保管しようとします。
- 物盗られ妄想(誰かに物を盗まれたと思い込む症状)
- 例えば、家族が安全のために財布を預かっただけでも「盗まれた」と感じてしまうことがあります。記憶の混乱により、自分がお金をどこに置いたかわからなくなり、結果的に「誰かが盗んだ」と結論づけてしまうのです。

家族が理解すべき認知症とお金の関係性
家族が認知症の人のお金に対する行動を理解するためには、まず認知症という病気がもたらす心理的変化を把握することが重要になります。
認知症の人だけでなく、多くの人にとってお金は安心感の象徴であり、自立性を保つための大切な道具でもある場合が多いです。お金があることで「自分はまだ大丈夫」という自尊心を保とうとしている可能性もあります。
また、記憶障害により、最近の出来事を忘れやすくなる一方で、遠い過去の記憶は比較的保たれることがあります。そのため、昔の金銭感覚で現在の物価を判断してしまい、「こんなに高いはずがない」と混乱することもあるでしょう。
認知症の人は変化に対する適応力が低下します。いつもと違う状況や新しい支払い方法(カードやスマートフォン決済など)に戸惑い、現金への依存度が高まることがあります。現金は目に見えて手で触れることができるため、より安心感を得られるのです。
家族としては、認知症の人の行動を「困った行為」として捉えがちですが、実はその行動には必ず理由があります。お金への執着も、不安や恐怖から身を守ろうとする自然な反応と考えることができるでしょう。
また、金銭管理の問題は認知症の進行とともに深刻化する可能性があるため、早期からの対策が必要になります。
認知症の人のお金に執着する行動への対応策
認知症の人のお金に関する行動に困った経験がある家族は少なくないでしょう。適切な対応方法を知ることで、本人の不安を和らげながら、安全な生活環境を整えることができます。
「財布が盗まれた」妄想への適切な対応方法
認知症の人が「財布が盗まれた」と訴える場面では、家族の対応方法が症状の改善に大きく影響します。このような妄想的な訴えに対して、どのように接すればよいのでしょうか。具体的な対応策として、以下のようなものが挙げられます。
- 頭ごなしに否定しない
- 「そんなことはない」「誰も盗んでいない」と強く否定すると、認知症の人は自分の気持ちを理解してもらえないと感じ、さらに不安が増大してしまいます。
- 相手の気持ちに共感する
- 「財布がなくなって心配ですね」「不安な気持ちはよくわかります」といった言葉で、まず相手の感情を受け入れることが大切です。
- 一緒に探す姿勢を示す
- 「一緒に探してみましょう」と提案し、実際に本人と一緒に財布を探す時間を作ります。この際、あらかじめ財布を見つけやすい場所に置いておき、「見つかりました」という成功体験を提供することも一つの方法でしょう。
- 日頃から財布の定位置を決めておく
- いつも同じ場所に財布を置く習慣をつけることで、紛失する機会を減らせます。明るい色の財布に変える、大きめのサイズにするなどの工夫も効果的です。
認知症の高齢者の意思決定を支援する際は、まず本人との信頼関係を築くことが重要とされています。お金に関する妄想的な訴えに対しても、寄り添う姿勢で接しましょう。
こうした妄想が頻繁に起こる場合は、医師に相談することも大切です。薬物療法や環境調整により、症状の改善が期待できる場合もあります。

お金の管理と使いすぎ防止の具体的な工夫
認知症の人の金銭管理には、段階的で実践的なアプローチが必要です。使いすぎを防ぎながらも、本人の尊厳を保つ工夫が求められます。
- 財布に入れるお金の額を調整する
- 大金を持ち歩くことによるリスクを減らすため、日常的な買い物に必要な金額のみを財布に入れるようにします。全くお金を持たせないのは本人の不安を増大させるため、少額でもお金を持っているという安心感を保つことが重要です。
- 銀行口座の管理
- ATMでの操作が困難になった場合は、家族が代わりに引き出しを行うか、銀行の窓口での手続きに切り替えることを検討しましょう。多くの金融機関では、認知症の人の財産を守るための様々なサービスを提供しています。
- 買い物の際は可能な限り家族が同行する
- 一人で買い物をする場合は、お店の人に事前に事情を説明し、協力をお願いすることも一つの方法です。
- クレジットカードの管理
- 利用限度額を低く設定するか、場合によっては解約を検討することも必要かもしれません。インターネット通販のアカウントも同様に、パスワードを変更するなどして不要な購入を防ぐ対策を取りましょう。
金銭管理においても本人に寄り添う姿勢が必要です。一方的に制限するのではなく、本人が納得できる範囲で段階的に支援を強化していきましょう。
詐欺や悪徳商法から守るための予防策
認知症の人は判断力の低下により、詐欺や悪徳商法の被害に遭いやすくなります。事前の予防策で被害を防ぐ工夫を行っておきましょう。
まず、電話による詐欺への対策として、留守番電話の設定を活用することが効果的です。知らない番号からの電話には直接出ないようにしましょう。ナンバーディスプレイ機能を使って、知らない番号を表示させることも大事です。
訪問販売への対策では、玄関に「訪問販売お断り」のステッカーを貼ることから始めましょう。また、インターホンで相手を確認してから扉を開ける習慣をつけることが大切です。
知らない人が来た場合は、家族に連絡してから対応するようにルールを決めておくとよいでしょう。
郵便物のチェックも重要な予防策の一つです。「当選しました」「緊急」といった目を引く文言が使われたダイレクトメールや、高額な商品の請求書などがないか、定期的に確認することが必要になります。
近隣住民や地域包括支援センターとの連携も効果的な対策といえます。厚生労働省のガイドライン事例でも、地域住民との協力により高齢者を守った事例が紹介されています。
日頃から近所の人に事情を説明し、可能な範囲で不審な訪問者や電話があった場合の協力をお願いしておくことが重要でしょう。
合わせて金融機関との連携も検討しておきましょう。
多くの銀行では、高齢者の不審な取引を察知するシステムを導入しています。大きな金額の引き出しがある場合は、銀行から家族に連絡してもらえるよう事前に相談しておくことも一つの方法です。
認知症の人のお金の管理対策と相談先
認知症が進行すると、日常的な金銭管理だけでなく、財産全体の保護や法的な手続きも課題となります。専門機関を活用し、本人と家族の両方が安心できる環境を整えましょう。
家族信託と任意後見制度による財産保護の方法
認知症の進行に伴い金銭管理が困難になった場合、法的な財産保護制度の活用を検討することが重要になります。主な選択肢として、家族信託と任意後見制度があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
家族信託は、認知症になる前に本人が信頼できる家族に財産の管理を託す制度です。本人が委託者となり、信頼できる家族を受託者として財産を託します。この制度の最大のメリットは、本人の判断能力があるうちに将来の財産管理について詳細に決めておけることでしょう。
家族信託では、不動産の売却や賃貸、預貯金の管理など、具体的な財産管理の方法を契約で定めることができます。また、本人の生活費として必要な金額を定期的に給付する仕組みも作れるため、認知症が進行しても安定した生活を維持することが可能になります。
一方、任意後見制度は、本人の判断能力が低下した後に効力を発揮する制度です。判断能力があるうちに、将来後見人になる予定の人(任意後見受任者)と契約を結んでおき、実際に判断能力が低下した時点で家庭裁判所に申し立てを行います。
これらの制度を利用する場合は、必要に応じて司法書士や弁護士、税理士などの専門家に相談しましょう。

口座凍結された場合の対処法と金融機関制度の活用
金融機関が口座の持ち主が認知症であることを把握した場合、預金口座が凍結されることがあります。多くの金融機関では、このような状況に対処するため認知症の人やその家族を支援する制度を導入しています。
例えば、代理人カードの発行や、家族による代理取引を可能にするサービスなどがあります。これらのサービスを利用するためには、事前に金融機関で手続きを行う必要があります。
成年後見制度を利用している場合は、後見人が法的に財産管理を行う権限を持つため、必要な書類を提出することで口座からの引き出しが可能になります。
ただし、後見制度では本人の利益を最優先に考えるため、使用目的が明確でない場合は引き出しが制限されることもあります。
重要なのは、認知症の診断を受けた早い段階で、金融機関に相談することです。各金融機関は高齢者支援の専門窓口を設けているところが多いため、まずは取引のある金融機関に相談してみることをおすすめします。
地域包括支援センターと専門機関への相談タイミング
認知症の人の金銭管理に関する問題が生じた場合、適切なタイミングで専門機関に相談することが重要です。一人で抱え込まず、地域の支援体制を活用することが問題解決の近道となるでしょう。
地域包括支援センターは、高齢者の生活全般に関する相談窓口として重要な役割を果たしています。認知症の初期段階で金銭管理に不安を感じ始めたら、まずはこちらに相談することをお勧めします。
相談のタイミングとしては、以下のような症状や問題が見られた場合が適切です。
- 同じものを何度も購入してしまう
- お金の計算ができなくなる
- ATMの操作に戸惑うようになる
- 詐欺の電話に騙されそうになる など
問題が深刻な場合は、成年後見制度の利用も検討しましょう。この場合は、地域の権利擁護支援センターや社会福祉協議会に相談することが効果的です。
相談の際は、具体的な困りごとや心配事を整理して伝えることが大切です。いつから問題が始まったのか、どのような行動が見られるのか、家族としてはどのような支援を求めているのかを明確にすることで、より効果的なサポートを受けることができるでしょう。
まとめ
認知症の人がお金に執着する行動は、決して理解できない行為ではありません。脳の機能変化により記憶や判断力が低下することで、お金に対する不安や恐怖が強まり、様々な行動として現れるのです。
認知症の人のお金への執着には、医学的・心理的な背景があります。頭ごなしに否定せず、まず相手の気持ちに共感することが重要です。
詐欺や悪徳商法から身を守るためには、留守番電話の活用や訪問販売対策、法的な財産保護制度の検討など、日常的な予防策が効果的です。
これらの問題は、家族だけで抱え込まず、金融機関の専門窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。地域全体で支えることで、認知症の人も介護家族も安心して生活できる環境を整えることができるのです。