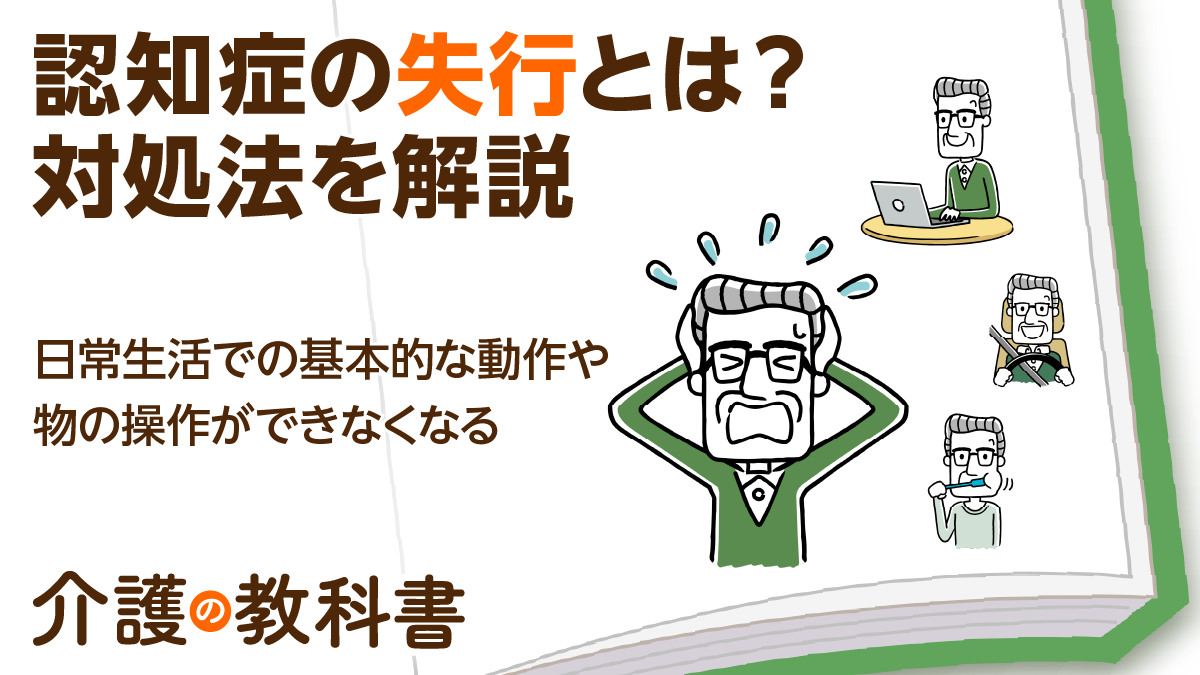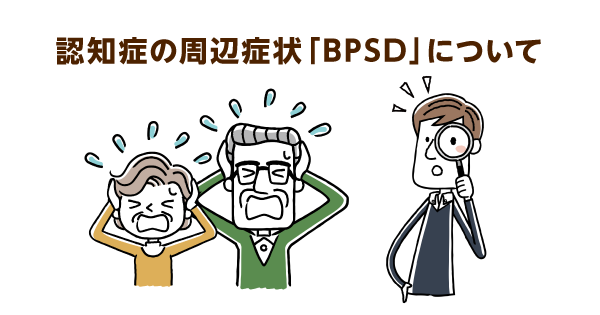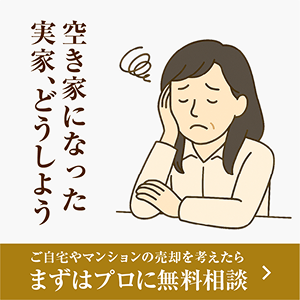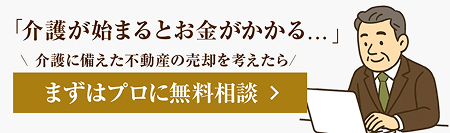高齢を迎えると誰にでも起きやすい認知症は、脳の機能が低下し記憶や判断、思考などが障害されます。症状の進行にともなって、歯ブラシの使い方や椅子からの立ち上がり方が分からなくなる「失行」という症状が出てくることがあります。
この記事では、認知症における失行と失行が起きた時の対処法について事例を含めて解説します。
認知症における失行とは
認知症の方が、歯ブラシの使い方が分からなくなったり、服を裏表に着てしまったりすることはありませんか?これは、失行という症状です。失行は、認知症の進行にともなって出てくる中核症状の一つで、日常生活での基本的な動作や物の操作ができなくなる症状です。
認知症の方は、物忘れや判断力の低下など、さまざまな症状に悩まされます。その中には、BPSD(行動・心理症状)と呼ばれるものがあります。BPSDとは、認知症の方が見せる不安やイライラ、徘徊や暴力などの行動や感情の変化のことで、認知症の方だけでなく介護者や家族にも大きな負担となります。
このBPSDの一つが「失行」です。具体的に、次のようなことが現れることがあります。
- 食事の時に箸やスプーンを使うことができない。
- 椅子から立ったり座ったりが分からない
- 服を着たり脱いだりするときに、歯ブラシや電気カミソリを持つことができない。
- 電話やテレビのリモコン操作ができない
失行が起きた時の対処法
失行は認知症の方にとって、自立した生活を送ることが困難になるだけではなく、自尊心や自信を失いがちになります。一方、介護する家族は、失行に対応することがストレスになることがあります。そんな方に向けて、失行が起きたときの有効な対処方法をお伝えします。
声かけを工夫する
失行のある方の場合、言葉で指示をされても理解することが難しい場合があります。そのため、椅子から立ち上がる場合は、「立ってください」というよりは、「足首を少し引いて」」「膝を伸ばしましょう」などの具体的な声掛けを行うのが望ましいでしょう。
手本を見せる
言葉だけではなく、手本を見せることも効果的です。椅子から立ち上がりや椅子に座るときには「足を少し手前に引いて立ち上がります」と言ってご本人の目の前で立ち上がり動作を見せるようにしてみてください。
手助けをする
自分で動かすべき身体の部位がわからない場合でも、すべてを介助してしまうと、ご本人は「自分で出来ることを奪われた」と思い自信や自尊心を低下させる場合があります。
ご家族で失行のある方を介助する場合は、できる範囲はやってもらい、できないところだけ家族が優しく触れて、動かし方を示すことや「一緒に立ちましょう」と言って手を差し伸べて身体的にサポートするのがポイントです。
ほめる
失行のある方が、椅子から立ち上がりや座ることができたときに、ほめることにより動作の強化や自信につながります。「上手くできましたね」と言って笑顔でほめることは、とても大事です。
対処法の事例紹介
私が、以前勤務していた老健施設であった事例を紹介します。
80歳女性のAさんは、アルツハイマー型認知症で入所生活をしています。Aさんは椅子からの立ち上がりや座ること、衣類の着替え、箸をうまく使うことができないことで自信がないような顔つきで生活していました。
そのようなAさんに対して、ケアスタッフが椅子からの立ち上がりや座り方のケアを行いました。椅子に腰かけているAさんに「椅子から立ち上がって庭でも見ませんか?」という声かけを行い「私が椅子から立ち上がるので見ていてください」といって立ち上がりを見せました。
その後「Aさん、両方の足を少し手前に引いて、テーブルに両手をつきましょう」という指示をだし、脇に座って一緒に立ち上がったところ、スムーズに立ち上がりができました。さらに、約2分立位を保持でき、スムーズに椅子に腰かけることができたのです。
Aさんが椅子からの立ち上がりや座ることができたことを見ていたスタッフが「Aさん立てたね、良かったね」という声をかけると嬉しそうに笑顔を見せました。結果Aさんは、スタッフの声掛けや、一部介助で椅子からの立ち上がりや座ることができたことで、自信がつきました。食事面でも見守りや声かけをすることにより箸で上手く食べれるようになり生活面も向上しました。
まとめ
認知症の進行にともなって、日常生活での動作や物の操作ができなくなる「失行」という症状について、原因と対処法を解説しました。
失行のある方には、具体的な声かけや手本を見せること、できる範囲は本人にやってもらうこと、成功したらほめることなどが効果的です。失行に対する理解と配慮も持って、認知症の方とのコミュニケーションをとっていきましょう。