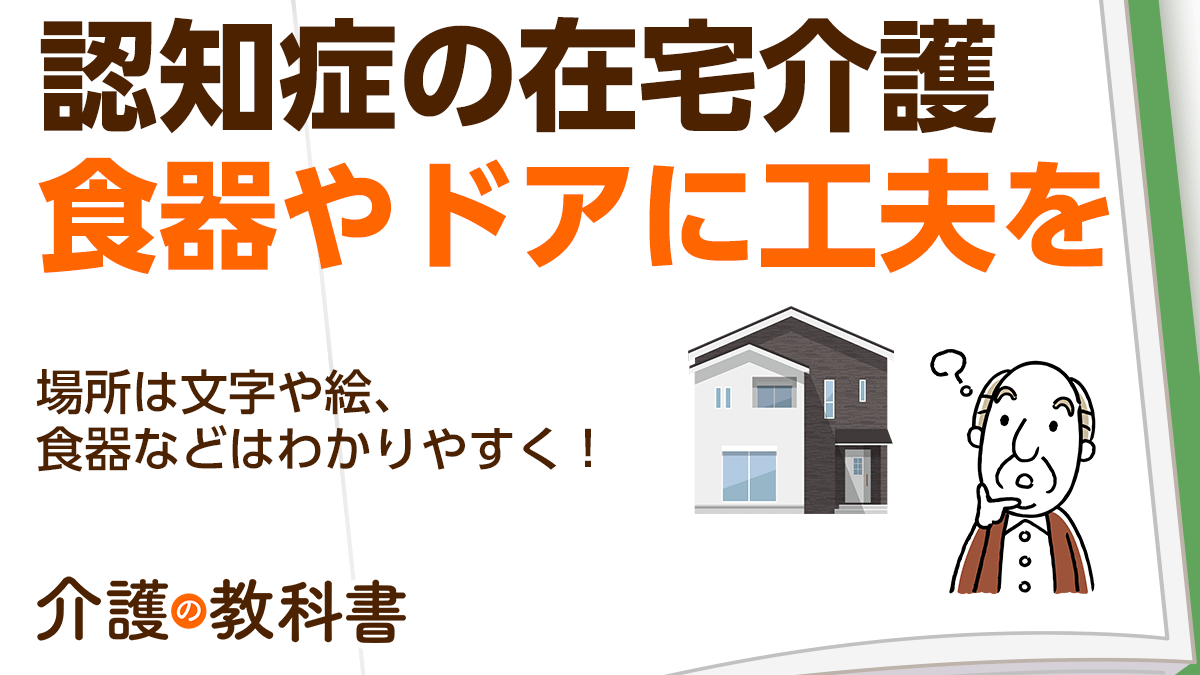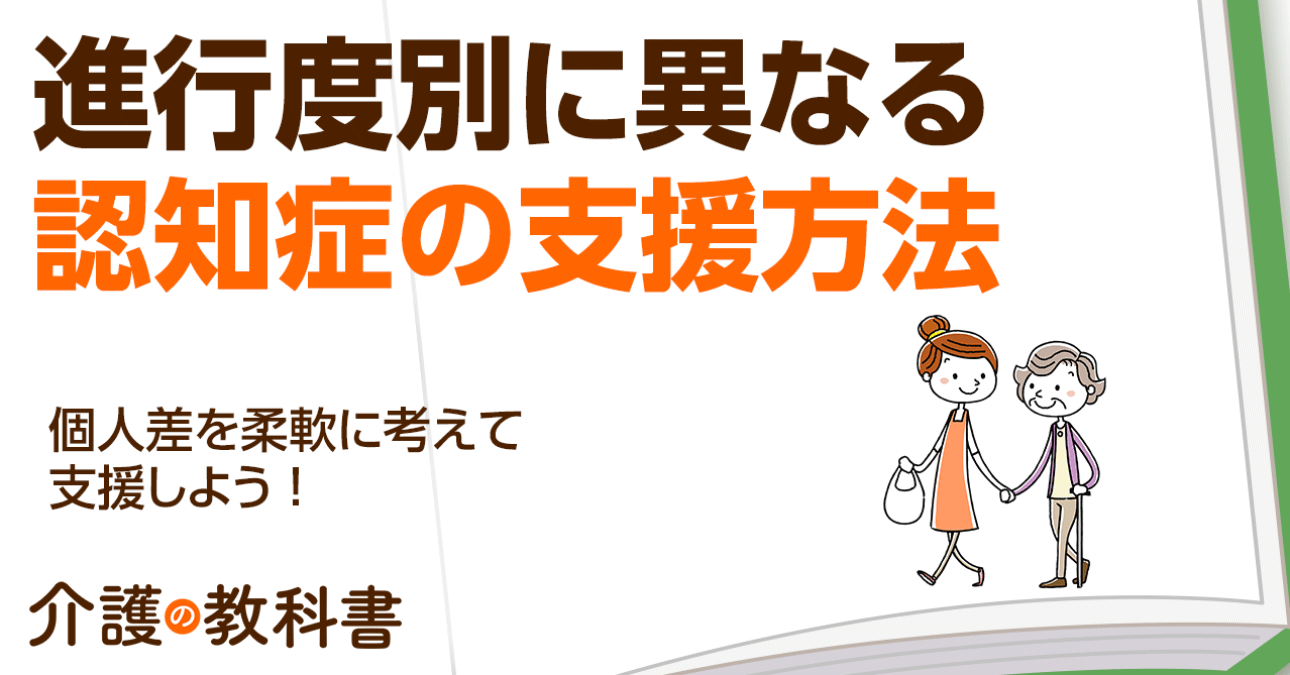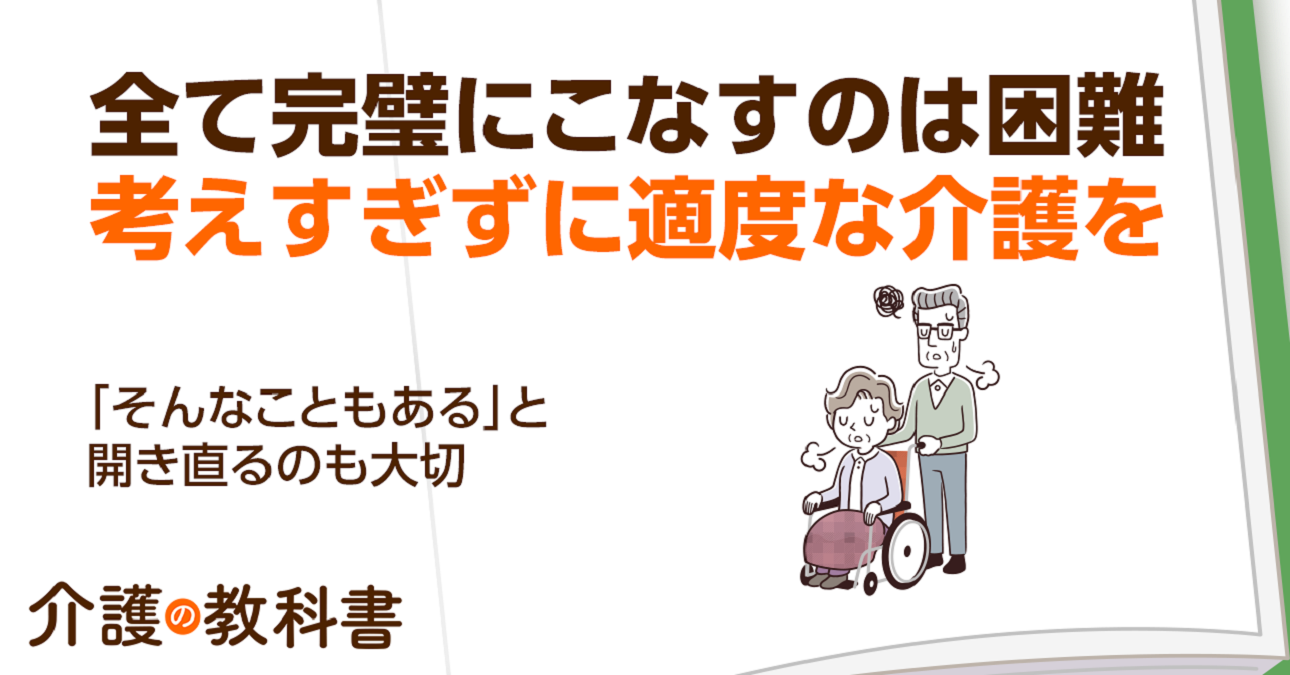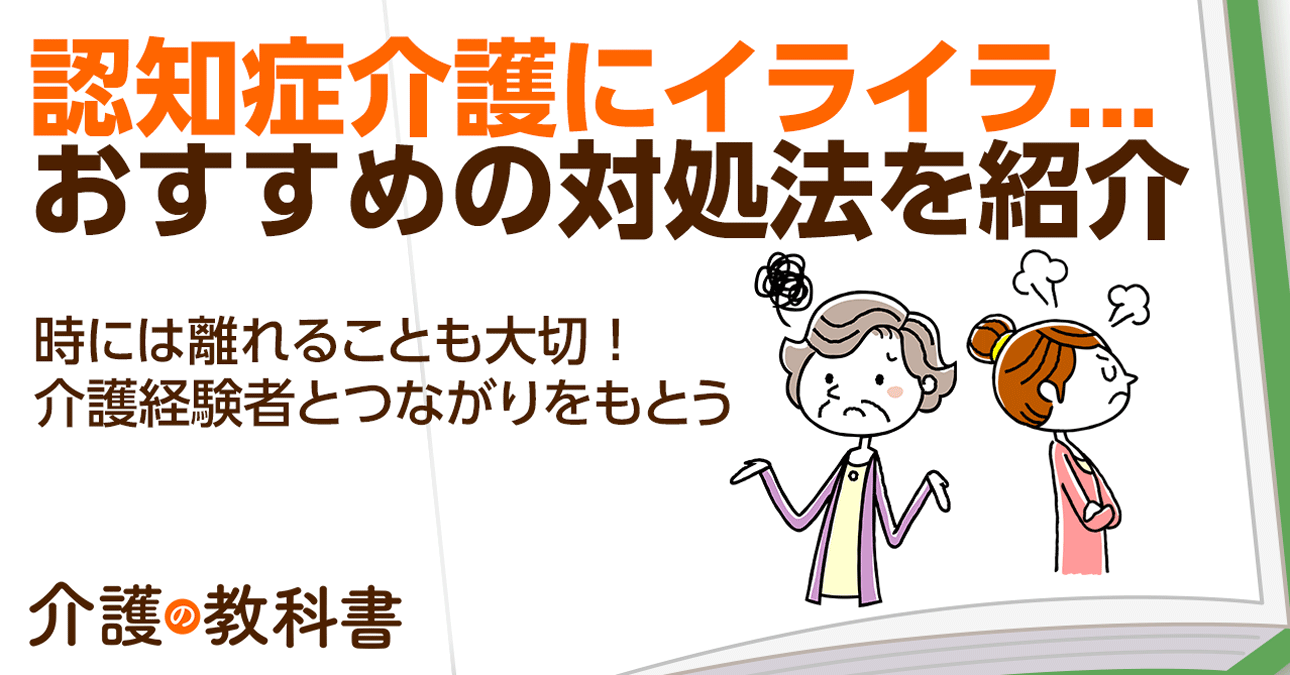私は、認知症の人だけが暮らす介護施設のグループホームで約10年働きました。本来、グループホームは家庭的な環境の下で暮らすことを目的に始まった施設ですが、認知症の人にとって住みにくい場所に感じることもありました。
そこで今回は、認知症の人にとって住みやすい家の環境とはどのようなものかについてお話します。
認知症の人がわかるように「かいて」場所を知らせる
まずは部屋の位置です。選択肢がないのであれば仕方ないのですが、可能な限りほかの家族がよくいる場所(リビングなど)の近くが望ましいでしょう。
離れた場所にあると、同じ家族であってもお互い声をかけにくい関係になりがちだからです。何かあったときに声をかけられることで安心につながります。また孤独感の防止にもなり、たとえ顔が見えなくても人がいる気配を感じるだけでも有効なのです。
そして何と言っても場所。そこがどういう場所なのか、わかりやすいことがポイントです。たとえば、認知症でない人にとっては、いちいち書いていなくても、そこがトイレなのか自分の部屋なのかはわかります。
しかし、認知症になると扉が閉まっているときには判別がつかず、わからなくなることがあります。家でやることに抵抗のある人もいると思いますが、「かいて」貼っておくことが有効です。読んで理解できる人であれば字で書いて、難しければ絵などで描いてみてください。
また「見て」わかる人であれば、写真を貼るか、トイレは使っていなければ思いきって扉を開けておくといった対応も考えられます。
食器やテーブルクロスの色・柄に注意しよう
家庭内にある「もの」も重要なポイントで、端的に言えば紛らわしさをなくすことが大切です。
たとえば、ご飯を入れる茶碗の色。多くは白系統だと思いますが、白系統の物の上にご飯(白色)となることで同化してしまうのか、ご飯が入っていること自体を認識できなくなり、手をつけられないことがあります。
そんなときは「ご飯は茶碗に」という既成概念を捨てると良いでしょう。私が働いていたグループホームでは、おみそ汁を入れるお椀にご飯をいれることで、これまでご飯を食べないと思っていた人が食べられるようになった人もいました。
また、別の例として、机などに敷いてあるテーブルクロスを挙げてみましょう。模様や柄などが一切ないシンプルなものであれば問題ありませんが、おしゃれやかわいさなどを優先したものであれば注意が必要です。
私が今かかわっている方には、机の木目調のテーブルクロスを見て、その年輪を汚れていると思ってか「取れないな」と言いながら、ふきんで拭き続けている人がいます。
また、食事中、テーブルクロスにプリントされている果物に箸を伸ばして口に持っていかれている人もいました。きっと本当の食べ物と認識されているのだと思います。
いずれにしても認知症ではない人にとっての当たり前を忘れることです。どうしてわからないのかとイライラするのはよくありません。どうしてそうなるのか、どうすれば良いのかとの視点を持って環境を整えることが大切なのです。