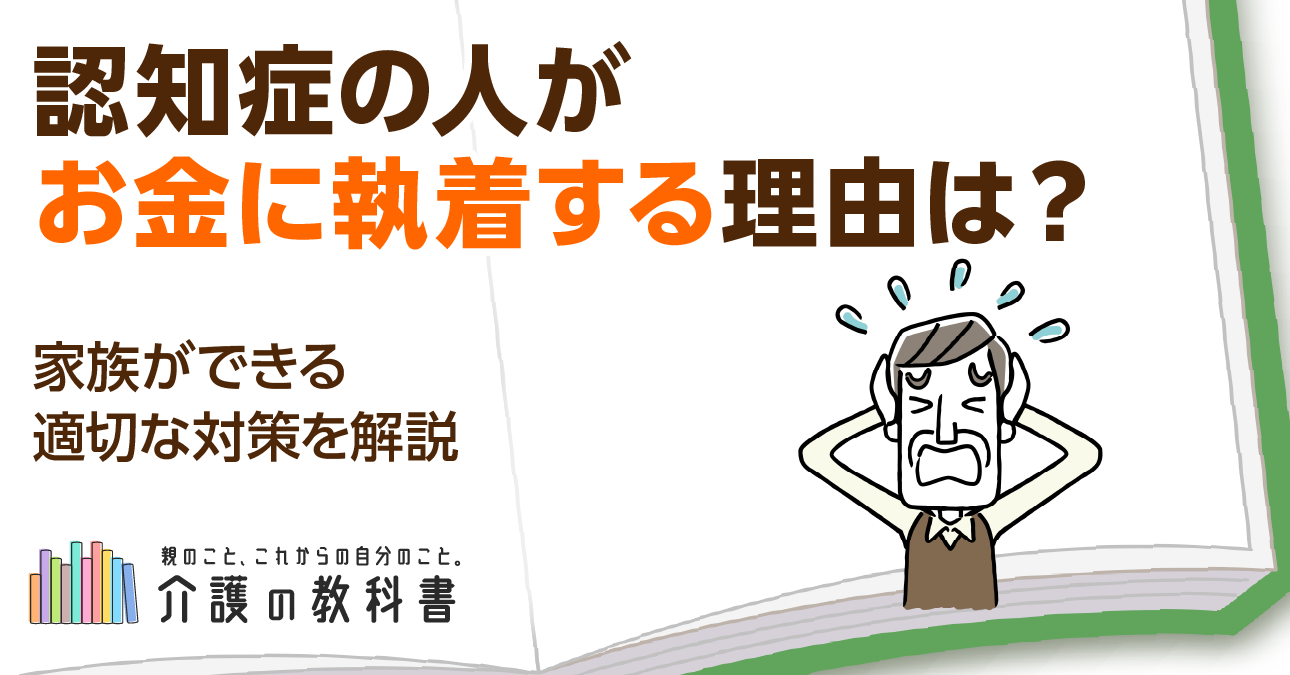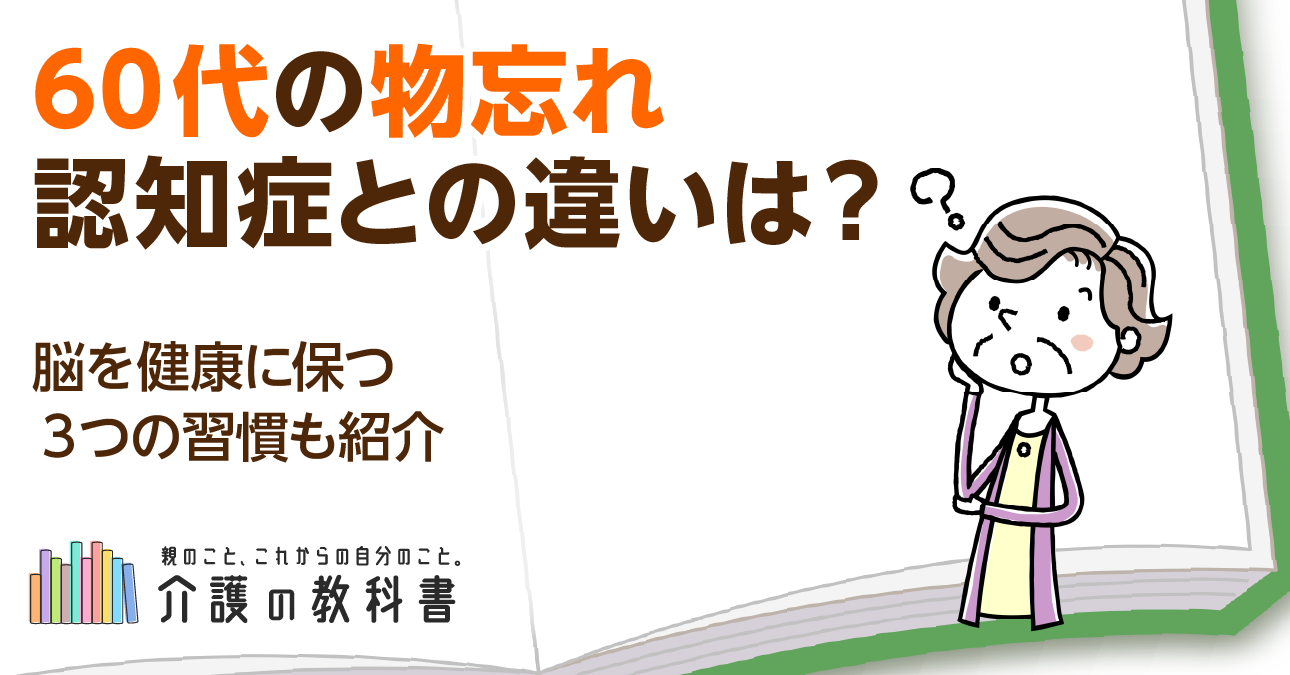2023年6月「共生社会の実現を推進するための認知症基本法(以下、認知症基本法)」が国会で可決・成立しました。
本法律によって、認知症介護の現場にはどんな影響があるのかを考えていきたいと思います。
認知症基本法を「見る・知る」ことが大切
本法では、以下のような目的が明文化されています。
- 認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと
- 認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会
認知症の本人だけではなく、国民の一人ひとりが他人事ではなく、「我が事」として認知症を考えていきましょうというメッセージを国が発信したのです。
これまでも介護保険法やその他関係法令において、認知症について発信をしてきましたが、認知症や介護を遠い存在にしか思えていない方にとっては、我が事と捉えられていない印象も少なからずありました。
認知症基本法の制定により、多くの国民に我が事として考えるきっかけになることを期待したいと思います。そのためには、認知症基本法を多くの方が「見る・知る」ことが重要です。
法律は法文の体裁をとっているのでなかなかわかりづらいのですが、福祉介護評論家・ジャーナリストの町永俊雄さんが認知症基本法の「わかりやすい版」を作成しています。その名の通り、とてもわかりやすいのでぜひ読んでみてください。
介護現場でも変化が生まれる可能性
さて、今回の認知症基本法の制定により、認知症介護の現場にはどんな影響があるのでしょうか。
認知症基本法の法文を読み込むと、「認知症の状態にある方の意思決定支援」「共生社会実現のための国民の認知症の知識・理解を啓発推進」「バリアフリー化の推進」「保健医療・福祉サービスの切れ目ない提供」「家族等の支援」などの基本的な方針を示しており、抽象的な内容にとどまっています。
そもそも「基本法」は、「国の制度・政策に関する理念、基本方針を示すとともに、それに沿った措置を講ずべきことを定め、基本法の目的、内容等に適合するような形で、さまざまな行政諸施策が遂行される」とあります。(出典:参議院法制局)
つまり、今後の介護保険法改正や介護報酬改定等において、認知症基本法の内容が考慮されることになると考えられます。
そのため専門職の皆さんは、認知症基本法の内容を読み込み、理解しておくことが大切になります。
着目したいポイント
第十四条 認知症の人に関する国民の理解の増進等
(認知症に関する教育の推進等)
第十四条 国及び地方公共団体は、国民が、認知症に関する知識及び認知症の人に関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育における認知症に関する教育の推進、認知症の人に関する理解を深めるための運動の展開その他の必要な施策を講ずるものとする。
「認知症とは何か」「認知症の状態にある人に対する正しい認識や理解」のために、学校教育等において認知症における教育の推進等が求められています。
このような機会に、専門職がぜひ活躍してほしいと期待します。なぜなら、専門職は自身が働く施設・事業所の職員であると同時に、市民が要介護状態になった際の「生活の護り手」でもあるからです。
「認知症の正しい知識」と「認知症の状態にある人に対する正しい認識や理解」は学びと実践を重ねている専門職だからこそ国民に語ることができます。多くの専門職が、地域に出て発信していく。それがさらに専門職を成長させる機会になると考えます。
第十七条 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護
(認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護)
第十七条 国及び地方公共団体は、認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保護を図るため、認知症の人の意思決定の適切な支援に関する指針の策定、認知症の人に対する分かりやすい形での情報提供の促進、消費生活における被害を防止するための啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
認知症は、過去にとかく介護者が中心の視点で物事が語られがちな風潮がありました。
また、自分が自分らしくいるために大切にしている考え方や生き方などを指す「尊厳」が疎かにされがちな過去がありました。
起きたり寝たりする時間、食事の時間、お風呂に入る時間や曜日など、本人の意思とは関係なく、施設が決めたスケジュールに入居者が合わせることがまだまだあります。
このような課題の背景には、人員や環境等の影響もあることは事実です。しかし、だからといって、本人の意思を疎かにして良いわけではありません。これらを変えることは容易なことではありませんが、私たち専門職には、諦めず、割りきらず、できることから地道に実践していくことが求められています。
意思決定支援や権利利益の保護が法で謳われるということは、現状としては不十分であることの裏返しです。この重さを私たちはしっかりと受け止め、実践で還していく必要があります。
制定されて間もない認知症基本法ですが、専門職を含めた多くの国民が、この法に込められた意味を読み込み・語り合い・考えていくことが重要だと考えます。
利用者・専門職の双方で認知症基本法について真剣に考え、真摯に向き合っていくことが大切ではないでしょうか。