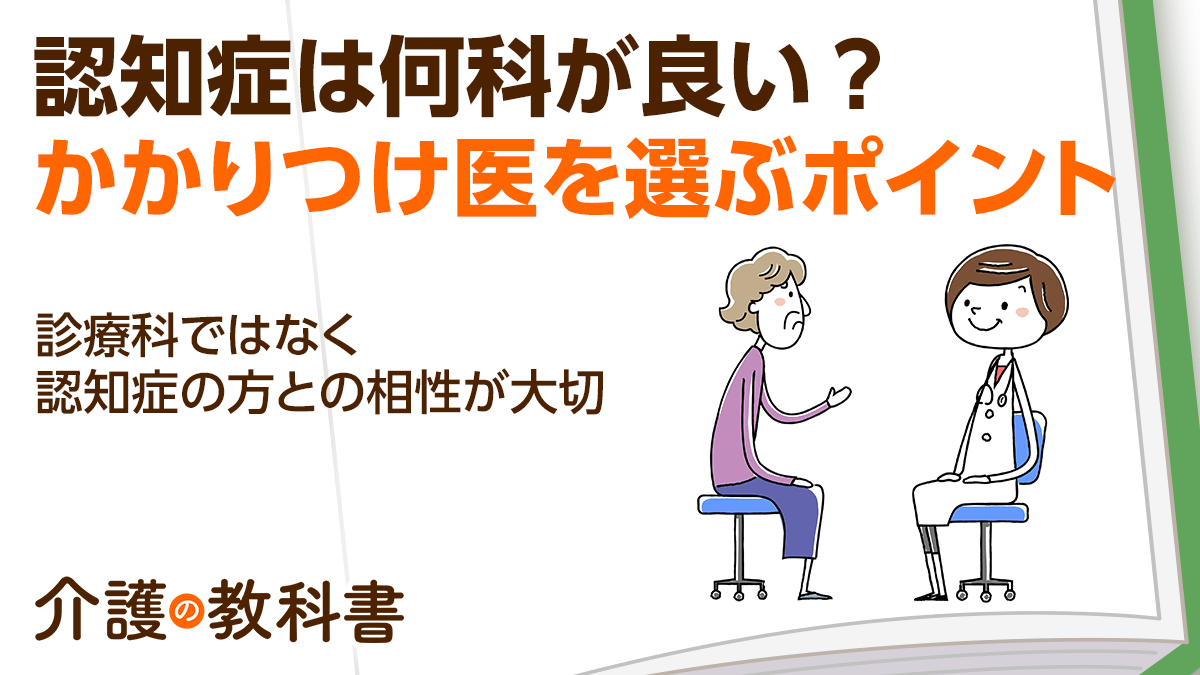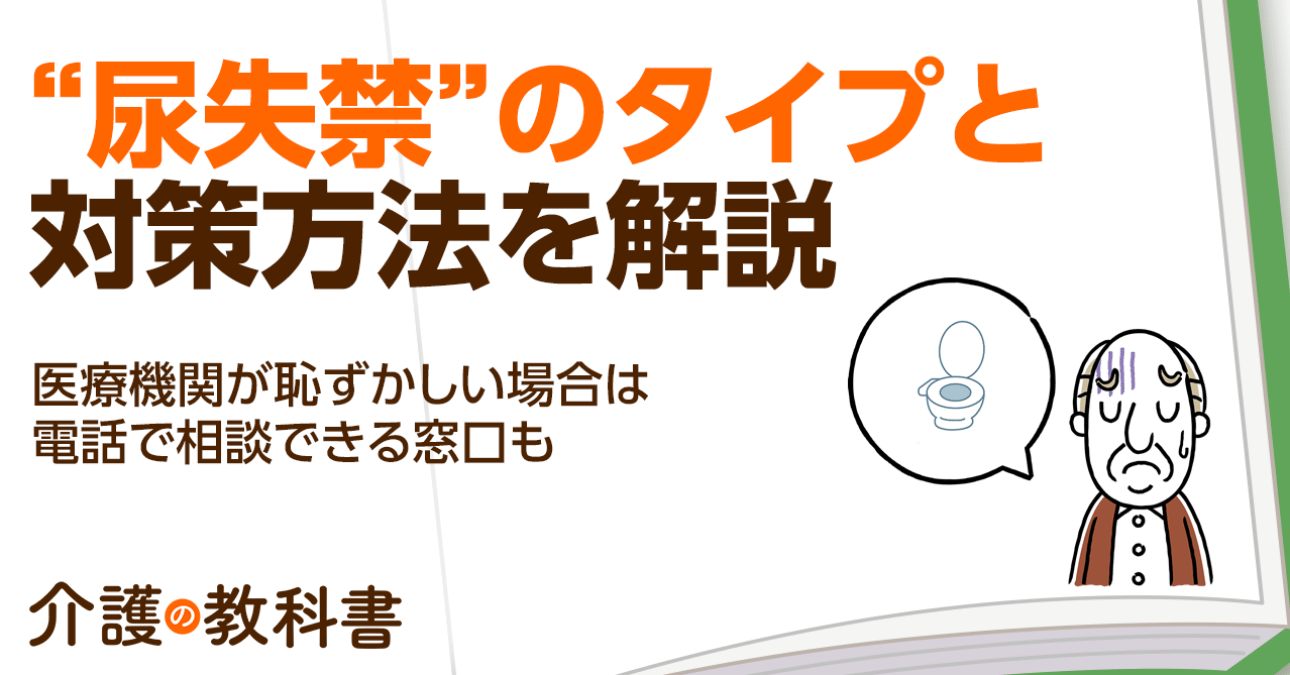認知症によって介護が必要な状態になると、どんな医療機関にかかるか悩む時期があることでしょう。
特に、「何かあったときに診てもらえる“かかりつけ医”を持ったほうがいい」と耳にしている方も多いのではないでしょうか。
ただ、そのような医師を見つけたとしても、認知症の方と合わなかったり、説明に納得できなかったりする場合があるかと思います。
そこで今回はかかりつけ医についての向き合い方についてお話します。
認知症の原因疾患は70以上もある
私自身、認知症に関するさまざまな相談を受けてきましたが、よくあるのが「何科の医師が良いのか」というものです。
皆さんは認知症を疾患と考え、認知症を専門的に診る科として精神科のような科を考えるかと思いますが、私はその必要はないと思います。
それは認知症の人にとって良い医師=認知症を専門的に診てくれる人では決してないからです。また、認知症専門医という医師もおり、その分野のエキスパートのように捉えがちですが、必ずしも当てはまらないのが現実です。
一般社団法人日本専門医機構は、専門医を以下のように定義しています。
何らかの病気に対しての専門医であれば頼って良いのかもしれませんが、認知症は違います。なぜなら、認知症は病気ではないからです。あくまで認知症は症状(状態)を指す言葉なのです。
その症状を引き起こすのは、アルツハイマー病を筆頭に、実に70~80ほどの原因となる疾患があります。それらすべての病気を解決することは現代医学では難しいと言われています。つまり、専門医であっても認知症によって起こる問題を根本的に解決するのは難しいのです。
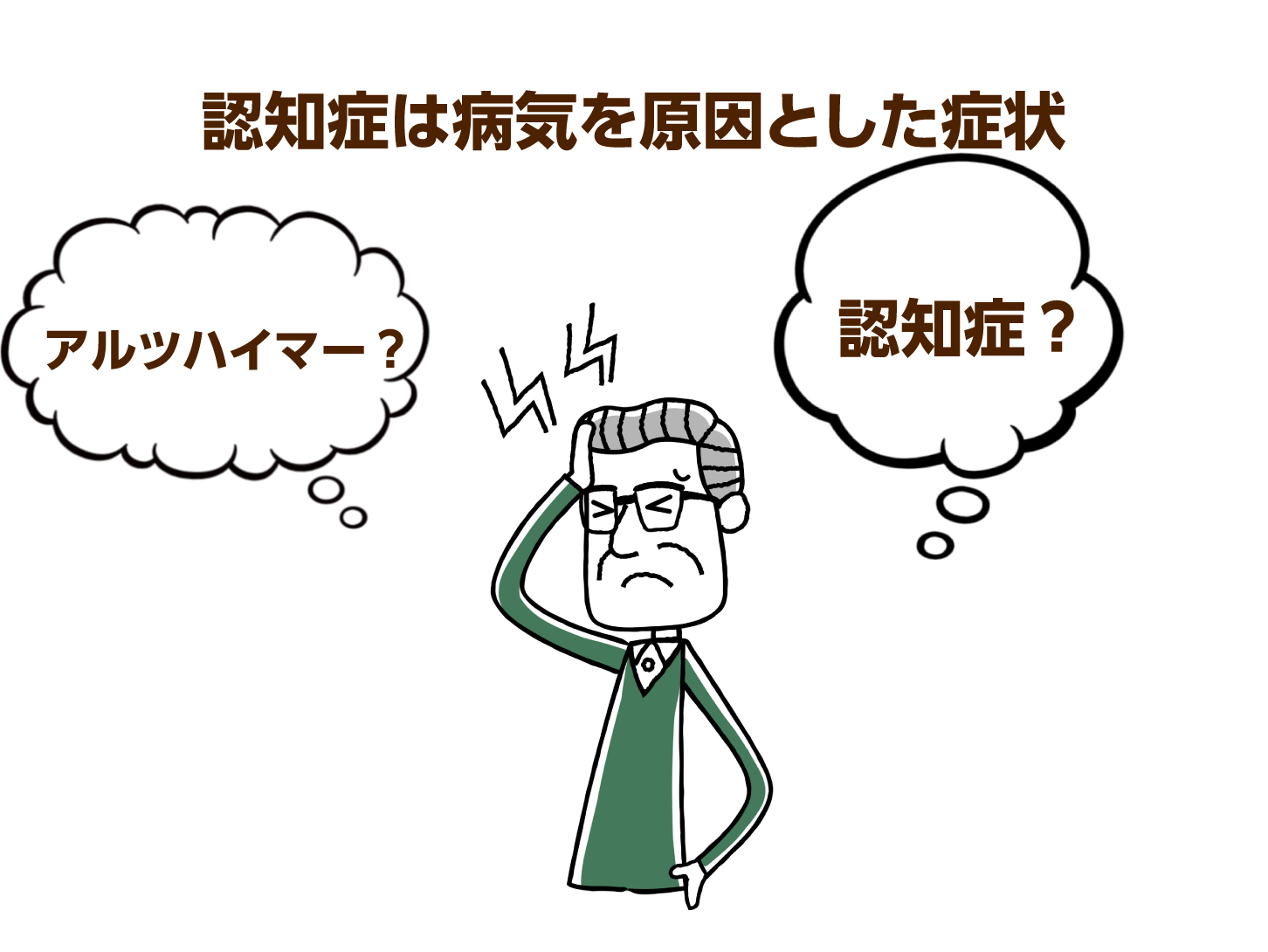
話を聞いてくれる医師なら専門医でなくても良い
ではどのような医師が良いのでしょうか。
私が毎月参加している「認知症の人と家族の会」での集まりで、以前ある参加者がこのように話していました。
「認知症の人に名医はいらない。相性が良い医師を選ぶことだ」
認知症の特性上、ケアをする人との相性が大切です。それは介護職だけでなく、医師にも言えることを示した的確な言葉だと思います。
最低限の知識と技術があれば十分で、認知症を「正しく」理解していることが重要ということです。何も特別なことではありません。
まず一般的なことに対応できる内科を中心として、科を問わず認知症の方であっても話を聴いてくれるという当たり前の医師が良いということです。
逆に言えば、話を聴いてくれない、説明に納得ができないなどあれば、かかりつけ医であっても問題が生じかねません。合わないと感じたなら、まずは医師に正直に打ち明けることが大切です。
直接言いにくいのであれば、看護師さんや相談員さん、苦情を受け付ける部署などに話を聞いてもらうことも一つの方法です。結果として、それを理解されて対応が変わって良くなる医師であれば、かかりつけ医として問題はないと考えられます
当たり前のことのようですが、認知症を「正しく」理解し、対応してもらえる医師ばかりではないというのが私の経験から言える正直な思いです。そのうえで「認知症の方に何を言ってもわからない」などという言動があったり、いっこうに対応が変わらないようであれば、別の医師を探すべきでしょう。
それくらい認知症の人にとっては「合う・合わない」というのは介護と同様に医療を考える意味においても大切なことなのです。