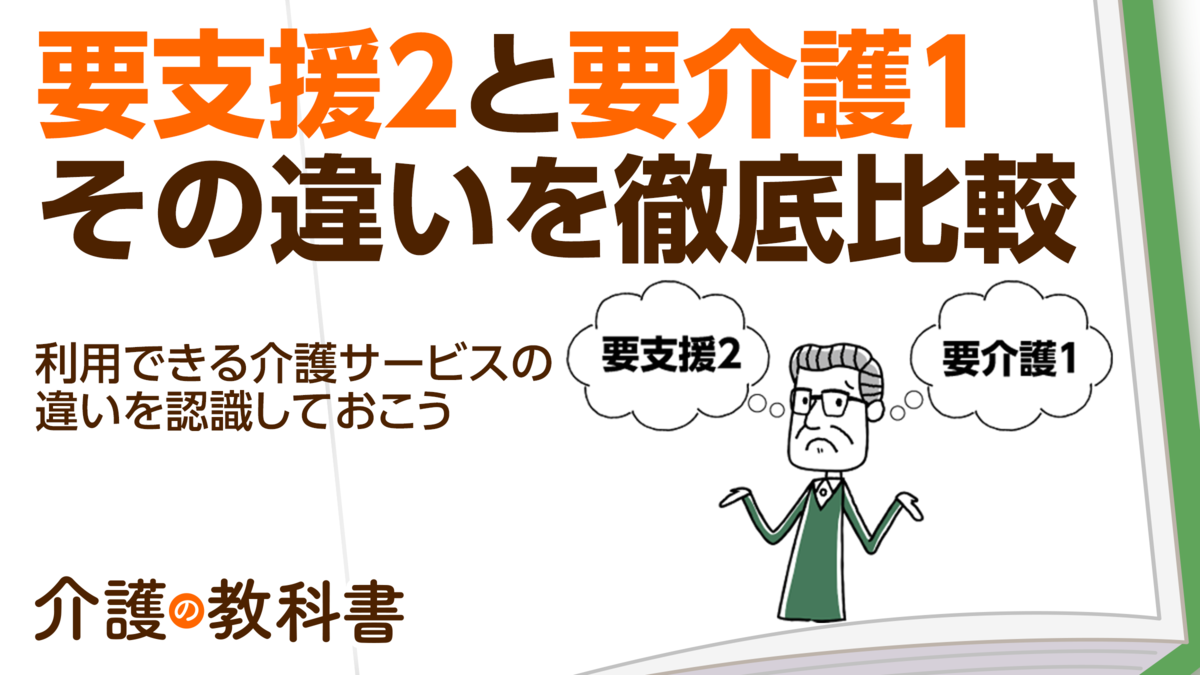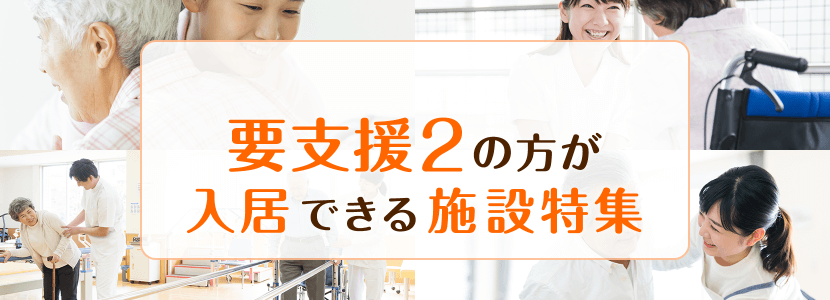要介護度のうち、要支援2と要介護1は非常に近しい状態にありながら、利用できる介護サービスに大きな違いがあります。
今回は、双方の違いについて徹底比較していきます。
要介護度を決める流れ
介護保険サービスを利用するには、お住まいの市区町村へ申請を行い、認定を受ける必要があります。要介護認定には、要支援1・2、要介護1~5までありますが、どの区分に認定されるのかは、介護認定審査会によって決定されます。
要介護認定の流れは、以下の通りです。
- 認定申請
- 訪問調査及び主治医意見書の作成
- 1次判定※
- 2次判定(介護認定審査会)
- 要介護状態区分等決定
※訪問調査による高齢者の心身の状況調査の結果と主治医意見書の意見をコンピュータに入力します。コンピュータ判定では、調査項目ごとに設けた選択肢によって高齢者を分類し、そこから要介護認定等基準時間(表参照)を推計。仮の要介護度を決定。要介護認定等基準時間は、「介護に要する時間」のことです。ただし、要介護認定等基準時間は、ひとつの「ものさし」であり、実際の介護時間とは異なります。
| 区分 | 要介護認定等基準時間 |
|---|---|
| 非該当 | 25分未満 |
| 要支援1 | 25分以上32分未満 |
| 要支援2・要介護1 | 32分以上50分未満 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 |
| 要介護5 | 110分以上 |
上記のように要介護認定等基準時間が「32分以上50分未満」の場合に、要支援2または要介護1の対象となります。
要介護認定等基準時間が同等である要支援2と要介護1の境界線はどこにあるのでしょうか。
一概に線引きはできませんが、「認知症がある場合」や「主治医により状態が不安定(体調が悪化する可能性がある)」と判断されると、要介護1になる可能性が高いといわれています。
要支援2と要介護1の状態の目安
以下が要支援2と要介護1の状態例です。
【要支援2】
- 身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする
- 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする
- 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある
- 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる
【要介護1】
- 身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする
- 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする
- 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある
- 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる
- 理解力の低下がみられる
比べてみると、要支援2と要介護1の状態例はほとんど一緒ですが、要介護1には「理解力の低下」という認知症状と関連する項目があります。
利用できる介護サービスが違う
サービス利用開始までの手続き
- 【要支援2】
- 原則、サービスを利用する前に、地域包括支援センターに依頼し、介護予防サービス・支援計画(介護予防プラン)を作成(サービス種類によっては、その事業所のケアマネジャーが作成する場合もあります)
- 【要介護1】
- 原則、サービスを利用する前に、居宅介護支援事業所等に依頼し、利用したいサービスの内容を具体的に盛り込んだ居宅サービス計画または施設サービス計画(ケアプラン)を作成
利用できるサービスの種類
- 【施設サービス】
-
施設サービスは、上記の通り要介護状態の方が対象であり、要支援の方は利用できません。
要支援2 要介護1 対象外 〇施設介護サービス費
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
→原則として要介護3~5の方が対象。ただし、要介護1・2の方であっても、やむを得ない事情により指定介護老人福祉施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与のもと、入所が認められる
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設(随時、介護医療院に移行)
・介護医療院認定には有効期間があり、引き続き介護サービスを利用を希望する場合は、更新申請が必要です。
ただし、更新申請を実施した際に、要介護から要支援になる可能性もゼロではありません。その際には、施設サービスが利用できなくなりますので、注意が必要です。
- 【居宅サービス】
-
要支援2 要介護1 ①介護予防サービス費
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防福祉用具貸与
②地域密着型介護予防サービス費
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
③介護予防福祉用具購入費
④介護予防住宅改修費
⑤介護予防計画サービス費
⑥高額介護予防サービス費
⑦高額医療合算介護予防サービス費
⑧特定入所者介護予防サービス費①居宅介護サービス費
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
②地域密着型介護サービス費
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護
③居宅介護福祉用具購入費
④居宅介護住宅改修費
⑤居宅介護計画サービス費
⑥高額介護サービス費
⑦高額医療合算介護サービス費
⑧特定入所者介護サービス費要支援2では、これら以外に介護予防・日常生活支援総合事業を利用することも可能です。
以上のように、要支援2と要介護1では利用できるサービスに違いがあるので、注意しましょう。
支給限度基準額(支給額の上限)
要介護度別に限度額が決められており、それを「支給限度基準額」と言います。この基準内であれば、利用者は居宅サービスと地域密着型サービスを組み合わせることが可能です。
| 要支援2 | 要介護1 | ||
|---|---|---|---|
| 単位数 | 費用の目安※ | 単位数 | 費用の目安※ |
| 10.531 | 10万5,310円~ | 16.765 | 16万7,650円~ |
※地域によって料金は異なります
要支援2と要介護1では、月に約6,000単位(約6万円)の差があり、利用できるサービスの量も異なります。
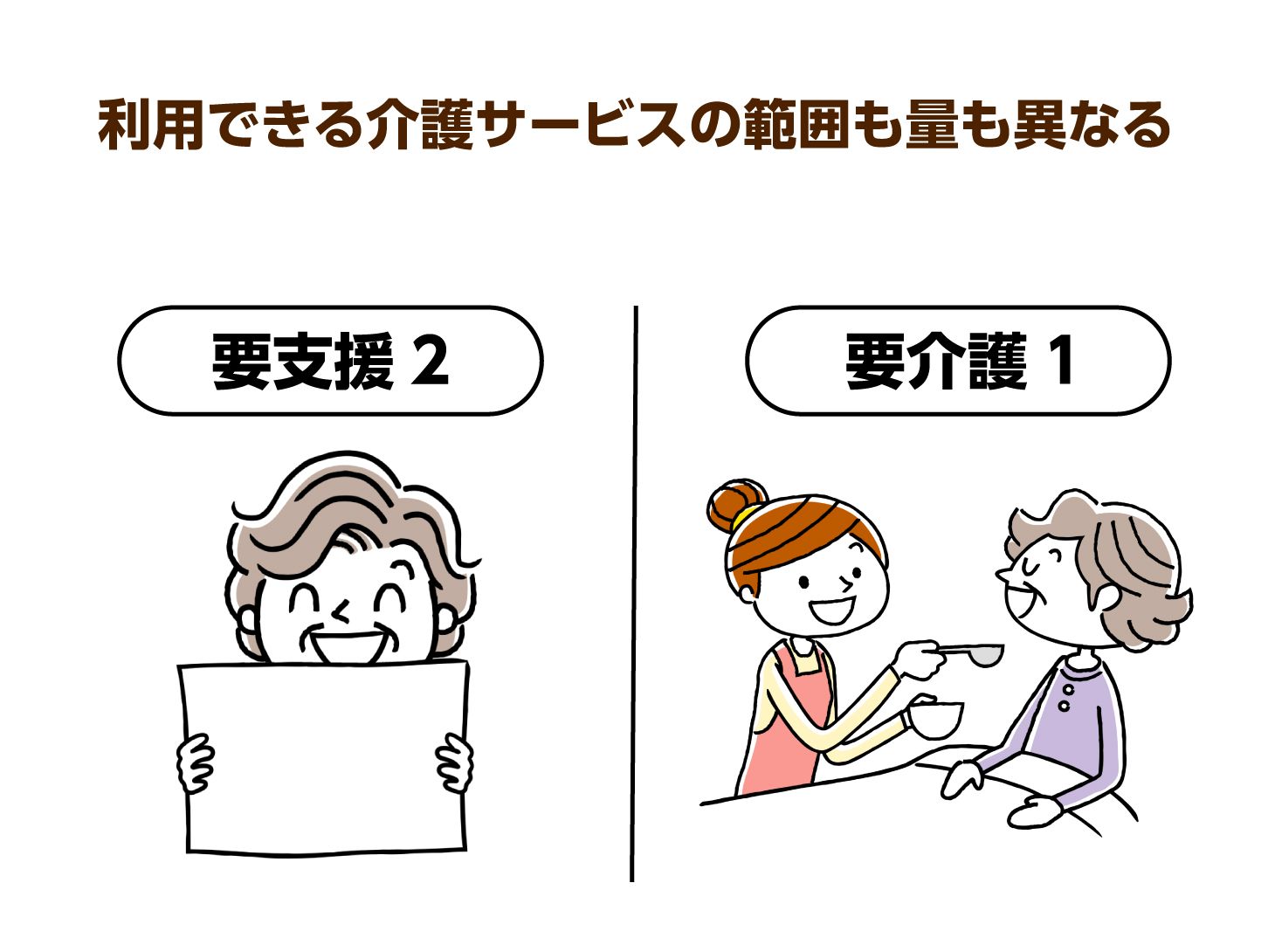
認知症は、原因疾患に伴い、知的能力が衰退し、日常生活に支障をきたした状態です。いわば「自分の意思を行動に移すことはできるけれどやり遂げられない」状態といえるでしょう。
そのため、生活を営むために他人の手を借りる、支援が必要になります。
介護サービスは、そのような方々の生活をサポートする重要な役割を担いますが、要支援2と要介護1では、利用できるサービスの選択肢に大きな差が生じることを知っておきましょう。