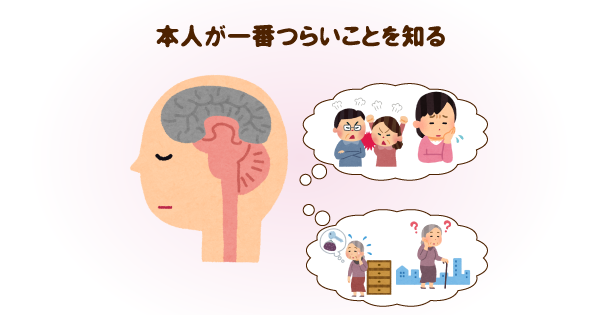認知症の方の対応が難しいことは皆さんもご存知の通りです。しかし、原因はさまざまです。多くの方は、認知症の方のほうに原因があると思われるかもしれませんが、そうとは言い切れないケースもあると私は考えています。
あくまで私の経験の範囲内ですが、介護をする側の話し方や接し方が対応を難しくしていると考えられるケースもあるのです。
今回は、私が日頃心がけている「認知症の方と会話するときに忘れてはいけない3つのポイント」をお伝えします。
適切な声で話をすること
高齢になると誰もが耳が遠くなる、と思っている人が少なからずいます。そう思い込んでいる人はいきなり大きな声で話し始めるので、普通に聞こえる認知症の方には不快に感じさせてしまいます。
当たり前のことですが、その人の耳の状態に合わせることが大切です。まずはいつも通りの声の大きさで話をし、相手の表情を見ながら調整しましょう。
例えば、相手が顔をしかめたときは声を小さくし、話を聞いていないようにしているときは、声を大きくするなどの対応が必要です。
また、声の大きさだけではなく、高低も重要です。若い女性に多い、高い声は不快に感じることが多いので注意が必要です。無理をして低い声を出す必要まではありませんが、あまり高い声にならないようにだけは気をつけておくことです。

話し方はゆっくり、はっきり
簡単にいえば早口にならないようにすることを心がけてみましょう。話が盛り上がり夢中になってくるとつい早口になってしまいます。
それが親しい関係や若い人であれば特に問題とはなりませんが、年齢とともにそうはいかなくなります。話についていけなくなるのです。
それでも認知症でない場合であれば前後の内容から推測して補うことはできますが、認知症の方はそれも難しくなるのです。
普通の人であれば、内容が聞き取れていなくても話を聞いているかのようにうなずく人もいると思います。
それは言わば、話をしている相手に対して聞いているとのサインですが、認知症の方の場合は、聞いているというより何も理解できていない可能性もあります。うなずいている=理解しているというわけではないのです。
うなずいていたから理解していると思っても、認知症の方に怒られている介護者をよく見ました。つまり、言ったことが伝わっていなかった状態です。
意識をしないと難しいことですが、ゆっくり話すことを心がけましょう。そのためには言葉の一つひとつをはっきり話すようにすると、うまくいきます。
流行りの言葉は使わない
最近使われるようになった言葉はなるべく避けましょう。何をもって最近というのは人それぞれですので明確な基準はありませんが、認知症の方が理解できるかどうかを考えることが必要です。
自分にとっては当たり前に使っている言葉であったとしても、それが他の人にとっては理解できない言葉があります。
なかでも認知症の方の場合は、理解できる言葉が減って、考えることが難しくなってきます。状況を見ながらできる限り平易な言葉で話をすることが大切です。

会話をすること自体は誰でも日常的にすることなので特別なものではありません。しかし介護をするうえではどの場面においても重要なことなのです。
当たり前にしていることだけに軽視しがちですが、改めて考え直すきっかけになればと思います。