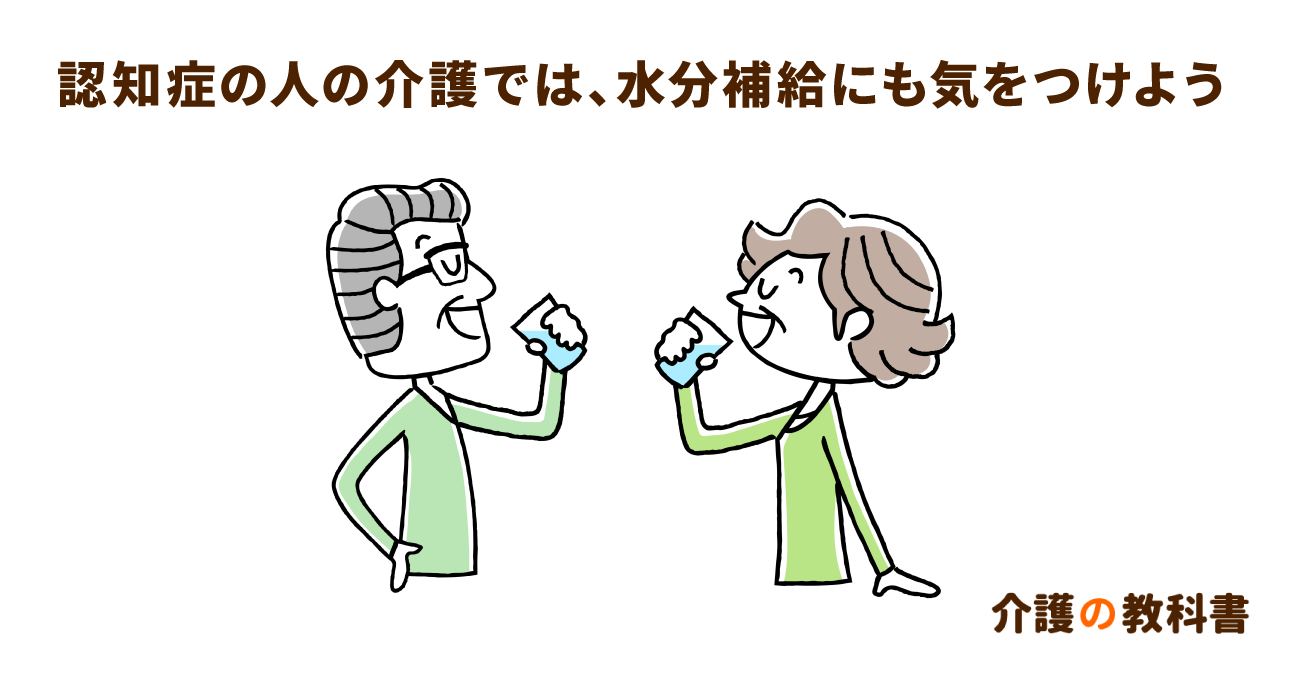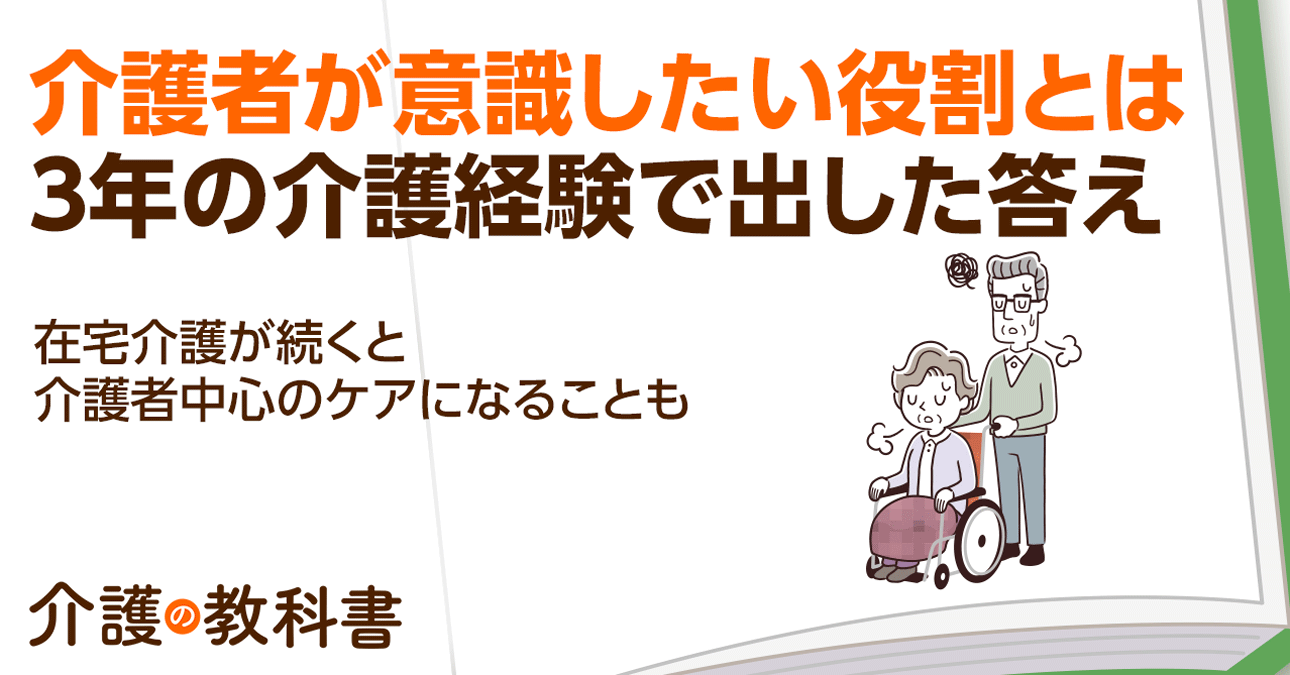認知症の人の介護は大変なものです。しかし、介護者の中にはそれをいい意味で「逆手に取って」対応している人がいます。
今回は、私がこれまでに見聞きした、認知症の人の対応で工夫されている実例をお話していきます。
認知症の人の表情は介護者の写し鏡
親戚の消息が気になり、何度も聞いてくる母に困っていたNさん。当初はその都度答えていたそうですが、途中からうんざりしてきたといいます。
そこで、聞いてくるであろう話題をクイズ形式にしたそうです。具体的には「○年○月に亡くなったのは誰でしょう」と問題を出し「△△さんか」と答える母に対し、「ブー、□□さんでした」といったようなやり取りをしていました。
その結果、Nさんは母との話題が広がったといいます。他人に聞かれたら不謹慎だと思われることは十分にわかっていますが、誰かに見せるわけでもない2人だけなのでとのことです。
「また同じことを」と腹を立てながら対応するよりは、自分の精神状態を考えたうえでも良かったと振り返っていました。
認知症の人の表情は、介護者の表情を映し出している鏡に例えられることがあります。介護者が笑っていれば認知症の人も笑顔などの穏やかな表情になります。心では腹が立っていても笑顔でいることで認知症の人の対応は変わるのです。

発想を転換してかける言葉を変える
Tさんは、自分の家にいるにもかかわらず「帰ります」と言っては外に出ようとする夫に困っていました。ここが自分の家であることを何度言ってもわかってくれなかったそうです。
そこで、発想を転換してみようと遊び心が生まれました。それは、行こうとするのを止めるのではなく、家に入ってもらうためにはどうすれば良いかという転換でした。
思いついたのは、出ようとする夫に対して「おかえりなさい」と逆の言葉をかけることです。出ようとするのをやめて戻ってきた夫の表情はどこか戸惑っているように見えたそうですが、有効な方法なのではと考えられたといいます。
また、同じように発想を転換したのがKさんです。家の中にある食堂は狭いにもかかわらず、夫がいつもふんぞり返って座っていたそうです。「邪魔になるから前にいって」と何度声をかけても動かずじまい。
そこで「後ろを通らせてほしい」と声をかけてみると、結果として夫は椅子を前にやってくれたといいます。ストレートにしてほしいことをお願いするのではなく、少し言葉を変えるだけで伝わることがあるのです。
大変な中でも楽しさを見つけることが大切
最後にIさんの例をお話します。奥様が家の中をウロウロしてはIさんの知らない間にいろいろな物を本来とは違う場所にしまいこみ、後になって出てくるそうです。
Iさんは、それを見つけては怒っていたそうですが、疲れてしまいました。そんなある日、怒った後に何気に口から出た言葉に思わぬ効果があったそうです。
その言葉は「なんでやねん」。奥様の行動を漫才でいうボケと捉え、それに対していわゆるツッコミの言葉「なんでやねん」と言うことで、腹立たしい気分が少し落ち着いたそうです。

このように、人によって対応はさまざまですが、いずれも共通することがあります。
それは、状態の変化に戸惑いながらも、どう声をかけていくのが良いのかと、ある意味で楽しんでいることです。大変な状況でも楽しみを見つけることは、認知症の人の対応を考えるうえで有用なのかもしれません。