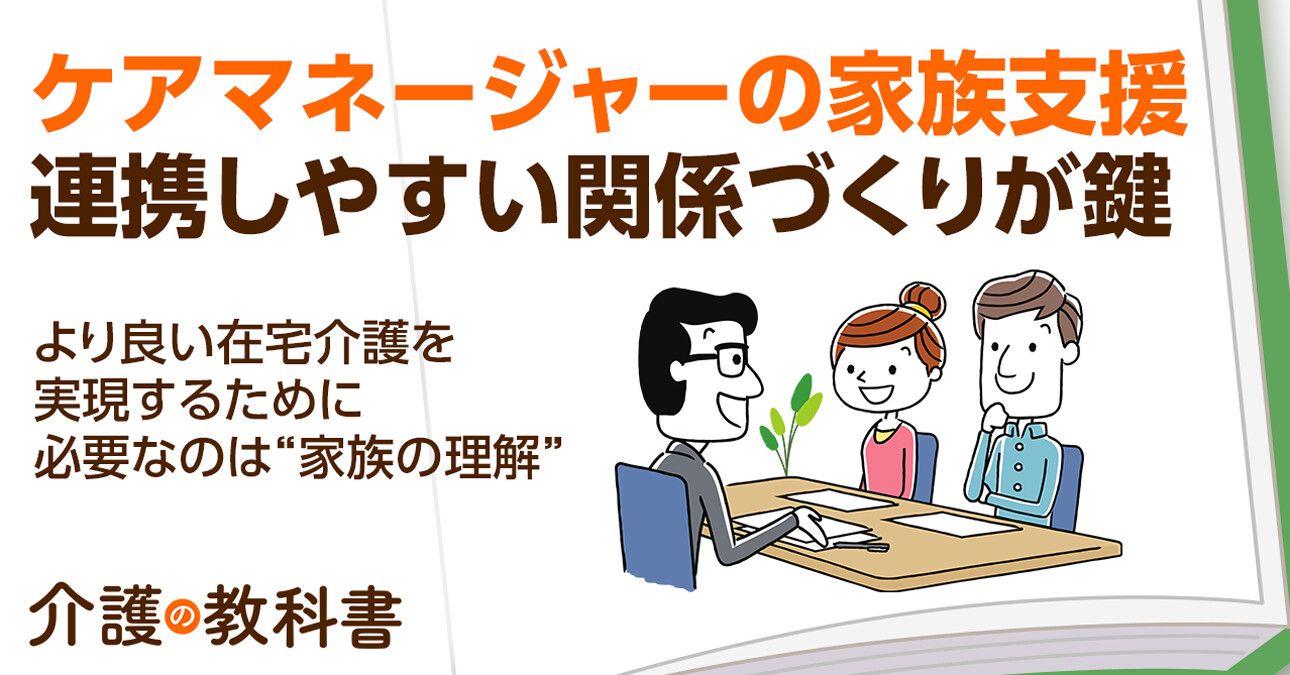わが国では、認知症の増加を背景に、さまざまな施策を打ち出しています。いわゆる団塊の世代の方々が、75歳以上となる2025年を見据えて、国は2015年に認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)を策定しました。
新オレンジプランの総合的な推進役として期待されているのが、認知症地域支援推進員(以下、推進員)で、2018年度から全国の市町村に配置されました。
今回は、この制度を簡潔に解説します。
認知症地域支援推進員の3つの役割
これまで、市町村では認知症関連の事業が複数実施されてきました。例えば、認知症サポーター養成講座の開催や認知症家族介護者への支援、見守り・SOSネットワーク構築、認知症初期集中支援チームの設置、地域ケア会議の開催などが挙げられます。
行政だけで、これらの取り組みの企画・周知・運営を行うことは効率的ではありません。
そこで、力を発揮している専門職の一つが推進員であり、いわば「つなぎ役・調整役」といえるでしょう。推進員に期待されている役割は、主に以下の3つに分類されます。
1.医療・介護などの支援ネットワークの構築
認知症になったとしても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、介護・医療関係者以外にも、地域住民の支えや関係機関の連携が重要です。そのために各自治体が打ち出している「認知症ケアパス」の作成・普及・活用を通じたネットワーク作りが推進員の主な役割です。
認知症になったら、介護・医療の必要性は高くなりますが、それだけで暮らすことはあり得ません。認知症の本人と家族がより良く暮らしていくためには、社会とのつながりが大切です。
地域住民の一員として社会とつながって暮らすことは、人が生きるうえで大切なポイントなのです。
2.関係機関と連携した事業の企画・調整
推進員は、認知症の正しい認識や対応力向上などのため、学びの場や機会の企画・調整も行っています。また、認知症カフェの開設や認知症の人の社会参加のための体制整備なども実施しています。
今でこそ認知症は一般的に正しく認識されつつありますが、過去には差別的な見方をされていました。
認知症は、2004年まで「痴呆」と呼ばれていました。当時の辞書を調べてみると、痴呆は「ばかのこと」などと書かれています。なぜこのような記述になっていたのでしょうか。
その背景には、認知症の人たちが一般的に「何もわからない、何もできない、おかしな困った人」と認識されていたからです。その言葉の通り、ひどい扱いを受けていたのです。
当時、認知症の方が、次のようなことを発信しました。
一般の人が認知症に対して偏見を持ったり、対応を誤ってしまうと、認知症の人や家族は大きなダメージを受けてしまいます。
そのため、認知症を正しく認識してもらうことや対応力を向上させることが重要です。
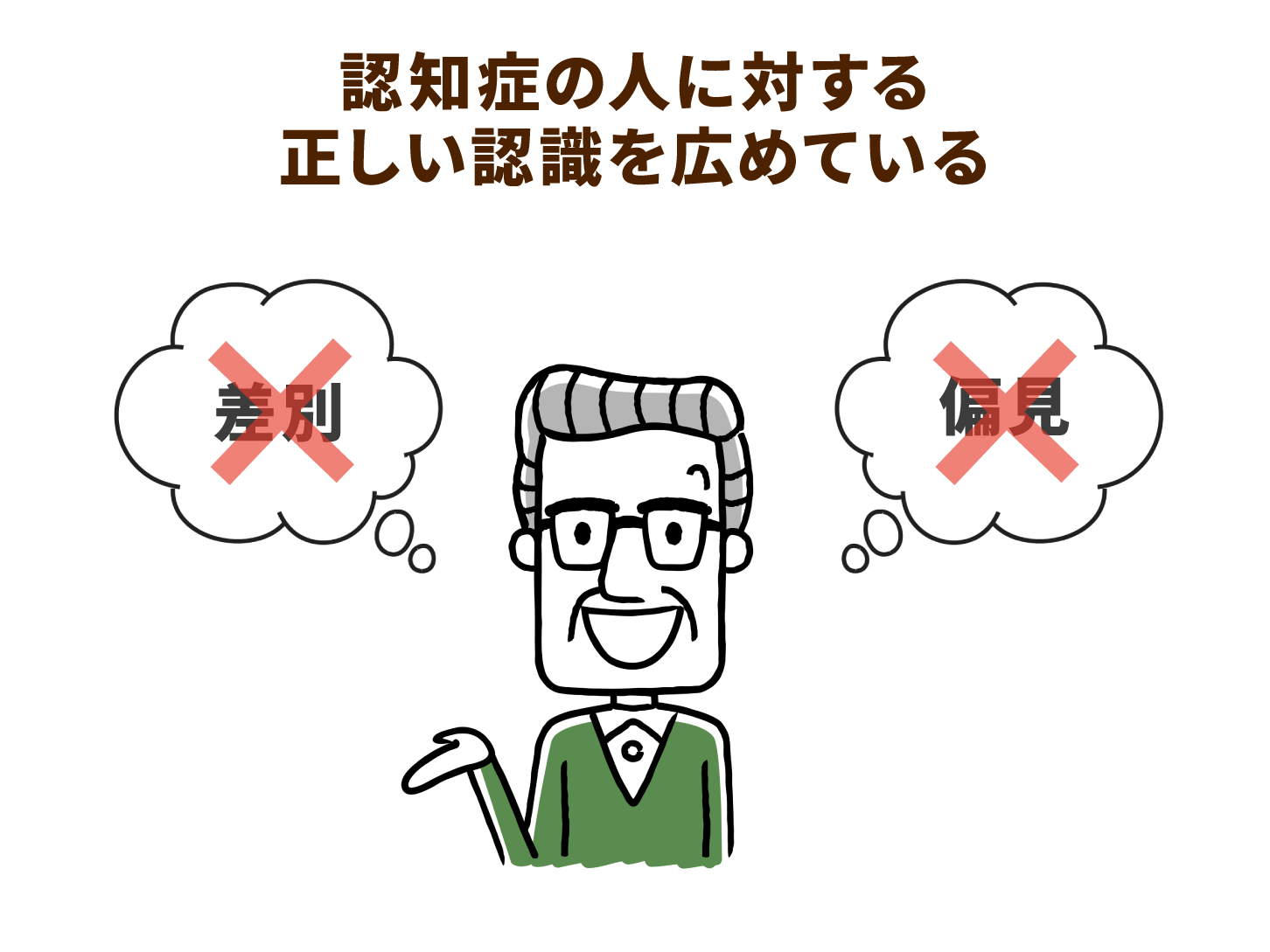
3.相談支援・支援体制構築
推進員は地域包括支援センターに所属し、地域住民の個別相談を受け、介護認定や介護サービスの提案、その他関係機関へつなぐ役割も担っています。
認知症が疑われていて介入ができない事例については、認知症初期集中支援チームとの連携を図ることもあります。
新たに加えられた家族支援の役割
厚生労働省は、推進員の業務内容として、新たに「認知症の人と家族への一体的支援事業」を加えました。
その通知には以下のように記されています。
まだまだ事例は多くはありませんが、今後、公共スペースなどを活用して、認知症の本人と家族が活動を共にする場を創出するイメージです。これにより、認知症の人の安心感につながり、家族からすれば「本人の可能性」に気づく機会になります。

今後さらに高齢化が進み、認知症の人は増加することが見込まれているため、推進員にはさらなる活躍が期待されています。
推進員の役割を知っておくことで、一般の方でも相談できる選択肢も広がります。何かお困りのことがあったら、まずは地域包括支援センターで推進員に相談してみてください。