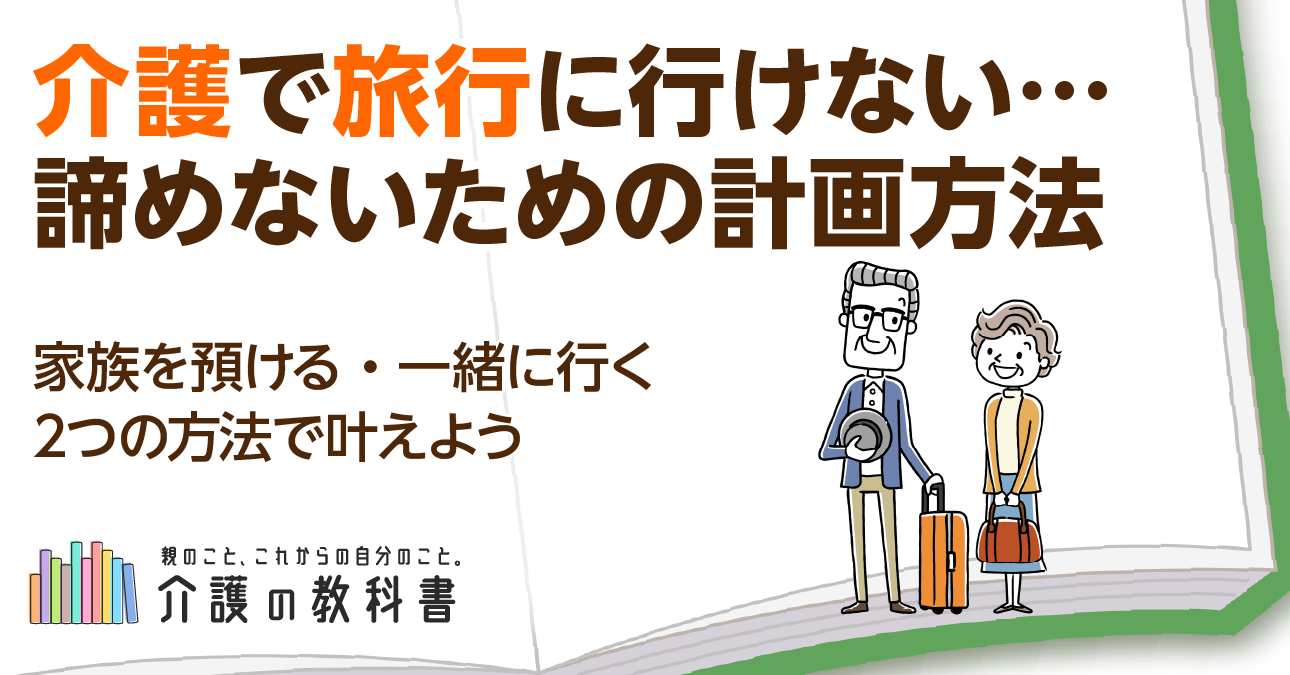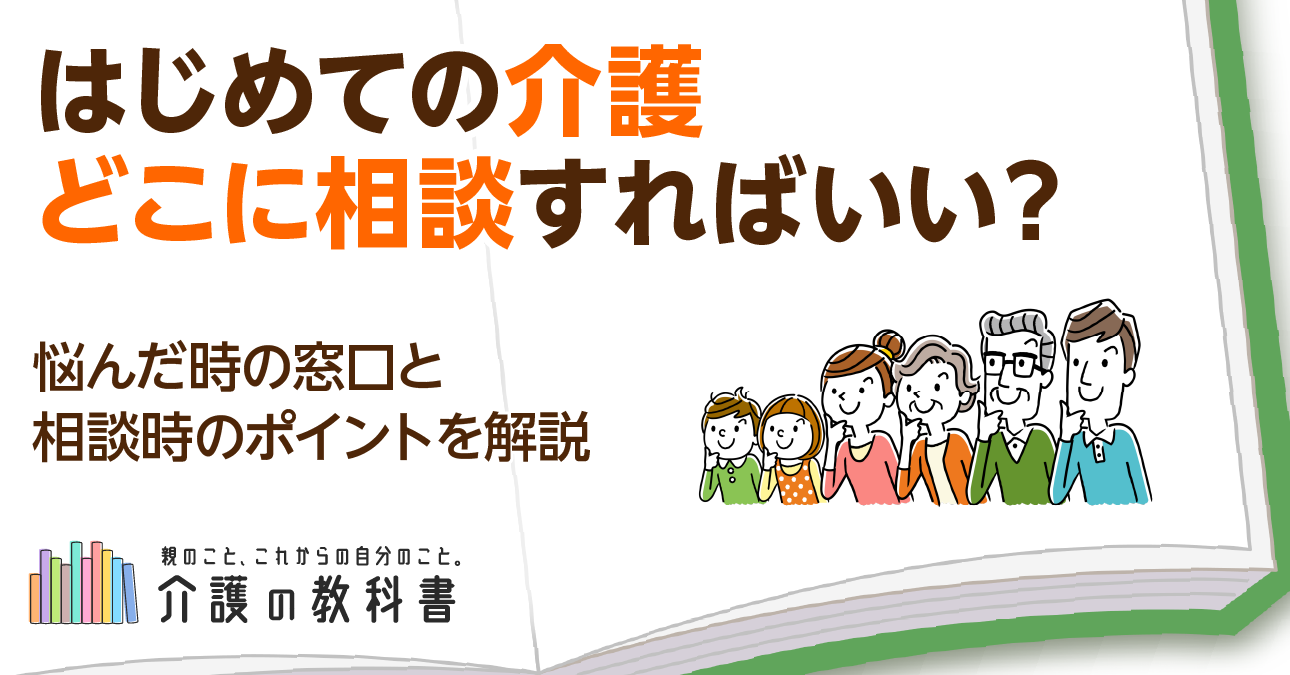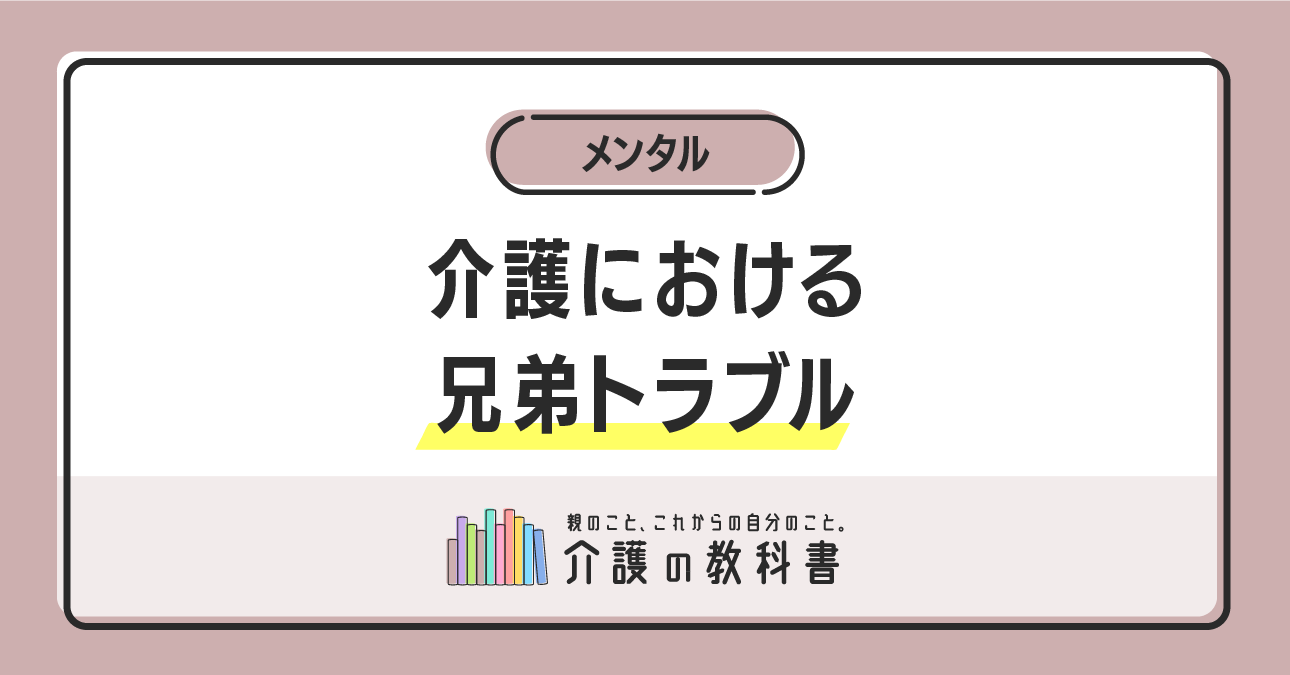株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
厚生労働省が2019年に行った国民生活基礎調査に、「要介護度別にみた介護が必要となった主な原因(上位3位)」が掲載されています。
それによると、認知症は要介護度1~3で1位、要介護度4、5では2位となっています。そして、要介護者(要介護全体)では認知症が最も多く、次いで脳血管疾患(脳卒中)という結果でした。
国民生活基礎調査は毎年行われていますが、3年に1度大規模調査が実施され、「介護が必要となった主な原因」が公表されています。
2001年の調査では脳血管疾患が圧倒的な1位で、認知症(当時の呼称は「痴呆」)は4位。その後も1位は脳血管疾患でしたが、2016年調査で初めて認知症が1位となり、2019年調査でも同じ結果となりました。
介護が必要となる原因に占める認知症の割合は今後も大きくなっていくでしょう。
高齢の親や配偶者が元気に暮らしていると、「介護はまだ先のこと」と思うものです。しかし、高齢になればいつ認知症が始まり、介護が必要になってもおかしくありません。
そこであわてないために介護における「心構え」や、「介護の予備知識」についてお伝えします。
介護における心構えで必要な3つの基本
介護は突然始まり、長引くことも多い
2020年の日本人の平均寿命は、男性が81.64歳、女性が87.74歳でした。
次に、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を示す「健康寿命」をみると、厚生労働省は、男性が72.68歳、女性は75.38歳だったと発表しました(2021年12月)。
平均寿命から健康寿命を引いた数は、「何らかの介助・介護などが必要な期間」といわれています。まずこの数字を抑えておきましょう。
- (男性)平均寿命81.64歳-健康寿命72.68歳=8.96年
- (女性)平均寿命87.74歳-健康寿命75.38歳=12.36年
ただし、実際の介護は突然始まるもの。そのため、「介護が始まるのはいつ?」と予測して、そこにあわせて準備を進めることが難しいのです。また、「うちはまだ大丈夫」という過信は、介護に備えること自体を遠ざけてしまいます。
介護への備えは、「突然来ても慌てない、長期間になっても乗り切る」ためにも大切です。
生活時間の配分と、他人に託す覚悟が大切
現在の自分の生活時間配分(平日)を考えてみてください。
睡眠、食事、買い物、家事、育児、身の回りの用事、移動(通勤を除く)、休養・くつろぎ、趣味・娯楽・スポーツ・学習、交際・付き合い、仕事、通勤など、実にさまざまな行動をしています。
もし介護を担うことになったら、上記で挙げた時間の内どこかを削り、介護に充てる必要が出てきます。
だからといって、あらゆるものの時間を介護にまわしていっては、介護者(自分)の心身がもちません。許容範囲以上に仕事の時間を削る、もしくは退職してしまえば収入がなくなり、生活自体が成り立たなくなってしまいます。
だからこそ、「他人に託す覚悟」が必要です。
ここでいう他人とは、介護保険サービスを提供する介護従事者(施設・事業所など)を中心としたフォーマルサービス、ほかの家族、友人、近隣の人、民生委員、ボランティアといったインフォーマルサポートのことです。
介護は状態や状況が常に変化する
要介護者(親や配偶者)は高齢のため、状態が変化しやすいものです。
そのため、介護開始直後(初動期)に要介護者の状態や、家族の状況などに合わせて支援体制を整えたとしても、それがずっと続くとは限りません。
支援体制は、「再調整が常に必要」という心構えが大切です。
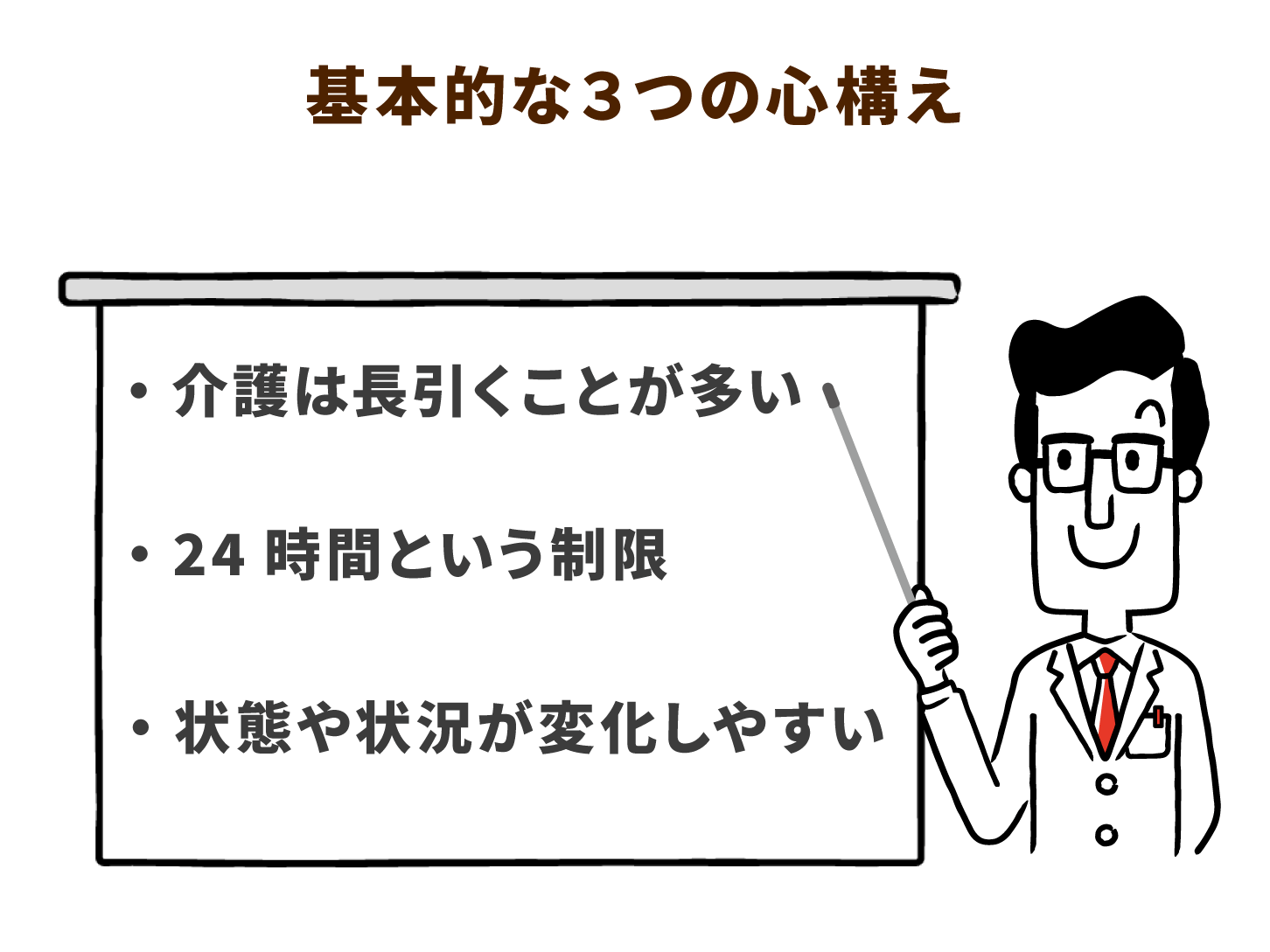
あらかじめ備えておきたい介護の予備知識
私が定義する「介護への備え」とは、「介護の予備知識」を獲得すること・蓄えておくことです。
突然介護を行なうことになったとき、助けになってくれる介護経験者や相談できる人が自分の近くにいるとは限りません。
ただでさえ、これまでの生活時間配分の中から介護に時間を充てているのです。実際に介護が必要になってからでは、落ち着いて介護のことを勉強したり、調べたりすることは難しいでしょう。
そのため、いざというときに慌てないため、「介護の事前学習」に取り組むことは、とても大切です。
予備知識としては、以下のようなものが考えられます。
自治体の「介護保険制度」や「介護サービスの概要」を把握する
介護に直面したとき、どこに相談すればいいのか(窓口)、介護が必要になったときの手続きの仕方、介護保険制度でどんなことがお願いできるのかを知っておくだけで、いざというときに慌てずに済みます。
ちなみに、どの自治体でも介護保険の窓口には、このような情報をまとめた冊子が必ず置いてあります。介護保険制度などの手引書として家庭に1冊、置いておくと良いでしょう。
職場の介護関係の制度を把握する
企業は国からの要請によって、仕事と介護の両立のために、仕事を一定期間休むことのできる「介護休暇制度」と「介護休業制度」を整備しているはずです。概要や手続きの仕方などを聞いておくと良いでしょう。
また、最近では、従業員の多様な働き方を応援する企業も増えていますので、自社における介護関係の「法定外福利厚生サービス」が存在するかも把握しておきましょう。
介護技術を含めた介護の基礎知識を持つこと
介護が長期間に及ぶと、先が見えないため、精神的にも肉体的にも負担がかかりやすくなります。また、介護を始めたばかりでも、ちょっとしたことで腰を痛めてしまうこともあります。
そこで大切なのが、介護技術の知識です。正しい介護技術を持っていると、自分の体を守りながら介助できるので、肉体的負担の軽減・腰痛予防にもつながります。また、要介護状態にある親や配偶者と向き合うためには、介護の基礎知識が必要です。
つい要介護状態になる前と比較してしまい、「こんなこともできない・わからない」と、イライラを募らせてしまいます。しかし、介護や認知症に関する知識を知っていると、「これは仕方がない」「まあいいか」と、現状を肯定できるようになり、精神的負担の軽減につながります。
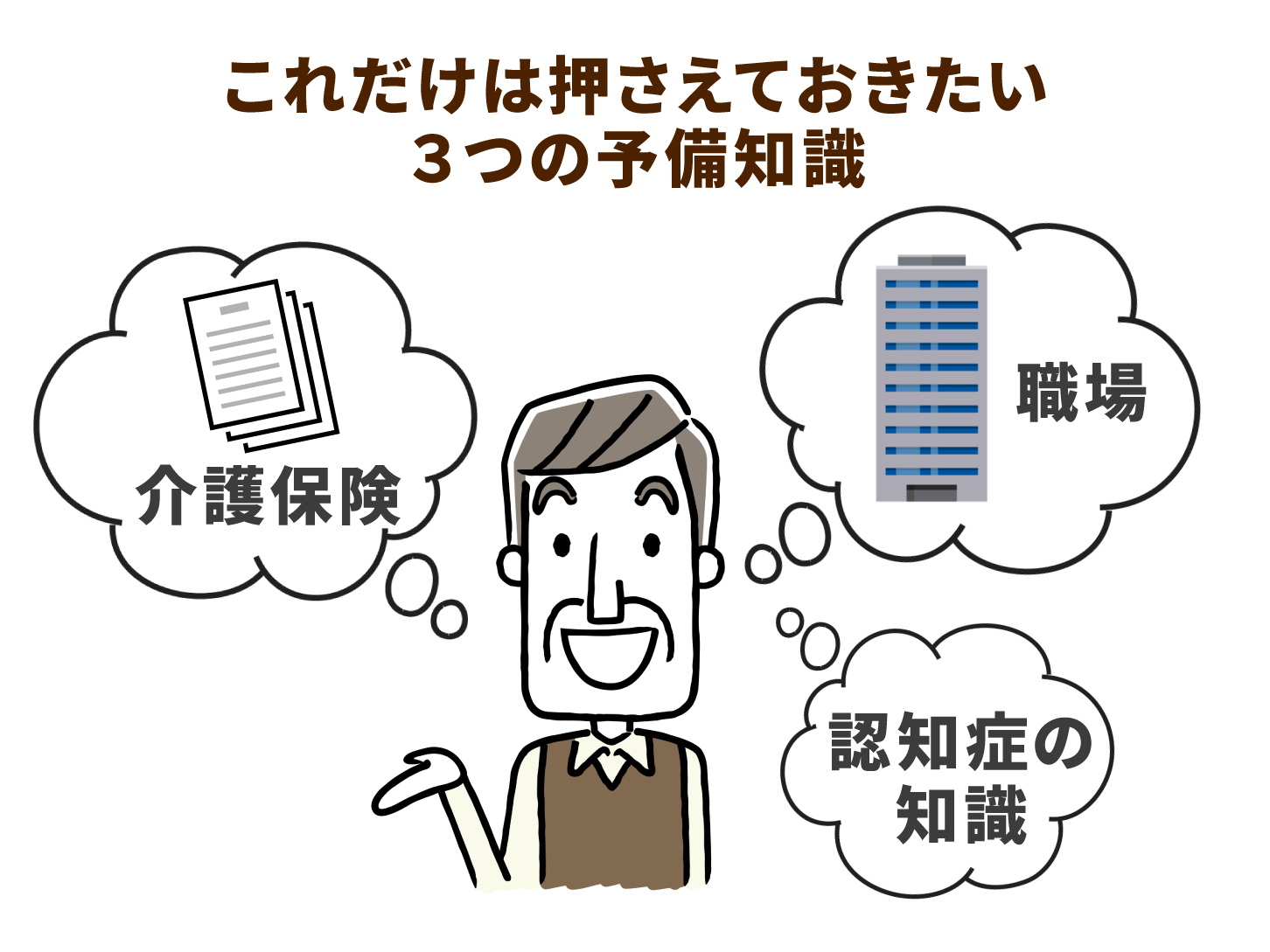
次回も、認知症の介護と向き合うために必要なことをお伝えします。