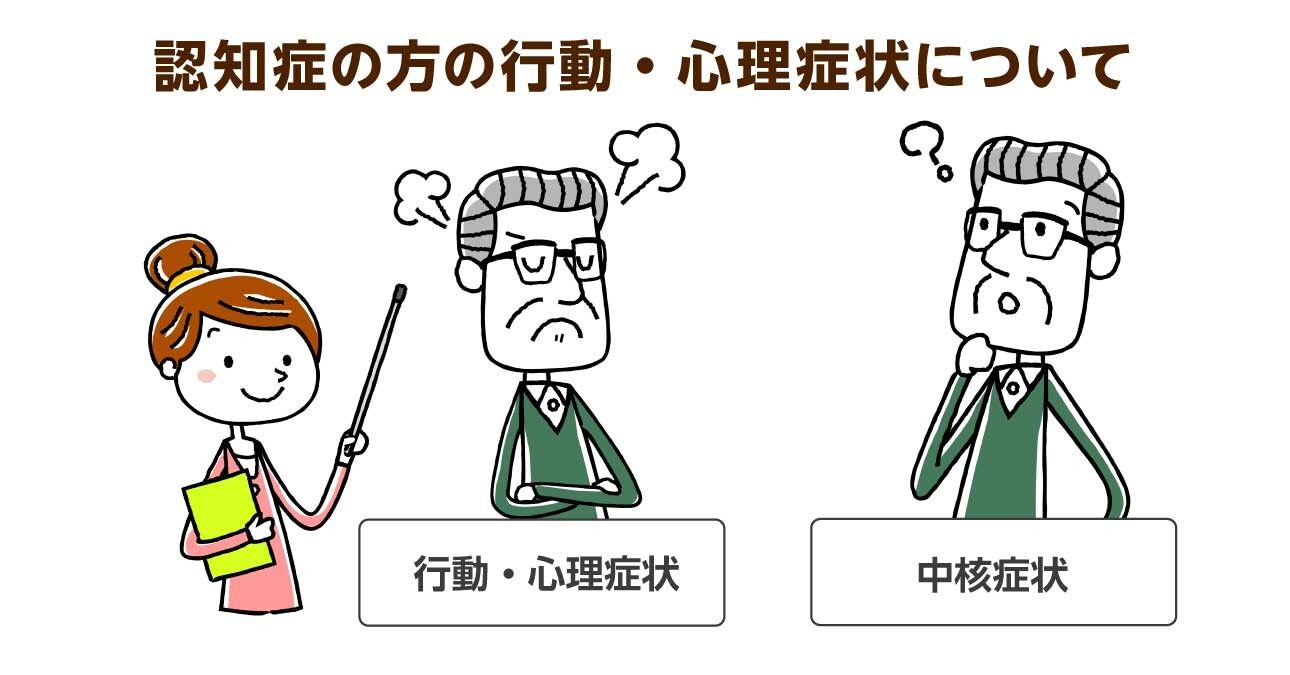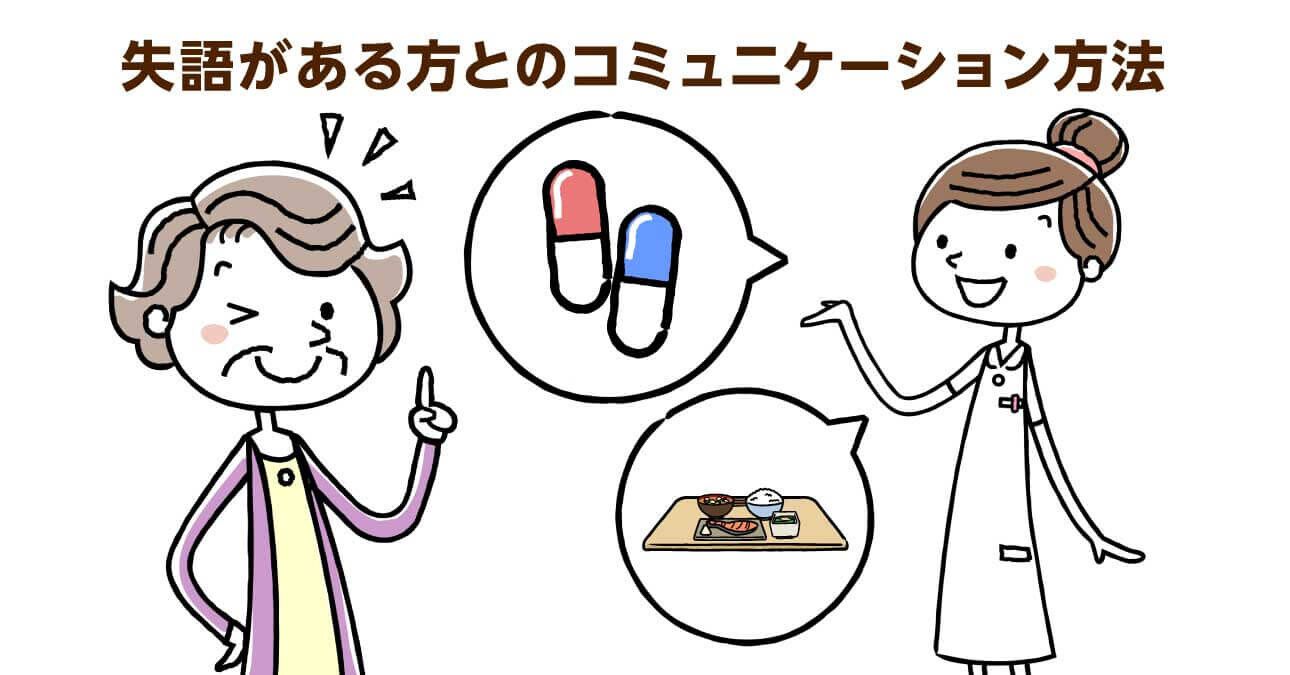特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。
介護をするうえで欠かせないのが、「要介護者の暮らし」を一生懸命考えて、一人ひとりに合わせたサポートを行なっていくことです。しかし、自分以外の人の生活を考えることは簡単なことではありません。
なかでも、認知症の方は中核症状などの影響で、自分の思いや気持ちを言葉で的確に表現しにくい状態にあります。そのため、要介護者の気持ちを推し量ることは非常に難しいのです。
最近では「認知症の人の感覚(世界)」をわかりやすく表現した書籍が話題を呼んでいます。認知症の人の感覚を完璧に理解することは難しくても、理解しようと努める姿勢は大切です。
認知症になったことがないから理解ができない
介護者は、認知症の状態にある人が引き起こす不可解な言動を問題視しがちですが、あくまでそれは「病態である」ことを理解しましょう。
私たちが普段何気なく送っている生活も、当事者からすると大変なことがあります。認知症に関係なく、どんな病気やケガも本人が一番辛いということを理解する必要があります。
介護者は認知症になったことがありません。そのため、認知症の状態にある人の思いや気持ち、つらさを想像しにくいのです。
実際に自分が罹ったことがある病気であれば、相手の気持ちや辛さを想像して対応できますが、経験のない症状には共感することさえできないのです。
そういった前提を忘れずに、認知症の状態にある人に向き合うことが、介護の心構えと本人を理解する基本的な姿勢です。
認知症の2つの症状
認知症は緩やかに進行することがわかっていますが、現代の医学では完全に食い止めることはできません。そのため、時間が経過するとともに、できないことやわからないことが次々と増えていきます。
その症状は、一般的に2つに分けられます。1つは中核症状で、記憶障がい・失認・失行・失語・実行機能障害・見当識障がいなどが挙げられます。
- 記憶障がい
- 物事を覚えること、覚えておくこと、思い出すことが難しくなる
- 失認
- 目は見えているのに、それが何かがわからなくなる
- 失行
- 手足に麻痺などの障がいがないのに、意図した動作ができなくなる
- 失語
- 言葉を理解したり、言葉を発したりすることが難しくなる
- 実行機能障がい
- 計画を立てる力が弱まり、手順がわからなくなる
- 見当識障がい
- 時間、場所、人の見当がつけられなくなる
2つ目の症状は行動・心理症状です。行動・心理症状は「徘徊」「不穏」「暴言」「暴力」「放尿」「帰宅願望」「異食」「介護抵抗」「妄想」「幻覚」「不安」「不眠」「抑うつ」などで、以前は問題行動と呼ばれていました。
認知症という状態になると、中核症状の影響を受けて、物事の認知がずれてきます。例えば、直前に話していたことも、記憶障がいによって忘れてしまい(覚えられず)何度も同じ話を繰り返したり、ゴミ箱を便器と誤って認識をしてしまいゴミ箱に排尿するなど、例を挙げたらきりがありません。
こうした症状は、支援者(家族・専門職)にとって大きな負担になります。そのため、行動・心理症状に直面すると「認知症が進行した」と捉えがちです。

事例から考える、認知症の人を理解するということ
認知症の状態にある人の理解しにくい言動は、何でもかんでも「認知症の症状」に括られてしまいます。
しかし、行動・心理症状は認知症の状態にある人すべてに起こるわけではありません。認知症の中核症状に加えて、不適切なかかわり(コミュニケーション)、物的環境への不適応、個人の生活歴、健康状態の変化(病気の可能性・体調不良や痛み)などが影響することで起こるとされています。
そこで、私たち専門職は「かかわり方は適切か」「環境への不適応がないか」「健康状態はどうか」などを探ることを重視しています。そうした背景に対して、地道に支援していくことが大事なのです。
事例1
アルツハイマー型認知症のAさんは、「今日は何月何日?」と繰り返し妻に確認します。妻は「今日は○月△日ですよ」と繰り返しAさんに返答。しかし、数分おきに同じ質問をされるので、妻は「もういい加減にして」と声を荒らげてしまいました。
認知症になると記憶障がいなどによって、今まで覚えていた記憶が抜け落ちたり、新しいことを覚えにくくなることがあります。そのため、常に「○○の話はしただろうか」「○○を聞いておかなければ」など、不安な気持ちで苦しんでいる可能性もあります。
また、まわりに迷惑をかけたくない思いで、周囲の人に確認をしている可能性もあります。常に「忘れないように」と意識しているからこそ、何度も聞いて「忘れないようにしよう」と確認している可能性も考えられます。
事例2
アルツハイマー型認知症のBさんは、トイレではないゴミ箱に排尿をしてしまうことがあります。それを見たBさんの妻は、「そんなところにおしっこしないで!」と強い口調でBさんを責め立てました。トイレ以外の場所で排尿されると、介護者が「何やっているの」と言いたくなる気持ちは理解できます。
しかし、本人からすると、一生懸命に行動した結果なのかもしれません。例えば、Bさんは尿意を感じたため、トイレに行こうと考えます。トイレを探している途中にゴミ箱を見つけ、目の前のごみ箱を見て一生懸命考えます。丸くて穴が開いているゴミ箱を、便器と誤って認識をされてしまった可能性もあります。
人の脳は「わからないこと(以下、空白)」を嫌う傾向があります。例えば人の顔は頭に浮かんでいるけど、その人の名前が思い出せずモヤモヤした経験はありませんか?そして、ふとした瞬間に、名前が浮かび上がってくるとスッキリした気持ちになります。
このように脳に空白ができると、それを埋めようとするのが人の心理です。同じように認知症の行動・心理症状に直面したときに、支援者側の脳に「空白」が生じます。「なぜ、テーブルを何度も叩くのだろう」「なぜ、家に帰りたいというのだろう」「なぜ、何度も同じことを聞くのだろう」と考えます。
しかし「なぜ~」という空白を「認知症が進行したから」や「認知症の症状だから」と判断すると、そこで思考が停止してしまいます。
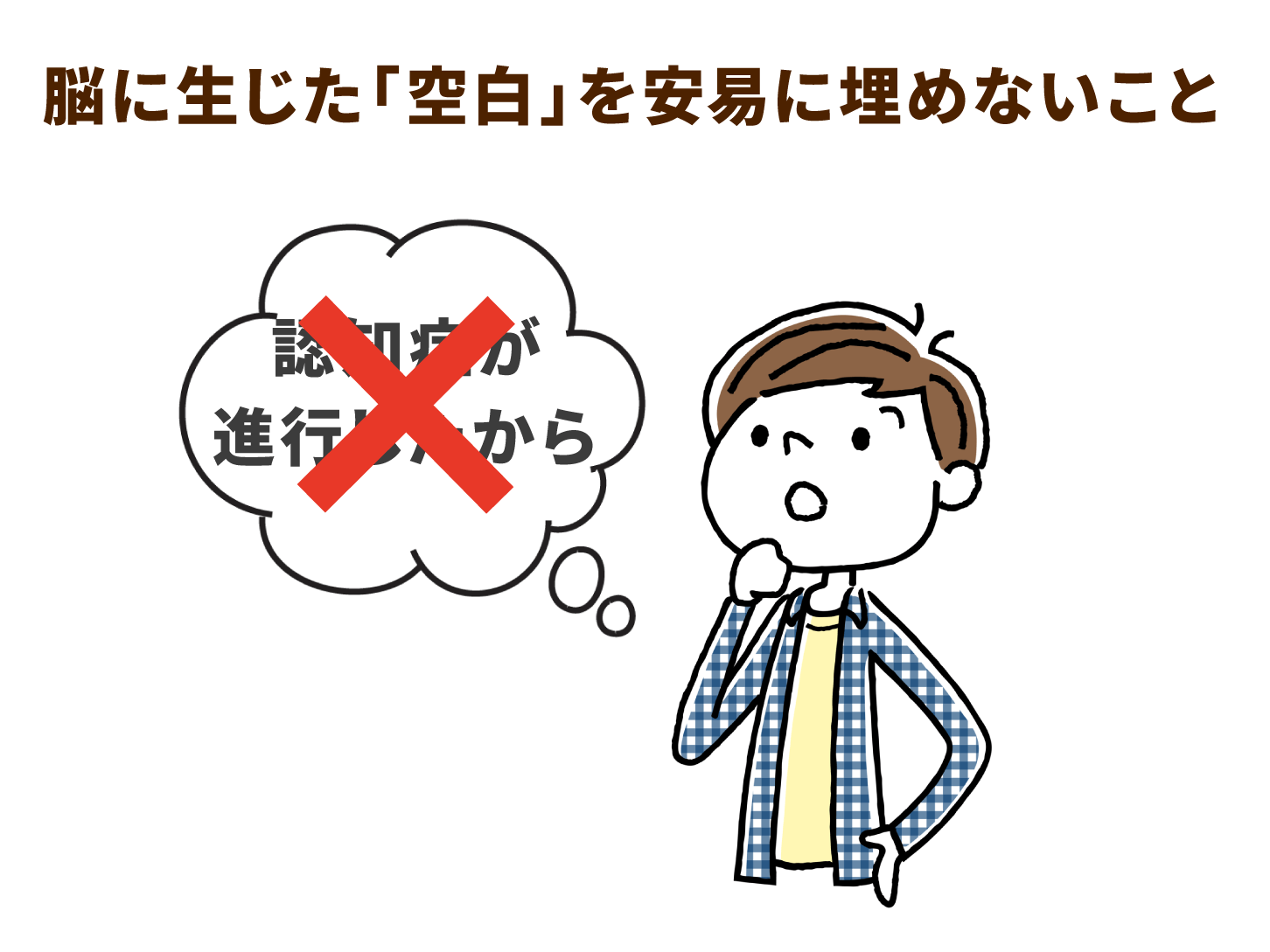
認知症の人の感覚を理解することは非常に難しいです。だからといって諦めずに、相手の立場に立って、その人が見えている世界から景色を見ようと努めること、その人の気持ちに思いを馳せてみることで、認知症の状態にある人の困りごとが見えてくるのではないでしょうか。