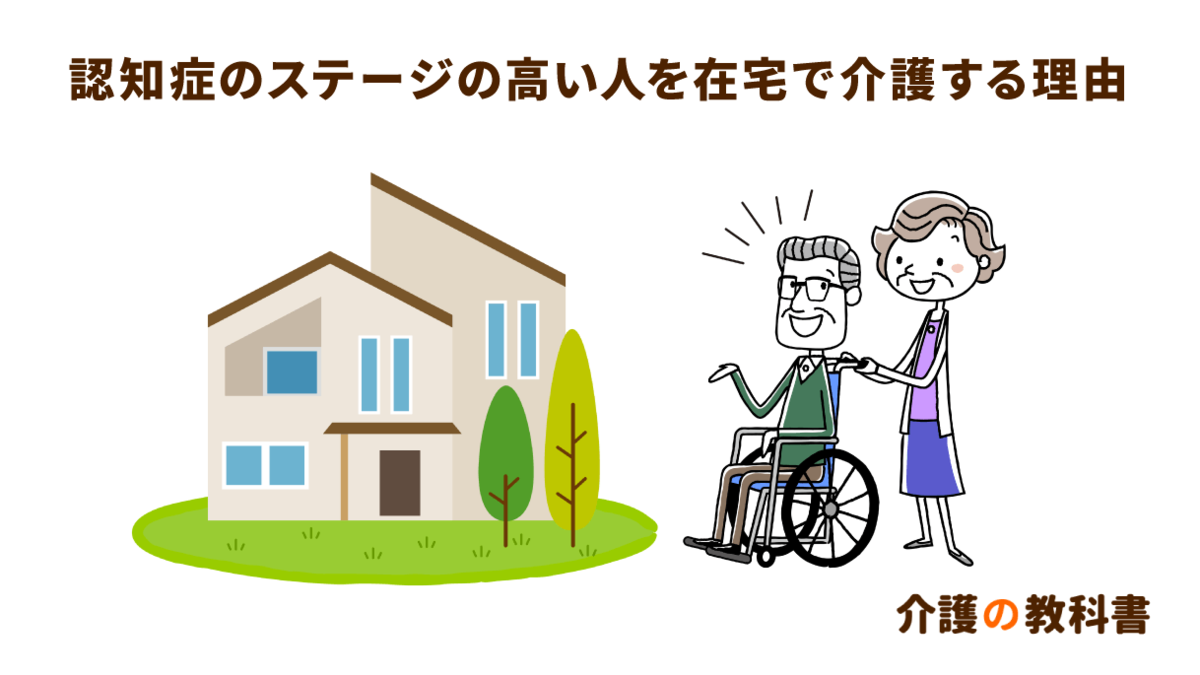皆さん、こんにちは。認知症支援事業所 笑幸 代表の魚谷幸司です。
認知症の高齢者を在宅で介護している人の中には、周囲から「症状が進行しているのに、よく家で介護しているね」と驚かれる人がいます。
そこで今回は、認知症の人の在宅介護について3つの点から考えます。
認知症の人への対応は「不安の解消」が大切
認知症の人への対応では、ご本人の不安を解消することが基本とされています。
では、在宅介護の場合、認知症の人はどのような気持ちなのでしょうか。それは、認知症の症状の程度(ステージ)や住んでいる環境によって大きく変わります。環境についていえば、認知症になる前から住んでいる家なのか、認知症になったことで子などと同居することになった家なのかということです。
認知症になる前から住んでいる家であれば、ご本人の認知症のステージが進んだ状態であっても、見慣れたものに囲まれているために安心して生活することができます。たとえ足の踏み場がないほどにものがあふれた環境であったとしても、同様です。
したがってこの場合は、対応する側(介護者)の考えや都合だけで、家を片づけたりすることで環境を変えるようなことがあってはならないのです。
また、子などと同居することになった場合は、環境の変化によって認知症の人は不安な気持ちになることが多くあります。新しいことを理解することが難しい認知症の人にとって、慣れない環境に身を置くことは大変なのです。それは、施設へ入居することになったときも同じです。まったく知らない人に囲まれて暮らすことは、大きな不安になります。
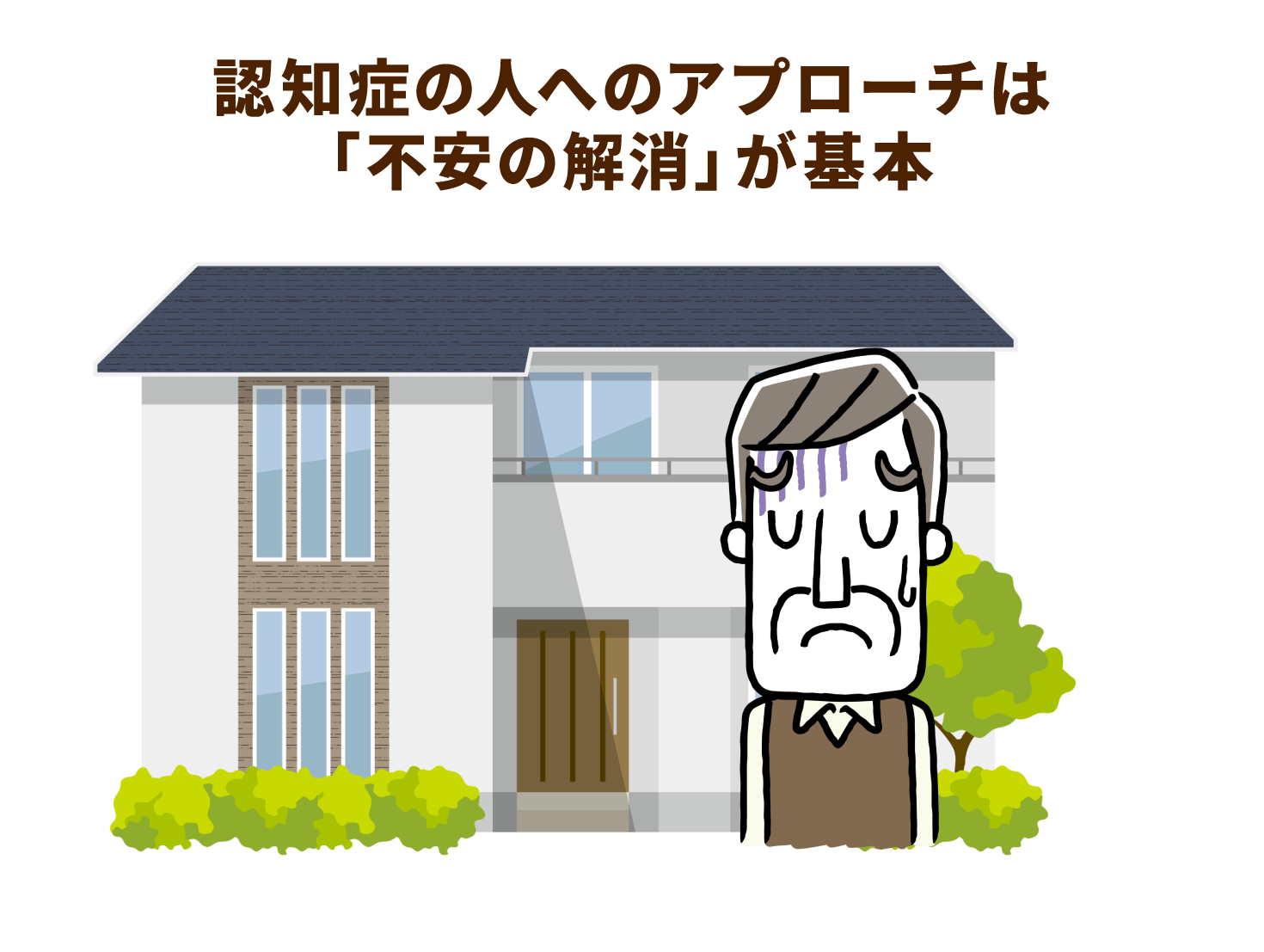
周囲の人の理解が在宅介護を可能にする
次に、「認知症のステージが進むこと」による在宅介護の難しさを考えてみましょう。認知症の面だけをみると、ご本人や介護者が異変に気がついたときから、周りの状況を把握できなくなる時期までが1番難しいのです。
最後のステージになると、身体的な介護が増えることによる介護の困難さはありますが、そのステージまでは異なります。認知症の人のおかしな言動に介護者は混乱し、結果として言動を訂正をしたり言い返したりと良くない対応をしてしまいます。
ただ、これは仕方がない点もあります。元気でしっかりしていた頃を知っているからこそ、そのギャップに戸惑ってしまうのです。こうした状況では、さまざまな人の助けをうまく借りる(サービスを利用する)ことが必要になります。
認知症の人への対応で1番大切なことは、身内や近所の方も含めて、周囲のすべての人が認知症について「正しく」理解することです。特に難しいことではなく「わからないことがあれば教える」「できなければ代わりにやる」と言った「当たり前」の対応です。その「当たり前」を積み重ねることで、在宅介護を続けていくことが可能になるのです。

男性の介護者は周囲の支援を受け入れにくい
私はこれまで数多くの家族介護者の話を聞いてきました。施設入居を選択できる状況にありながら、在宅を選んで介護されている方の想いを書いていきたいと思います。
何といっても男性の介護者で、妻を介護する夫の場合は「自分がしなくては」といったような義務感に近いものを感じてしまうことが多くあります。純粋に「すばらしい」と思える反面、外部に対して閉鎖的になり、周りの支援を受け入れにくくなってしまう傾向があります。こうした人に対しては、「適度に手を抜く大切さ」や「人の手を借りる必要性」を伝えていくことが必要です。
ただし、介護者が一人で頑張りすぎてしまう背景には「自分の家族だから」という気持ちがあるのではないでしょうか。腹が立つことがあっても、大切な家族なのです。本人に対して「きつい言葉をかけてしまった」「言いすぎたかもしれない」と後悔される家族をこれまでに多く見てきました。認知症になっても家族への愛情が変わることはないため、介護者はご本人のために在宅介護を続けているのです。